
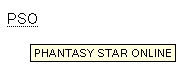
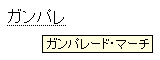
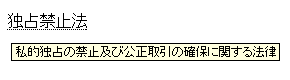
この要素はその内容が省略されている語句であることを示します。そして必要ならば title 属性で元の(省略されていない)語句を記述しておけば、ブラウザによってはその属性値を何らかの形で表示してくれるかもしれません。
<abbr title="Dreamcast">DC</abbr><abbr title="PHANTASY STAR ONLINE">PSO</abbr><abbr title="ガンパレード・マーチ">ガンパレ</abbr><abbr title="私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律">独占禁止法</abbr>上記の例では、 DC 、 PSO 、ガンパレ、独占禁止法の各単語が abbr 要素によってマークアップされ、それらが省略形であることを示しています。そして title 属性の属性値によって、元の言葉が補足情報として付加されています。

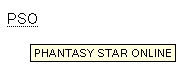
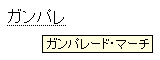
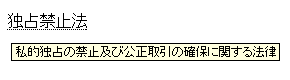
これらの画像は実際に上記のようなソースを記述し、 Netscape 7.0 PR1 ( 6.0 以降で対応)で表示させたものです。デフォルトでは abbr 要素に点線の下線がつき、その上にカーソルを持っていくことで、 title 属性の内容が表示されています。カーソルがキャプチャーできないのでこちらの画像では見えていませんが。
また、この説明文が表示されない、もしくは表示されていないときでも、このように他のテキストとは違った表示をすることで、それが「省略されている言葉」であることは認識できるわけです。例えば同じ文中で、元の言葉の説明を加えたりするのが冗長に感じられるときなどに使用するといいかもです。
なお Internet Explorer はバージョンを問わず対応していません。 abbr 要素と似たような要素に acronym 要素というのがありまして、 IE はそちらには対応していますので、 abbr 要素のかわりに acronym 要素を使う方もいらっしゃるようです。
abbr 要素は前述のように省略語全般、そして acronym 要素はその内容が頭文字語であることを示すとされていますが、正直この使い分けについては、 abbr 要素の方が汎用的に使えるということ以外はよくわかりません。
で、聞くところによると以下のような事情があったそうですが。
abbr 要素と acronym 要素は当初、 HTML 4.0 の規格が協議されていたときに、省略語を示す要素として候補に上がっていた。そしてマイクロソフトが、(自分たちが提唱していた) acronym 要素を IE に実装してリリースしてしまった後で、省略語としては abbr 要素の方が正式採用されることになった。ところが IE が acronym 要素にしか対応しておらず、 abbr 要素には非対応だったために、しかたなく acronym 要素も HTML 4.0 の正式な要素として採用することになり、 abbr 要素は省略語を示し、 acronym 要素は頭文字語を示すと決められた。
といった話ですが、本当のところはわかりません。ただ、( IE の abbr 要素への)対応が間に合わなかったというだけでしたら、いまだに対応していないのはおかしいですし、いかにもありそうな話だなとは。