|
変調のいろいろ |
| 変調??、別に調子が変になるわけではありません(^_^;)。アナログ・デジタルを問わず無線による通信では、音声などの情報を何らかの方法で電波に乗せてやる必要があります。 それが”変調“という操作です。当サイトには至る所に変調形式(QPSK etc.)が登場しています。それらの解説や用語集を作らないままでいたことを反省し、ややこしいブロック図やイミフな数式等を用いず、ビジュアルで理解できるように工夫し・構成したつもりです(^_^;。 少なくともどのように電波に情報が載せられて、我々の使う各種無線機器まで届いているのか、それだけでもお伝えできれば幸いです。 |
|
波形の位相・振幅の意味 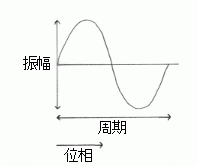 変調について解説するとき最低限避けられないのが、信号の位相・振幅と周期(周波数)についてです。まず右図をご覧ください。 変調について解説するとき最低限避けられないのが、信号の位相・振幅と周期(周波数)についてです。まず右図をご覧ください。「振幅」は波の高さを表します。次に周期ですが右図の矢印内の期間を「一周期」といいます(周期=1/周波数)。そして一周期内の波の位置を、「位相」と言います。 これら三つは変調を理解する上で極めて重要な要素です。特に位相は角度で表され、一周期のスタート点を 0゜とし、最後の部分を 360゜として扱います。 また、掲載している図解は文字入れ以外、ほとんど手書きのため、多少正確さを欠くことを予めご了承ください。 |
搬送波とスペクトラム(占有帯域幅について) 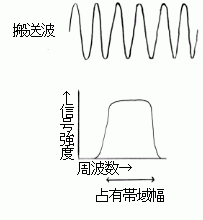 参考程度に知っておいていただきたいのが、搬送波と占有帯域幅についてです。 参考程度に知っておいていただきたいのが、搬送波と占有帯域幅についてです。搬送波とは情報を載せる前、すなわち変調前の信号を差し位相も振幅もそろった正弦波を用います(例えば 800MHz なら 1 秒間に 8 億周期の正弦波となります)。 そしてこれが増幅されて電力としてアンテナに乗り、電波となって空中へ伝搬していく源となるのです。 次に図中下部のグラフをご覧ください。これは縦軸に信号の強さ、横軸に周波数をとったもので通常スペクトラムと呼ばれます。 そしてこのスペクトラムの横幅を占有帯域幅と言い、ベースバンド信号(伝送すべき元の情報)により変調された信号は変調方式に応じ、必ずある幅をもちます。例えば、身近な例を挙げると PDC 方式の携帯電話ではおおよそ 50KHz、PHS では 240KHz あまりの幅があります(アナログ変調でも同様に占有帯域幅がある)。 さらにスペクトラム拡散方式を用いる 3G(第三世代)携帯電話では、1MHz ないし 1.25MHz もの幅に広げて通信を行います(音声通話時)。従来は占有帯域幅を狭めて(狭帯域変調方式)、単位周波数あたりの利用効率を高める、ということが積極的に行われていました。 しかし、発想の逆転で非常に広い帯域を使うかわりに、CDMA(符号分割多重)という技術を用いることで、その帯域を複数のユーザーで共有する、ということを行っています。 |
アナログ変調(AM と FM) 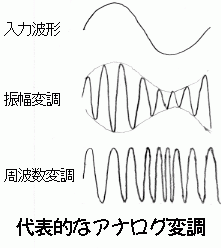 もっとも直感的に理解しやすいのが、振幅変調(AM:Amplitudemodulation)でしょう。入力波形(音声)と、変調された搬送波の振幅が、一対一(正確には相似)で対応しているからです。 もっとも直感的に理解しやすいのが、振幅変調(AM:Amplitudemodulation)でしょう。入力波形(音声)と、変調された搬送波の振幅が、一対一(正確には相似)で対応しているからです。また、振幅変調の波形上下頂点を結んだ線を包絡線といいます。この図ではわかりやすくするために便宜的に書いているだけで、実際の波形には包絡線はありません(^_^;)。 この方式は比較的歴史も古く、一番身近なところでは AM ラジオ放送が、その他代表的なところでは V・UHF 航空無線が該当します。 AM は原理上、送受信機の構成がシンプルに出来る、ある程度混信しても内容が聞き取れる、というメリットがある反面あまり音質は良くありませんし、ノイズに弱いという欠点があります。 また、地上波アナログテレビの映像信号も、AM 変調されています。しかしそのままでは帯域が広くなりすぎるので、スペクトラム成分のうち下側波帯(搬送波より周波数の低い側のスペクトラム成分)を一部カットして伝送されています(VSB-AM=残留側波帯振幅変調)。 さらにこの側波帯の上下いずれか片方と、搬送波を両方ともカットしたものが SSB(Single Side Band)です。回路は複雑になりますが、この方式は音声が乗ったときにしか電波が出ないので、より少ない電力で遠距離通信ができるメリットがあります。 この方式はアマチュア無線や船舶関係、短波帯の航空機洋上管制などに使用されています。また両側波帯ではあるものの、搬送波のみを抑圧したものもあり(電波形式では A3H)など歴史が長いせいか、バラエティが豊です。 続いて周波数変調(FM:Frequecncy modulation)ですが、これは入力に応じて搬送波の周波数を変化させる方式で、やはりベースバンド信号と周波数変化には相似の関係にありますす。 この方式では振幅は一定なので、周波数の変化だけが解ればもとの信号を取り出せます。ですからもしノイズが乗ってしまっても、リミッターで振幅ノイズ成分は除去できますので、比較的雑音に強いのが特徴です。 また、変調に伴う周波数変化を大きめにとれば、裸のダイナミックレンジ(信号の強弱の幅)と S/N 比はよくなり、かなりの高音質で信号を伝送できます。FM ラジオ放送や、ライブステージ等で使用される、ワイヤレスマイクの音質がよいのはこのためです。 変調に伴う周波数の変化を周波数偏移といい、FM では音質や占有帯域幅を決める重要な要素です。たとえば、同じ FM 方式でもテレビより FM ラジオの方が高音質なのは、周波数偏移が多く占有帯域幅が広いためです。 |
信号のデジタル化 デジタル変調の解説に入る前に、信号のデジタル化(A-D 変換)について、簡単にふれておきます。おそらく、このページに訪れる方の大半?は、この程度のことはご存知だと思うので、不要な方は読み飛ばしてください(^_^;)。 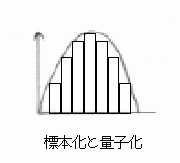 まず右図をご覧ください。アナログ−デジタル変換には、大まかに分けていくつかの手順があります。最初に連続的な波形を、図の棒グラフの様に一定間隔で区切ります。 まず右図をご覧ください。アナログ−デジタル変換には、大まかに分けていくつかの手順があります。最初に連続的な波形を、図の棒グラフの様に一定間隔で区切ります。これを標本化といい、伝送をしたい最高周波数の 2 倍で標本化すれば、もとの信号を再現できることになっています。これが、有名なサンプリング(標本化)定理です。 例えば電話の場合、4KHz 程度の帯域が再現できればよいので、8KHz というサンプリング周波数が良く用いられます。ですからサンプリング周波数を高くとれば、より高い周波数の信号まで再現できることになります(CD=44.1KHz)。 次に棒グラフの縦軸、この値はまだアナログ値であり、波形のある瞬間ごとの値を切り取ったものに過ぎません。ですから、これをある決まったステップ(量子化ステップ)でまるめ、近似します。 具体的には振幅の最大値を 2V として、8 ビットで量子化した場合を例に挙げると、1 ステップは約 7.8mV ですからこの量子化ステップの整数倍で近似することになります。これを量子化といい例えれば、もともと連続的ななめらかな波形を、階段状にしていくのに似ています。 この階段一段あたりの、踏みしろの幅が標本化間隔、その高さが量子化ステップの整数倍になります。そしてこの 1 サンプルごとの値を、二進数化することでようやく信号がデジタル化されたことになり、これを符号化といいます(8bit 例:123=01111011)。 ただし実際の 8bit システムでは量子化誤差が大きいため、用途によってはリニアスケールでないこともありその場合、ちょっとした工夫が凝らされているものがあります。 例えば音声伝送に利用される符号化方式では、量子化誤差の目立ちやすい小振幅時にはステップ幅を狭め、逆に量子化誤差の目立ちにくい大振幅時に荒く、という操作で見かけ上の品質を保っています(耳のマスキング効果を利用している)。 DVD/BD などの音声トラックにおいてわざわざ PCM を、「L-PCM」(リニアすなわち、直線量子化ステップの PCM)と表記することがあるのは、きちんとした意味があるのです。 この量子化ステップ数は、8 ビットで量子化した場合 2^8=256 なので、256 ステップとなります。この量子化ビット数を大きくとれば、ダイナミックレンジと S/N 比は高くなります(CD=16bit=65536 ステップ)。 ここまでを全てまとめると、デジタル信号の基本特性は標本化間隔が時間分解能を、量子化ビット数が振幅の分解能を決めると言えます。 実際には多くの場合、符号化された先の二値データは必要に応じて高効率圧縮符号化(コーデック)が適用されます。また必ずいかなるシステムにおいても、ある決まったデータ単位ごとに(フレーム)、エラー分散のためのシャッフリング、エラー検出および訂正のための符号付加等が行われた後に、ようやく変調されます。 |
ASK ASK(Amplitude shift keying)は、実際の無線通信にあまり用いられることはありませんが、一番簡単なデジタル変調方式です。 この変調方式では入力波形(ベースバンド波形)に応じて、搬送波を断続(振幅変化でも構わない)するような操作を行います。これは例えると無線でのモールス通信に似ている、と言えるでしょう。 あの大ヒット映画「タイタニック」で、船の通信士が遭難信号を打っていたアレです(^_^;)。ただ、当時最初に使用されたのは SOS ではなく、CQD(Come quick distress)という、遭難・救助求むを意味する語呂合わせだったそうで、最初に CQD を打ちその後に SOS を使ったと言われています。 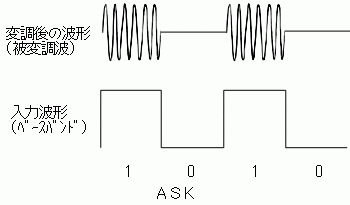 ベースバンド波形は、デジタル信号の 0 と
1 を、単純に二値波形に置き換えたものです。 ベースバンド波形は、デジタル信号の 0 と
1 を、単純に二値波形に置き換えたものです。ASK は回路構成がとても単純になる反面、実際の通信では受信レベル変動や、ノイズに弱いため誤り率が悪い、という難点があります。 モールスでしたら信号を聞き分けるのは人間の耳と脳ですので、訓練されていればそれなりのノイズやフェージングの中からでも、モールス符号を受信することは出来ます。また、使用するのはキャリア成分のみでよいので、狭帯域で急激な減衰特性を持つフィルタを通すことで、さらに了解度を上げることができます(まさにアナログならでは!?=人間デコーダ?)。 しかし ASK の受信では、受信波形の振幅をあるしきい値をもって、0 と 1 を判定するので受信信号のレベルが変わる(振幅変動)と、まこと都合が悪いわけです。実際に ASK が使用されているものをあげると、身近なとろこでは電波時計に利用される、JJY(長波帯標準電波局・単純な搬送波の断続ではなく振幅変化を利用している)や有名な国産 PDA ザウルスの赤外線通信ポートがあります。 近年では時々バグることで有名?な、ETC も ASK の範ちゅうです。 |
FSK FSK(Frequency shift keying)は、ベースバンド波形(0と1)に応じて搬送波周波数を、変化させる変調方式です。 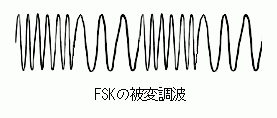 ベースバンド信号に応じ搬送波周波数を変化させる、という意味においてはアナログ変調での
FM に類似する概念といえるでしょう。 ベースバンド信号に応じ搬送波周波数を変化させる、という意味においてはアナログ変調での
FM に類似する概念といえるでしょう。しかし連続的変化だったアナログの FM とは異なり、FSK はあくまで 0 か 1 かの 2 値信号(離散したベースバンド信号)を用いて変調を行うのがポイントで、被変調波も右図のようになります。 FSK では伝送速度が上がるにつれて占有帯域幅が広がってしまう、という特性があるため高速通信には向きませんが、比較的送受信機の構成はシンプルに出来ます。 また ASK と違い周波数の変化として、変調されているため振幅は一定です。そのため受信側での 0・1 の判定が波形の振幅に依存しないので、移動体通信にも容易に適用できます。 更に被変調波の振幅が一定のため、電力増幅器の非直線性の影響が少なく、電力利用効率がよいというメリットがあります。 代表的な例として FSK は国内のポケットベルに採用されていましたし、近距離ワイヤレス技術として国内でも普及のめざましい Bluetooth にも FSK が用いられています。またヨーロッパのデジタル・コードレスホン規格である、CT-2 等に採用されているのが MSK です。 MSK(Minimum shift keying) は FSK の一種で、FSK の周波数偏移を最小にしたものといえるでしょう(正確には変調指数、つまり最大周波数偏移の2倍と信号速度の比率が 0.5 となる FSK)。 この方式は、CT-2 以外では DECT、CS-PCM 音声放送や欧州規格の携帯電話 GSM、FM 文字多重放送等に採用されています。 |
PSK 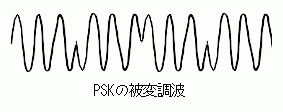 PSK(Phase shift keying)は搬送波の位相をある決まった位置で、変化させる変調方式です。右図ではベースバンド波形に応じて(0・1
の変化点)、位相の変化する様子が解ると思います。 PSK(Phase shift keying)は搬送波の位相をある決まった位置で、変化させる変調方式です。右図ではベースバンド波形に応じて(0・1
の変化点)、位相の変化する様子が解ると思います。図ではちょうど 0゜と 180゜の二点の位相変化を利用することからこれを特に BPSK(Binaly PSK)といいますが、実際の移動体通信に適用されることはあまりありません。 BPSK の代表的な例として GPS があげられます。スペクトラム拡散方式を使用いてはいますが、拡散前のデータ変調(一次変調という)に低速の BPSK(50bps)が用いられているのです。 コンスタレーションは横を I 軸 =cos・同相成分、縦を Q 軸 =sin・直交位相成分として表した、極座標系表現です。(コンスタレーション図をスペース・ダイヤグラム、ということもあります) BPSK では搬送波の位相に 2 値をとるので、図では 180 度異なる位相をもった 2 つの信号点が現れているのが解るでしょう。 ただしこれは位相偏移で表した場合(以降 QPSK でも同様に表しています)を示しているので、π/2(90゜)だけことなり Q 軸上に信号点が現れているのがポイントです。 図では位相は右回りに回転していくように表します(800MHz ならば 8 億回転となる)。また Q・I 軸の交差する原点から外へ向かっての距離が、振幅成分を表しており PSK では位相のみの変化(振幅は一定)を利用しているので、それぞれの信号点は必ず円周上に出現します。 それを構成する回路は複雑になりますが他の変調方式に比べて、一度に送れる情報量が増える(信号点すなわち位相が 4 通りなので、一度に 2 ビットずつ)ため、BPSK と比較して周波数利用効率は良くなります。 QPSK は PDC 方式携帯電話や PHS、CS デジタル放送など非常に多くの伝送方式に使われています(厳密に言うと細かい違いがありますが)。 また更に位相差を小さくした 8 相PSK というものもあり、BS デジタル放送に使用されています。 |
QAM QAM(Quadrature amplitude modulation)は、搬送波の位相と振幅の両方に情報を載せる変調方式です。 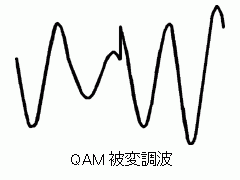 QAM のうち移動体通信で最もよく使用されるのが 16QAM(16値QAM)と言って良いでしょう。 QAM のうち移動体通信で最もよく使用されるのが 16QAM(16値QAM)と言って良いでしょう。16QAM の伝送波形例を右図に示します。右図の波形は変調されたデータが 1100/1101/1001/1000 のときで、実際には 16 種(※)あります。このため一周期ごとの波形も 16 種のうちいずれかが、データ列と一対一で対応して並んだものとなります。 ※データ列は 0000〜1111 の16 通りとなる 少なくとも波形図から波の高さ(振幅)が 3 種類あるだろうこと、波がいびつな形状になっているところなど(位相)が読みとれるのではないでしょうか。これらを踏まえた上で詳細を解説します。 変調には直交した搬送波(90゚ 異なる位相を持つという意味)にそれぞれ 4 値の振幅変調をかけこれらを合成して、振幅(3 種)と位相(12 種)両方に段階的変化を持つ信号を得ています。 このように作られた変調信号は振幅 3 値・位相 12 値なので、下図(コンスタレーション)のように碁盤の目状に縦 4 点×横 4 点、合計 16 個の信号点(シンボル)が発生することになります。 従って 16 通りの状態(二進数で 0000〜1111)のうちから 1 つを表すことができるため、一度に 4bit 分の情報が送れる方式となっています。 ※図の信号点それぞれに二進数の 0000〜1111 を一対一で割り当てる QAM の特徴は QPSK と比較し同じ帯域幅では、2 倍の伝送速度を得ることが出来るという点があげられますが、やはり位相と振幅の両方を利用しているからに他なりません。 言い換えれば単位周波数あたりの利用効率に優た方式である、と言うことができるでしょう。 しかしながら QAM では振幅も利用しているためフェージングには弱く、誤り率も悪いという難点があります。そのため QPSK と同じ性能を実現するには、約十倍の送信電力が必要になってしまうのです。 また移動体通信に適用する場合には、波形等化などが必須となってきます。代表的な 16QAM は古くからデジタル MCA(業務用無線)に、近年では 3G 携帯電話の高速データ伝送方式である HDR や HSDPA の変調方式として利用されています。 他の身近なところでは、'03-12 月に始まった地上波デジタル・テレビ放送用としても使われており(移動向 16QAM・固定向 64QAM)、NTT 等の固定対固定マイクロ波多重中継には、更に多値となる 256QAM が利用されています。 |
OFDM 最後に変調方式そのものではありませんが、近年 Wi-Fi や地デジはもとより LTE の下り信号など多用されるようになってきた OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)、直交周波数分割多重についてごく簡単に概念的な解説をしておきたいと思います。 |
※当サイト「3G-LTE の概要」の記事でも触れていますがより簡単にということで^ ^; もちろん、スペクトラム・キャリアごとに”脚“はありません♪ |
OFDM とは隣接する狭帯域変調スペクトラム同士で互いに干渉しないよう、びっしりとサブキャリアが並べられた特殊な状態を指します。 厳密には異なりますが「○人●脚」風イラスト図のような感じをイメージしていただければ、少しは解りやすくなるのではないでしょうか。 通常の周波数分割多重では干渉してしまうため、サブキャリア同士を密に並べることも出来ませんし、ましてや○人●脚のように肩まで並べてびっしりとサブキャリアを敷き詰めることなど、到底不可能です(通常、ガードバンドというスペクトラム同士のすき間も必須)。 それが OFDM のようにサブキャリア同士が直交(互いに干渉しない特殊な状態)した状態である、という条件により一部が重なるような高密度のスペクトラム配置を可能にしているのです。 ○人●脚でも通常では人同士がぶつかり合って、うまく歩けないような間隔でもお互いの息をと歩調を合わせ、腕や肩を組むことによりピッタリとくっついたまま移動が可能になりますが、これとなんとなく似ています!?(例えとしてあやしい、かもしれないが…)。 3G-LTE の記事とも重複しますが、あるサブキャリアのピークに着目した場合それぞれ隣接するサブキャリア成分が、ゼロになる状態(直交の条件)というのがポイントでしょう。 しつこいようですが OFDM は多重方式の一種であり、変調方式ではありませんが地デジへの完全移行が完了したことや、LTE(Wi-MAX/AXGP を含む)の全国的な整備・対応端末機の普及に伴い、同方式がより身近になってきたことから例外的に取り扱いました。 とくに LTE 等通信系サービスでは下り信号に OFDM を用いた、多元接続方式となる OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access)が採用されており近年では欠くことのできない無線技術である、との判断によります。 |
終わりに 変調方式は、その伝送路特性やニーズに応じて使い分けがなされています。それはまさに適材適所、という言葉がふさわしいでしょう。またデジタル・アナログ変調ともに、ここで紹介した以外にもいくつかの種類が活躍しています。 |