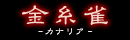 <09> ―――お家忘れた 子ひばりは 広い畑の 麦の中 母さんたずねて ないたけど 風に穂麦が 鳴るばかり――― 「エドワード、お客さんだよ」 黒髪の女主人からの声に、エドワードは首を傾げた。 ロイが来る時は、いつも護衛についている金髪の彼の姿が見えなかったからだ。 彼が格子越しに顔を見せて、簡単な会話を交わしてから、ロイがやって来た事を 告げる女将の声が聞こえるのが、いつもの習慣だったのに。 「…あれぇ…?」 格子から外を覗くと、門から離れた向かいの路地に、少尉と同じ軍服を着た軍人の 姿が見える。 少し恰幅の良いその姿に、少尉とは違う人なのだと理解した。 「…詰まんないの」 無意識のうちに頬を軽く膨らませ、ロイの待つ部屋へと足を運んだ。 「…どうしたんだい?今日はご機嫌ななめじゃないか」 ロイの指が、エドワードの髪を撫でる。 ――行為を終えた後の、ロイのいつもの癖だ。 「そんな事無いよ」 けだるい体で寝返りを打ち、エドワードはロイに背を向けた。 背後から抱き締めるロイが、小さく溜め息を漏らす。 「…昨日から、ちょっと体調が良くなくて…それで、かも……」 ロイを落胆させたくなくて、エドワードは咄嗟にそんな嘘をついた。 「…そう言う事なら、早く言いなさい。無茶をさせて悪かったね…」 ロイの指が、エドワードの髪を優しく撫でる。 その優しさが後ろめたくて、エドワードの胸がちくりと痛んだ。 「ロイ、ごめんね」 ころん、と再び寝返りを打ち、ロイの胸に顔を埋めて小さく呟く。 「気にせずに、ゆっくり休みなさい」 柔らかなロイの唇が、エドワードの額に降りてくる。 ――ちくり。 エドワードの胸が、また小さく疼いた。 「……ごめん、ね」 何に対して謝っているのか。 それは、エドワードにも解らない。 ――こんなに、ロイには良くしてもらっているのに。 ロイが去った後、薄暗い部屋の中で、エドワードは灯りも点けずにぼんやりと外を 眺めていた。 空には満点の星と、猫の瞳のように細い三日月。 「…お喋り…したかったのにな…」 ぽつりと呟いて、抽斗の中にしまっていたビー玉を取り出して、手のひらで弄ぶ。 それは夏祭りのあったあの日、少尉から贈られたもの。 『良いから、手ぇ出せ』 手渡された瞬間に、自分の掌を包み込んだ彼の温もりが、今も鮮明に思い出される。 ごつごつした、大きな手。 照れ隠しに帽子を深く被って、耳まで赤く染めていた姿を思い出し、エドワードは 口元を思わず緩めた。 ――あの時の顔は、ちょっと可愛いかったな―― ビー玉を床に散りばめ、指先でパチンと弾く。 ガラスが触れ合う軽やかな音が、エドワードの胸に心地よく響いた。 「会いたかった…な」 口をついて出た、本音。 今迄は、格子の外に少尉の姿を見つけると、ロイが自分に会いに来た事が解って 嬉しくなった。 いつからだろう。 それが逆になったのは。 ロイが自分に会いに来てくれる事は勿論嬉しい。 それは今でも変わらない。 ――いつから、だろう。 少尉が護衛で付いて来る事を楽しみにして、ロイが訪れるのを待つようになったのは。 少尉と格子越しに交わす他愛の無い会話のやりとりが、何よりも楽しかったのだ。 「なんで…だろ…」 第一印象は、嫌な奴だと思った。 からかい半分で声を掛けたら、反対にからかわれて。 会うたびに、お互いに一言ずつ嫌味を言い合って。 人を馬鹿にしたように煩いだの何だのと。 なのに、何故か彼の事を嫌いにはなれなかった。 ――それは、きっと優しかったから。 彼の声が、瞳が、指が、とても優しかったから。 「もう…来ないのかな…」 それも良いか、とエドワードは呟いて布団の上に横になった。 枕元にビー玉を置いて、それを眺める。 「だって…オレは…」 自分はロイに囲われている身。 しかもロイは、少尉の直属の上官だ。 自分はロイを裏切る事も、少尉にロイを裏切らせる事も、出来ない。 そして、こんなに自分に親身なってくれているロイを、悲しませたくは無い。 だから、このまま会えないのなら、その方が良い。 「…寝よ…」 ころん、と寝返りを打つ。 瞳を閉じても、なかなか眠りにつけそうになかった。 「……やっぱり…会いたい……な……」 瞳を閉じて浮かんでくるのは、ロイではなく碧い瞳。 どうしよう。 ――胸が、痛いよ―― 数日後。 エドワードがビー玉を指で転がしながら、格子の外をぼんやりと眺めていると、 見慣れた姿がそこにあった。 「よぉ」 軍服ではなく、私服の上着を肩に掛けたハボックが、格子から顔を覗かせていた。 返事を寄越さないエドワードを訝しって、ハボックは再び声を掛けた。 「おい、そこの小さいの」 「小さいって言うな!!」 エドワードは『小さい』と言う単語に咄嗟に反応し、格子を掴んでハボックに喰って 掛かった。 最初、呆気に取られた顔をしていたハボックは、エドワードの顔を暫らく眺めていたが、 ぷっ、と吹き出すと腹を抱えて笑いだした。 「…はははははっ!!反応早ぇなあ〜!!」 「わ、笑うな!なんだよ!いきなり顔見せたと思ったら、いきなり馬鹿にしやがって!」 顔を真っ赤にして反論するエドワードに、ハボックは『悪い悪い』と苦笑を浮かべると、 煙草を取り出して火を点けた。 「最近、来なかったから…護衛…クビになったのかと思った」 エドワードは精一杯の強がりで笑顔を作り、平静を装う。 ハボックは『いや』と首を横に振り、短くなった煙草を地面に落として足で踏み消した。 「久しぶりにまとまった休暇が取れたから、田舎に帰ってたんだよ。 で、さっき戻って来たってワケだ」 いつものようにハボックが格子に背を預けて、汽車に揺られて疲れたのか、腕を天に 向かって伸ばしながら、大きな欠伸を一つついた。 「少尉の故郷って、どんなトコ?」 盛大な欠伸に思わず笑いながら、エドワードは畳の上にぺたりと座る。 …こうすると、中二階にあるこの部屋でも、ハボックと同じ目線の高さになるのだ。 「…田舎だよ。田んぼと山と川しかない。…でも、のどかで良い所だと、俺は思ってる」 柔らかい表情で微笑うハボックの横顔に、エドワードの胸が、とくんと鳴った。 ――こんな顔、するんだ―― それは、今まで見た事が無いほどに、優しくて、穏やかで。 「…少尉の故郷、行ってみたいな」 枕元に転がしたままのビー玉を、指先で弄ぶ。 「連れて行ってよ。少尉」 その言葉に、ハボックがゆっくりと体を振り向かせ、正面からエドワードの顔を真直ぐに 見つめた。 心地良い風が、二人の間を吹き抜ける。 「……ああ」 碧い瞳が、エドワードの琥珀の瞳を捉える。 海のような、穏やかで優しい瞳。 「連れてってやるよ。お前が本当に望むなら」 ――どこにだって、連れてってやるよ―― それだけ告げると、ハボックは『じゃあな』と言い残して、暑い日差しが照りつける中を 去って行った。 「…オレが……望むなら……」 エドワードは暫らく畳の上に座り込んだまま、動く事ができなかった。 ――お前が望むなら、どこにだって連れてってやるよ―― 行きたいよ。 少尉と行きたいよ。 今すぐ此処から逃げ出して、貴方と一緒に、誰も知らない遠くまで。 だけど、オレは籠の中の鳥だから。 ――翼はあるのに、どこにも行けない鳥だから―― |