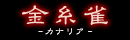 <10> ―――赤い鳥 小鳥 何故 何故 赤い 赤い実を食べた――― …ぱちり。 ……ころころ……。 …かつり。 小声で歌を口ずさみながらエドワードがビー玉を弾く。 弾いたビー玉が、朱格子にぶつかり、小さく音を立てた。 ―――ぴちゅ、ぴちゅ、……。 その音に驚いた金糸雀が、高い声で囀る。 「またそれで遊んでんのか?」 格子の向こう側から聞こえた声に、エドワードは顔を上げた。 「…少尉」 既に見馴れた男の姿に、エドワードはふわりと花が咲くように微笑む。 ―――そんな顔して、微笑うなよ。 ハボックはエドワードの笑顔を見て、微かに眉を顰める。 ―――その笑顔が、自分の物では無い事を知っているから。 ちくりとした胸の痛みを打ち消す様に、ハボックはポケットから煙草を取り出して咥えた。 「ねぇ少尉。小鳥は赤い実を食べたから赤くなったんじゃなくて、赤い実の色に 食われたんだと思わない?」 ―――オレが誰かの色に染められてしまって、もう元には戻らないみたいに。 ふとエドワードはビー玉を弾く手を止め、ハボックの顔をその琥珀の瞳でじっと見つめ、 そう問い掛ける。 「…エドワード」 ハボックはそれには答えず、低い声でエドワードを呼んだ。 「何?」 エドワードは格子に額を付けると、小首を傾げる。 さらりと零れた長い前髪が、格子の朱に映えた。 ハボックはそっと、その髪に触れる。 微かに、エドワードの頬が桜色に染まった。 「…また、遊んで欲しいの?」 ―――この気持ちを悟られてはいけない。 この関係を、壊しちゃいけない。 エドワードは業とらしく艶然とした笑みを作って、悪戯っぽく小指を差し出す。 「……」 と、不意にハボックが、その手を荒々しく掴んで引き寄せる。 「……ッ」 しゃらりと音がして、エドワードの髪から紅い簪が落ちた。 掴まれた手の痛みにエドワードは眉を顰める。 困った様にハボックを見つめたエドワードは、怖い程に真剣なその瞳に思わず 言葉を失う。 「……遊びじゃ、ねぇよ」 …ハボックの、血を吐くような、苦々しい声。 「……そんないい加減な気持ちで、お前を抱いたりなんかしねぇよ」 「…小…尉…」 エドワードが困惑した表情を浮かべる。 僅かの間、二人は黙ったまま見つめ合った。 ……そして。 「…ごめんね、少尉」 エドワードが小さな声で謝った。 「オレは、あの人のモノだから」 どこか哀しげに、エドワードがそう、呟く。 「オレはあの人が好きで、あの人もオレが好き。だから、少尉とは行けない。 …………解るだろ」 エドワードが瞳を伏せる。 「…連れてけって言ったのは、お前だろ」 それは、あの日の他愛も無い、約束。 「……」 エドワードは瞳を伏せたまま、沈黙する。 「…それがお前の本心か?」 ハボックが低く問うた。 エドワードは、一瞬躊躇う表情を見せたが、やがてゆっくりと頷く。 それを見て、徐々にハボックの指から力が抜けていった。 やがて、二人を繋ぐ手は静かに離れた。 「…エドワード」 ハボックが、掠れた声で想い人の名を紡ぐ。 が、エドワードはそれに答えず、くるりと背を向け何故かその場に屈み込んだ。 「…簪、折れちゃったな…」 エドワードは独言のようにそう呟くと、不意にぱん、と両の手を合わせる。 その行為にハボックが驚く間も無く、エドワードは合わせた手を開いて そっと簪に翳した。 簪を、淡い薄蒼の光が包む。 「ホントは、もう錬金術使っちゃいけないってロイに言われてるんだけど」 そう言ってエドワードは完全に復元された簪を髪に刺し、苦笑した。 「…もう、行かなきゃ。ロイが待ってる」 エドワードはぎこち無い笑顔でハボックに笑いかけ、紅い裾を翻す。 その姿が奥に消える前、エドワードが小さな声で呟いた。 「……金糸雀、戻って来ちゃったね。 やっぱり、一度飼われてしまうと、二度と空には帰れないのかもしれない」 部屋の片隅で、自分の事を言われていると気付いたのか、金糸雀がぴちゅぴちゅと囀る。 「……かもな」 ハボックの言葉に、エドワードが一瞬顔を歪める。 ―――まるで、泣きたいのを堪えるみたいに。 しかしエドワードは踵を返すと、今度こそ立ち止まる事無く奥へと姿を消した。 「…ふ…ァッ」 吐息が熱い。 この人に触れられるのはどの位振りだろう。 馴れた優しい指が、確実に自分を高みに導いてゆく。 ―――そういえば、…… 高揚する意識の片隅で、ふと別の男の指の感触を思い出す。 …もっと、ずっと、荒っぽくて…貪るような。 自分の情人と全く違う掌の感触。口付ける仕草。 「…エドワード?」 『…エドワード』 ロイの声に、蒼い目の男の声が重なる。 その甘さに、思わず躯を大きく震わせた。 「…うわの空だな」 不意にロイに冷めた声でそう囁かれ、驚いて閉じていた瞳を開く。 …怒りと、悲しみを含んだ、漆黒の瞳。 「…ロイ…ッ!」 何か言おうと開いた唇は、強引にロイに塞がれる。 「…ん…っ…ふ…ぅ…」 くぐもる息の合間に、潤んだ琥珀でロイを見つめる。 「……ッ」 不意に唇に痛みが走る。 噛まれたのだと気付いたのは、そこを舐めたロイの唇に微かに血の色が滲んで いたからだった。 ぺろりと、ロイが血の痕を舐め取り、そして耳元で囁く。 「この可愛い嘴で、何を強請った?」 その言葉に、大きく目を見開く。 「違…っ…そんな事…ッ」 反駁の言葉は、再び訪れた荒々しい接吻にかき消される。 その後は、ただ、無言で何度も絶頂まで追いやられる。 「…ロイ…っ…ロイ…」 意識は朦朧として、ただ情人の名と「違う」という否定の言葉を譫言のように繰り返す。 「……ッ!!」 仰け反った白い喉に唇が触れて、きつく吸われる。 息が止まるようなその感覚に、瞳からはぽろぽろと涙が零れた。 ―――与えられる、蕩けるような甘い快楽。 思い出す、魂ごと引き寄せられるような力強い、愛撫。 …そして、意識を完全に手放しかけた、その刹那。 漆黒の瞳が切なげに何かを囁いたのが聞こえた。 ―――君は、私のものだよ。決して、誰にも、渡さない。 意識を失ってしまった小さい躯を軽く身繕っていつもの部屋に運ぶ。 格子の向こうには見慣れた己の部下の姿。 それには声を掛けず、格子に背を向ける。 落とした視線の先には、朱塗りの鳥籠に入った金糸雀と、いくつかの硝子玉。 ―――その硝子玉は、自分以外の男が贈った物。 店に入った時、ちらりとエドワードが格子越しにハボックと手を取り合っていたのを見た。 この硝子玉は、きっと彼から貰ったのだろう。 そんな二人を見ているのが辛くてすぐにその場を立ち去った。 こんなにも自分があの子供に執着してるのだと気付いた。 硝子玉から視線を戻し、黙って部屋を出る。 店を出て格子の下に行くと、ハボックは咥えていた煙草を地面に落とし足で消した。 「…随分と長い逢瀬で」 ハボックが軽口を叩いて肩を竦める。 「…さすがに今日はやりすぎたと後悔している」 唇に自嘲的な笑みが浮かんだ。 「では、帰りますかね」 歩き出そうとしたハボックを、その場に視線で縫い止める。 「大佐…」 ハボックの口元から、笑みが消えた。 「…ハボック、お前、エドワードを、」 ―――抱いたのか。 そう問おうとした、その瞬間。 ―――ダァーーーン…… 店の方から、鈍い銃声が響いた。 |