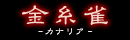 <11> ――行きはよいよい 帰りはこわい こわいながらも通りゃんせ 通りゃんせ―― 突如として夜の闇をつんざいた銃声に、ハボックとロイは顔を見合わせ、 店の中に土足で上がり込んだ。 確かに部屋の中から聞こえた銃声に、二人の顔が青褪める。 「エドワード!!」 逃げ惑う客達を押し退け、二人がエドワードの部屋に辿り着くと、そこには 銃口をエドワードに向けた、宿屋の女主人の姿があった。 「やっと確信が持てたわ…錬金術師の坊や…」 黒い着物を身に纏うその姿は、死者を地獄へ誘う案内人のようだった。 緩くウェーブの掛かった漆黒の髪を揺らして、ゆっくりと二人を見据える。 その瞳は、獲物を捕らえる蛇に似ていた。 「あら…戻ってきてしまったのね…」 着物から覗く胸元には、ウロボロスの入れ墨。 「ロイ!来ちゃダメだ!!」 エドワードは部屋に飛び込んできた二人に向かって咄嗟に叫ぶ。 「…この…っ!」 ハボックが懐から拳銃を取り出し威嚇射撃を試みるのと、ロイが発火布の 手袋を装着し、女に向かって火花を作り出すのは、ほぼ同時だった。 ドン! 大気中の空気が、女を中心に燃え上がる。 煙が起こり、視界が白く霞む中、ハボックがエドワードに駆け寄り、その腕を取って 自分の胸に引き寄せた。 「エドワード、無事か?」 「うん、弾は当たってない…っ」 ハボックはエドワードを背に庇いながら、女主人に銃口を向けて牽制したまま、 ロイの元に歩み寄る。 不意に火柱の中から、女の声がした。 「…その子、大切な人柱なのよ」 炎が、消える。 黒焦げになっているはずの女主人は火傷一つ負わずに、その口元に妖艶な笑みを 浮かべていた。 「…バケモンかよ…」 ハボックが苦笑を浮かべながら、引き金に掛けた指先に力を込める。 「失礼ね。一応呼び名はあるのよ」 ニッ、と唇の端を持ち上げて女が笑う。 『ラスト』とその紅い唇が動いた瞬間、ロイの放った火炎と、ハボックの銃口から放った 弾丸がラストに襲い掛かる。 二度、三度、ラストの体が衝撃を受けてよろめいた。 すかさずハボックが踏み込み、腹に掌底を喰らわせる。 ぐうっ、とうめいて体を二つに折るラストの背中に、容赦無く肘を叩き込んだ。 続けて腕を逆に捕らえて関節を捻り、ラストの体を床にねじ伏せる。 「お前の目的は何だ?何故この子を付け狙う?」 床に這いつくばるラストを冷ややかに見下ろし、ロイが問う。 「……その子が、優秀な錬金術師だからよ」 ラストに取って不利な形勢にも関わらず、その口元には相変わらず妖艶な微笑が 湛えられていた。 「何故、その事を知っている?」 「つい、さっき…その子が錬金術を使う所を見たのよ。 用心深くて、なかなか尻尾を掴ませないから、大変だったのよ?」 その言葉に、ロイは咄嗟にエドワードを厳しい目で睨み付けた。 「あれほど…人前では使うなと言っただろう!」 エドワードの肩が、ぴくりと震える。 「だって………、ごめんなさい……」 何か反論しようとしたが、困ったように眉を寄せてエドワードは俯いた。 その寂しげな瞳の色に、ハボックの胸がずきんと痛む。 エドワードが大切な人から貰ったかんざしを壊してしまった原因は自分なのだ、と。 己の想いをエドワードに打ち明けてしまったが為に、こんな重大な事になってしまった。 悔しさに、唇を噛み締める。 「まだお前には聞きたい事がある。…一緒に軍の司令部まで来てもらおうか」 ロイが顎をクイと上げ、それに応じてハボックがラストの体を無理矢理立ち上がらせる。 廊下を歩きながら、ロイがハボックにぽつりと囁いた。 「まさか、飼い犬に手を噛まれるとはな…」 その声は冷たく研ぎ澄まされて、ハボックの胸に突き刺さる。 「どう言う、意味ですか」 ハボックは努めて冷静に受け答えたが、ラストの腕を握るハボックの指先に、無意識の うちに力がこもる。 「…いいや、特に他意は無い」 ロイがエドワードを抱き寄せた。それを視界の端に捉えて、ハボックは奥歯を噛み締める。 早く立ち去ってしまいたい気持ちを抑え、ラストを連行したまま店の門をくぐった。 銃声を聞き付けたのか、軍服を纏った五人の将校達が、花宿の門の前でロイ達をぐるりと 取り囲んだ。 「あらあら、お仲間が来たようね」 取り囲まれ、完全な劣勢にも関わらず、ラストは余裕の表情を浮かべていた。 「随分余裕だな、アンタ」 どこかいつもと違う緊迫した空気が、ハボックに軽口を叩かせる。 ――味方が応援に来たと言うのに、この違和感はどう言う事だ―― それを感じ取ったのはロイも同じだった。 何故、彼らの銃口はラストではなく自分達に向けられているのか。 冷たい汗が、ロイの頬を伝う。 「――だって――」 ニヤリ。 ラストが残虐な微笑みを浮かべる。 「彼らは私達の仲間ですもの」 その言葉と同時に、将校達の構える拳銃から一斉に火の手が上がる。 ハボックは瞬時にラストの体を前に突き飛ばし、反動を利用してロイとエドワードの 腕を取り、塀の後ろへと身を隠した。 ロイが塀から半身を乗り出し、炎を飛ばして牽制する。 その横で弾の補充をしていたハボックの右肩に、弾が掠めたのか血が滲んでいた。 「少尉、怪我してる…」 「ああ」 「オレの所為で…」 「馬鹿言ってんじゃねぇよ。まさか軍の上層部が一枚噛んでるとはな…」 ぽん、とエドワードの頭に手を置くと、柔らかい眼差しを向けた。 その優しい眼差しに、エドワードは戸惑いを覚える。 自分が欲しいと言った時と同じ、真剣で温かい――何処か、覚悟を秘めた碧の瞳。 「大佐と裏口から出て、逃げろ」 それだけ言うとハボックはロイと場所を入れ替え、ロイにも同様の事を告げた。 「…お前はどうするんだ」 ロイはエドワードの体を抱き寄せると、ハボックに問う。 しかし、ハボックの答えは、聞かなくても解るような気がしていた。 「俺は此処で食い止めますよ。護衛の相手に死なれたら、元も子も無いでしょ」 いつもと変わらぬ飄々とした口調で答えながら、ロイに言葉を返す。 「行ってください、大佐。……その子の事…頼みます」 「あとで必ず落ち合おう。……死ぬなよ」 ハボックの横顔に、微かに笑みが浮かぶ。 その横顔に彼の決意を察したロイは、エドワードの腕を掴んで裏口へと歩き出した。 「…嫌だ!少尉!……少尉ぃっ!!」 嫌がるエドワードの体をロイが無理矢理引き摺って、裏口へ続く通路へと姿を消した。 「通りゃんせ、か」 ダァン! ハボックの撃った弾が、一人の将校の体を貫く。 いつの間にか、ラストの姿は消えていた。 『通りゃんせ…ここはどこの細道じゃ…』 幼い頃好きだった女の子に、この歌を歌いながら道を塞いだ記憶が、ふと蘇る。 『意地悪しないで、通してよぉ…』 泣きべそをかいていたあの子は、今どうしているだろうか。 ダァン!! ハボックの銃が、再び火を吹いた。 「…行きはよいよい、帰りはこわい…」 ハボックの瞳の奥に、闘いの炎が静かに揺らめき、口元に酷薄な微笑が宿る。 「…アンタらさぁ」 ――通れるものなら通ってみろよ―― |