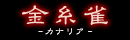 <14> ―――揺り籃の唄を 金糸雀が唄うよ――― せっかく逃がしたと言うのに。 そのまま行けば良かったのに。 逃がした筈の、可愛い小鳥。 「…少尉っ!!」 ――どうしてお前は、戻って来たんだ―― 「少尉!!」 エドワードが悲鳴をあげてハボックに駆け寄った。 ハボックの体は血塗れで、体から流れた血が軍服をどす黒い紅に染めている。 「しっかり…しっかりして…っ…」 エドワードは自分の着物の端を引き裂き、一番酷い右胸の傷に押し当て、止血を試みる。 しかし今更そんな行為に意味は無い事を、エドワードもハボックも知っていた。 「…も…良い…から……」 逆に傷口を押さえ付けられて苦しいからと、ハボックはエドワードの腕を力無く掴んで、 首を横にゆっくり振った。 エドワードが今にも泣きそうな顔をして、ハボックの体に縋り付く。 「嫌だ…嫌だよ……少尉…」 エドワードの体から伝わる温もりが心地良くて、ハボックの表情が和らいだ。 金色の長い髪を、ハボックは愛しげに何度も撫でる。 「…お前、さあ……」 エドワードの頬にこびりついている血痕を、指の腹で擦ってやると一段とエドワードの顔が 哀しげに歪んだ。 「…紅い…色、似合わねぇよ…」 ハボックはそう言って、懐からかんざしを取出し、エドワードの髪に差してやる。 夏祭りがあったあの日、ビー玉と一緒に渡そうと思って渡せずにいた贈り物。 ロイからかんざしを貰ったと言って喜んでいるエドワードを見たら、どうにも 渡せなかったのだ。 空のような碧色のガラス珠と銀細工で作られたかんざしは、戦闘の衝撃で中心の ガラス珠に亀裂が入ってしまっていた。 「…まだ…ガキなんだから、こう言う色の方が…似合うよ、お前…」 エドワードに紅が似合わないとは思っていない。 ただ、この子は紅を身に付けると、大人びた態度を取るような節があるのだ。 置かれている環境が環境なだけに、彼はそうならざるを得なかったのかも知れない。 ――本当は、子供のように笑えるのに―― 「…俺と居る時ぐらい、ガキのままで居ろよ」 真摯な眼差しで見つめ、エドワードの髪を撫でる。 こつり。 軍靴が石畳を叩く音が聞こえ、エドワードが咄嗟に振り返った。 「…此処に居たのか」 エドワードの背後から、ロイの声がした。 「…ロイ…っ」 エドワードが、小さくその名を呼ぶ。 ロイは一目ハボックを見ると、この傷ではどうする事も出来ない、と瞳を伏せた。 「……大、佐…」 ハボックが僅かに体を起こし、ロイに何かを伝えたいような視線を向ける。 ロイはハボックの隣に身を屈め、どうした、と低く問うた。 「…大…総統が…裏で…、だから…どうか…気を付けて…ください…」 途切れ途切れに、ハボックが言葉を紡ぐ。 ロイは頷いて応えると、ハボックの髪と頬を一度ずつ撫でた。 「ああ、解った。疲れただろう……少し、休め…」 それは、別れの挨拶だった。 ハボックが静かに頷くのを確認するとロイは立ち上がり、エドワードに告げる。 「私はやる事が残っている。……傍に…居てやりなさい」 くるりと背を向け、歩きだす。 二人から離れ、将校達の遺体を調べていたロイは、爆発で崩れた塀の瓦礫の中に 埋もれていたハボックの銃を見つけ、それをそっと拾いあげた。 「…馬鹿者が…」 銃身を手のひらで撫でながら、ぽつりと、ロイが呟く。 「…お前以外に、私の護衛が勤まると思うか…」 ロイは懐にハボックの銃をしまうと、再び将校達の遺体検分を再開した。 大切な部下を奪った連中を許す訳には行かない。 漆黒の瞳が、決意を秘めた鋭い眼差しに変わる。 「…ハボック…」 夜空に火の粉が舞う。 それは、戦友を弔う送り火のように、空高く昇っていった。 ぱち、ぱち…っ。 時折、木材のはぜる音がエドワードの耳に届く。 「少尉…」 微かに聞こえるハボックの呼吸が、徐々に小さく、擦れていった。 「少尉…嫌だよぉ…」 目を開けて居ることさえ辛いのか、閉じている事が多くなった目蓋を薄らと開け、 ハボックは碧色の瞳でエドワードに視線を向けた。 「…死んじゃ…嫌だよぉ……」 エドワードは涙が零れそうになるのを堪え、ハボックの掌を自分の頬に押し当てる。 「………だって…少尉はオレにいつも嫌味ばっか言って…、 意地悪な事ばっか言って……オレの事…からかってばかりでっ!!」 エドワードの語気が荒くなり、ハボックに縋りついてその肩を叩く。 「……っでも…っ!でも、楽しかったんだよ…!!少尉と話すの、楽しかった…。 少尉だけが、子供扱いしてくれたから…っ!」 エドワードの瞳から、涙が一筋零れ落ちる。 「嫌だよ…まだ少尉の名前だって…知らないのに…」 絞りだすように、エドワードが呟いた。 そう言えば、名前を教える機会が無かったなとハボックは考え、そっとエドワードの 耳元に唇を寄せて囁く。 「……教えてやらねーよ…」 悪戯っぽく笑いながら、エドワードの髪をといた。 ひくっ、とエドワードの肩が跳ね、今まで堪えていた両方の瞳から涙がぽろぽろと 零れ始める。 「どうして、そんな事言うんだよっ!教えろよ!」 エドワードは手の甲で涙を拭いながら、ハボックを睨み付けた。 しかしすぐに唇を歪ませ、ハボックの袖を軽くも引っ張って、何度もしゃくりあげ始める。 「…意地悪すんなよぉ……っ!!」 泣いて縋るエドワードと、幼い日の好きだった女の子との姿が重なる。 ――ああ、泣いちゃった―― 『意地悪しないでよぉ…』 泣きべそをかいた女の子。 どうにも泣きやんでくれなくて、仕方なく謝って、手を繋ぎながら家まで送った事を 思い出す。 ハボックはエドワードの髪に手を伸ばし、その金色に目を細めた。 「少尉なんか、嫌い…だ…っ…」 時々エドワードの肩が大きく波打つ。 ――こんな時、どうすりゃ良いんだっけ―― 泣き止まない、子供。 「……ゆ…りかご…の………う…たを……」 幼い頃、自分を寝かし付けながら、母が歌ってくれた子守歌を口ずさむ。 「少…尉…?」 涙に濡れた瞳をハボックに向け、エドワードが不思議そうな顔をした。 「…か……なり…や…が…、……う…たう………よ……」 ハボックは碧い瞳でエドワードを見つめ、耳を澄まさないと聞き取れないぐらいの か細い声で、旋律を口ずさんでいた。 ――口元には、穏やかな笑みを浮かべて。 自分をあやしてるつもりなんだろうか、とエドワードは苦笑を零した。 「……エ…ド…………」 ふと、ハボックがエドワードを愛称で呼ぶ。 なあに、とエドワードが反応すると、ハボックの瞳がゆっくりと閉じられ、エドワードの髪を 撫でていた腕が、するりと地面に落ちた。 「……少……尉……?」 エドワードは呆然とした表情でハボックに視線を移した。 「…少…尉…?」 震える手でハボックの頬に触れる。 何度触れても、空のような碧い瞳は、閉じられたままで。 エドワードは首を何度も横に振り、ハボックの体を自分の胸に掻き抱いた。 徐々に冷たくなっていくハボックの頬を何度も撫で、溢れる涙も拭わずにハボックの掌を 自分の頬に押し当てる。 「…名前…教えてもらってないよ……少尉…」 何を問い掛けても、優しい瞳は二度と開く事は無い。 大きくてごつごつした掌で、髪を撫でる事も、無い。 冷たくなったハボックの唇に、エドワードはそっと口付けた。 夜空が炎で橙に染まる。 それはまるで、金糸雀の羽の色。 傍らには、子供のような顔をして眠る貴方。 ――揺り籃の唄を 金糸雀が唄うよ―― |