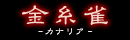 <15> ―――小鳥や 小鳥 籠の小鳥 紅い花舟浮かべれば あの人哀しと 川辺に唄う あの人恋しと 囀り、嘆く…――― 手入れの行き届いた庭に面した縁側で、エドワードが謡う。 口ずさまれる歌声に合わせて、ぷらりぷらりと足が揺れた。 「小鳥や…小鳥…」 遠くから聞こえる、秋祭りの音。 時折ちりりと仕舞い忘れた風鈴が秋風に揺れて寂し気な音を立てる。 エドワードは立ち上がり、一度部屋に入って箪笥の引き出しから朱に塗られた箱を 取り出すと、また縁側に腰掛ける。 箱の中には淡い水色の布包みが一つといくつかのビー玉が入っていた。 エドワードは、水色の布に包まれたそれをそっと取り出す。 ゆっくりと布を解くと、碧いガラス玉と銀細工に彩られた簪が現れた。 エドワードはじっとそれを見つめる。 ガラス玉には真中に大きな亀裂が入っていた。 ―――あれから、一年。 あの後、炎が渦巻くあの場所からどうやって連れ出されたのか覚えていない。 ぱちぱちと木のはぜる音。 怖い程綺麗な橙色をした炎。 段々と冷たくなってゆく、あの人の、身体。 その身体を抱きながら、このまま死んでもいいと思った。 弟の事も、ロイの事も忘れて、このまま彼の亡骸ごとこの炎に飲み込まれてしまえば 良い、と。 壊れたように子守歌を小さく口ずさみながら、男の髪を撫で続けた。 背後で朱い格子が崩れ落ちる。 遠くで自分を呼ぶ、ロイの声がした。 …エドワードが覚えているのはそこまでで、次に気付いた時はすでにロイの 私邸にいた。 事件の顛末がどうなったのか、詳しくは知らない。 ただ、一ヶ月程経って久し振りに帰ってきたロイが言った。 「全部、終わった」 「…終わった…?」 「ああ。あの事件は、終わった。 そして、もう君が軍から追われる事も、命を狙われる事も、 ……少尉の仇を討つ必要も、無い」 ロイの言葉に、エドワードは瞳を伏せる。 俯いたエドワードの頬を、一筋、涙が伝った。 『終わった』という言葉が、何故か無性に悲しかった。 「全部、終わった。でも、忘れる必要は、無い。…彼の気持ちも、君の気持ちも」 ロイは少しだけ哀しげに微笑い、そっとエドワードの頬の涙を拭う。 「……ロイっ」 「…何も言わなくていい」 何か言おうとしたエドワードを、ロイは抱き寄せた。 「…エドワード」 「……」 「少尉の名前、知りたいかい?」 ロイの問い掛けに、エドワードは暫し沈黙するが、やがて小さく首を横に振った。 「知らなくて、いい」 「…そうか」 ロイの腕の中で、エドワードの身体が微かに震える。 泣いているのだと悟ったロイは、ただ無言でエドワードの髪を撫で続けた。 エドワードはそこまで記憶を辿ると、手にしていた簪を夕焼けに翳す。 ―――きっと、これからも一生髪に飾られる事が無いであろう、碧いガラス玉の簪。 …これを髪に飾って、笑ってくれる人は、もういない。 遠くで、祭りの音に混じって鳥のさえずりが聞こえる。 『…ぴーちくぱーちく煩ぇって事』 不意に男の言葉が脳裏に蘇り、胸が詰まる。 口調は意地悪だけど、温かい声音。 逞しく大きな掌。 ……荒っぽい口付けと、胸が痛い程に優しく、強い抱擁。 「…馬鹿少尉…もう…鳴けない、だろ…」 小さく呟いて、簪をぎゅっと胸に抱く。 …涙は、もう出なかった。 最後にロイの腕の中で彼を想いながら泣いた、あの日から。 「エドワード」 物思いに沈んでいたエドワードをロイの声が不意に現実に引き戻す。 エドワードは慌てて簪を布でくるんだ。 ロイはエドワードが手にしている水色の布包みを見ると僅かに表情を曇らせるが、 それは一瞬の事で、すぐにいつもの柔らかな笑みに戻る。 「川向こうの祭り、行くんだろう?準備しなさい」 「分かってる。…先、玄関に行ってて」 エドワードがそう答えると、ロイは頷いて部屋を後にした。 エドワードは立ち上がって箱を引き出しに戻すと、紅い着物を纏う。 姿見の前でくるりと回ると、紅い裾がひらりと翻った。 緩く編まれた三つ編みに見え隠れする、紅い、痕。 エドワードは鏡に映った己の姿を見て苦笑を浮かべた。 ―――金糸雀は、ずっと金糸雀のまま。 エドワードはロイから貰った朱塗りの簪を髪に刺すと、ゆっくりと歩き出した。 ロイに手を引かれて、川辺を歩く。 ふとエドワードはそこに咲く紅い花を見て足を止めた。 ―――血のように紅い、曼珠沙華。 「ちょっと、待ってて」 エドワードはそう言い残すと、緩やかな土手を降りてゆく。 ぷつりと白い指が紅い花を手折った。 そのまま茎から花だけを千切る。 「小鳥や、小鳥…」 エドワードは小さく口ずさむ。 「紅い花舟浮かべれば…」 謡いながら、先刻千切った曼珠沙華の花を川に浮かべる。 花はまるで小舟のように静かに流れていった。 「…あの人哀しと、川辺に唄う…」 花はゆるりと川を流れてゆく。 「…連れてってくれるって、約束したのに」 流れてゆく紅い花が、段々と見えなくなる。 「…オレが望むなら、何処へだって、連れてってくれるって」 ―――なのに、何で一人でいなくなっちゃったんだよ…… エドワードはきゅっと唇を噛む。 紅い花は、流れの向こうに静かに消えた。 エドワードは立ち上がるとロイの元に戻り、その手に再び自分の手を絡める。 「…花舟」 ふと、ロイが小さく呟いた。 花で出来た舟を川に流すのは、鎮魂の意。 …そして、曼珠沙華の花言葉は。 「エドワード、あの花の花言葉を知ってるかい?」 川辺を歩きながらロイが問う。 エドワードは小さな声で答えた。 「曼珠沙華の花言葉は…悲しい、思い出」 ロイは漆黒の瞳でエドワードをじっと見つめる。 エドワードはそれを琥珀の瞳で真っ直ぐに見つめ返すと、大人びた表情で微笑った。 「行こう、ロイ。お祭り、終わっちゃう」 するりと繋いだ手が解けて、エドワードは紅い袖を靡かせながら数歩先に行き、 ロイを振り返る。 夕焼けに染められたエドワードの着物が、まるで金糸雀の羽ように煌めいた。 「……ああ」 ロイはそれを眩しそうに目を細めて見つめると、静かにその後を追った。 ―――曼珠沙華。 花言葉は、『想うは、貴方一人』。 …何処かで、小さく金糸雀が鳴いた。 [fin] |