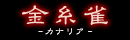 <金糸雀夜話-花霞-> ――― さくら さくら 霞か 雲か 朝日ににおう ――― 「少尉、川の向こうに桜の木が沢山あるの、知ってる?」 いつものようにハボックが格子に身を寄せて紫煙を吐き出していると、紅い小鳥が そう尋ねる。 「あぁ」 短くそう答えると、小鳥は鮮やかな羽を翻しながら格子に寄り指を延ばしてハボックの 頬に触れ、囁いた。 「オレ、桜が見たいな。…少尉と」 小鳥は緩く編んだ金糸を弄びながら、何処か遠い眼差しでハボックの肩の向こうの 景色を見る。 ―――まるで此処からは見えない遠くの薄紅色の花を見ているかのような、朧げな瞳。 「ね、いつか…桜、見に連れてってくれる?」 小鳥が、甘く囀る。 「……」 頷くのは、簡単な事。 小鳥の瞳も、其がたとえ嘘偽りだったとしても構わない、刹那の答えを望んでいる。 ……でも。 「見に行くのは、俺じゃ無くて御主人様とにしておけよ。 あの人なら連れてってくれるだろ。……何処へだって」 一瞬、小鳥の顔が歪んだ。 しかしそれは本当に一瞬の事で、小鳥の表情はあっという間にいつもの揶愉するような 艶めいた笑みに変わる。 「…冗談に決ってんだろ。アンタを、揶愉っただけ」 小鳥はそう言うと、くるりと背を返した。 「…帰りなよ。ロイ、今そっち行くから」 背を向けたまま感情の無い声で小鳥はそう告げると奥に姿を消す。 「本当は、俺だって、……」 ハボックはそう呟きながら主のいなくなった朱い籠を一瞥すると、ゆっくりと歩き出した。 部屋の奥で、金糸雀が呟く。 「…………意気地無し」 花見で賑わう人ごみを避けて、エドワードは寂れた川縁を歩く。 鮮やかな並木道から外れた其処には、朽ちかけた一本の桜の木。 老木であるその木は、今年で花も最期なのだろう。 その枝を彩る花は、酷く美しかった。 命が絶える間際の、壮絶なまでの輝き。 はらはらと舞い散る花弁がエドワードの豊かな金糸に絡み付く。 エドワードはそれを払いもせずに、唯黙って薄紅の花を見つめていた。 「少尉…アンタと一緒に、見たかったよ」 エドワードが小さく呟く。 籠の外の風景を。 頬を撫でる春風を。 泣きたくなる程綺麗な青空によく映える、桜の花を。 「…アンタと、見たかったのに」 ……一緒に見たいと望んだ人は、もう、いない。 エドワードは降り注ぐ白い花雪を鋼の掌でそっと受けた。 淡い花弁は雪のように溶ける事無く、鋼を彩る。 ふと、花弁の清廉は自分の手にはふさわしく無いような気がして、エドワードは 掌からそれを地に還した。 その思いを感じ取ったかのように風が地に還る前の花弁をさらってゆく。 「そういえば、桜の木の下には死体が埋まってるんだっけ…」 昔何処かで読んだ本の一節。 それが真実だったら良いのに。 此の下にあるのが、あの人の亡骸だったなら。 亡骸さえ遺さず、自分を置いていった人。 …亡骸さえも欲しいと、恋焦れた人。 エドワードはぺたりと木の幹に頬を寄せる。 冷えた木に、あの人のような温もりは無い。 ―――あの時。 あの時、嘘でもいいから頷いて欲しかった。 一緒に見ようと、言って欲しかった。 ざわり。 不意に強く風がざわめいて、花弁がまるで吹雪のようにエドワードの視界を奪う。 薄く目を開くと、白く花霞む風景に幻のように浮かぶ、懐かしい蒼の瞳。 「少…尉…?」 花影は優しく微笑む。 愛しい男の面影で。 「少尉…ッ!」 エドワードが、必死に手を延ばす。 …ざわり。 再び強い風が吹き抜け、激しく花弁が舞った。 エドワードは思わずきつく目を閉じる。 『エドワード』 一瞬。 それは、ほんの一瞬だけ。 愛しげに自分の名を口ずさみながらふわりと抱き締めるあの人の腕。 ―――それは、…それは確かに。 嵐が過ぎてエドワードが目を開くと、其処には唯桜の老木が最期の花を散らしている だけだった。 「兄さん、何処にいるの?」 遠くでアルフォンスの自分を呼ぶ声が聞え、エドワードは桜から身を離す。 「……さよなら」 花を見上げて呟いた言葉は、老いた桜へか、散りゆく花へか、…それとも。 エドワードはひらりと紅を翻すと、弟の待つ方へと歩き出した。 『俺も、一度でいいからお前と一緒に桜が見たかった』 小鳥が去った桜の下で、不意にふわりと風に逆らうように不自然に花弁が舞う。 『…じゃあな、エドワード』 誰もいなくなった桜の下に何処からか煙草の煙が流れて、やがて…消えた。 ――― さくら さくら 花ざかり ――― |