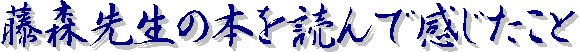
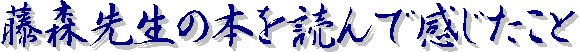
『旧石器の狩人』 学生社 昭和
40年|
|
|
『旧石器の狩人』 |
私が、この本を最初に読んだのが、高校生の頃だと思う。『かもしかみち』『かもしかみち以後』をすでに読んでいたので、吸い込まれるように藤森先生の世界に引きずり込まれていった。
考古学という学問の道を歩む狩人の、軌跡を生き生きと描いている本書は、代表作にしようと意気込んで書かれただけに、非常に熱の入ったものになっている。
前半で、曽根遺跡との出会いが藤森先生が考古学の世界へと入っていくきっかけとなった、というエピソードが語られている。その、曽根遺跡の明治時代からの官学の学者の研究を支えていた、多くの在野の学者たちがいたことを藤森先生は生き生きと描いている。その中で、小沢半堂という全てを考古学そして、曽根に賭けた男の物語は鬼気迫るものがある。藤森先生は『旧石器の狩人』を書かれた頃は、高血圧の発作が何度もあり、非常につらい時であったといわれている。おそらく、自分の運命を小沢半堂に重ね合わせながら書かれておられたのではないかと思う。同じ病気を持つ親友の杉原荘介先生が、諏訪の寒い冬を心配して、高血圧の藤森先生に冬だけでも、暖かい房総での転地療養をすすめるのも断って、執筆に情熱を傾けられたのである。
曽根でのエピソードに続いて、明石原人と直良信夫先生のエピソードが語られる。この直良信夫先生と藤森先生は非常に強い信頼で結ばれていた。森本六爾先生の亡くなられた後に、悲嘆にくれる藤森先生を励まし、東京考古学会の再建に協力してくれた直良先生、そして、藤森先生の出征後は残されたみち子夫人のために直良先生は原稿料も取らないで、何冊もの本を書いてくれた。この暖かい直良先生の心に答える藤森先生の心がこの物語を書かせたのであろう。しかし、学問の世界は、非情な一面をもっている。この、信頼すらも明石原人の証明のためには何の役にも立たなかったのである。この物語が書かれたあとずっと後になり、直良先生も、藤森先生も亡くなられた後の平成
10年になって明石原人が立証されるのだ。そうした、学問の非情さは多くの旧石器の狩人たちへ襲いかかってくるのだ。北風に向かって立つ男、相沢忠洋さんもそうした学問の非情さに翻弄された一人であることを藤森先生は生き生きと、暖かい目で描かれている。藤森先生が訪ねた相沢さんの東毛考古学研究所は、藤森先生の諏訪考古学研究所と比べて兄たり難く、弟たり難しといった状況で非常に親近感をもっていた。そのため、非常に伸び伸びと、そして生き生きと相沢さんの姿をとらえている。
やがて、最後に再び、諏訪湖にもどってくる藤森先生の姿がそこにある。曽根遺跡に佇み、死期を感じながら、半世紀にわたったこの遺跡との関わりを思い出しながら、去っていく藤森栄一の姿がそこにはあった。すなわち、学問をするということの本質は可能性を信じて、その解明のために一歩ずつでもいいから前進することなのであるという信念を抱きながら……。
最後に藤森先生は本書を書き終えた後で、次のような感想で締めくくられておられます。
かき終わって、読み返してみると、いろいろな学問の狩人の生き方が、次々に思い出されて、まるで、旧石器人を追っているのか、追う人が旧石器人なのか、それとも、まわりで、つまらんことに夢中になる奴がいるものだと笑っているのが旧石器人なのか、私にはわからなくなってしまった。