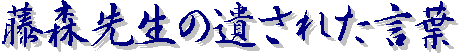
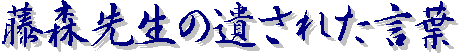
藤森先生は多くのこころに響くことばを遺しておられます。私の独断と偏見で選んでみました。
|
かもしかみち 私の考古学手帳から 深山の奥には今も野獣たちの歩む 人知れぬ路がある。 ただひたすらに高きへ高きへと それは人々の知らぬ けわしい路である。 私の考古学の仕事は ちょうどそうした かもしかみちにも似ている。 藤森栄一 |
藤森先生の最高傑作、多くの人々を勇気づけるとともに
考古学を捨てようとした先生のカムバックの支えになった。
写真は『かもしかみち』あしかび書房 第2版 より
|
いいんだよ。ゆっくり休んでいこう。
どんな廻り道だって、人生に無駄だったなんてことは一つもないんだ。 一度ともした灯を消しさえしなければね。 『かもしかみち以後』『心の灯』より |
私が、最も感動した藤森先生のことばです。
「彼の死去は1973年(昭和48)12月19日。病に臥せること多い日々、得られた静安の心根は次代を背負う若い人々、さらにその次代を嗣ぐ人々にまで呼び掛ける「心の灯」、そうした心を伝えることに執着した。「灯を消さないように」と書き送った彼の手紙は一人の青年が今日まで考古学を学ぶ、そうした礎と活力となる言葉となった。自からが森本六爾の一葉の書簡で考古学を学び始めた経緯を想い、噛みしめての一言であろう。」
( 水野正好「藤森栄一論」『弥生時代の研究』10研究のあゆみ 雄山閣より)この水野先生の藤森栄一論は藤森先生を深く敬愛された水野先生ならではのすばらしい論文である。ぜひ一読をおすすめいたします。
「考古学に興味をもったアナタよ、せっかくともした灯だ。消さないでおこう。私はいま、ベッドで考古学を学んだために楽しく幸福だった過去を思い、明かるい将来を待っている。さようなら」
(藤森先生「一度つけた灯を消さないこと」『信濃考古』より)| 杉原は必然性にのみ生涯を捧ぐると云う。僕は可能性にこそ生涯を捧げようと願う。 |
昭和11年2月20日の日記より
文中にある杉原とは盟友の杉原荘介先生のことである。両氏の学風、性格をあらわした言葉である。この年の1月22日に森本六爾先生の臨終に立ち会い、一時日記は中断していたが、再開後真っ先に記されたのがこの言葉である。
「考古学に恋し、その必然性に賭けた先生(杉原先生)と、可能性を追求した栄一、行動と思索、動と静と云われた異った性を持った二つの命は、その足跡を残し乍ら相たずさえて天空に飛び去った。」
(藤森みち子「考古学に捧げた命二つ」『長野県考古学会誌48』より)「同じ病気を経験したわたくしは、冬だけでも伊豆か房総で暮らしたらと、再三にわたり注意した。しかし、君はついにこの言葉を受け入れてくれなかった。いまもかわらない信州への思慕が、君の身体をそこから一時もはなさなかったのである。
そして、君はついに信州の草の中に土の中にだきこまれてしまった。さきにともに森本先生の骨を拾い、またわたくしはいま君の骨を拾う。一体、わたくしの骨は誰が拾ってくれるのか。お前の伝記はおれが書いてやるといった君は、いまはもういない。
しかし、生きていた四十年、真実の友としてつきあったことはわれわれの宝であった。われわれのような仲よしは、外にはいないだろう。君もそう思っているだろう。やはり二人は同じ世界にいるのだ。
さきにいって、静かにねむってくれたまえ。」
|
はなむけ
慾の時代は去って しあわせを求める 時代がきた 激しく愛しあい いつもよく語りあい 二人して掌をとり合い 歩いていきたまえ そして そして いつか満足して 静かに 消えていきたまえ
|
昭和48年、愛する甥の結婚式での言葉
最高の結婚式の祝辞であろう。藤森先生とみち子夫人の生き方をそのまま言葉にしたものにちがいない。藤森先生も、満足して静かに愛する諏訪の土になって消えていかれたのであった。
|
きっと私の存命中は、いや永遠に仮説としておわるかもしれない。
ただ、私という人間が生きて、ただひたすらに生きて、迷ってさまよっていったことは、まぎれもない事実なのである。 |
『考古学とともに』のあとがきより
縄文農耕論を提唱された藤森先生であったが、師の六爾先生もそうであったように学界の反応は冷たかった。しかし、奇しくも師の跡をなぞるように、死後栽培植物であるエゴマが発掘され縄文農耕は実証されたのであった。
|
私はアマチュア考古学者である。
もの心つくから五十九歳まで、ただ一筋にやってきたのだから、アマチュアではあっても素人ではない。 |
『考古学とともに』のまえがきより
藤森先生は折に触れて自分は生涯アマチュアの考古学者でした。という言葉を残されておられるが、その正確な意味をあらわす言葉がこれである。
|
我が半生の血汐を分けて、三箇の器に移す。
その一は来るべき我が半生の困窮の友へ。 その二は父母へ その三は今はなき森本六爾先生へ。 |
『藤森栄一日記』より
昭和11年2月22日
『信濃考古学』を出版しようとした栄一先生が序文として考えられたもの。
|
センセイノシニサイシソノゴイシニワガシウセイヲササグルコトヲチカフフジモリエイイチ
先生の死に際し、そのご意志に我が終生を捧ぐることを誓ふ。 藤森栄一 |
森本六爾先生のお葬式に際しての父森本猶蔵さんへの弔電である。
文字どおりに栄一先生はその決心を終生忘れなかった。
| 掘るだけなら掘らんでもいいのだ。資料も知識もそれ自身つまるところの何のオーソリティーにも価しない。それよりも高い知性と鋭い感性と強い情熱によって、一日も早く一つの学問を形成しよう。それからこの国の人々のすべてから、古い考古学の観念を叩き出してしまおうではないか。 |
「掘るだけなら掘らんでもいい話」昭和13年
戦前京都大学で日本考古学界で後にも先にもただ一度という大不祥事が起こった。その事件に対する抗議の意味をもって書かれたもので、栄一先生の魂の叫びとも言うべき声が聞こえてくる。しかし、この問題は裏を返せば現代考古学のあまりにもの不毛状態を予言する言葉ともなっている。すなわち、多くの行政発掘の増加によって資料は増加したが、それは多くの掘るだけのために消滅した遺物の上に成り立っているといえる。こうした意味合いで、再び先生の言葉を噛みしめて見ようではないか。
また、「掘るだけなら掘らんでもいい話」には次のような言葉も見られる。
|
私たちの唯一の師は、ひしがれ、ひしがれて巷に血を吐いて死んだ。資料もなければ、教室もなかった。それなのにその幾人かの弟子共は、その現身を師の学の各々に与えられたその延長線上に捧げようとしている。資料の学問より人間の学問へ、古代日本人の生活とともに、われわれの限りなき魂の延長の探求へと腕組みをして出発している。まず新しい学問の大系を建てるためには、第一に古い学問の死骸をとりのぞくことだ。そして自己の信ずるままに自己の信ずる道を求むることだ。近い将来において、それが考古学であったって、また考古学ではないといわれたってどうでもよい。少なくとも人と命の現身をこの祭壇に、厳然と要求しうるだけのすばらしい精神力と情熱に燃えた新しい学問をうち建てるのだ。 |
藤森先生の言葉について
藤森先生の言葉を語る上で忘れてはいけないことがある。それは、先生の言葉の一つ一つは、苦しい人生経験を経て導き出された珠玉の言葉であるということである。すなわち、言葉が感動を誘うのではなく、先生の人生が私たちの感動を誘っているのである。可能性を追求する藤森先生の現身は62年の長さであったが、先生がこの世を去られて25年、いよいよと混迷の時代を導く言葉として私たちを支えてくれることであろう。最後まで、可能性を信じてその実現のために最善を尽くされた先生の生涯は、私を捕らえて離さないのである。