
No.005 東日本旅客鉄道 東海旅客鉄道 西日本旅客鉄道
165系急行「ちくま82号」(8802M) 長野 ⇒ 大阪 試乗日 2000年2月13日(日)

長野駅1番線に入線してきた165系急行「ちくま82号」
最近、急速に姿を消していく165系急行型電車。 現在では既に定期急行運用も無くなり、JR東日本の「ムーン
ライトえちご」以外は、JR西日本の紀勢本線で細々と走るのみとなってしまった。 また近年盛り上がってきた国鉄
型車両ブームの中、ファンの注目度も、ますます高鳴って来ている様でもある。
今回で3回目となる165系関係の試乗記であるが、今日はこの165系電車を使用する臨時急行「ちくま82号」に
乗って、今だ衰えない急行型電車の魅力とその旅を満喫していきたいと思う。



小雪がちらつく長野駅から出発 急行「ちくま82号」のサボ (左:行先札 右:号車札)
2月13日、日曜日。 今日は建国記念日より続いた3連休の最終日だ。 始発駅となる長野駅は小雪がちらつく
天気であるが、今シーズンは暖冬の為か、それ程寒いという印象はなかった。
早速改札を通り1番線へ降りてみる。 今日は連休最終日であり、また今回が「165系を使用する「ちくま」の最
終運転になる。」という噂が流れた為か、入線前からカメラをぶら下げたファンの姿が見につく。 確かに今日は、
そんな話を異口同音に聞く事が出来た。
| (補足)取材後に入手した「春の臨時列車予定」では、使用車種が日根野区の381系に変更されていた。 確かに、噂は本当だった様である。 |
発車10分前、篠ノ井側の留置線にいた165系電車が、3両編成でゆっくりと入線してきた。 ホーム上では大勢
のファンがカメラを構え、入線を待っていた。
入線してきた165系のドアが開いたので、早速車内に入ってみる。 この車両は普段、紀勢本線で走るJR西日
本日根野電車区所属車である。 車内は既に、座席モケットの張替えなどの改良がなされており、原型の165系と
は少々感じが違う。 しかし昔と変わらない湘南色の外板塗装と、前面方向幕の「急行」表示が、急行型電車であ
る事を誇示している様だった。
10:55分、急行「ちくま82号」は、ゆっくりと長野駅1番線を離れた。 いよいよ7時間半にも及ぶ、電車急行の
旅が始まった。 ここから次の停車駅の篠ノ井までは、長野新幹線の高架脇を走り抜けていく。
もう既に先頭車デッキ付近では、数人のファンがビデオカメラを構えていた。 篠ノ井には11:04分に到着した。
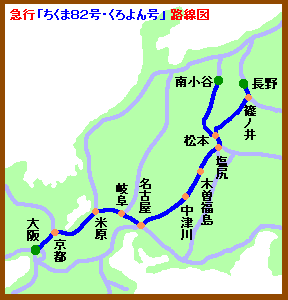
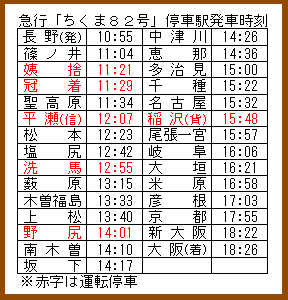
篠ノ井からは篠ノ井線に入り、いよいよ最初の山越えである「冠着峠」を越える事となる。 稲荷山駅を過ぎると、
やがて列車は山の斜面に沿った急勾配を登って行く。
その内だんだん高度が上がり、やがて眼下には雄大な善光寺平が広がってきた。 遠方にはこの列車の愛称にも
なった「千曲川」が流れるが、あいにくの天候で微かに伺えるだけだった。
やがて勾配を進む165系のスピードが緩やかになってきた。 これはスイッチバック駅の姨捨に近づいたからで
ある。 やがて引き上げ線に入線し一旦停車の後、今度はバック運転で姨捨駅のホームに入ってきた。
この姨捨駅では、長野行き普通電車と交換する為、5分程運転停車する。
もちろん、客扱いが無いのでドアは開かないが、それでも多くの乗客が車窓の善光寺平を眺めていた。
ところで、この時点での乗客数であるが、3両全体で50名弱位で、約20%位の乗車率であった。 始発直後の
乗客数としてはまずまずであるが、その約半数が鉄道ファンらしき姿をしていた。
  |
(左)長野〜篠ノ井間は 長野新幹線の高架脇を行く (右)姨捨付近の車窓から |
やがて長野色の115系が、隣のホームに滑り込んできた。そしてこちらの出発信号が青に変わると、また列車は
冠着峠に向け走り出した。 しばらくは、善光寺平を眺めながら走っていたが、やがて列車は冠着トンネルに突入し
ていた。 電動車のモーター音が高鳴り、付随車である1号車にも響いてきた。
余談だがこの「冠着トンネル」は蒸気時代からの難所で、当時は「ばい煙」による被害を低減する為に、篠ノ井側
の入口に送風機を設置し、峠の頂点になる松本側の出口に向け、風を送っていたそうである。 要するに片勾配の
トンネル全体を「煙突」として機能させ、機関車からの「ばい煙」を、列車の前に送っていた訳である。
そんな歴史のあるトンネルを抜けたところが、冠着峠のサミットである。 ここ冠着峠の頂点に位置する冠着駅で
も、長野行き「しなの7号」との行き違いの為、2分間の運転停車を行う。 駅の周辺は完全に雪の埋もれており、
峠を越えただけでまるで別世界になっていた。 雪の冠着駅を出ると、次は聖高原に停車する。
聖高原は11:32分の到着である。
  |
(左)聖高原付近の車窓 (左)平瀬信号所では |
聖高原を出発したところで、私は長野駅で購入した「栗おこわ弁当」に箸を付ける事にした。 これは「山菜と栗の
おこわご飯」に、「山菜の煮物」と「野沢菜のカラシ漬け」が入り、竹の子の皮に包まれていた。
本当に山菜と、栗の味が忘れられない駅弁であった。
この駅弁を平らげる頃には、列車は明科付近を通過し安曇野に入っていた。 こちらは長野付近と違って、すっ
かり晴れ渡った良い天気をしていた。 そんな空の下を快調に飛ばしていくのだが、また松本の手前の平瀬信号所
で、10分程の運転停車となった。 今度は「しなの11号」との待ち合わせだ。
考えてみれば、篠ノ井線の篠ノ井〜松本間は単線ながら、特急・ローカル列車を始め、貨物列車も往来する重要
路線でもある。 だからこそ、その中を走る臨時列車のスジは、遠慮がちになるのは仕方が無いのであろう。
やがて高速度で383系「しなの11号」が通過すると、こちらもまたゆっくり動き出した。
そして車窓がだんだん都市化し、右手側に大糸線の北松本駅が迫ってくると、松本駅は目の前だ。
  |
「ちくま82号」と「くろよん号」の連結作業 松本駅での連結作業は、多くのファン |
12:11分、急行「ちくま82号」は松本駅4番線に到着した。 ここでは大糸線南小谷駅始発の、急行「くろよん号」
と併結作業を行う為に、12分間の停車となる。
客の大多数がホームに出て休憩したり、駅弁等の購入の為に売店に並んでいた。 また、併結作業が行われる
3号車付近には、多くのファンが詰め掛けていた。
12:18分、いよいよ「くろよん号」がホームに入線してきた。 多くのファンが見守る中、係員の手馴れた作業で、
併結作業は異常なく終了した。 そして「くろよん号」のドアが開くと、こちらからも多くの乗客がホームに出てきて、
ホーム上はかなりの人が溢れていた。
12:23分、165系6連となった急行「ちくま82号・くろよん号」は松本駅を離れていった。 向かって右側には
E351系や、183系が留置された松本運転所が見えるが、今日は横浜からの「はまかいじ号」が運転されている
ので、緑3本のストライプが特徴の、185系電車が留置されているのも見えた。
またまた余談だが、日根野区の165系は、国鉄末期の大量車両移動によって日根野区に転じる前は、松本に配
属されていた。 ここでは主に急行「アルプス」等の中央線急行に使用されていたのである。
そんな過去があるので、パンタグラフのあるモハ164系は全車、低屋根構造の中央線タイプ車(800番台)になっ
ている。 まさに日根野の165系にとって、松本は故郷でもある。
そんな古巣の松本を後に、どんどん旅路を急いでいくのだが、この区間は線路状態が良いので、165系の最高
速度である110Km/hをキープして走りつづける。 ここで初めて165系電車は、優等列車らしい走りを見せ付け
てくれた。 しかし、塩尻駅が近づくと急に徐行運転になり、とうとう場内入口で信号停止してしまった。
この辺もまた臨時列車の宿命といった所であろうか?
やがて、塩尻駅を塞いでいた松本方面行きの普通電車とすれ違うと、いよいよ塩尻駅に入線である。
塩尻は12:38分に到着し4分程停車するのだが、松本と同様にこちらでも駅弁を求める客で、ホームがごった
返していた。 私も、個人的にお気に入りの駅弁である「とり釜飯」を一つ購入した。
売店のおばさんも「ちくまのお客様優先です、しばらくお待ち下さい。」と言いながら、短い時間の駅弁販売に奮闘
していた。 ちなみに、この先はJR東海管轄となるので、停車時間中に運転士が交代していた。 なお車掌は、JR
東海の車掌が長野から通しで乗務しているので、交代は無かった様である。
  |
(左)急行「ちくま82号」の車内 (右)塩尻駅の売店の様子 |
12:42分、いよいよ列車は塩尻を発車し、中央本線へと足を踏み入れた。 列車は快調に木曽路を走り抜ける
かと思ったのだが、隣の洗馬駅でまたしても「運転停車」となってしまった。 今度は名古屋行きの「しなの12号」に
追い抜かれてしまうのである。
この辺りでまた車内を見渡してみるが、「ちくま号」の指定席となる2・3号車や、「くろよん号」となる4〜6号車は、
スキー道具を抱えた乗客や一般旅行客が多く見られた。 6両全体では110名位の乗客が乗車しており、乗車率
にして約25%程であった。
やがて「しなの」が轟音と共に通過していくと、いよいよこちらも発車となった。 今度は快調な足取りで、次の山越
えである「鳥居峠」を目指し走り出した。
奈良井宿が有名な奈良井を過ぎると、信濃川流域と木曽川流域との分水嶺となる、鳥居峠に差しかかっていた。
中央本線はこの峠を「鳥居トンネル」を介し、通りぬけていく。
この鳥居トンネルを抜けると、もうそこは「木曽路」であった。 今日は木曽路も天候が良く、差し込む日差しで
少々眠気を催しそうだった。 やがて列車は、木曽路最初の停車駅である薮原に到着していた。
  |
(左)洗馬駅では「しなの12号」 に追い越された (右)今日の木曽路は快晴だった |
薮原を過ぎると、次の停車駅は木曽福島である。 木曽福島には13:29分に到着したが、ここでも4分程停車時
間があるので、ホームに出て観察してみた。 ホーム横の留置線には、早朝到着した臨時快速「きそスキーチャオ
号」の311系が留置されていた。 また線路沿いの駐車場には、デコイチこと、D51型蒸気機関車が静態保存され
ていた。 このD51型は電化以前の中央西線の主役で、383系振り子電車が往来する現在の中央西線からは、
想像も出来ない存在になってしまった様である。
木曽福島を13:33分に出ると、次駅である上松にも停車する。なお上松付近の木曽川流域は「寝覚めの床」と
呼ばれ、大変美しい渓谷が続いている。 これは車窓からでも十分に堪能する事が出来る。
また時折車窓からは、雪を頂いた中央アルプスの山並が見え、大変楽しい車窓になっていた。
  |
(左)木曽福島駅にいた311系 「きそスキーチャオ号」 (右)上松は林業の町だ |
この辺で、先程塩尻駅で購入した「とり釜飯」をいただく事にした。 「とり釜飯」と言うだけあって、中身は「鳥のそ
ぼろ」と「から揚げが」入り、他にも「うずらの卵」や、「野沢菜」が入った豪華な釜飯である。 早速食べてみるが、ま
だ暖かさが残っており美味しかった。 またメインの「から揚げ」の歯ごたえも良く、美味しくいただけた。
何よりも、車窓の美しい風景を見ながら食べる駅弁は、また格別であった。
こんな木曽路の旅を楽しんでいるうちに、運転停車駅の野尻に到着した。 野尻では長野行き「しなの19号」との
交換の為の停車だ。 しばらく待つと、穏やかな午後の光の中を383系「しなの」が通過していった。
  |
駅弁も旅の楽しみだ!! (左)長野駅 (右)塩尻駅 |