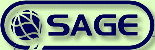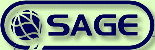保健と
グローバリゼーション
プロジェクト
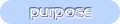
プロジェクト概要
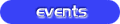
イベント
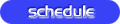
いつ活動してるの?
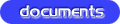
議事録・報告書など
|
保健とグローバリゼーション
プロジェクト概要
目的
モノ、カネ、特に近年では情報や人が、かつて見られなかったほどの自由度・スピードで時間を超え、国境を越えて移動する時代が、まさに現代のグローバリゼーションの時代です。この時代こそ、国境や人種、民族、文化の壁がたやすく乗り越えられる時代であり、またここ数年特にその傾向が顕著になってきています。このような状況の中、共通認識の形成、さらには共通の制度の形成がなされるのは必然とも言えるでしょう。しかし一方で、実際に制度の共通化を図る中で、さまざまなきしみが顕れてきています。
そのきしみの一つが顕れているのが、保健・医療の分野でしょう。内戦などによる不安定な国内情勢への対応や、増え続ける対外債務の返済に政府が追われる中で、発展途上国では最低限の保健さえ保証されえないでいる人が数多くいます。そして、技術が移転される、資源的・人的・社会的土壌が未熟なために、時刻で保健をまかなうことが難しい国が多くあります。また、先進工業国と発展途上国との間の物価水準の格差が、医療用具・薬品などの購入にあたって障壁となることもまた現実です。さらにはただでさえ大きい価格差に加え、開発において巨額の投資を要したAIDSなどの病気に対する特効薬は、その投資を回収する企業の正当な権利として、より高価な価格が設定され、そのためにそれを必要としている(中には死に瀕している)途上国の患者の人々がそれらを購入できずにいます。同時に、製薬会社が、利潤追求を目的とする企業として、利益率の低い途上国向けの基礎薬品の製造には極めて消極的な姿勢であることも、途上国における保健の向上の妨げとなっています。そして、国際舞台では、WTO(世界貿易機関)において、知的所有権保護の強化を図って企業の権利を保護する一方で、規制緩和の名の下に、保健・医療も含めた「サービス」の自由化=民営化を推し進め、これらのサービスの民間企業による提供を促進しようとしています。この流れは、利益になりにくい貧困層への医療がおろそかになることに繋がりかねません。
最低限の保健を保証されえない現実、基礎薬品にも事欠く惨状、高価な先端医療、そして民営化によって貧困層への医療が除外されかねない流れは、良い方向に向かっているとはいいにくいのではないでしょうか。しかも、これらを人ごととして座視していてもよいものなのでしょうか。まさにグローバリゼーションの下での共通のルール作りの中で、日本の身の回りにおいてもまた、医療サービスの民営化などが行われようとしています。
このような地球大の流れに対抗する動きもまた世界中で起こっています。そしてその動きの第一線で活躍されているのが、国際民衆保健協議会(IPHC)日本連絡事務所代表の池住義憲さんです。今回は池住さんを京都に講師にお招きできる機会を活かし、グローバリゼーションという流れの中で、特に発展途上国における保健がどのような影響を受けているかについて、学び、そして日本に住む私たちとして何ができるのかを探るよいきっかけとしたいと考えています。
内容
池住義憲さん(国際民衆保健協議会(IPHC)日本連絡事務所代表)をお招きしての、
・ワークショップ「保健とグローバリゼーション」の開催
・講演会「PHA(国際民衆保健会議)報告会」の開催
|