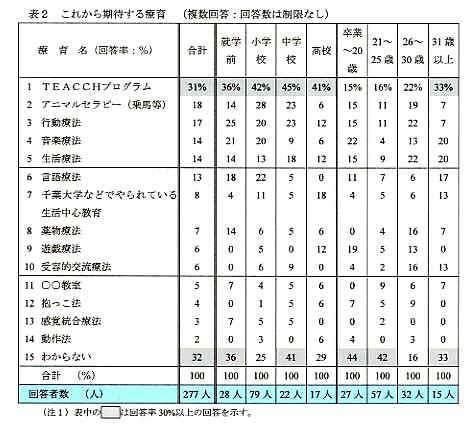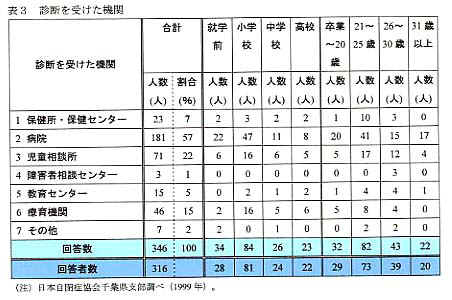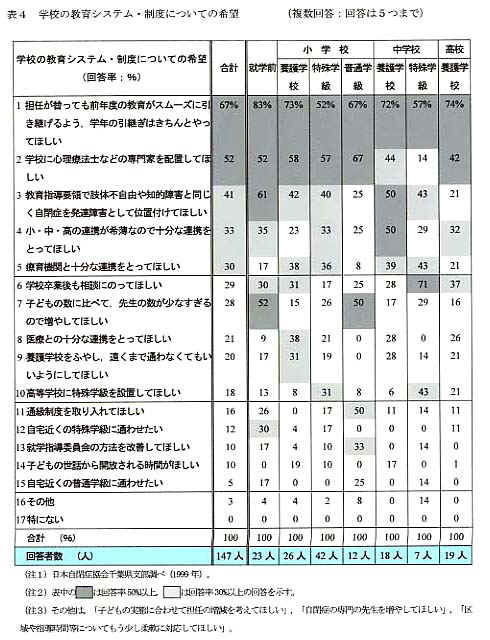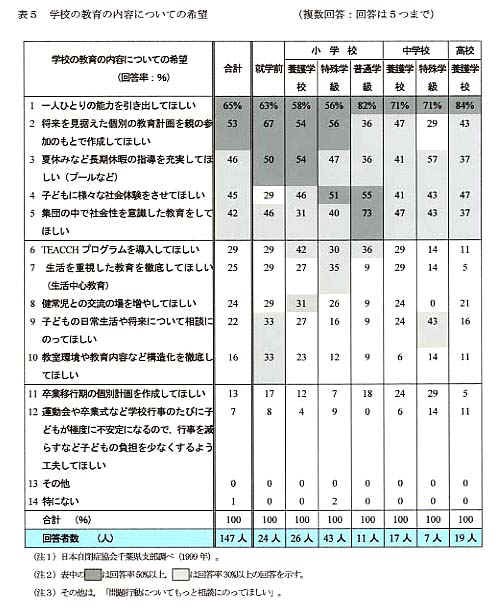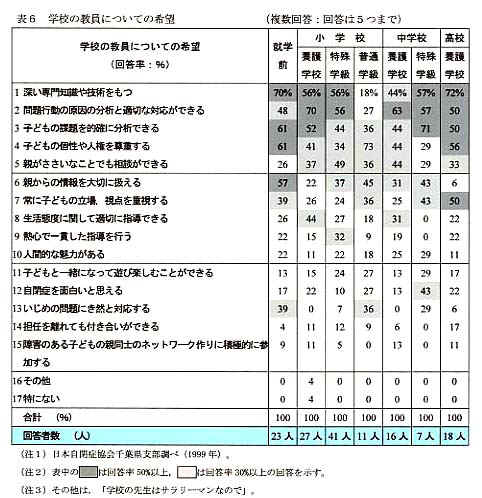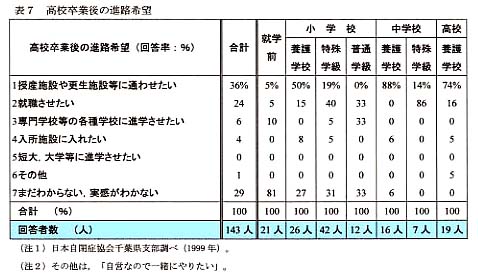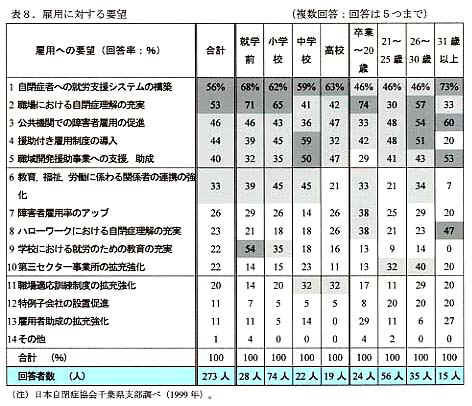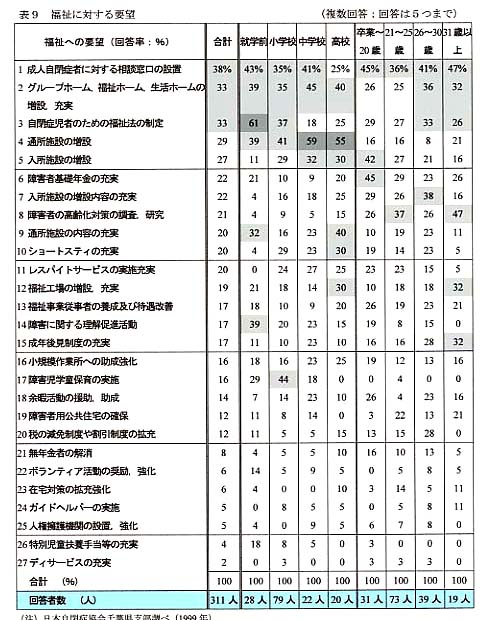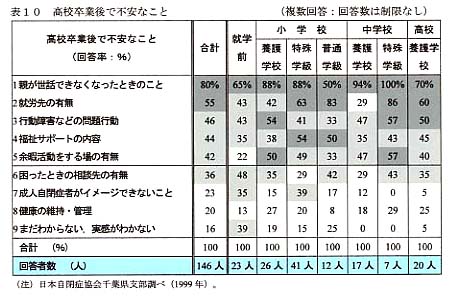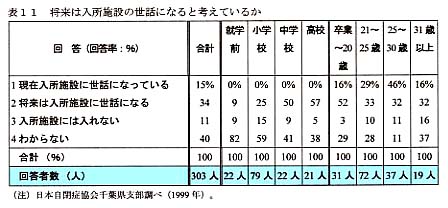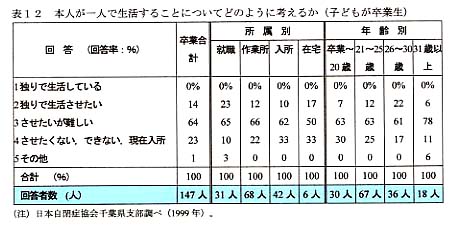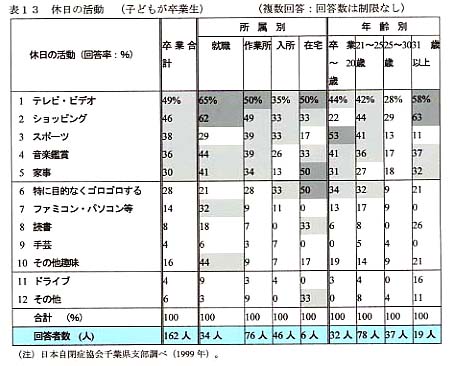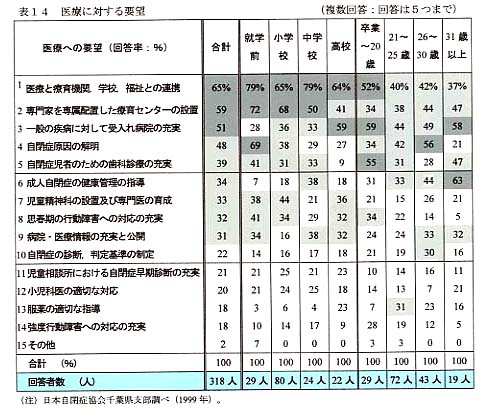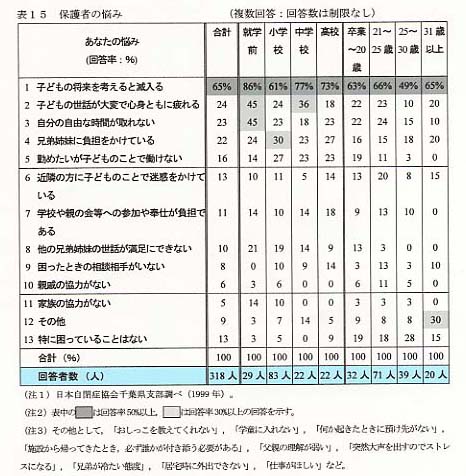|
平成13年8月10日
千葉県知事 堂本 暁子 殿
千葉県教育長 清水 新次 殿
社団法人 日本自閉症協会 千葉県支部
支部長 古屋 道夫
要 望 書
時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げますとともに,日頃より自閉症の人達と私共の活動にいろいろな形でご援助とご指導をいただいておりますことに感謝申し上げます。
日本自閉症協会は「自閉症児者に対する援護・育成を行うとともに,自閉症に関する社会一般への啓発を図り,もって自閉症児者の福祉を増進すること」を目的として,その達成のため,様々な事業を行ってきています。私たちは日本自閉症協会の千葉県支部として,自閉症児親の会の時代からほぼ30年,この目的のため千葉県下で活動を展開しております。
さて,わが国における自閉症施策は,「自閉症を障害として位置付けた」平成5年11月の障害者基本法の改正,「知的能力の障害というより人間関係の障害のために生活適応ができないという自閉症の特性を踏まえつつ,自閉症に関する処遇方法の研究・開発等施策の充実を図るべきである」と報告した平成9年12月の厚生省3審議会合同企画分科会による「今後の障害保健福祉施策の在り方について(中間報告)」,及び「自閉症児への教育的対応」を明確に書き分けた平成13年1月の文部科学省調査研究協力者会議による「21世紀の特殊教育の在り方について(最終報告)」を基本とし,障害者基本計画の策定によって推進されています。
千葉県においては,平成7年4月に策定されました「障害者施策新長期計画」にて,自閉症を障害の一つとして位置付けしていますが,自閉症児者を取り巻く現状と課題について記載がなく,自閉症児者の障害特性を理解した施策についても十分に盛り込まれているとは言えません。高機能自閉症となると,現状からも計画からも全く欠落しています。
自閉症は,個別に援助を必要とする障害の中でも,治療も教育も圧倒的に困難であると考えられている障害です。私たち,(社)日本自閉症協会
千葉県支部(以下「千葉県支部」という。)は,千葉県に暮らす1万2千人の自閉症の人,自閉症児として毎年生まれてくる110人の全ての新生児のため(500人に1人いるとされている疫学調査の結果から試算。このうち半数は高機能自閉症。),下記について要望いたします。
本要望書は,関係部局,関係出先機関及び関係審議会にご配布いただけるよう,配慮方お願い申し上げます。
記
1.
自閉症に対する対策を千葉県障害者施策新長期計画に反映するとともに,市町村が策定する市町村障害者基本計画に反映されるよう,強力に指導してください。
2.
自閉症に関する各種施策を立案されるときは,私たち千葉県支部から直接ヒアリングして決定してください。
3.
私たち千葉県支部は千葉県における自閉症に関する唯一の団体です。千葉県支部が行う各種事業を支援してください。また,分会をその地域の福祉関係団体として位置付け支援するとともに,関係市町村が分会を積極的に支援するよう指導してください。
4.
県立の療育機関及び学校に,TEACCH(ティーチ)プログラムなど世界的に評価の高い自閉症プログラムを導入するとともに,これらプログラムを市町村が療育機関,学校及び福祉的就労施設に導入できるよう指導してください。
5. 一般社会に,自閉症の正しい理解の普及を推進するほか,千葉県障害福祉課に自閉症に詳しい相談員を配置するとともに,全ての市町村の障害福祉担当課に自閉症に詳しい相談員を配置するよう指導してください。
6.
以下の個別の要望をかなえてください。
(1)自閉症センター
千葉県に,高度の医療専門機関として自閉症等の発達障害がわかる専門医(精神科,小児科)及び心理士を配置し,自閉症等の診断及び診断後の治療・療育相談を行うとともに,生活支援及び就労支援機能をもたせた,「自閉症センター」を設立してださい。また,センター内に,千葉県支部の事務所を置かせてください。
(2)早期発見及び早期療育
1) 1.5歳及び3歳児検診では,もれなく自閉症の早期発見ができるよう,市町村自治体の検診システムに自閉症に詳しい専門医の参画を義務付けるとともに,保健所,児童相談所における自閉症の早期発見システムを確立してください。また,母子保健における保健婦・士の養成研修を推進してください。
2) 県立の医療療育機関には,自閉症のわかる医師(精神科,小児科)及び心理士を配置し,自閉症の診断及び診断後の治療・療育相談ができるようにしてください。
3)
千葉県支部及び分会が実施する自閉症相談事業を支援してください。
4)
自閉症の早期発見及び早期療育に努めてください。そのためには,上記以外にも自閉症の診断と専門的な療育相談の行えるよう市町村を指導して下さい。
5)
保育所及び幼稚園の職員及び管理職への自閉症理解の啓発普及を行ってください。
(3)教育支援
1)
地域社会で生活するという最終ゴールを目標に,個々の自閉症児の障害特性や発達レベルに配慮した,きめ細かく,かつ一貫した教育システムを構築し,県立養護学校及び市町村を指導してください。そのためには,教員並びに介助員の自閉症に対する理解はもちろん,外部専門家である療育機関及び医療機関との柔軟な連携を図ってください。
2)
県立及び市立の全ての学校において,自閉症の困難性に応じた職員の加配ができるよう措置してください。
3)
学校と家庭が共通の認識のもとに連携・協力を深めることが大切であり,全県下において個別教育計画の導入を推進してください。
4) 子どものニーズに応えるため,全ての市町村において介助員制度を導入するとともに,通級による情緒障害学級を設置することを,市町村が積極的に取り組むよう指導してください。
5)
養護学校高等部の教育は福祉的就労施設等との連携を深め,一人ひとりの個別就労計画を作成してください。
6) 通常学級・特殊学級の教職員,管理職及び介助員への自閉症児教育の研修を行うとともに,全ての関係者に研修への参加を義務付けるよう,市町村を指導してください。
7) 学校における,本人及び兄弟へのいじめの問題に対して学校が毅然と対処するよう,市町村を指導してください。
8) 特殊学級,養護学校の教育が地域格差,学校格差が大きいのでどこにおいても高い水準の教育が受けられるようにしてください。
(4)就労支援
1)
各市町村単位に就労支援センターを設置し,自閉症の人の就労の促進を図るとともに,ジョブコーチ事業の専従職員(所長との兼任ではない)を配置し,事業を強力に実施してください。
2)
自閉症の人の民間企業における雇用拡大を図るとともに公的機関においても採用してください。
3) 授産施設,福祉作業所等の福祉的就労施設では,自閉症に詳しい指導員・相談員を配置するなど活動内容を充実するとともに,新設するよう,市町村を指導してください。
4)
福祉的就労施設に自閉症の困難性に応じた職員の加配ができるよう,県から自閉症者のいる施設に重度加算・行動障害加算制度等を補助してください。
(5)生活支援・家族支援
1)
強度行動障害で悲惨な状況にある本人と家族を救済する強度行動障害支援事業の対象枠を確保・増加するとともに,市町村が同種の事業を実施できるよう積極的に指導してください。
2) 一時緊急保護をはじめ夏休み,冬休み,放課後に利用できる機関を,全県下で県が設置してください(あるいは市町村の実施を促進させるべく補助してください。)。
3)
グループホームなど多様な地域生活の場を整備してください。
4)
「障害者地域生活支援センター」設置については,国基準である30万に2カ所を越え,柔軟に配置を行ってください。また,センターの設置に当たっては,業務としてショートステイ,ガイドヘルプ,ホームヘルプ,レスパイト,デイサービス,障害児学童保育,グループホーム,レクリエーション開発,ケアマネジメントなどを対象とするとともに,自閉症の人,一人ひとりに合わせた運営を行ってください。
5)
千葉県の一部の市町村で独自に行われている「一時介護委託料助成制度」を「障害児・者生活サポート事業」などとして対象事業を拡大するとともに,一人当たり利用額(現在年間数万円)の増額を行えるよう全県下で県が実施してください(あるいは市町村の実施を促進させるべく補助してください)。
6)
支援費制度の導入に当たっては,千葉県支部に説明し意見を聞くとともに,障害程度区分の設定では知的障害を伴わない(あるいは軽度な)高機能自閉症やアスペルガー症候群の人において不利のないよう,障害の困難性を適切に評価してください。
7)
入所施設の職員が定着して仕事に生き甲斐をもって取組めるよう条件を整えるよう,市町村及び法人を指導してください。
8) 入所施設の経営は,社会福祉法人が保護者からの寄付金を当てにせずに済むように行政から財政措置してください。
9)
ホームヘルプ事業については平成15年度より実施される支援費制度における重要なメニューの一つとして利用時間の制限なく積極的に市町村が取り組むよう,指導・支援してください。また,国の通達では,障害児・知的障害者ホームヘルプ事業において中軽度児が対象外となっていますが,この部分については県単独事業として補ってください。
10)
ガイドヘルプ事業(支援費対象外)についてこれとは別途実施し,自閉症の人について,年齢制限なく参加できるようにしてください。
11) ホームヘルプ,ガイドヘルプなど生活支援に関わる方への,自閉症に関する研修を実施するよう,市町村を指導してください。
12)
千葉県支部が実施している親子の旅事業の支援をさらに充実してください。
13)
自閉症の人のための高齢化対策について,調査研究してください。
14)
自閉症の人のための成年後見制度を充実してください。
(6)高機能自閉症
1)
自閉症の困難性を評価する尺度が研究されるまでは,IQ70の知的ラインに関係なく,対応の困難さによって療育手帳を措置してください。
2)
知的障害を伴わない(あるいは軽度な)高機能自閉症やアスペルガー症候群の人について,相談事業を行うとともに,就労支援及び生活支援に取り組んでください。
3)
県立の医療療育機関及び特殊教育センターおいて,高機能自閉症児やアスペルガー症候群の専門家を配置し,診断及び治療・療育・教育相談ができるようにしてください。
4) 県内の全ての学校において,高機能自閉症やアスペルガー症候群の実態調査を実施してください。
5)
高機能自閉症やアスペルガー症候群の人の教育は,障害に配慮しつつも,発達レベルにふさわしい教育が保障されるよう,市町村を指導してください。
|