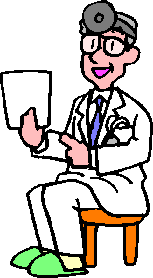
いとしごNo.59から
小児科医に自閉症協会の活動を知ってもらおう
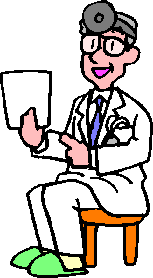
長男が生まれてから8年間,私は自閉症児の親の立場で多くの専門家にお会いしてきました。同時に,私は公立病院の脳外科に約20年勤務しており,精神科や小児科の同僚と共に,小児の神経に関する医療に従事してきました。
現代の医療の中で自閉症を仕事の対象としている医師は限られています。一つが児童精神科医,もう一つが小児科出身の小児神経科医です。私の経験では,山崎理事,太田理事や佐々木理事に代表される児童精神科医はほとんどが自閉症に対して強い興味と使命感をお持ちです。小児神経科医も,江草会長のように自閉症医療に多大な貢献をされている先生が大勢いらっしゃいます。ところが,神経を専門としない一般の小児科の先生方となると自閉症に興味を持たない方が大多数な印象です。しかし,地域の一般小児科医は,自閉症児が生まれて最初に接する医師である可能性が高く,病気の時にも必ず受診するという点で大変重要な存在です。
日本では幼児検診を通じて,自閉症の早期診断に大きな成果を上げている都市もありますが,未だに診断や親への告知が不十分な地域もたくさんあります。親が子供の異常に気づいていても,「様子を見ましょう」と言われそのまま1年2年も放置される例が少なくありません。自閉症であることを診断されず,親が自覚しないで小児期を過ごすことの弊害は皆様もご存じの通りです。診断,告知をしないことによって,子供と親に大きな損害を与えていると言っても過言ではありません。
医師の仕事は,患者さんを診察し,病気を診断し,治療を行うことです。親から見て自閉症児者を患者,自閉症を病気と呼ぶことには抵抗がありますが,小児科医の多くも自閉症は医療の対象ではないと考えているようです。肺炎に対する抗生物質のように完治できる有効な治療法が自閉症にはありません。完治できなくともせめて対処法がわかれば,深刻な内容でも告知することができます。例えば脳卒中の患者さんには,「半身不随は治りませんが,リハビリすれば社会に復帰できます」と説明できます。しかし,多くの小児科医は子供の異常に気づきつつも,自閉症児に対する具体的対処法を持っていないように思われます。自分で診断・告知するのがむつかしいなら,自閉症の専門家に紹介するというのが最も適切な対応ですが,専門病院に紹介すること自体がかなり手間のかかる行為です。病院以外にも紹介しやすい療育機関があればいいのですが,それもなければ放置することになりがちです。
このような場合に,自閉症協会の地方組織が医師からの受け皿の一つになり得るのではないかと私は考えております。定期的な勉強会,講演会など立派に活動しているグループがたくさんあります。小児科医が自閉症の診断を疑った場合,自閉症協会の地域の勉強会などの活動を親に教示してもらう。親が,他の親と話し合っているうちに自発的に専門家に受診する気持ちを持つようになることもあるでしょう。さらに,親が子供の障害と向き合い,適切な対応を絶え間なく継続するための,精神的・技術的な支えにもなれるでしょう。悩める親にとっては救いとなり,医師にとってはこの「病気」の対処手段が一つ増え,我々にとっては仲間が増えることになります。
残念ながら,私の経験では自閉症協会の活動を知っている一般の小児科医はとても少ないようです。日本には障害や病気を持った人の団体はたくさんあり,自閉症協会はその中の一つです。また,自閉症児を数多く診療されている専門家であっても,自閉症協会の活動には関心がない先生もいらっしゃるようです。実際,自閉症協会主催の催しに参加する医師は多くありません。今後,各地域において,医師会組織やダイレクトメールなどを利用して,支部の具体的活動状況や日程を,繰り返し宣伝する必要があると思います。
全国レベルでの宣伝も必要です。今年の日本小児神経学会総会の会場では,障害児者(レット症候群,もやもや病等)の団体がデモンストレーション活動を行っており,私も強い印象受けました。全国規模の学会なら,一度に多くの医師にアピールできます。一人でも多くの医師に親近感を持ってもらうために,また自閉症協会が医師にも役に立つ存在だと認識してもらうために有意義と思われます。上記学会は平成12年度は大阪,平成13年度は岡山で開催されます。他にも小児科の学会は(もちろん精神科の学会も)いくつもあります。これらの学会に対して本部が積極的に働きかけて,開催地域の支部にもご協力いただき,何らかのデモンストレーション活動を行う機会を得られれば,有効な宣伝戦略の一つになると思いますが,いかがでしょうか。会員の皆様にご意見をいただければ幸甚です。
東総地区分会 大屋 滋 (旭中央病院脳神経外科)