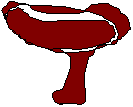 |
 |
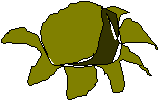 |
なに?? |
キララタケ |
ツチグリ… |
The Ability of Mushroom
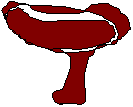 |
 |
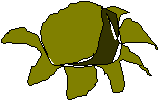 |
なに?? |
キララタケ |
ツチグリ… |
きのこはけっして神出鬼没ではなく、必ずゆえあって現れるのである。これによって後始末はとどこおりなく行われるし、また行われなければならない。それが円滑に行われるようにわれわれは自然を維持すべきであるし、また自然に荷重な負担をかけてもいけないのであると思う。(相良直彦:「きのこと動物」より)
さて、スーパーでは何種類のきのこが売られているでしょうか。 なめこ、しいたけ、シメジ、えのき、えりんぎぃ、マッシュルーム、たもぎたけ、ひらたけ、まいたけ・・・。
それぞれは人工栽培されたものですが、野性のそれらには、風味はもとより色や形など、格段の違いがあります。 そこで、手頃な森、北大付属植物園へきのこを求めて侵入しました。
おぉっと、いきなり枯れたハルニレの木の中ほどに、シロタモギタケ(Hypsizigus ulmarius)の群生を発見。 ずんずん中ほどに進み、広葉樹と笹だらけのところで念入りに地面、木を観察してみると、あるわあるわ・・・。まずは、アカチシオタケ(Mycena crocata)が腐れた木片から群生、柄が赤く一本折り取ってみると、どくどくと真っ赤な血が滴り落ちる。それから、枯れ枝に張り付いた真っ白なザイモクタケ(Oxyporus ravidus)、うまげなヒラタケ(Pleurotus ostreatus)。これは、シメジの名で売られている。 ちなみに、ホンシメジとして売られているのは、ブナシメジのことである。 それからそれから、童話に出てきそうな愛らしいキララタケ(Coprinus micaceus)、制ガン性のあるコフキサルノコシカケ(Elfvingia applanata)、そして自然のエノキタケ(Flammulina valutipes)。売り物の、あの真っ白でほそっちぃのとは大違いで、短く、かさも大きく栗褐色であった。イヌセンボンタケ(Coprinused disseminatus)の群生、目玉模様のサカズキカワラタケ(Poronidurus conchifer)、中心が少しとんがっているオオキヌハダトマヤタケ(Inocybe fastigiata)。針広混交林に移りまして、太陽のような形のエリマキツチグリ(Geastrum triplex)、サーモンピンクの何層にも重なったマスタケ(Laetiporus sulphureus var.miniatus)、硫黄色で苦いニガクリタケ(Naematoloma fasciculare)トドマツの下のくさい網がついたキヌガサタケ。芝生に潜入、ささくれいっぱいのツチスギタケ(Pholiota terrestris)に、押すとほこりの出るホコリタケ(Lycoperdon Perlatum)などなど・・・。結構あるんですなぁ。(ちなみに文字の色はきのこの色を模しました。)
さて、そもそもきのこってなんでしょう。実は、「樹の子」と書きます。ちなみに中国語では「木耳」とかきます。木に腐生、共生、寄生といった形で取り付き、養分の交換、あるいは略奪をして元気に暮らしています。そんな彼らは、自然界の生産(植物)→消費(動物)→分解(きのこ)という一連の物質循環系が、絶え間なく、滑らかにしかもバランスよく行われるための大役を担っているのです。さてさて、そんな彼らの生活方法を見てみましょう。
森を見ていく上で、どんなきのこがあるかに注意をしていると、その森や木が今どんな状態であるかがわかるんですね。つまり、きのこは必然的に生えているので、「指標現象」となります。(例えば、ナガエノスギタケというきのこが生えていたら、その下をがんがん掘ると必ずモグラの巣跡にたどり着くとかね。)具体的にどんな指標になりうるかは次回のお楽しみ・・・。 それではみなさんごきげんよう。 続く・・・
余談
きのこを見ると食べられるか否かをすぐに聞いてしまうのが人間ですが、食べるといえば欧米とアジア、特に日本、中国では、食し好まれるきのこに大きな違いがあるそうです。欧米で好まれるのは、味がしっかりしていて、地面から生えてくるきのこ、つまり菌根菌であるが、中国、日本では死生きのこ(死んだものを分解する)が好まれるのです。輪廻の思想が関係するのだろうか、みなさんどう思います?
菌根菌・・・生きている樹木の根にのみつくもの。樹木細根の乾燥防止、保水作用、ある種の窒素化合物などの栄養補給、根の増殖、吸収面積の拡大、病原菌の防除など、樹木の側に利点が多く、反面菌の立場では、樹木より炭水化物などを得て、樹木と菌とは共生関係にある。
参考文献
高橋郁雄 「北海道きのこ図鑑」
相良直彦 「きのこと動物」
ご協力
文・絵 M.H