国会議員が公設秘書給与を流用する問題は、何やら目障りな政敵を黙らせる
手段に流用されている観がある。流用の目手には①生活費等へ全くの私的なも
の②個人秘書給与や事務所経費への流用等がある。
①は論外だが②の場合に内実は変わらないのに、適法か否か(無届け)で糾
弾の対象に成ると云う、所謂「形式犯」である場合が多い。要するに「もっと
酷い」事例でも、各種の届けを怠らねば良いと云う事だ。
国家公務員として国費(税金)から給与を支給される公設秘書に、勤務実態
があるのか無いのか不明な親族を登用しても、法的には問題無しなのだ。共産
党の手法として有名な、公的な給与から党職員としての給与相当額を差し引き、
差額を「自主的な政治献金」として政治献金として上納させる慣習も問題だ。
自主的に献金している秘書はおそらく皆無だろうが、議員周辺からの献金「命
令」を拒否する事は不可能な筈だ。任免権は議員にあるのだから。
身分が保障されぬ特別職とは云っても、数百万円から一千万円を超える年収
は果たして適正なのか?所得に働きが釣り合わない「高級取り」だから、ピン
はねの的になって居るのだろう。実際は議員個人の懐に入る政党助成金と共に
廃止して、別の形で政治活動を支援するのも良い。代替案を出さずにすっぱり
と廃止するのも一考だ。
ここ数年の「国会劇場」を観ていると、政敵潰しの為に旧悪や身辺問題を引
き合いに出す風潮が蔓延している。形式犯とするには余りにも人を食った弁明
や振る舞いが多過ぎ、罪は罪として「断罪」する必要があるのは言うまでも無
い。言い方に語弊もあろうが、「形式犯」で国会が紛糾するのも情けないと云
う事に、我々も政治家も早く気付くべきである。
例えば期限を切って秘書給与などの「不適正処理」を申告或いは是正させ、
その後の法的責任を問わないと云う「時限立法」を考えられないか。何時か問
題に成った「経歴詐称」等、「重箱の隅」もこの際考慮の範囲ではないか。
その上で以後は議員にも政党にも重い自覚を求めて、万一にも不祥事の際は厳
格に対応する法を創る。先に述べた時限立法の期間内に、正直な申告をしなか
った不逞議員を一段と厳しく罰する事は当然の事。
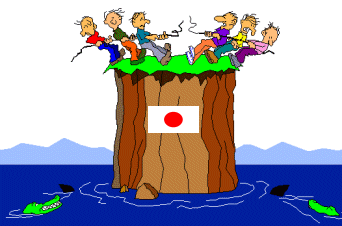
***********関連記事**************
2002.05.25朝日
私の視点 花見忠 日本労働研究機構会長 上智大学名誉教授
「議員秘書 労働者の権利に配慮必要」
議員秘書の給与を流用した疑いで、国会議員の責任が問われている。
実際には雇っていなかったり、国からの給与を他の目的に流用したりしている
場合には詐欺や横領の罪に問われ、流用した給与を届け出ていない場合には政
治資金規正法違反になる。しかし、これらの法違反の問題以外にも、流用は労
働基準法などで禁止されている「中間搾取」に該当する疑いがある。労働基準
法にある賃金の「直接全額払い」の原則に反することが、ほとんど問題にされ
ていないのは不思議である。
私的流用は許せないが、政党ぐるみの制度化した「公的流用」は許せるかの
ような主張もある。しかし、労働者である秘書の給与が、「寄付」という形で
「中間搾取」されている実態からすれば、徴収方法や使途が制度化されていれ
ばより公明正大だ、という感覚は理解しがたい。党内で制度化されているほう
が労働者の権利を公然と無視しており、こそこそやっているほうが、まだ救い
があるようにも思える。
制度化されていれば、給与の一部の寄付を拒否する自由はなく、拒否すれば
職を失いかねない。ただ、どちらの場合も、政治家にとっては、秘書の労働者
としての権利への配慮は二の次で、政治資金の源として「秘書給与」が大切な
ようだ。公設秘書は、国家公務員である。公務員法には給与の「直接全額払い」
の規定はないが、公務員にも労働基準法は準用される。政治家は管理監督者に
過ぎないとしても、労働基準法上は使用者責任がある。
秘書給与をめぐる議論の中で、制度化されていれば問題にならないという発
想の延長から、米国式の総額方式が一部で注目され、将来この方向で制度化さ
れる可能性も浮上している。この制度が機能するためには、政策秘書と一般秘
書といった職務の内容の厳密な区分と、それに見合う給与の基本的見直しが前
提である。また「中間搾取」の禁止など労働者の基本的人権についての配慮が
必要だが、これまでの議論を見る限りでは、そんな配慮は見えない。
もっと弱い立場の私設秘書については、ほとんど議論がない。こんな感覚の
政治家が唱えている構造改革や政治改革は、本当に労働者や一般国民のために
なるのか、心配である。