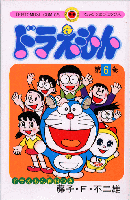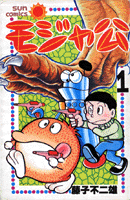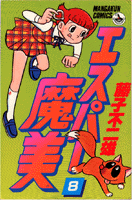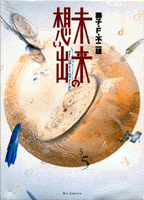|
■「ドラえもん」ほど国民的なマンガもそうないだろうし、そのおもしろさはすでに日本中(世界中?)に認知されているといっても過言じゃない。ので、今更ありきたりに紹介してもなんなんで、「ドラえもん」の子供向けマンガとしての素晴らしさに的を絞って、くどいくらいアピールしたい。 このマンガには、文庫版のタイトルにも見受けられる通り、「SF」「恐怖」「ナンセンス」「ギャグ」etc...と、まあ現在存在するジャンルのほとんどを横断する幅広さがある。 これがとんでもなく驚異的なことなのは言うまでもないだろう。 音楽でたとえれば、実験的ミクスチャー音楽なのに「みんなのうた」でかけれる、というようなもんだ。(ちょっとたとえがおかしいか?)そして「ドラえもんなんて、大の大人が読むもんじゃない」とか思ってる人はもう一度ゆっくり読み直せば、そこに描かれている内容の年齢を越えた普遍性、そして今も自分にはね返ってくる内容の深みに、気がついたらついつい黙々と読んでしまうだろう。 子供の頃とは違う視点から、このマンガのすごさに驚かされるのだ。大の大人の観賞に十二分に耐えうるにも関らず、子供(幼児)の目でもすんなり入り込め、なにかを受け取ることができる。なんという離れ業!! こども/おとなの明確な境界がない以上、これはいかなる年代になっても楽しめるマンガなのだ。それでいて、子供マンガの最高峰!! 児童マンガがサイコウの総合芸術、と言ったのは故、石ノ森章太郎だが、「ドラえもん」はその意味においても、別の文脈で語っても、普通に、にこにこしながら読んでても、やはりすごいのだ。 さあ、もう一回読んでみよう。(雅) ■僕の「ドラえもん」に関する思い出を。
|
![]()
|
■藤子・F・不二雄の作品は大別して、「SF生活ギャグ」ものと「SF短編」ものに分けることができる。そして、その2つの要素をあわせもったSFストーリーギャグが「モジャ公」。 地球人の子供、宇宙生物、ロボットのコミカルな主人公トリオの宇宙旅行の行く先々で生じる、異種文明とのギャップ(藤子SFに頻出するテーマ)。そこから生まれる笑い、スリル、サスペンス。 奇抜な発想とストーリーテリングの見本市とでも言うべき素晴らしい作品だ。 そして、奇想天外な展開の中にさりげなく混ぜられたシビアな視点、理解のすれ違い、社会の残酷。 それが子供向け。そしてもちろん大人向け。まさに藤子・Fの本領発揮! (あと、宇宙人の造形やネーミングも凄い。自殺評論家ケッカロン氏なんて存在自体ナンセンスギャグ)(雅)
|
![]()
|
■低年齢層向けと、SF短編のちょうど間くらいのバランスが秀逸な藤子・F・不二雄の佳作。 その内容は、「ドラえもん」などより、更に一歩具体的に踏み込んでおり、(主人公たちの年齢は他の藤子子供向け作品より若干上。)コミカルな面と、シリアスな面を実に見事に融和させている。 藤子作品に特徴的なのは、子供の頃に読んでも、今の視点で見てもそれぞれにおもしろいということだが、この作品においてはそれが特に顕著。 思うに、高畑や魔美の父親というのはかなり露骨に藤子・F自身の言い分が投影されてるんじゃないだろうか? 特に魔美の父親は、評論家には評価されないが、信念を持って売れない叙情的な絵を描き続け、(劇画ブームの折、藤子はかなり不遇の時代を経験しているらしい)魔美への忠告っぽくない忠告はいつも的確だ。登場頻度も実に多い。なによりいつも眼差しがあたたかい。まあ愛情余って娘のヌード描いてたりもするけど。 しかも心温まる話だけでなく、2巻収録の、オチで沈黙させる「魔女・魔美?」のように、鈍く重い読後感を残すものもさりげなく混ぜられている。 結局、超能力で人が救えるのではなく、真の超能力は人の持つ心なのだ。(雅)
|
![]()
|
■運命のいたずらに翻弄されながら、人生を何度も死んでは繰り返す漫画家納戸理人が運命に反逆する壮絶なストーリー。(絵柄がいつもの通りだからぱっと見は全然壮絶じゃないが)この主人公に作者本人をかなり投影しているとすれば、この切実さは尋常ではない。 納戸は「ざしきボーイ」が大ヒットして一躍一流漫画家に躍り出るが、一発屋に終わり、後の人生を寂しく送る。藤子・F自身は生涯ヒット作家ではあったが、自らのお気に入りの連載(「21エモン」や「モジャ公」など)は早々に打ち切りの憂き目にあっているのが共通している。 ところで夢や想像力というのは、現実に対する鬱憤から生まれることが多い。 藤子・Fは小学校4年生の時にずっと入院生活を送っており、友達ともろくに遊べず、学校にもいけない状況で、豊かすぎるほどの想像力を育んだらしい。 それはある意味、現実に対する藤子・Fの復讐戦であったはずだ。 これは、そんな藤子・Fの半生の鬱憤の結晶なのかも知れない。 決して逃避ではなく、絶対手の届かないものに対する挑戦のためのファンタジー。(雅)
|
![]()
|
|