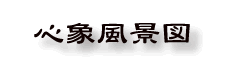
僕は走っていた。暗い一本道を、黙々と走っていた。足元の草の影は流れを示し、目前に映る半円内のアスファルトは確かに僕を通過していた。単調に運ばれる二本の足はうっすらと汗ばみ、生の蒸気を放散し続けていた。しかし疲れは感じず、息も乱れず、ただ一途に進行していた。
道の両端に立つ街灯は油が塗られて鈍く光り、笠を被った小さな電球はこちらに向かって微笑んでいる。その街灯が並んでつくる光の点は、緩く曲線を描きながら空高く天頂に向かって伸びている。一つ一つ光の間隔が遠くにいくに従って狭まり、二つの光の点線が遂には一点に重なっている。風を切る僕の横を光の点が後へと流れていく。一歩、足を踏む度に、その振動は心臓を快く揺らしている。
手のひらが火照り、汗ばんできた。僕は手のひらを広げてひらひらと振ってみた。そうすると冷たい大気が手のひらを覆って熱を吸収していった。
この世界は、空のようでもあったし湖のようでもあった、もしかすると宇宙なのかもしれない。大地のような気もする。ただ暗かった。闇に包まれた世界。ただ見えるのは目前のアスファルトと光の線だけだった。足の裏に感じる堅い感触、肌に感じる生温かい風、僕は黙々と走った。
両方の親指をそれぞれの四本の指で握り締めながら、唇を堅く閉じて。すると今度は頬が火照ってきた。僕は急いで両方の手のひらを開いて風になびかせて、その手で顔を覆ってみた。顔の熱がどんどん逃れていく。そして指と指との間を開いて外を見てみた。その時、僕はふと「春」を感じた。この暗黒の世界に。僕の身体が本能的に「春」のやわらかさを感じた。
「春なのか」、僕は心の中で呟いてみた。「そうか、キミが春だったのか」、僕の顔には微笑みが浮かんでいた。心臓の下、胃の上の方からジワジワと、興奮のようでいて、全く異質の感情が喉元まで昇ってきた。それは、喜びの感情だった。それは懐かしさに遭遇したときの一種のときめきだった。何故なんだろう、この喜びは。僕にも、まったくその喜びの意味が分からなかった。それは掴み切れない一塊の浮遊体のようであった。その浮遊体がフワフワと自分の周りを取り囲み、口から、鼻から、目から、皮膚の毛穴から、自分の体内に入り込み、刻々と充満していくのを感じた。
「さあ、きみは『春』なんだろう、早く正体を現してごらんよ、姿を現しておくれよ。」僕は闇に向かって問うてみた。しかし、返事は無かった。ただどす黒い対流が乱れあっているだけだった。僕は、だんだん気が急いていた。
「さあ早く、出て来いよ、早く」。僕の言葉は感情に満ちて多少乱れてきた。息も荒くなり、心臓の鼓動も早くなっている。前後に絶えず振られている二本の腕も力が入って固くなり、微妙に震えているようだった。薄赤く火照る皮膚からは汗が流れはじめ、前後へしぶき、心なしか足取りも力強くなった。二本の足から吹き出る汗と合流して、地に「ポタリポタリ」と落ちていた。
しかし、何の返事も返ってこなかった。それどころか、先程感じた「春」の気配もどんどん薄らいでいき、掴めなくなっていくようだった。身体に感じたあの浮遊体も今はもう消えていた。僕は焦った。何とか春を呼び戻そうと、急速に離れて行ってしまう「春」を連れ戻そうと。そして僕は大声で絶句した。
『春よ、なぜ逃げる、春よ。』その瞬間、目前で続くであろうはずの道が、うっすらと青みを帯びた電光で現れた。美しい光のレールが、目の前を浮かんでいた。いつの間にか、光の点を描いていた街灯が無くなり、薄青い光に包まれた神秘の道が、天頂に向かって細くなり、点となるまで伸びている。僕の手や足も、青い光が反射して青一色に包まれた。それは、あくまでも青く、純粋な空の色、スカイブルーの鮮やかさであった。
その美しさが僕の心の奥を撫ぜ、不思議な感情に導いた。それは記憶の無い自分が虚ろな目で見た街のネオンの光の様だった。その一色の光が、自分の記憶の根源を快くくすぐり、ある一種の溝に落ちて行く自分を感じた。
春の去った後に残された闇の中に浮かぶ青光の道は、冷たく、涼しく、そして爽やかな印象を僕の胸に焼き付けて、なおも光り続けていた。
僕は冷たい風を受けながら、視界に伸びる青い帯を「トストス」と走り続ける。誰も語りかけてはくれなかった。
僕の耳には、ある二種類の音が、交ざり合い、乱れ合って侵入していた。それは単調な地を蹴る音と、そして光の鳴る音だった。その青く浮かぶ道は、絶えずある音を発していた。それは、高圧電流の電線に近づくと聞こえる音、電流が激しく怒涛のように移動するときに発する、あの身体を震わせる振動音だった。その音が遠くの方から微かに、『フオオウ』と僕の身体に微振動を伝えていた。走るに従って、その振動音の音量が増し、自分の身体が震源地に近づきつつあることを示していた。
僕は青い道の下方を横目で覗いてみた。やはり真っ黒の世界だった。僕にはその世界が何千、何万メートルも深い、底の無い、無重力の宇宙のようにも見えたし、全く落差の無い地面のようにも見えた。そう思うと、僕はとてつもない恐ろしさを感じた。今の自分には、こんなにも近い、すぐ側の地の深さすら掴むことができない。自分にとって、それは、足を踏み外さなくては知ることのできない、死を掛けなくては知ることのできない謎であるのだ。
道の鳴る音は、ますます音量を強め、耳をガンガンと突つき、鼓膜はもう、これ以上の許容は許さなくなった。その振動は身体全体を包み込んで、走る足取りにも支障をきたしている。それはここが震源地であることを示していた。
暗い空を「ヒュンヒュン」と、電気の光が飛び交い、道の青い光が、一層強く輝いて、青い光の中を白い稲妻が右へ左へクロスを作り行き交っている。そんな奇景が展開していた。
僕は息を飲み、その奇景の前に足を止めてしまった。両足を大地に突っ立てて、ただ呆然と、その人間単位では計り知れない雄大な映像に包み込まれて。
「無数の光の切れ味が、宇宙を鋭く切り刻み、青い光は「ウォンウォン」と、光を強め弱めして、激しく、苦しく、のたうち返し、耳で感じる最大限のボリュームで、電気はうめき泣き叫び、僕の鼓膜を突き破る。」
もうこの世界は極限に近づきつつあったのだ。そして、それはすぐ側まできている。もうすぐこの世界は爆発して、巨大な風船が割れるように、この世界も一瞬の間に姿なく萎んでしまうのだ。
そうしているうちに自分はあることを思い出した。「元に戻ればいいんだ」・・・そうである、この先が行けないのなら、今来た道を辿ればいいのだ。元に戻れば、もう自分の記憶に残っていない、この道の始発点。僕が第一歩を踏んだ原点にすら戻ることができるはずだ。そう思うと、心に日が差し込んだような気がした。そして周りの状態などもう大したことではないように思えた。少なくとも自分には逃れる道があるのだ。その時点で、もうこの世界は極限では無くなったのであるから・・・。
それから自分は、薄笑いすらも浮かべて、自分の首を回転させていった。そこには、自分が歩んで来た道、数々の記憶する物々、自分の原点、そして「春」の手掛かりが数多く、そのままの形で残っているはずだから。頭の先から足の先まで、喜びや緊張、そんな興奮を循環させながら視界はどんどんと左へと移って行く。「走ってやるぞ、胸が苦しくたって、足が痛くたって、走り切ってやる」。目をギラギラと輝かせ、顔を紅潮させ、拳を汗ばませ、頭を後方へ回転させていく。
そして、ついに僕の目は百八十度後方へと据えられた。
しかし、そこにはもう道のかけらすらも残っておらず、ただ氷点下の冷たい風が左から右へ静かに流れる感覚が漂っているのみであった。
・・・その瞬間、僕の意識は消えていた。2 気がついたとき、僕は壁の谷間に寝転んでいた。壁に頭をもたれかけ、足も手も放り出していた。手は冷たくカサカサして、何だか青く感じた。
僕は頭の中を重く回転する鉄球を感じながら、その回転を制止させようと、前後左右に頭を強めに振ってみる。そうすると少しは平衡感覚が元に戻ったようだった。
今はもう夜なのかあたりは暗い。僕は、高く長い巨大な二つの壁に挟まれた細長い一本の路地にいる。視界の利く範囲で、その路地はまっすぐとどこまでも続いている。もっとも、途中からは闇に飲み込まれて視界の利くはずは無いのだが、それでも何だか、その道はまだ先へ続いているように見える。そして両側を挟む壁は断崖絶壁といえるほど、高く、不気味に連なっている。車二台がようやくすれ違うことのできるほどの細長い裂け目の中を、自分はよろよろと歩きだした。
やはりここは路地なのだ、それは都会の裏通りに見かける何の変哲もない風景の中であるのだ。
ポリバケツに山と積まれたゴミが、あちらこちらに散らばって路地を雑然としている。一匹の野良犬が道を横切り、闇に消えて行く。壁は落書きされつくし、どす黒くにじみ、半分破れたポスターが風にヒラヒラいっている。
そんな風景が沈黙の中進行していた。
まだ目が覚めきっていないのか、鉄球の回転はまだゆっくりであるが続いている。そのため自分は右へ左へゆらゆらと鉄球のバランスをとり歩いて行く。
心に染みる風景だ・・・。下から吹き上がってくる冷たい風をあごで受けながら僕はそう感じた。
〜一枚の新聞紙が風に吹かれて舞い上がる〜背中を猫背に屈ませて、紙切れの散在する薄暗い路地をヨタヨタと歩く自分。以前のように走る気力さえもう既に失っていた。
「この風景は僕の心だ」・・・そう自分は思った。まるで自分の身体は廃人のように動かなくなっている。落ちぶれたものだ。なおも自分は、歩こうともしないのに、ユラユラと歩いていた。
そのとき、自分の手の甲が薄っすらと明るくなっているのに気づいた。黄色く投影されたその光が自分の身体を包んでいた。それは街灯だった。街灯が一本、わびしく、暗く、僕の周りの道を照らしていた。それどころか、ふと気づくと、目の前にも黄色い点が間隔を次第に狭めながら奥へ奥へと続いている。
「そうだ、この風景は初めてじゃない。以前にも見た風景だ。」そう思うと少しは力が湧いてきた。
〜もしかしたら、春に会えるかも〜
そのとき、無人のはずの空間から一人の男の声がした。振り返ると、それは薄汚れた灰色の作業服を着た老人であった。浅黒い顔、小柄だが引きしまった体格、深い額のしわ。そしてトロンと垂れた優しそうな目。
「何をしてるんだ」
自分はその言葉を白々しく思いながらもある事を思いついた。・・・「この老人なら春のことを知っているかもしれない。この老人に聞けば何か分かる気がする」。そこで僕はその老人に聞いて見ようと、その老人の方へ顔を向けた。そうするとその老人は不吉さをも感じさせるような笑みを顔一杯に湛えてフムフムとうなづいている。
「上を向いてごらん」と、その老人は言った。
そのとき僕は何かが頭を走ったように感じて、出来る限りの早さでアゴを突き上げた。地面、老人、壁が流れ、そして真上で静止した。又ひとつ何かが頭を流れ、自分を震わした。なんと、自分が長く続く絶壁だと思ったものは実はどこまでも続く二つの超高層ビルディングだったのである。この暗さは夜のせいではなく、ビルが日を遮っていたためであった。その証拠に遥か高くにチラチラと赤や青の星のように細かい光が無数に散らばっているのが見える。多分あれらはビルを装う飾り物が日の光に反射したり、或いは自身で光ったりしてあのように見えるのであろう。ただしそれらの星はかなり上方でないと付いていなかった。下の方は全くの無装飾、全くの灰色の壁なのである。
そして、その星の空間を一線の白い光の糸が中央を分割していた。その糸が空である。
この、今自分がいる空間は青空の下に位置する闇の世界であるのだ。
『空がない』僕はこう呟いた。確かに空はあった。しかしそれは僕にとって空ではないのだ。それは単なる光の筋であるのだ。しかし、そういいながらも自分は内心笑い出したくなるような気持ちも備えていた。それは、あまりにも突然姿をのっこりと現した空の、その奇態が何とも滑稽だったからである。その隠れていた空をあざ笑うかのような気持ちで、その筋を横目でにらんでやった。
〜何と卑怯なヤツだ〜
老人は言った。
『そうだ、ここには昼は無い、いつも暗い夜ばかりだ。だからあの電灯はいつも灯っているんだよ』
僕は振り返ってみた。それは道を暖めている。あの木でできた街灯だった。長く続く陰気な暗い路地、ゴミが散在し、落書きされつくした、どす黒い壁。そんな風景に、暖かく、うつむきながら、優しく、精一杯、ほのかな明かりを送り続けていた。
老人は突然に僕の手首を力いっぱい握り締め、何も言わずに無理やり引っ張った。仕方なく僕はその力に抵抗せず、されるままに、その路地の奥へ奥へと侵入していった。
この世界は壁だけではなかった。しばらく行くと両側に人の住む家らしいものが、分厚いコンクリートの壁に掘られていた。そんな洞穴が両側の壁にほぼ並んで作られている。だいたいのものは四角くて狭い部屋がひとつ。その中にベットがひとつ、ただそれだけの風景だったが、中にはある程度飾られた家や扉のついた家もあった。そのほかに何やら商店らしい家もあり、そこには薄汚れたコップや皿、そのほかにタオルやシャツなどが石の台の上に数個並べられていた。
『粗末な住宅だな』・・・僕は心の中で呟いた。人間の住む所じゃないとも思った。岩を刳り貫いただけの住居では人間らしさが無いとも思った。そう思いながら黄土色した「たいら」じゃない壁を「細い目」で見下している自分にその老人が言った。
『優しい町じゃろう』と・・・。僕は老人の言葉がそれらしい言葉として耳に残っただけで、『ええ』と口から漏らして、なおも「細い目」をして歩いていた。
それから数歩歩く間に、微かに耳に残った「語句」が身体の中を循環し、ようやく脳へと到着したころ、異質な感情が身体の中を逆循環した。「優しい町!?・・・どうしてこの粗末な洞穴が、この落ちかけた壁が、この暗い道が優しいのか」あまりに唐突なことだったので、正常な意識にするまでには相当時間がかかった。数十歩歩いてから、自分の心はこう打ち出した・・・・「たしかにこの街灯は優しい。しかし、春じゃない。この洞穴も、壁も、この街灯も、秋のわびしさだ。わびしさゆえに優しい、あの雰囲気だ。ならば自分は春じゃなく秋を追っていたのか。・・・ただ単なる優しさよりも、うらかなしさゆえの優しさのほうが深く、本物だというのか」。いつの間にか細い目が一層細くなって、もうすでに閉じているのと同様になっていた。
『この先には仲間がいる。みんな優しいヤツばかりじゃ。この街のようにみな優しいヤツばかりじゃ』。老人が言った。
自分はこの老人の言葉に背筋が震えた。その優しさに会うのが怖かった、恐ろしかった、気味悪かった。その優しさに会った瞬間、自分の生気は抜き取られ、この街になることがどうしようもなく悲しかった。
僕は足を止めた。老人は後ろを振り向いた。僕は老人の目を見た、老人も僕の目を見た。その目が急に白く光り出し、老人がコックリとしたとたん、僕の頭からは一切の映像が抜き取られ、目先が真っ暗になった。そして気を失っていった。
3
「カラカラ」「カラカラ」
遠く彼方から、耳の中、三半規管を、ゆっくり風のように流れるものを感じながらも、目はまだ闇のほかは何も感じないでいた。そうしているうちにその「カラカラ」という音がじょじょに耳の中を圧迫し始め、目にも薄い光が侵入し始めた。気がついたとき、自分はある鉄筋コンクリートの建物の通路にうつ伏せになって寝ていたのである。右側には「眼科」と書かれた札が下がった部屋があり、その閉ざされた扉の外には金属製の異様な器具が無造作に「ワゴン」の上におかれている。その外に酸素のボンベやゴムの管やら、そんなものが 前後左右に散在している。左側にも同じ部屋がありこちらにも「眼科」の札が下がっている。前を見てみた。空間を型作る四本の線が確かに一本につながろうと僕の視線の中心へと伸びているが、数メートルの向こうはだんだんと薄暗く、その先は闇である。後ろを向いてみた。そこも全く同じ情景である。そのとき僕は気づいた。この空間で明かりの灯っているのは自分の真上の電灯だけだということを。その明かりが僕の頭を中心に丸く、柔らかく、優しく、この空間の一部を照らしているのだ。
「じゃあ、この音は何だ」。僕は思った。確かに「カラカラ」という音は以前にも増して耳に感じている。しかし、どうしても、その音の出元を知ることが出来なかった。四方八方から遠くの方から、ゆっくり風のように・・・。音の感覚だけは眠りの中で感じた音を少しの差異も無く、自分の耳に侵入していた。
氷のように冷たく、岩のように重く、石灰のように白い、そんな前後に通じる無慈悲な、無機質な空間を僕はその音源を探るために、フラリフラリと前方へ足を踏み出した。
「コーン」とかかとが鳴る音が四方八方へ響き渡った。その音が「カラカラ」という音と近づき合いぶつかり合って融合するのを身体で感じつつ、光を背にして歩いて行く。光から5メートルも歩んだところで「フーッ」と電灯が消えた。空間には光は無く、その暗さは既に眼球の許容を越えて、頼れるはずの五感の一つを喪失した状態に陥った。暗闇の中で僕はどうすることもできず、ただ、じっと立ち尽くしていた。そのとき、遠くのほうに「ホーッ」と明かりが灯った。もうすでに五感の一つは十分な活動に及んでいる。目を凝らして見るとその遠くの明かりの下に人影を見た。と思った瞬間、その人影は恐るべき速さで僕の後ろへと通り去った。はっきりと姿が見えたわけではなかった。ただ天井の明かりが前方から後方へと、次々と点いては消え、ものすごい速さで僕の後ろへと流れて行ったのだ。多分あの明かりの下に人がいたのだろう、まるで大砲が前方から後方へつきぬけていったように、全く突然な出来事だった。
「コツコツ」と音をたてながら歩く、不思議なことに天井の電灯はその真下に来ると点灯し、そこから離れると消灯する。また次の電灯の下に来ると点灯し離れると消灯する。その電灯を二十も過ぎたとき、先程人影が立っていたあたりに差しかかった。
その右手の病室を見てみると、中は明るかった。そこは個室でベットが一台と長椅子が一脚置いてあり、ベットには老女が一人仰向けに横たわっていた。更に中へと入って行くと、電灯が青白く灯っており、壁の掛け時計が7時35分を示している。僕は恐る恐るベッドに近づいて、その老人の顔をのぞこうとしたとき、急に外が騒がしくなって、勢い強い靴の音と、先程から耳から離れなかったカラカラという音が次第に音量を強めながらこちらに向かっているようであった。そのうち血相を欠いた中年の女性と「ワゴン」をひいた看護婦、そして医師がこの病室に飛び込んで来た。そのとき僕はその老女の顔をのぞき込み背筋を震えさせた。それは、昨年死んだ僕の祖母であるのだ。そうだ、これは正しく母から聞かされた祖母の臨終の場面ではないか。そうすれば、この中年女性は・・・やはりそれは僕の母である。
そう思った瞬間この映像は全く静止し、医師も看護婦も母も全く動かなくなった。その上これらの人物は人形に変じており、そして額や手にヒビが入り、しまいには全ての人形がボロボロと崩れ始めた。そのとき僕は巨大な風圧に全身を強打され僕の身体は窓ガラスを突き破り深い深い溝へと落ち込んで行った。4
気づいたとき僕は既に街の中を歩いていた。左右に並ぶ建物は、書店であったり電気店であったり、普通の繁華街の風景である。ただ違うのはその店には一人として客が入っておらず、品々が整然と置かれていること、そしてすべての人間は僕の歩く反対の方向へと歩いていることだった。僕だけがその流れに反抗して歩いている。よく見ると、その人間の顔が何と無表情なことか、全ての人間が笑いもせず怒りもせずただ単純な顔付きをして、皆同じ速度で歩いている。その上にその顔はいくつかのパターンがあって、全く同じ顔の人間が幾つも幾つも歩いている。まるでベルトコンベアーに乗せられた機械製品のような人々の群れ、僕はいたたまれず、その中の一人の腕を握ってみた。するとその腕が「スポン」と抜けた。しかし彼は何もなかったように歩いていった。僕は「この人間たちは死ぬんだな」と直感し、その横にある地下鉄の階段をホームへと走って降りて行った。
ここには全く人影は無かった。歩いているのは自分だけだ。数百段もの階段を下って、やっとホームに着いた。そうすると、まるで自分を待っていたかりように右手の方から電車がやって来た。銀色に輝く新しい電車、中には一人の人間もいない。運転手すらいない。僕が乗車すると扉が閉まってゆっくりと動き出した。電車はどんどんと速度を増して行く。それから五分もしたころ、前方に明かりが見えて来た。「外に出るのか」と思いながら扉の窓から外を眺めていると、それは崖と崖との間をつなぐ透明な筒であった。その筒を通過する一秒に満たない間に僕は全てが分かったような気がした。その崖というのは巨大なビルである、この地下鉄も先程の街も、すべてビルの中に作られた人工の空間だったのだ。そしてまさしくその瞬間に見た裂け目の世界は、以前に老人と見上げた、その空間なのだ。その裂け目の下に、あの老人と老人が「優しい」といった人々と、あの暖かい街灯がいる。
それからも地下鉄はますます進む。また五分ほど過ぎたとき、停車駅に着いた。しかし、そのホームにも誰ひとりいない。電車から降りて階段を上がろうとしたとき不意に後ろから声がした。振り返って見ると、それはまだ5、6歳の子供だった。『お兄さん、ちょっと来てごらんよ』その子供はそう言いながら僕の左腕をつかんで引っ張った。その子供が指さしてるのは鏡であった。言われるままに等身大の鏡の前に二人は立った。そうするとその子供は『この中に入ろう』と言う。『そんなことできないよ』と言おうとしたとき、その少年の身体はもうすでに半分も鏡の中であるのだ。・・・自分も中へ入ってみた。
そこには二つの部屋があった。一つ目の扉を開けると中は映写室になっていて暗い。座席が五台並んでいるだけの狭い四角い部屋だった。もう一方の部屋をのぞいてみると、それはとてつもなく長い長い部屋だった。両手で届くほどの幅なのに奥行きが深く、その終点が見えないほどである。その部屋の両側には無数の映画フィルムが隙間もなくぎっしりと詰まっており、先の先まで両側の壁がフィルムが黒くなっているほどだった。僕らは映写室の座席に腰を下ろした。そうすると一本の映画が始まった。タイトルが映る 「19**.04.05.02.35.26」一人の子供が布団の中でスヤスヤと眠っている。そんなシーンが延々と続く。よく見るとそれは5才の頃の僕の姿だった。その年の4月5日午前2時35分26秒。そうだ、隣の部屋に保存されているのは、僕の生まれた瞬間から始まる、完全記録映画だったのだ。そのフィルムには僕の行動の全てが記録され、今までの人生を一秒も逃さずに記録している。
気持ち良さそうに眠る幼い日の自分の顔をよく見ると、隣に座っている子供と同じなのに気づいた。驚いて横を向いたとき、その子供はこちらを向いて慢心の笑みを浮かべて深くうなづいている。そして画面の方を指さした。その指にしたがって画面に目をやると、そこに映し出されているのは、色とりどりの花々が散らばめられた草原であった。まぶしい光が緑の草に反射して草原全体が輝いているようだ。そう、それは僕の記憶の深層に残る場面。僕はその情景がいったいどこだったのか思い出そうとしても思い出せず、大人になった今でも、その問いを明かそうといたるところでそのきっかけを求めていた。それは僕の夢の中の一場面だったのだ・・・・。
僕の目は驚きのあまり、感動のあまり見開いて動かすことができなかった。血液が体内を早く巡り、身体が紅潮してきた。握り締めた手のひらは汗で濡れている。そう、これこそが僕が長い間探し続けてきた春の情景なのだ。僕は隣に座る幼い僕とともに映像の中へ飛び込んだ。
「ウワーッ」。大の字になって花の中へと寝転んだ「やっぱりここは天国だったんだ」、青く冷たい清らかな川、目にしみるほどの緑の草、色とりどりの花々、白や黄の美しい蝶、白い雲、青い空、涼しい風、遠くに連なる山々、すべてが僕の脳裏に染み付いていた、春の正体だ。
そのとき、幼い僕が僕を呼んだ。そして『この穴をのぞいてごらん』とひときわ草の茂っている場所を指さして言った。草をよけるとそこには両手のひらを並べたくらいの小さな穴があいていた。少しのぞいて見ると、中は暗くてとても広い空間のようだ。もっとよく見るために頭をその中へ入れるようにしてみた。窮屈な穴を何とか抜けて、頭一つその世界に飛び出した。そこにはもうひとつの世界があった、闇のその空間を目を凝らして見た。そうするとはるか遠くに青くて細い光の線が緩やかなカーブを描いているのが見えた。僕は笑を隠さずにはいられなかった。それは僕が春を探していたときに「トストス」と走り続けた光の道だ。やはりあの光の出発点がこの「春」だったんだ。
そうしているうちに僕の身体の半分がすでにその世界へと飛び出ていた。そして僕はすべてを悟った。−そろそろ僕は、もう一度光の道を走らなければならない−
終わり