出勤前の情景。
毎朝繰り返される、儀式にも似た習慣。
今朝もきっちりとネクタイを締め、ベストを着け、上着に袖を通す。
最後にそっと胸ポケットに右手を重ね、頭を垂れて目を閉じる。
暫し微動だにせず、一心に想う。
キリエ(主よ)・・・キリエ(主よ)・・・
キリエ・エレイソン(主よ憐れみたまえ)・・・
漸く面を上げた私は、ふとこんな事を始めたのはいつからだったろうと思い返してみる。
出勤前の僅かな時間でさえ惜しい時に、何時からか身に付いてしまったこの習慣。
私は無神論者だ。
かといって、他に何かを信仰しているというわけでもない。
だが・・・いつか偶然耳にした言葉が、私にこんな行動を取らせる。
神を信じないという私が祈る言葉は果たして、天におわすという神の元へと届いているのだろうか?
キリエ(主よ)・・・キリエ(主よ)・・・
キリエ・エレイソン(主よ憐れみたまえ)・・・
縁あって、この家の持ち主である老婦人から管理を任され、もう一人の同居人と共に暮らし始めて数ヶ月。
純日本家屋の家の中で、台所と、私の居るこの部屋だけが洋風に作られている。
持ち主の亡くなったご主人が書斎として使っていた部屋を、今は私が自室として使わせてもらっている。
こぢんまりとした部屋ながら使い勝手もよく、シングルサイズの簡素なベットも置ける。
互いの仕事柄もあって、同居人とは寝室を完全には同じくしないことを話し合っていた。
(時間的なものや気分次第で、一つの布団に眠ることもあったが)
最近の私は、一人で暮らしていた時より心もち早く目覚まし時計をセットし、起床している。
昨夜遅く帰ってきて、今日は非番だという同居人は隣室でまだぐっすりと眠っているはずだ。
起こさないように、静かに戸を開いた時、やっとこの不思議な習慣を始めた頃の事を思い出した。
開いた戸に手を掛けたまま私は動きを止めた。
普段から心身を擦り減らすような仕事をしているせいか、家に居る時、私はよく庭を眺める。
何を思うでも無く、全身で梢を渡る風を感じ、こちらを癒してくれるような何処か優しい植物の芳香に包まれ、萌え咲競う様に目を奪われる。
いつまでも飽きることなどないように、立ち尽くすこともしばしばだった。
確か、その日も私は庭にいた。
「室井さ〜ん♪」
そんな私を、同居人が探す声がする。
「ここだ!」
返事をするとすぐに、廊下をバタバタと近付いてくる音がする。
「ココだったンすか〜。探したんスよ」
廊下の角から青島が姿を現す。
そして私の姿を認めると、クシャッとその整った顔を笑顔でいっぱいにする。
「どうした?」
彼のこの全開の笑顔に、私はいつも少し切なくなる。
「折角今日は非番一緒だからって思って。夕飯とかの買い物、一緒して貰っちゃおっかな〜と思って♪」
これもいつもの少し甘えた物言い。
私はフッと笑って、青島の居る縁側の方に近付いた。
「今からか?」
「室井さんさえ良ければ」
私を見下ろしながら、青島は相変わらずニコニコと笑っている。
「わかった、行こう」
庭用の下駄を脱いで縁側に上がろうとする私に、さり気なく青島の手が差し出される。
「この位・・・女子供じゃないんだから、上れる」
少し高めとは言え、私には軽々と上れる高さだ。
「え?そんなつもりじゃ・・・」
シュンと、見る間に無いはずの尾を垂れた青島が哀れで、甘やかしているなぁと思いつつ、差し出されたまま行き場を無くしていた青島の手に自分の手を乗せた。
途端、青島の垂れていた想像上の尾がピンと嬉しげに持ち上がった。
だが・・・私は、青島が私の手を掴んだ瞬間、その手のヒンヤリとした冷たさに、過去の忌まわしい事件の一場面がなんの前触れもなく唐突に、フラッシュバックとなって甦ってしまった。
グラリと周りの景色が歪む。
一気に体温が下がるのが、自分でもわかる。
その場に踏ん張ってみたが、膝下の方から生気が抜けていくような感覚から逃げられない。
慌ててもう片方の手も使って私を抱きかかえようとする青島の、私の素肌に触れる感触が耐えられない。
しかし目の前の暗さが増してゆき、身体の自由さえおぼつかなくなった私には、冷たさを不快と感じても、駄々を捏ねる子供のように、小さく嫌々と首を振りながら目を閉じる事しか出来なかった。
フラッシュバックの光景。
普段はまるで、そんなことがあったのか?と言えるほど記憶の中からきれいさっぱり消し去っている筈の光景だった。
それが目の前に、今現在行われていることのように甦っていた。
血溜まりの中に横たわる青島。
自分の無力さに、立ち尽くす私。
彼の命が、その身体から抜け出してゆくのを、ただ見ていることしかできない私。
私が下した、最良で最悪の命令。
青島の手の冷たさを憶えている。
忘れることなど出来はしない。
流れ出る命の暖かさに比例して、冷たくなってゆく彼の身体。
あの冷たさが甦る。
私の心から、身体から、いや私を形作る全ての物から悲鳴が迸る。
決して他人には聞こえることはないけれど、私自身の声なき声だ、どれだけ堅く耳を塞ごうと、力の限り走れる限り早く遠くへ逃げようと、途切れることのない悲痛な叫びが私の鼓膜から消えるはずもない。
身体が粉々に砕けてしまうかと想われるほどの痛みにも、「痛い」という言葉の変わりに私が叫ぶ言葉は「青島」という言葉だけ。
気も狂わんばかりの痛みにのたうちまわり、粉々になってしまった私の心。
そこに不意に浮かび上がってきた言葉。
キリエ(主よ)・・・キリエ(主よ)・・・
キリエ・エレイソン(主よ憐れみたまえ)・・・
何時、何処で聞いたのかも定かではなかった。
しかし自分の内でそっと呟いた言葉に、本来の意味も知らないまま、痛みや苦しみが、ほんの僅かばかりでも軽くなった気がしたのだ。
うっすらと開いた私の目を、覗き込んでいた青島の大きな瞳が捕らえた。
心配なのだろう、眉を寄せ、私をジッと見つめている。
「・・・心配すんな、大丈夫だから・・・」
いつの間にかカラカラに乾いていた喉に、たったそれだけ言おうにも声が出にくくて苦労した。
口をへの字にしていた青島は、私がたったそれだけ口にしただけでもホッとしたようで、泣きそうな眉のまま無理に笑顔を作った。
「なんて顔してんだ。情けない顔すんな」
「室井さん、俺心配してんのに。酷いッスよ〜、そのいい方」
口調だけはいつもの調子に戻ったの青島に、私も安心する。
気分が安らいだせいか、すぐにまた目の前が薄ぼんやりと暗くなってくる。
今度私を捕らえようとしている闇は、先程の底の知れない暗い闇ではなく、暖かな眠りへと続く闇だった。
彼には悪いが、もう少しだけ眠らせてもらうことにした。
再び目を閉じる私を、独り言のような青島の呟きが、子守歌のように追いかけてくる。
その囁きは高く低く、心地よいリズムで私を抱き締める。
私は母親に守られる赤子のように、心から安心しきって、目の前の闇に身を委ねた。
夢現に聞こえる青島の言葉。
「おやすみなさい、室井さん。俺はずっとここにいますから。あなたの側に、ずっといるから大丈夫」
次に目覚めた時。
この言葉通りに、彼は私の傍らにいるだろう。
日頃の疲れに、居眠りしながら。
或いは、読みかけの本を片手に。
私の起きた気配は直ぐに彼に伝わって、「あれ?もう起きちゃったんですか?」言って、覗き込んでくるに違いない。
そして二人はたわいもない話を始めるだろう。
このところの忙しさに、話しそびれたことが山ほどある。
少しの間、寝転がったまま二人で話をするのもいいかもしれない。
二人きりの時間。
その時間こそが、私には何よりも得難く大切に思える。
頬と頬を寄せて、互いの身体の温かさを感じられれば、それが私には何よりも幸せだと思える。
情熱的に抱き合い、熱く燃えるような口づけを交わすよりも、静かに二人で寄り添うだけの時間。
擦れ違いの毎日でも、二人で暮らしているという、それだけの事に喜びを感じる。
他には何もいらない・・・とさえ思える。
ささやかだが、切実な願い。
何もいらない、二人だけで生きていければ。
私を抱きしめる手。
君を抱きしめる手。
互いの手だけを頼りに、愛し合い、生きていければそれでいい。
この生命をかけて、生命の限りに君を愛したい。
君だけが・・・君こそが・・・・・
だが私は知っている。
これほどささやかな願いでさえも、成就することが、どれほどに厳しいことか。
君を大切に想っている。
その気持ちだけで暮らしていけるのなら。
その気持ちだけでこの暮らしを守ることが出来るのなら。
全てをかけて、この気持ちを貫こう。
そうして君だけを・・・君こそを・・・・・
だが私は知っている。
いつか来るその日が、やがて、しかし確実に近づいていることを。
その日が来るのが避けては通れない事ならば、せめて一日でも、一時間でも遅くと祈らずにはいられない。
『愛しき日々』
私達二人だけの、限りある小さな世界。
だからこそ、今日も祈らずにはいられない。
脆く穿かない小さき世界のために。
一時の夢のために。
美しくも哀しい想い出を創るために。
この先、一人でも前に進んで行けるように。
この世界での日々を拠り所として。
昔耳にした言葉が甦る。
キリエ(主よ)・・・キリエ(主よ)・・・
キリエ・エレイソン(主よ憐れみたまえ)・・・
ゆっくりと2度ほど目をしばたいた。
手を掛けたままだった戸から廊下に出て、小さな家の廊下の際奥にある自室の前から、出来るだけスリッパの足音にも気を付けて玄関へと向かう。
歩きながら、いつものように同居人と顔も会わすことなく先に出る時は、食堂のテーブルの上に一言書き置いてくるのを忘れていない事を頭の中でチェックする。
玄関には、彼方も遅く帰ってきて疲れていただろうに、同居人によって完璧に磨かれた靴が、キチンと揃えられて私を待っていた。
それを見ただけで、自然と微笑みが洩れる。
鞄を脇に置いて、上がり口に腰を下ろす。
下駄箱の横に掛けてある靴べらを取って、靴を履く。
美しく磨かれた靴の履き心地を確かめて、私は漸く立ち上がった。
靴べらを元に戻して、鞄に手を伸ばす。
と、私の手が鞄に届くより一瞬早く、鞄は持ち上げられた。
「いってらっしゃい」
私に鞄を差し出しながら、何時の間に起きてきたのか側に来て同居人が言った。
寝起きの、ボサボサの頭とパジャマ代わりのスエット姿ままで見送ってくれるらしい。
「行ってくる」
「気を付けて。夕メシ、美味しいもん作って待ってますから」
低血圧が辛そうな笑顔に、私は返事の代わりに一つ頷くと鞄を受け取った。
玄関の戸を開いて一歩外に出る。
「室井さん」
私を呼ぶ声に振り返る。
ポケットに片手を突っ込んで、同居人が手を振っていた。
彼が好きだと言う笑顔を残して、私は歩き出した。
ささやかでも、何物にも代え難い日常。
守るべき「小さな世界」。
祈ろう。
明日もこの世界で朝が迎えられるように。
キリエ(主よ)・・・キリエ(主よ)・・・
キリエ・エレイソン(主よ憐れみたまえ)・・・
主よ 今日も世界をお守りください
私に生命を与えたもうた その御手で
キリエ(主よ)・・・キリエ(主よ)・・・
キリエ・エレイソン(主よ憐れみたまえ)・・・
主よ あなたの元に私の祈りは届いていますか?
私の このささやかな願いは叶うのですか?
キリエ(主よ)・・・キリエ(主よ)・・・
キリエ・エレイソン(主よ憐れみたまえ)・・・
あなたの望むまま 心のままに
あなたの与えたもうた この命さえも捧げます
だからどうか・・・・・
キリエ(主よ)・・・キリエ(主よ)・・・
キリエ・エレイソン(主よ憐れみたまえ)・・・
出勤前の風景。
毎朝繰り返される、儀式にも似た習慣。
そして一日が始まる。
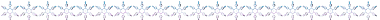
♪作者様からのコメント♪
うささんとお知り合いになって以来、とても仲良くしていただいております。makkeと申します。先日はお忙しいうささんに、HP作成を手取り足取り。ウチはうささんが作って下さったも同然です。
で、ナニかお礼をと申しましたら「『踊る〜』のお話下さい♪」即答でお返事を頂きました。あの!!うささんに「下さい(にっこり)」と言われて驚愕した私の姿を皆さま、想像するに難くないと思うのですが(^^;呆然としつつも「はぁ・・・」とお返事してしまいました結果がコレです。うささんのお話は言うまでもなく、ゲストの皆さまのお寄せになったお話の数々の足元にも及ばないお話ですが、私なりに一生懸命書かせていただきました。
ウチの二人は、よそ様よりチョイとばかりアナザーワールドを形成しておりますのでお解りづらいとは思うのですが、こんな二人しか書けない私でして。どうぞお許し下さい。
エセムロイストを自称している私の室井さんはこんなヒトです。これからも眉間の皺を消すことなく、苦悩し続けて頂こうかなと・・・・・(・・;
とにかく、今は皆さまの御気分を害するであろうと言うことだけが気がかりです。苦情、ご批判を真摯に受け止め、反省のため籠もる穴も用意しましたので、お気遣いなくバンバンお叱り下さい。首を洗ってお待ちしております。
makke 様へのご感想はこちらまで
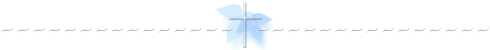
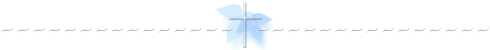
へ戻る