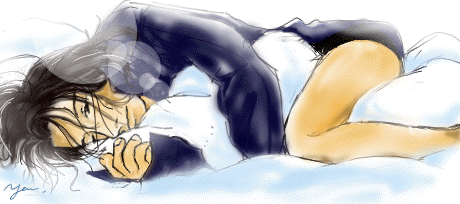
天からの贈り物じゃないけど、黙って受け取って?
『Gift番外編』
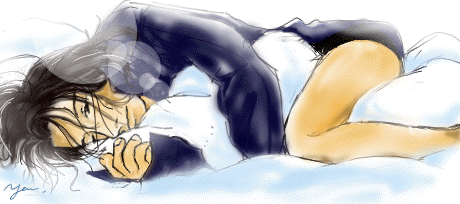
このページの画像は、すべてyen@gallery様から使わさせていただいております!皆様も遊びにいらしてくださいね!
ギフト番外編122話『チョコレートを届ける』
バレンタインやしね。当然やね♪

正広にとって、至福のシーズンがやってきた。
正広には、至福のシーズンが年間いくつもあるが、その中の一つ、2月14日、バレンタインデーである。
「たぁだいまぁ〜〜♪」
浮かれあがった正広の声に、由紀夫はこめかみをぎゅうっと押える。
「見て!これ、可愛くないー?」
「可愛くない」
「見てないじゃん!」
「見せてねぇじゃん!」
んもぅ〜。
ダッフルコートにマフラー、さらに耳当てまでした正広は、そのままの格好で、可愛いピンクの紙袋から、うやうやしく、透明プラスチックケースを取り出してきた。
「ほら!」
「あぁ。クマな」
「えぇ!?」
両手でそのクマ入りケースを支えながら、正広は大きく仰け反る。
「それだけ?!」
「何が!」
「可愛いじゃん!チョコのクマだよ!」
「おまえ、そんなのいくつ持ってんだよ!!」
そう言われて正広が数えてみたところ、クマは、14個あり、これが15個目であることが判明した。
「結構あるね」
「結構どころじゃねぇだろ!クマだけじゃねぇのに!」
男二人暮らし。ウジが湧いても不思議ではないはずの空間には、チョコレートが大量に飾られていた。どうやら今年の正広的トレンドは、なんらかの形に成形されているチョコらしい。
クマだけじゃなく、色んな動物だったり、乗り物だったり、そんなチョコレートが部屋中に溢れかえり・・・
「甘んだよ!!」
「だって可愛いじゃん!」
「だって、って理由になったねぇだろ!!」
由紀夫とて、チョコレートが嫌いな訳ではないが、部屋中が甘い香りというのはなんだか気持ちが悪くなってしまう。
早くバレンタインなんか終わればいいのに!と思う由紀夫は、当日、すざましい量のチョコレートをGETすることになっていた。
「だって、兄ちゃんのとこにくるチョコレートは、ゴディバだ、トゥール・ダルジャンだ、ペニンシュラだ、デメルだ、なんだー、かんだーって、絶対カッコいい系じゃん!だったら可愛い系は自分で用意するしかないじゃん!」
「何を言うのかね、正広くん」
正広が嬉しがって買い集めてくるチョコレートの香りに包まれながら由紀夫は言った。
ポン、と、正広の肩に手を置いて。
「正広くんのとこにも、たくさん可愛いチョコがくるじゃないか!」
「え〜」
精一杯の笑顔で言ったのに、正広は不服そうに唇を尖らせる。
「そりゃちょっとは来ると思うけど、兄ちゃんみたいに本命バリバリチョコこないもーん!俺はね、自分のキャラを解ってんの。俺なんかね、俺なんか、下手したら、『ひろちゃん!一緒にチョコ買いに行かない!?』キャラなのっ!!」
って、だからそれはおまえが、ホントに毎日ように様々なチョコを買いにいってるからじゃあ?
見るだけといいながら買ってくるからじゃあ??
「あ、兄ちゃん」
その目を見て正広は言い切った。
「これでも、吟味に!吟味を!重ねた結果!なんだからねっ!!」
欲望のままに買ってたらこんなもんじゃすまないんだからっ!
なぜかプンスカ怒りながら、正広はそのクマ型チョコを、出窓にディスプレイしていく。
「かーわいーー・・・」
「この、月光町ちっちゃいものクラブ員め・・・!」
アニメおじゃる丸から、解りづらいののしり言葉を吐いてみる由紀夫だった。
このように、正広は、どっぷり!バレンタインデーに浸かっていた。正確にはチョコレートに浸かっていた。つま先から頭のてっぺんまで、チョコレート漬けになり、この時期にしか見られない、数々の素敵なチョコを見て回っている。
そして当然買ってもいる。
彼にとってのバレンタインデーは、女の子から愛の告白をされる日ではなく、信じられないくらいのチョコレートが売られている日だ。
「でも、やっぱり手作りじゃない?」
こちらは、数々の手作りチョコレートの本をGETし、準備に余念のない千明と典子。
「そりゃ、手作りよぅ〜。どんなに高いチョコより、あたしのあ・い・が!こもってるもの♪あ・い・がっ!」
その『あ・い・を』!捧げられそうになっている由紀夫は、心の底からイヤそうな顔で会話には参加しない。してたまるかという孤高さを保つ。
でも、正広はやたらと食いつく。
「あ!あのね、これ!この本簡単なのあった!」
その本とは、『林’s ショコラ』。探偵ナイトスクープでおなじみの、辻調は製菓の先生、林先生が出したチョコレートの本だ。
「これね、簡単そうじゃない?チョコ溶かして、生クリーム入れて、固めるだけ。そしたら生チョコっぽくなるんだって」
「えー!簡単そー!」
「チョコが、なんだっけ。カカオ分何パーセント以上とか?生クリームも、脂肪分何パーセント以上とかあるけど、簡単っぽかった!」
「由紀夫ぉ〜。それでいい〜?」
「それくらいなら、材料のチョコを貰った方がいい」
「んもぉー!」
「それ!!!」
千明がぷくーーとほっぺたを膨らませたところで、奈緒美の声が、腰越人材派遣センターを揺らした。
「それにしましょう!」
「はいっ!?」
「何が!」
驚く社員達を尻目に、奈緒美には言い切る。
「そのチョコを作りましょう!」
「なんで!!」
しかし由紀夫は押し切られずに聞き返した。
「なんでそんなチョコをいきなり・・・!」
「仕事だからよ!」
「ここは何屋だーー!!」
「人材派遣会社です!」
奈緒美は胸を張り、腰に手を当て仁王立ち。
「人手の足りないところに、仕事を求めている人を派遣する!それが我が社の仕事よ!」
「チョコ作りの手が足りないってことは、どっかのお菓子屋さんですか?」
ちっちっち。
正広の当然といえば当然の質問を、奈緒美は指を振って却下する。
「アイドルの手作りお菓子を作るのよ」
「・・・アイドルの、手作りお菓子?」
一瞬間があいたところで、正広がポン!と手を叩いた。
「腰越人材派遣センターのアイドル、由紀夫兄ちゃんが手作りチョコを作って、ファンの皆さんにプレゼント!」
「ん!それはそれでいい企画ね!」
「じゃああたしあたし!あたしにちょうだい!由紀夫!」
「そんなこと、誰がやるかぁ!」
「あの、私、作っても・・・」
「いやよー!野長瀬さんの『手作り』ってー!なんかいやぁー!」
「お黙りなさーーい!!」
奈緒美は大きく叫び、口々に騒ぐ社員たちを黙らせる。
「アイドルよ、アイドル!アイドルが明日ファンの集いをするけど、そこで手作りチョコを配りたいって言うのよ!」
「え?」
由紀夫が聞き返す。
「じゃあ、そのアイドルの変わりに、チョコを作れってこと?」
「そゆこと。正解。あいがーりっ」
「・・・それって、解った、って意味じゃ・・・」
べらべらステーションを時々見ている典子が小さな声で突っ込むが、奈緒美には届かない。
「いかにもアイドルの子が作っていそうなのがいいじゃない!それにしましょ!ケーキは作るのが大変だけど、生チョコなら簡単だし!」
「あのっ・・・!」
野長瀬が、真剣な顔で一歩前に出た。
キリリ!と引き締まった、確かに男らしい顔をしている。
「何?」
なので、奈緒美も、真剣なビジネスマンの顔で向き合った。
「・・・アイドルって一体、誰が・・・!」
「の、野長瀬・・・」
由紀夫は力一杯脱力したが、意外なことに、事務所の空気は緊迫したまま。え?と正広らの顔を見ると、みな真剣な表情で、奈緒美を見つめている。
「アイドルって誰ってそんな気になるか!?」
「なるよ!当たり前じゃん!」
ミーハー全開の正広は、ひたっ!と奈緒美を見つめたまま叫ぶ。
全員の視線を集中させ、奈緒美もとてつもなくいい気分だ。
ふふ、驚かないでよ?と前置きして、口にしたそのアイドルの名は。
「綾浦マツ!」
「マツって!!」
「マツちゃんですか!!」
今時マツって名前はないだろう!!と由紀夫は思ったが、野長瀬は感激している。それはもう夢見る乙女になってしまっている。表情も、仕草も。
「何歳だ!マツって!」
「15歳ですよ!マツちゃんは!」
「マツちゃんって言うな!」
「へー、綾浦マツって15歳なんだぁ」
「マツって・・・!」
「あのね、兄ちゃん、綾浦マツってね、今、CMとかにも結構出てて、今時の可愛い顔に、マツって名前のギャップがいいって評判の子でね」
「あぁあぁそうですか、そうですか!」
もうこんな星とはおさらばしたい。なんなら、届け物の依頼がないか御用聞きに伺ってもいい!と顧客回りに出ようとまで考えた由紀夫に、当然と言えば当然の依頼が現れた。
「と言う訳で、そのカカオ分何パーセント以上とか言うチョコレートを、えーっとね。5kgばかし買って来て」
「5kg!?」
「いや、5kgじゃあれだからー。10kgいっとこうか。それと、何がいるの?」
「生クリームです。チョコの半分あれば大丈夫かな」
「じゃ、5kg」
「生クリーム5kg!?5リットル!?」
「とにかく由紀夫、急いで!明日なんだからイベント!だって作っただけじゃダメなのよ!ラッピングもしないと!」
「兄ちゃん、後ね、ココア!最後にまぶすから!」
こうして、腰越人材派遣センターに、尋常ではない量の製菓材料が集められた。
由紀夫が買ってきた材料の中でも、10kgに及ぶチョコレートは、ヴァーローナグラン・クリュ・シリーズの、グアナラ。1kg3300円というもの。
「・・・あんた、いい加減にしなさいよ・・・!」
「カカオ分、70.5%だぜ」
生クリームだって、オーム乳業ピュアクリーム48、1リットル1800円。ココアはやっぱりバン・ホーテン。
「たっかいものにつくわねぇーー!!」
材料費は、依頼費に含まれているため、奈緒美は少々むかついたものの。
「笑えるよね・・・」
1kgのチョコレートの塊は、確かに笑える。
クマとか、ウサギとか、そんな可愛い形にこだわってきた正広も、チョコレートの塊がもつ圧力に、なぜか半笑いになっていた。
が。
その半笑いは、15分後、全員の顔から姿を消す。
生チョコをつくるためには、まず、このチョコを削っていかなくてはならないのだ!!
「カンナ持って来い!カンナ!!」
「その気持ち解るぅー!由紀夫ぅー!!」
10kgのチョコを刻むという作業は、お菓子作りなどといえる代物ではない。
チョコレートを手の熱で溶かすわけにはいかないと、暖房の切られた部屋で、おのおの、チョコレートに立ち向かう。
作業場は、それぞれのデスクだ。
「あぁ〜、これで忘れたころに、チョコのくっついた書類とか出てくるんだわぁ〜・・・」
ひたすら1kgのチョコレート塊と格闘しているが、いつまでも削っている訳にはいかない。10kgのチョコレートを、一度に湯煎になどかけられないからだ。
正広が削られたチョコをかき集め、小さなボールにいれては、溶かすのだが。
「ちょ、ちょとまって!?これ、溶かすのはいいけど、生クリームいれなきゃ、また固まっちゃう!?」
「いれろよ、生クリーム」
「ま、まって、コンロが・・・!」
事務所なので、キッチンが大きいはずもなく、湯煎しながら生クリームとなると、それぞれの鍋が小さくなってしまうのだ。
「カセットコンロ買ってくるか?」
「そうして!由紀夫急いで!」
「兄ちゃん!後、バット必要、バット!」
「何で野球!」
「バットが違うぅー!!チョコ入れる金物だよぅーー!」
削れたチョコから溶かして生クリームと混ぜてバットに入れて冷やす。
その作業がひたすら繰り返される。
冷蔵庫の中身は、すべて出され、銀色のバットばかりが、キラキラと輝いていた。
ファブリーズしてもとれるのだろうかというチョコレートの香り。
しかし、作業している由紀夫たちは、意外に平気だった。
幸いなるかな。
人間の五感のうち、もっとも短い時間で鈍感になるのは、嗅覚だ。
まだ、チョコを削っている間に、固まったチョコをカットし、ココアをまぶして、パッケージに詰める作業も始まる。
綾浦マツのイラストがついた、透明なパッケージにチョコを2つずつ入れて、リボンで結んでいく。
無駄に可愛くレタリングされた『MATSU』の文字がなんだか哀しい。
「終わった!?」
あまりに無残な状況に、完全には状況を把握できず、奈緒美が言った。
「終わった・・・!と、思います!」
空っぽの冷蔵庫を確認し、野長瀬が答える。
「完成品は!?」
「こっちです!」
段ボール何箱にもなっている、綾浦マツ『手作り』チョコの側には正広がいた。
「来んのかよ、こんなにファン・・・」
ぐったりと時計を見る由紀夫は、5時半という現実の前に打ちのめされていた。
「来るか来ないかは私たちの知ったことじゃないけど、これを、明日イベント会場まで届け・・・」
「はいっ!!!!」
直立不動で、びしぃ!!と野長瀬が手を上げていた。映画、ハリーポッターを見たことのある人なら、授業中に優等生である女の子が、腕伸びるわ!というほど手を上げていたシーンを思い出していただければ目安となるだろう。
奈緒美はその野長瀬をチラリとも見ず、却下、と言い捨てた。
「なんでですかぁ!!」
「クライアントの気分をよくするのも仕事のうち!由紀夫と野長瀬と、どっちからチョコを受け取りたいと思うのよ!」
「由紀夫よねぇー!由紀夫ぉー!!」
「あー、うっせ、うっせ」
面倒くさそうに手を振って、由紀夫はソファに横になった。
「このままこっから行くわ」
「あ、じゃあ、あたし、そ・い・ね♪うぐっ!」
奈緒美に首根っこをつかまれ、放り出された千明だった。
そうして、バレンタイン当日。二時間ほど寝て、8時にイベント会場に到着した由紀夫は、綾浦マツと対面する事になった。
「あ、ちょこれーとだぁ、あのねぇ、まつねぇ、じぶんで、ちょこつくりたかったんだけどぉ、じむしょのひとが、だめってぇ」
すべての言葉がひらがなで聞こえたが、マツ、という名前を受け入れていることだけは素晴らしいことじゃないか?と内心で由紀夫は思う。
「それじゃあ、受け取りを・・・」
言いながらポラロイドを出すと、
「あっ!しゃしんだったらねっ、こっちこっちがね、かわいいとおもうのっ!でも、どうかな。まつ、こっちのほうがかわいいっ?」
「どっちも可愛いですよ」
「えーー!そぉかなぁ〜。でも、おにいさんも、きれいっ。いいにおいしてる〜。これ、どこのこおすい?」
「香水?」
「あっ!ひみつなのっ?まつには、おしえてくれないのっ?」
おしえて、おしえてっ!と、腕にしがみつかれても、香水をつけてる覚えなどなく、つけてないですよと引き剥がしながら答えるのだが、彼女は離してくれない。
「ねーねー、まねーじゃぁ〜。おにいさんね、いいにおい、してるの!まつね、きょう、いっしょにいたいっ!」
「はぁ!?」
「あ、あのっ!」
マネージャーと呼ばれた若い女性が、由紀夫とマツを引き剥がし、由紀夫を引っ張っていく。
「今日、楽屋の方にいてくださいません!?」
「何いってんですか!」
「いえ、あの、マツの好きな匂いがしてるんです!あなたから!」
「何が!」
「この甘い香り・・・!まさにチョコレートの匂いが!」
「あああ!!!!」
そして、髪にも、服にも、染みついてしまったチョコレートの匂いのせいで、面白くもない綾浦マツのイベントに1日つき合わせれる羽目に陥った由紀夫は、家に帰るなり可愛い可愛いクマや、うさぎや、サルや、カエルや、ゴリラのチョコレートをレンジでチンして、おかきの空き缶の中で固めてしまったのだった。
「ぎゃーーーー!!ひどぃぃーー!!しかも、おかきのかけら入りになってるし!!!」
「チョコ柿の種もあることだしな」
その後、由紀夫の元に山盛り到着したバレンタインチョコも、すべて同じ運命を辿ることになる。
別に松浦あやに興味はないんですが、綾浦マツって名前のインパクトが好きだったので(笑)
次回更新は、来週水曜日!の予定は未定にして決定にあらずっ!