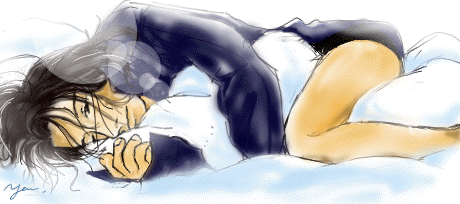
天からの贈り物じゃないけど、黙って受け取って?
『Gift番外編』
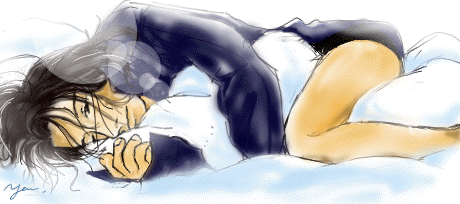
このページの画像は、すべてyen@gallery様から使わさせていただいております!皆様も遊びにいらしてくださいね!
ギフト番外編130話後編『カフェを作ろう?』

由紀夫や正広にはない男っぽさで、いきなり腰越人材派遣センター女性陣のハートをわしづかみにした純ちゃん。
純ちゃんの実家は流行らない喫茶店をやっているのだが、流行らないのレベルを超えた開いてるか開いてないのか解らないような店だという。
相談を受けた野長瀬が、今はやっぱりカフェ!カフェがいいよ!と己の憧れを込めて言ったのだが。
「それで、純さんのお店は、どんなお店なんです?」
今、その純ちゃんの接待をしているのは奈緒美だった。
「あ、あのですね」
なんか、距離ちけー、と、やや上半身を反らし気味にしているのは、同じソファの隣同士に二人が座っているから。純ちゃんは、背が高いがそれに負けじと足が長いため、座高は低めだ。
「純ちゃんのお父さんがやってるんですけど」
「野長瀬さんには聞いてませんよ、あ、お茶どうぞ」
奈緒美の反対側に典子が座り、野長瀬が正面に。
純ちゃん絶対絶命の図。
「大体、純ちゃんってなんなのよ、野長瀬。馴れ馴れしい」
「な、馴れ馴れしいって・・・!」
純ちゃんは、僕の友達なのに・・・!
「純さんは今は別のお仕事を?」
「はぁ、花屋をやっております」
「ま!カッコいいーーっ!」
奈緒美、典子ウットリ。
男前の花屋さんだなんて、なんて素敵なのかしら!その花屋に花を買いに行っていたのが、僕と智子ちゃんのスィートホームは、いつだってお花で飾りたいのさっ♪な男、野長瀬だったことは頭から無視したい二人。
「両親も、父親は普通のサラリーマン、母親も普通の専業主婦だったんですが、何を思ったか定年後突然喫茶店をはじめるって。自宅を改装しちゃったんですよ」
「なのに流行ってない」
「どうやって生活してるのかもイマイチ不明なんですが・・・」
「それはご心配でしょお〜?」
お茶だししたまま、座り込んだ典子に対し、あんたあっち行って仕事しなさいよっ!光線が奈緒美から発せられる。あたしは今から有休ですっ!バリアがどこまで対抗できるかが見物だ。
由紀夫は、またえらいことになってるなぁ、と思いながら、冷たい麦茶をごくごく飲んでいたところで、はっ!と弟の方を向いた。
あぁっ!
由紀夫呆然。
彼の弟、溝口正広は、キラキラした瞳で、純ちゃんを見つめている。
いや、正広は、純ちゃんを見つめている訳ではなく、純ちゃんの向こうに、『喫茶店』というものを見てキラキラした目をしているのだ。
正広は、『メニュー好き』だった。
何度行ったファミレスであっても、メニューの最初から最後までを眺める。値段とか、カロリーとか、写真とか、隅々まで眺める。注文するものが決まっていてもなかなか言わないのは、言ったが最後メニューが取り上げられてしまうからだ。
そこに、まだ行ったことのない喫茶店の人がやってきた。一体その喫茶店にはどんなメニューがあるのか気になって、気になって、気になってしょうがない。
しかし、今、その場は純ちゃん本人の話が盛りあがってるようだし、いつになったらメニューを教えてくれるのかしら、ワクワクワク。
そのワクワク具合は、兄弟だから、という理由じゃなくても、誰にでも解るものだ。正広の手元のコピー用紙には、どんどんメニューの名前やら、絵やらが描き込まれていっている。(ただし、正広の絵だけでは、それがなんのメニューかの判別はつかない)
「あのー」
見かねて由紀夫が声をかけた。
「お店、人が来ないっていってますけど、どういうメニューなんですか?」
「あ、それで、一応、メニュー持ってきたんですけど」
ぱああ!
正広の顔が3倍増し明るくなった。
「あ、め、メニュー?」
一応、それまでは事務所の下っ端ちゃんとして、大人しく控えていた正広も、メニューを聞いては黙っていられない。しかも、革張りに、金文字といったメニューらしいメニューだ。
「ひろちゃん、ひろちゃん!」
正広のメニュー好きを知っている奈緒美たちにも呼ばれ、メニューを見た正広は、それがメニューである、というだけで陶然とした。
「うわー・・・」
「・・・な、懐かしい感じ・・・!」
「古いでしょ」
純ちゃんが言う通り、典型的な『喫茶店』のメニューだった。
コーヒー、アメリカン、レモンティー、ミルクティー、ミックスジュース、ソーダフロート、スパゲティナポリタン。
「アイスクリームはもちろんバニラ。添えられてるのは、ウェハースに缶詰のチェリー」
「素敵っ!」
「銀のお皿で?」
「もちろん、アイスクリーム用のスプーンで」
奈緒美や野長瀬には普通の光景であっても、典子や正広の年代だと、それはまだ見ぬ新しい世界だったりする。
「ん?受けてる?」
純ちゃんは、喜ぶ正広や典子を見て首を傾げた。純ちゃんと野長瀬は、ほぼ同年代だ。
「あれ?メニュー的に間違ってない?」
「えっ!でもカフェー・・・」
野長瀬は、やけにカフェに未練があるらしく、カフェー、カフェーと呟いている。フレンチトースト〜、キャラメルソース〜、紅茶のシフォン〜。
「どこまで乙女なのよあんたわ!」
びしぃ!とそのメニューで野長瀬とぶっ叩いた奈緒美は、改めてメニューを広げる。
「典型的だけど、若い子には逆に受けるかも。問題は味がいいかなんだけど」
「アイスはレディーボーデンです」
「れ、レディーボーデン」
「えぇ。レディーボーデン。普通に買ってきたレディーボーデン」
「ま、味に間違いがないっていえばないっていうか・・・」
悪いところをあげろと言われれば、奈緒美にだっていくらでも上げられる。ただ、店の見ていない状態でのアドバイスには、さすがの女社長であっても限度がある。
「とりあえず行ってみましょう」
「え?」
奈緒美はすっくと立ちあがり、自慢の角度で純ちゃんに向かって微笑んだ。
「だって、純さんのご実家のことですもの♪」
「・・・俺、別に留守番でよかったのに・・・」
その、確かに薄暗い店の前で、由紀夫は呟いた。
腰越人材派遣センターオールメンバーマイナス1。
由紀夫はそのマイナス1になって、事務所で留守番をするつもりだったところを、無理やり連れてこられていた。
対して、行く気マンマンだったのに残されたのは野長瀬。
「あんなにカフェカフェってうるさい男なんて気持ち悪いでしょ!あの顔で!あの顔でカフェって!」
「まぁ、カフェっていう店じゃないよなぁ・・・」
確かに、典型的すぎる外見の喫茶店だ。昭和の時代なら、林立していたに違いないルックス。なぜ90年代の終わりにこの店を建てようとしたのか・・・。
なぜ、カーテンは閉められているのか。
このガラスの分厚さは何か。
「客に来てもらいたくない、って訳でもないんだろうけど・・・」
窓は、ピカピカに磨かれていて、中の色あせしていないカーテンが綺麗に見えている。openの札も、昔ペンションとかにあったような木製のものだが、ちゃんとかけらえている。
店の前にゴミなど落ちていないし、すさんだ空気はどこにもないが。
「・・・これだけ中の様子がわからないと、ちょっと入れないよねぇ・・・」
典子の呟きはもっともなものだと、全員が頷く。
「とりあえず、店の外にメニューでもおけば?」
「そうねぇ。値段だけでも分かればいいんだけど。・・・てゆーより、なんでこんなにきっちりカーテン閉まってんのか知りたいんだけど!」
「・・・店が出来た時には、こんなじゃなかったと思うんですけどねぇ・・・」
純ちゃんも不思議そうに言いながらドアを開ける。
カランコロンカラ〜ン。
美しい喫茶店の音だ。ドアベルの音だ。
奈緒美しんみり。正広うっとり。
「いらっしゃいませー」
店の中は、普通に明かりがついているが、決して煌々とではない。
「あら、純」
「相変わらず客いねーなぁ〜」
落ちついた色合いの店内には、クッションの良さそうな椅子と、木製のテーブルがいくつかあり、カウンター席もある。
そして店内には客がいなかった。
「どーすんだよ、この店」
「あらー、そんなことないわよ、ねぇ、お客さん来てくれるんだから」
純ちゃんの母親(銀粉蝶)は、傍らの父親(志賀廣太郎)に声をかけた。純ちゃんは一体誰から生まれたの!?というように、まったく似ていない父親は、奈緒美&典子のハートを軽く萎えさせた。
ウソ・・・。
まさか、純さん、年取ったらこのお父さんのよおになるというの!?このおとぉさんのよぉに!?
「うそぉ!!」
はっきりとした声が店中に響き渡った。
「これ、本物じゃん!」
店に入った途端、壁にはりついた由紀夫の声だ。
「本物って何?兄ちゃん?」
「これ、このポスター。復刻版とかじゃないですよね!」
「おっ。解る?」
純ちゃんの父親が嬉しそうにカウンターから出てきた。
「これ、たっかいでしょー・・・」
由紀夫が呆然と見つめているものは、古い映画のポスターだった。
同じように店のあちこちに飾られている。
「だからカーテン閉めてんだ」
「どゆこと?」
「このポスター、上映当時のホントのポスターだよ。海外のヤツも、多分。ですよね?」
「高いの?由紀夫」
「高い。ものにもよるけど、ここにあるヤツは、高いヤツばっかじゃないかな。・・・あ、これ!監督のサイン入ってんじゃん!」
「高いんだね!?」
そこで、ようやく正広も事情を把握した。
「直射日光に当てちゃダメなんだ!」
純ちゃんの父は、昔から、映画を見たらパンフレットや、ポスターを買ってしまう方だった。
憧れの喫茶店をはじめるにあたって、昔から捨てずにとっておいた洋画のポスターが綺麗だからと店に飾ってみたところ、これ、きっと高いよ、という話になったのだという。
売ってくれという人も現れた。
「それで、まぁ、ポスターの売買なんかも初めて」
「なんだぁそりゃあ!!」
そりゃ、息子の純ちゃんも怒ろうってもんだ。
全然客が入っていないというから心配してやってきたら、ポスターオークションなんかで、結構儲けているらしい。
「これだから、プロジェクタいれて、映像流してみたりとかしたらいいんじゃないかな。もう、映画マニアのための店にする。そして俺が通う」
「に、兄ちゃん!」
「ナポリタンも大好きだし」
「兄ちゃんってば!」
「おっ、あんたも映画が好きか」
「好き好き。いいなぁ、これ」
そんな訳で。
友達の実家の喫茶店を、カフェに変えたいという野長瀬の夢は、あっさりと費えた。
そして、ちょっと由紀夫の姿が見えないとなると、その店に入り浸っていることが多くなった。
本当にプロジェクターが設置され、映画が流れていたりするらしい。
由紀夫は、ナポリタンと、アイスアメリカンなどを飲みつつ、時々かけかえられるポスターを見ては、いいなぁ〜と眺め、なにせ金は持ってるもんだから、買っちゃおうかな、なんて思ったりしている。
彼は正広と違って、欲しい!買う!という短絡的な反応はないが、欲しい・・・・・・・・買う。となった時に使う額は半端じゃない。
「(からんころんからーん)あっ!やっぱりいた!兄ちゃん!」
その店に来る時は、携帯の電源がもちろんオフなので、正広がダッシュで呼びにくる。
「あ、どした」
「どしたじゃないでしょ。携帯電源いれといてよぅ!」
「迷惑じゃん。あ、アイス食べる?」
「・・・・・・食べる」
冷たく冷やした銀色の器に、ぽこんと半球のアイス。ウェハース、チェリー、やっぱり銀色のスプーン。そして。
「わ!いつもとちがーう!」
「早坂さんにも言われたから、メニューの開発もやってんだよ」
純ちゃん父の開発→レディボーデンのバニラアイスの上に、ハーシーのチョコレートソースをかけ、カラースプレーをトッピングする。
「・・・開発・・・」
首を傾げる早坂兄弟。
しかしまぁ、間違いのないアイスの味なので、二人でウキウキと食べていたら。
「あっ!だから、ゆったのに!二人とも呼ばれてますよ!」
今度は野長瀬がやってきて、紅茶フロートを勢いで頼む。
こうして、『喫茶おこのぎ』は、腰越人材派遣センター分室の様相を呈していくのだった。
志賀廣太郎さんは、どこからどうみても素敵なお父さんです。友達のまりちゃんがおとうさんバーを作ったら、ぜひ働いて欲しい人・・・!木村さんのお父さんだったこともあり(笑)
次回更新は、来週水曜日!の予定は未定にして決定にあらずっ!