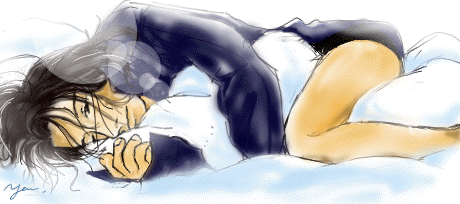
天からの贈り物じゃないけど、黙って受け取って?
『Gift番外編』
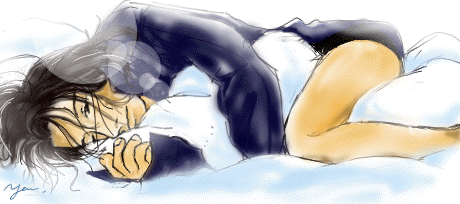
このページの画像は、すべてyen@gallery様から使わさせていただいております!皆様も遊びにいらしてくださいね!
ギフト番外編134話後編『夏限定和カフェを作る』

商店街の夏祭りに合わせ、腰越人材派遣センターの和カフェがオープンすることとなった。
オープン時間は、夕方5時から、お客がひけるまで。
「つまり、まだまだ準備ができるってことよ」
奈緒美は社員たちを前に、慈愛に満ちた笑顔で言った。
その日は、結果として、その夏一番の暑さとなる日だった。当然、出社してきた社員たちに笑顔はない。
「もういいじゃん、別に・・・」
暑い中、それでもスーツで、自転車に乗ってやってきた由紀夫は、クーラーの吹き出し口の前から動かず言った。
「何言ってんのよ!まだメニューもできてないじゃないの!」
「えっ?」
前日、10時過ぎまでせっせとメニューを作っていた正広がショック!と胸を押さえる。
「あ、違うのよ、違うのよ、ひろちゃん」
正広が作ったものは、テーブルの上に置くメニューであり、奈緒美が求めているのは、店内に貼る大きめのものだった。
「ほら!今日のお勧めとかそういう!」
「今日のって、明日もやる気か!」
「え?明日もお祭りあるの!?」
キラリ!と奈緒美の表情が輝く。あぁ・・・、と由紀夫は頭を抱えるばかりだ。
あぁ・・・、普通の仕事がしたい。
由紀夫はそう思った。
届け屋の仕事は好きだ。
いいことばかりじゃないし、夏は暑いし、冬は寒いけど、それが自分の仕事だと思える。
「じゃあ、画用紙を重ねて、文字は〜、あ、野長瀬さんの筆字とかどうです?」
「あー、ひろちゃん、それいいかも。野長瀬さんの字って、へたへたうまって感じで」
「・・・の、典子ちゃん・・・?」
「和だからね、和!それとー、実際のメニューだけども、野長瀬ちゃんと作れるの?」
「えっ?」
これからメニューを手書きして、それから、料理ですと?私が!?
あわわ、と軽くパニックになった野長瀬と、奈緒美の間に正広が入った。
「かき氷とかがメインだいから大丈夫ですー。僕でもできるし」
「あらぁ、そぉ〜?」
キリッ!な顔をした正広は、もう、楽しくて楽しくてしょうがないらしい。
高校に行ってないので、文化祭なんかを経験していないせいかもしれない。
そんな様子を見ると、普通の仕事がしたいと思っている由紀夫だって鬼ではなく、「あんこ受けとってくる」なんて準備のために出かけてみたりする。
が。
何せ、結果的にこの夏一番の暑さになる日だ。
老舗和菓子屋から特別に分けてもらうあんこを受け取りに自転車で道に出た由紀夫は、くらり、と、立ちくらみ感覚を味わう。
暑すぎる・・・!
由紀夫自身は、別に、あんこじゃん!と思うのだが、世の中には、つぶあんとこしあんにこだわる人はあまりに多い。なので、譲っていただくあんこは、つぶあんと、こしあん。これを、手作り最中や、宇治金時なんかに好みを聞いて使うことになっていた。
受け取る量もはんぱじゃない。荷台にあんこを2種類積んで帰るのか・・・。車を借りればよかった、と思ったが、すでに腰越人材派遣センターの駐車場は、カフェとしてセッティングをしてしまっているため、車は奈緒美の自宅におきっぱだ。
奈緒美の家とは反対方向の老舗和菓子屋を由紀夫は目指す。
雲一つない、晴れ渡る青空の下を。
「あーーぢぃーーー・・・」
「あっ兄ちゃんお疲れ様!」
絶対タクシーで行くべきだった!という道のりを、あんこニ種類、しかも、キロ単位で運んできた由紀夫は、クーラーにへばりつく。
「すげー、冷えてるぅ〜〜・・・!」
一度停電にあってクーラーが使えなくなった時があった。奈緒美はその時、本気で!自家発電を用意しようとしたほどだったが、今の由紀夫なら100%賛成する。
VIVAクーラー!引いてはVIVA電気!!発電するって素晴らしい!
「うわー、なんか、美味しそうなあんこー・・・!」
こちらも、あんこなんだから、つぶも、こしも、好き!という正広が、食べたい、と、顔に大書きしつつ、あんこ2種類を眺めている。
「いいからしまえ」
「えーー、でも、味見ー・・・!」
味見ー、味見ー・・・と、とっても未練を残しながら、正広は冷蔵庫にあんこを運ぶ。重たいもんだからよろよろと。
「あー、すずしー・・・」
由紀夫は、クーラーを18度にまで下げ、奈緒美からは環境の敵!と罵られながら、体が冷え切るまでクーラーにひっついていた。
「まじ、あっちー・・・」
長い髪はくくっていたけども、なんせ、そもそも豊かなものだから、頭も暑い。
「奈緒美さぁ、カフェとかじゃなくて、駐車場にコインシャワーでもおけばぁ〜?」
「うちは海の家じゃないの!」
「あ、ねねね、兄ちゃん」
未練たらたらながら冷蔵庫にあんこを収めた正広が戻ってくる。
「これ見て、これ」
手を引っ張られ、テレビの前につれていかれる。見せられたのは、お茶の講義用ビデオだろうか。お手前をしている着物の女性が延々映っている。
「・・・それで?」
20分くらいのビデオが終わった後、これがどうかしたか?と正広に聞くと、こっちこっちと、今度は倉庫に引っ張っていかれる。
「はぁっ!?」
そこには、さっきのビデオと同じような道具が並べられていた。
畳みではなくて、テーブルの上だったけども。
「兄ちゃんさ、さっきのって、できる?」
「さっきのぉ〜?」
由紀夫の映像的な記憶は奇跡的だ。それが、テレビに向かっていて、左右反転していたとしても頭の中で組み帰られる。
「えーっと・・・」
そして、案の定さっさとお湯をいれて、茶せんで感じよく素早く混ぜ、ひしゃくやらなにやらの扱いもビデオと寸分違わずできてしまうのだ。
「かっちょいー!」
「そうか?」
「じゃあ、宇治金時とかの時は、兄ちゃんがお抹茶いれられるね!」
「マジで!?」
これはこれで、昨日やると決めたにしては、変なところにこだわりのある和カフェなのだ。
届けられてる氷だって一流料亭に卸してるってものの横流しだし、抹茶だって宇治の名品だ。器にしても、本当なら薩摩切子を使いたいと奈緒美は思っていた。
思えば。
自分の店、というものを持つのは、これが初めてなのかも。
自分のマンションも、自分の会社も、自分の別荘も持っているけれど。
「そろそろ浴衣合わせてちょうだーい!」
そして、自分のウェイターも持っている奈緒美は上機嫌で、早坂兄弟を呼ぶ。
「こないだの金魚柄が可愛かったから、由紀夫はね、黒に赤い金魚のヤツにしたの」
「あぁ、こないだの・・・じゃない・・・?」
「違うわよ、新しくしたてたから。それで、ひろちゃんは、白地に赤い金魚で。ほらー!可愛いー!」
「きゃー!可愛いー!ひろちゃーん!」
「可愛い?可愛いっ?」
てへ!と白い浴衣を羽織って、正広はてへてへ喜んでいる。
「それで、由紀夫はこう男っぽく帯も結びたいんだけど、ひろちゃんはねぇ、せっかくだから兵児帯にして、リボンほどじゃないけど、ちょっと華やかにしようと思うのね」
奈緒美は、まだ浴衣を羽織っただけの正広の後ろにまわり、こんな感じで、と、兵児帯を結んだ。かなり、華やかに。
赤い兵児帯を、華やかに結んだ。
「・・・な、奈緒美さん・・・」
Tシャツジーパンの上に浴衣を羽織り、すそをずるずるさせながら鏡の前までいった正広は、後ろを覗き込み、言葉を失う。
「えっとー・・・」
「ひろちゃん、かぁわいいー!」
「の、典子ちゃん・・・」
確かに、その帯は可愛かった。
可愛い帯だし、可愛い結び方だ。
だが。
「に、兄ちゃん・・・」
しかし、果たしてそれが自分に似合うのか!?という目で兄を見ると、兄は、弟の視線を受けとめ、静かに目を反らした。
あぁ。そうなんだね。
その仕草で、正広も理解した。
似合う、似合わないじゃないんだね。
奈緒美さんがそうしたいというなら、そうしなくちゃいけないんだね・・・!
でも!でも、だったら僕は!!
「じゃあ、髪とかも可愛くしてくれますー!?」
「もちろんよひろちゃーん!きゃー!どうしようっかー!マニキュアとかするぅー!?」
「まっ、まにきゅあっ!?」
開き直った心を一気に叩き落された弟を見て、兄は、心の目頭を押さえる。
『がんばれ、正広・・・!』
贈れる言葉はそれだけだった。
だって、由紀夫の浴衣は柄も、着つけ方法も、帯も、ただ『カッコいい』だけなのだから。
「さ、準備いいわね」
時計の上では夕方だが、8月の5時なんて、単なる真昼間だ。
暑い。
大変に暑い。
そんな中、ようやく準備を終えた和カフェで、バカ高い夏の着物を着ている奈緒美が言った。
髪も、美容院でセットしてもらい、それはもうもちろん、「ママ」の風格だ。
雇われではなく、オーナーママ。
「じゃ、そろそろオープンしましょうか」
駐車場の周囲は葦簾で覆われていて、それをあけて、カフェオープンということになる。
それじゃあ、と、野長瀬が開けにいったところ、2階にある事務所に上がろうとするけたたましい足音がした。
「え?」
「お客さん?」
由紀夫が後ろからついて階段を上がろうとすると、ドアの前で、へたばっている人がいた。
「え!ちょっと大丈夫ですか?」
「あ、あの・・・!これを・・・!」
ほっそい。華奢な女の人だった。朝礼が8分続いたら貧血で倒れそうな人だ。当然、夏は日傘がなかったら外に出てはいけないはず。
そんな人が、風呂敷包みを抱えたまま、うずくまっている。
「正広!」
「はいっ!あの、氷です!」
事態をすぐ様把握した正広は、氷をいれたビニールを持ってきて、タオルと一緒に差し出す。
「どうされたんですか?」
その女性の顔に、正広は見覚えがあった。商店街で買い物をしている姿を見たことがある。彼女を見て、なんか、冗談みたいに失神しそうな人だと思ったことがあったのだ。気付けのブランデーを!とか言われてそうだと。
「あの、こちらでは、届けものができると・・・」
「はい、大丈夫です。どちらへ?」
由紀夫はすでに風呂敷包みを受けとっていた。
「娘に・・・!これを・・・!」
今にも意識を失いそうになっている女性は、苦しい息の下で娘さんのいる場所を告げた。
「かもめ・・・第三小学校・・・」
「・・・わかめちゃんか・・・!?」
「いえ、わかこといいます。磯野わかこ・・・!」
かもめ第三小学校に本当に磯野さんがいるってかい??
しかし、正広は、事務所をあけて、クーラーの効いた部屋に彼女を運ぼうとする。もちろん、お姫様だっこは由紀夫の仕事だ。
「私・・・!娘の荷物の中に、これを・・・!いれ忘れて・・・!」
さめざめ!と泣きくずれんばかりの勢いだった。これ?と風呂敷をあけた由紀夫は、これ!?と目を丸くした。
「盆踊りがあるんです・・・!」
「い、急ぎます!」
「兄ちゃん、がんばって!」
奈緒美から、どこいくのよー!オープニングセレモニーがぁー!と背中から怒鳴り声を浴びせられても、由紀夫は急ぐしかなかった。
浴衣すがたで颯爽と自転車にまたがり、かもめ第三小学校に急ぐ。
あんこを運んだ時と、きっと、気温は変わらない。
けれど、自転車のスピードは丸で違った。まさに飛ぶようなスピードだ。小学生の女の子が待っている。大事なものを待っているのだ。
かもめ第三小学校では、やぐらが組まれ、子供会主催らしき盆踊りの準備が出来ていた。子供たちが、それぞれに浴衣を着て集まってきている。
「あ!わかこちゃん!?」
そんな中、つまらなさそうに、スカートをはいたままの子供がいた。
健康的な小麦色の肌をした、しかし、顔はお母さんにうりふたつの磯野わかこちゃんだ。
「は、はい?」
急に呼びかけられ、わかこは驚いて由紀夫を見上げる。
浴衣を着た男に、自転車の上から突然声をかけられた小学生の反応としては普通だろう。
「お母さんが、これ忘れたって」
「帯!?」
そう。
子供会に行く娘のために浴衣を用意したわかこの母だったが、まんまと帯を入れ忘れていた。
それはもう、まんまとだ。
彼女は夏に弱い。夏に弱いが、冷房にも弱いため、部屋に冷房は極力つけない。つけないから暑い。暑くて寝られない。寝られないから起きておく。朝が来る。疲れて食欲が無いの悪循環に見事はまって状態で、浴衣に必要なものといっても難しい。
必要なものを書き出し、一つ一つチェックをしたが、そのリストの中に「浴衣」および「帯」という項目はなかったのだ。
忘れるはずないものだったのだのだ。
そしてわかこは、渡されたふろしきを手に、意気揚揚と小学校に向かったのだ。母親は直射日光に弱いから、夜になったら父親と学校まできてくれて、そこからは3人で縁日の予定だった。
学校では、友達のお母さんが着付けもしてくれるはずだった。
・・・まさか、帯がないとは思いもしなかった・・・!
そこに、奇跡のように帯を持った人が現れてくれたのだ。紺色にアサガオ柄という古典的な浴衣に、可愛らしいピンク系の兵児帯。やっと着られる!と思ったのに。
「・・・でも、ゆきちゃんのお母さん、帰っちゃったの・・・」
子供たちの着付けを一手に引きうけてくれていた美容師をやっているお母さんだ。
「え?着付け・・・!?」
確かに帯だけ持ってきても、着られなかったらしょうがない。
「えーっと・・・」
一度事務所に帰れば着付け名人はいる。いるが、今から帰ったのでは、スタートに間に合いそうもない。
由紀夫は一度目を閉じて、着付けられている正広を思い浮べた。
「こっちを合わせて、丈は、子供だから短くてもよくって・・・」
ぶつぶつ言いながら、服の上から軽く合わせてみる。
「ん!?いけるかも!」
こうして、由紀夫による着付けが行われ、正広とまったく同じ形の華やかな帯を結んでもらったわかこはとても喜んだ。
彼女の笑顔に、由紀夫の心も和む。
これが、届け屋の醍醐味なんだよなぁ・・・と。
そしたら。
「あのぉ・・・」
と、大人がやってきた。
学校の先生なんだか、ボランティアの手伝いなんだか解らないが、いわゆる妙齢の女性たちだ。
「あの、帯可愛いですね」
「はぁ」
「これではできませんか?」
「は!?」
柔らかい兵児帯だからこそできる帯を、普通の半幅帯でやれといわれ、由紀夫は硬直する。
「いや、それは・・・」
しかし、兵児帯軍団は、たくさんいたのだ。子供たちが、結構そうだったのだ。そして今の子供たちはおしゃれに敏感なのだ。
こうして、延々、由紀夫は帯を結びつづけることになった。
そんなこんなで、由紀夫が和カフェに帰りついたのは、すでに日も落ちてから。
奈緒美がひたすらお茶を立てつづける作業をしながら、氷の目で由紀夫を睨む。カフェは大盛況のようだった。
「あ!兄ちゃん、お帰りなさい」
「あのお客さんは?」
「日傘もなにもなしに飛び出しちゃって貧血起こしたみたい。うちでちょっと休んでから帰ってったよ。大丈夫だった?」
「あぁ、こっちは・・・。おまえ、足?」
「足?」
兄の視線が自分の足に落ちたのを見て、正広もそこを見る。そして、ざっ!と顔色を青くした。
「ち、血が・・・!」
鼻緒が擦れて、足の甲に血が滲んでいるいことに気付いていなかったらしい。
あまりに思った通りの展開だったが、正広はお盆を持っており、その上には、宇治金時ミルクが乗っている。も、持っていかなきゃ・・・!と涙目になる正広を見て、由紀夫はそのお盆を取り上げた。
「どこ?」
「あそこ、さくらのテーブル」
和カフェなので、テーブルにも、3番テーブルなんて名前は使わない。さくらであったり、かすみであったり、ともかく、なんとなく和な名前をつけてある。
由紀夫はそのテーブルに向かい、浴衣姿の女性ににっこりと微笑みながら、かき氷をサーブした。
「兄ちゃん、あんがとぉ」
「足、バンドエイドとかはっとけよ」
そんな中、手作りもなかセットをくれ、アイスはチョコで、とか、冷やしぜんざいぬるめで、とか、そんな謎の注文を受けながら、和カフェは大繁盛した。
「いたいよう」
帰り道、無感動に正広がいった。
足が痛いと庇って歩いているうちに、足全体の筋肉がどうにかなったらしく、うまく動けない。
せっかく正広も自転車でやってきたのだが、それで帰ることもできず、由紀夫の自転車の荷台に座っている。
「いたいよぅ」
「解ったから」
「兄ちゃん、いたいよぅ」
「だから、どーしろってんだよ!稲垣アニマルクリニックにでも入院させてもらうか!?」
「せめて森先生の病院にしてよ!」
なんだかんだ言いながら家まで戻ってきた由紀夫は、自転車のスタンドを立てようとして、正広が降りようとしないのに気がついた。
「どした?」
「思ったんだけど・・・」
「うん」
「俺も足痛いから」
「うん?」
「お姫様だっこされてもいいと思うんだけど、どうかな」
由紀夫は、なにせ器用なので、正広を座らせたまま、自転車のスタンドを立ててしまった。
「あれ?」
そして、そのまま二階に上がった。
「えー!ほっときー!?俺はほっときかー!兄ちゃーん!!」
一日にお姫様抱っこするのは一人で充分と思う由紀夫だった。
(その後、叫び続ける正広に負け、おんぶ、でお互いに妥協点を見出したという)
浴衣の帯は、「粋」と言い張れば結構なんでもありかもしれません(笑)ダメかな!ダメかな由紀夫ちゃん!そんでひろちゃんの足がすごくいたそうだ・・・!
次回更新は、来週水曜日!の予定は未定にして決定にあらずっ!