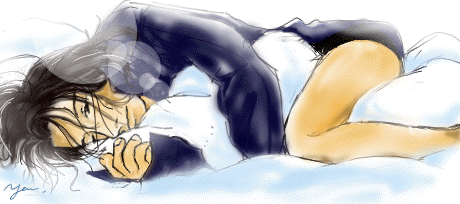
天からの贈り物じゃないけど、黙って受け取って?
『Gift番外編』
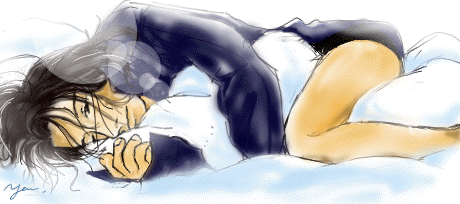
このページの画像は、すべてyen@gallery様から使わさせていただいております!皆様も遊びにいらしてくださいね!
ギフト番外編140話『あのおもちゃのぱったもんが届いた』

「バウリンガルって知ってる?」
正広がそう言うと、野長瀬がいきなり挙手した。
「欲しいです!」
「知ってるー。犬の気持ちが解るおもちゃでしょー?」
「ノーベル賞受賞ですよ!」
なぜか、自分が開発したかのように野長瀬は胸を張る。
しかし、野長瀬が言っているのは、ノーベル賞ではなく、イグノーベル賞。ノーベル賞のパロディ版として、犬の言葉が解るという、バウリンガルが受賞したのだ。
正広は、眺めていた雑誌で初めてその存在を知った。
犬の首につけて、吠えた声なんかを分析して、今の気持ちを絵や、言葉で解るようにするものらしい。
「ホントに解るのかなぁ」
「犬飼ってる人っていないよね」
「野長瀬さん、まだ買ってないの?バウリンガル」
「えぇ・・・」
野長瀬は、バウリンガルを知った時から、欲しくて欲しくてしょうがなかった。彼の大事なハニー、ミニウサギ(大)の野長瀬智子の気持ちが知りたかったからだ。
いかに自分たちがラブラブであるかを確認したい。
彼女の、自分に対する思いを、野長瀬は知りたかった。
そもそも、うちの智子ちゃんは、そこらの犬よりもずっと賢いはずだから、バウリンガルで充分気持ちは伝わると思っている。
でも。
野長瀬が、バウリンガルの購入に二の足を踏んでいるのは、智子ちゃん、ミニウサギなのに、犬用の首輪は大きすぎるんじゃないかな、と思っているからだった。
もちろん、ミニウサギと分類されながらも、智子は、下手なウェルシュコーギーよりも大きい。
「兄ちゃん、見たことある?」
「何を」
「バウリンガル」
「ないよ!どこで見るんだ!」
「えー。荷物届けた先でさー、バウリンガルのついた犬とか見たことないのー?」
「ない。せいぜい、ブランドものの首輪をしてるねぼけた犬くらいしかない」
「ブランドものって?」
「エルメスでオーダーしたとか」
「「「エルメスでオーダー!?」」」
「え、もうバレたの?」
フットマッサージ帰りで、パンプスすかすかだわぁーとご機嫌の奈緒美が、するっと言った。
「オーダーしたんですか!?」
「あぁ、バッグよ。いい革があるって言うから。ケリーとかじゃないんだけどね」
「おまえ、何者なんだよ!」
「何様って言いなさいよ」
「女王様って言いたいんだな!?」
「おほほほほーー!」
ご機嫌で社長席に座る奈緒美を見て、社員一同は首を傾げる。
・・・どこからその金が出ているのか・・・!
そんなむちゃくちゃな売上があるはずはないのに・・・!
まさか、自分たちの給料は搾取された後の・・・!?
そんな、下々のものたちの疑惑など気にせずに、奈緒美はデスクの上に手提げの紙袋を置いた。
「おもちゃもらったんだけど、誰かいる?」
「おもちゃ?」
「なんか色々入ってるけど」
なんだなんだと、わらわらと集まってきた社員たちだったが、その袋の中身は見たことがないようなものばかりだった。
「・・・なんなんですか?これ」
「さぁ。さっきマッサージ行ったら、知ってる人がいてね、その人がくれたの。会社の試作品だって言って」
「こないだ、なんでも鑑定団で、試作品のおもちゃが、50万くらいで売れてましたよ?」
「それは古いものでしょー。これは、開発はしたけど、商品にはならないってものじゃない?」
「じゃ、遊び方とかもよく解らないなぁ・・・」
とりあえず全部を出してみたところで、典子が悲鳴を上げた。
「こ!これ、もしかして!!」
「たっ、たまごっち!?」
かつて一世を風靡し、そして、あっという間に消えていったたまごっち、のような形をした電子おもちゃがある。
「たまおっちってのもありましたよね!」
「あったー!懐かしいー!」
「・・・てことは、これは・・・」
「ふぁ、ファービー!」
言葉を覚えるといわれていた電子ペット、ファービー、を、さらにリアルにしたようなものが由紀夫の手の中にあった。
「ただでさえ、イマイチ可愛くなかったのに、なんだこのリアルを追求したようなルックスは」
「こわー・・・」
正広は肩をすくめ、典子は、たまごっちのようなものの電源を入れてみた。
「え。何これ」
しかし、小さな画面を見つめて思わず呟いてしまう。
「なんだったー?典子ちゃん」
「・・・たっち、だって」
「たっち?」
「『たっちゃん!』『みなみぃ!』」
もちろん、青春のバイブルだったので、野長瀬が過剰反応したが、全員からスルーされた。
「た、タッチなんですか?南ちゃんの育成!?」
この言葉もほったらかされる。
「何、典子ちゃん、たっちって」
「多分、これ、赤ちゃんなんだよね」
薄暗い液晶画面に、ぎこちなく動くものが描かれていた。確かに、赤ちゃんのようだ。
「で。赤ちゃんが、最終的に、たっち、する」
「・・・た、立つ、ってこと・・・?」
てぇーーーーい!!!
典子がたっちをソファに投げつけた。女子とは思えないその勢いに、思わず男連中から拍手が出る。
「つつつ、つまんねーーー!!!」
「そりゃ売れないねー」
典子の叫びに相槌を打ちながら、山をひっくり返していた正広は、よく解らないものをみつけた。
「なんだろ、これ」
ペンダントのついたチョーカーのような形をしていた。
「アクセサリー?変身キットかな」
何気なく自分の首にまいてみた。長さは、細い正広の首でギリギリぐらいだ。
あぁ、子供のおもちゃなんだな、と思った時。
『ワンワンッ!』
おもちゃの山の中から、突然犬の鳴き声がした。
「うわ!びっくりしたー!」
『ウウゥーー・・・!ワンッ!』
「何ー!どれー!?」
がさがさひっくり返していると、液晶のついた、掌サイズのおもちゃから出て音がしていることが解った。
「もーなんだよー」
『ワフ〜・・・』
スイッチ切らなきゃ、と、そのおもちゃを見ていた正広は、大きな目を、さらに見開いたまま硬直した。
「どした?」
尋ねた由紀夫は、懐かしのゲームウォッチのばったもんを発見していた。車がゆきかう道を、カルガモの親子を無事に向こうに渡すという、テーマとしても古いだろうというゲームで遊んでいたのだが。
「こ、これ・・・」
『くぅん』
正広が言葉を発するたびに、おもちゃは犬の鳴き声を出し、そして、液晶画面には。
「・・・『これ、なぁに』・・・って・・・・・・・・・・・・」
由紀夫にも、最初何が書かれているのかよく解らなかった。
正広がこれ、と呟いた時に、犬の鳴き声がして、画面には、文字で、「これ、なぁに」。・・・ってことは。
「ヒトリンガル!?」
「やっぱりぃーーー????」
『ワォーーーン!』
正広は慌てて、首にとめていたおもちゃを外す。
「何これ、何これ!」
チョーカーを外してしまえば、犬の鳴き声はしない。しないけれど。
「こ、これ、すごくない!?人間の言葉を、犬の言葉に翻訳してるってことでしょ!?」
「すごいけど!すごいけど・・・」
「すごいですよ!!」
野長瀬は感動のあまり、目をウルウルさせていた。
自分の気持ちを、愛するハニー、野長瀬智子ちゃんにもっと伝えられるようになる!と。
智子ちゃんは、賢いから、自分の言葉も解ってると思うんだけど、でも、もっともっと・・・!
いくら、ウェルシュコーギーよりでかいとはいえ、智子は犬ではなくうさぎだ、という原則を、段々野長瀬は理解できなくなっているようだった。
しかし、愛は盲目という言葉が誰よりも相応しい男、野長瀬は、自分も!と、首にチョーカーをまこうとして。
「ぐ、ぐるじぃ!」
「む、無理ですよ!僕でぎりぎりなんですから!」
「っで、でも!どもごちゃんにっっ!」
知らず知らず、自らの指で、自らの気道を押さえるような形になりながら、野長瀬はがんばった。
どうにか!どうにかこれを首に!
「バカだバカだとは思ってたけど、性根の底からバカだね!あんたわ!!」
そして、自らの命を絶つ前に、奈緒美にはったおされた。
そう。ベルト部分が短ければ、ひもなり、リボンなりを足せばいいだけの話だった。
こうして、野長瀬は、嬉しそうにあれこれ喋り、おもちゃは犬の鳴き声を響かせまくり、液晶は野長瀬の言葉を文字にした。
「でも、こんなすごいのが、なんでここに来ちゃう訳?」
典子がもっともな疑問をさしはさむ。
「これ、すごいものじゃない?」
「あぁ、でも」
奈緒美は、興味を失ったようだった。
「多分、犬の声とかは、適当じゃないの?声の大きさに合わせるくらいで」
ただでくれちゃうおもちゃなんてそんなもんでしょうと奈緒美は言ったが、由紀夫は首を捻った。
「それだったら、人間が喋った言葉は、そのまま文字になってもいい」
「え?」
「これ、って正広が言った時に、これなぁに、と表示させる必要はないじゃん」
「あ、そっか。僕は、これ、って言っただけなんだから、これ、だけでいいんだ」
「もちろん、喋った言葉がそのまま文字で表示されるっていうだけで、大変な技術だけどさ」
由紀夫の言葉を聞いて、それぞれが手を叩いた。
「そうだー!すごい便利じゃん!それってー!テレビでテロップ出す人とかすごい楽じゃーん!」
「すっごい!これってそういうおもちゃなの!?」
「いやいやいや」
由紀夫は顔を振る。
「そうじゃなくて、これは、犬の音声に変わったものを、文字に変換してるんだろ」
「ん?」
「正広の喋った言葉を、なんらかの方法で犬の声に変える。そしたら、その犬の鳴き声に合わせて、文字を表示させる」
「兄ちゃん、よく解んない・・・」
「いや、だから。人間が喋った言葉は聞こえてるんだから、文字を表示させる昨日は特別必要じゃないじゃん」
そうなのだった。
どういう意味合いを持ったおもちゃか、というのが、これでは弱い。
人間の言葉を犬に伝えたいだけであれば、文字は必要ない。
そして、人間の言葉を犬の鳴き声に変換したからといって、それで犬に伝わるとは限らない。
「び、びみょーーーに・・・、中途半端・・・?」
「びみょーーーー、にな」
「んー、でもー・・・」
野長瀬が嬉しそうに首につけているおもちゃを見て、正広は考えた。絶対素晴らしいもののはずなんだ。何か驚くような使用方法が、きっと・・・!
「あ!解った!」
解った解ったと、兄の手を叩く。
「赤ちゃんだ!」
「赤ちゃん?」
「赤ちゃんにこれをつけて、犬語を経由させたら、眠いとか、おなかすいたとか、そういうのが解るじゃない?」
「・・・ひろちゃん、それナイス!小児科には、これ必要じゃない!?」
「・・・小児科・・・。そうか。小児科にこれがあったら、赤ちゃんが患者さんでも、いいんだ。そっかぁ」
奈緒美の手は、アドレス帳に伸びた。知りあいの医者という医者をあたって、製品を高く売りつけようという魂胆だ。
「赤ちゃんの気持ちが解るおもちゃなんだよ、きっと(犬語経由するけど)」
「赤ちゃんの気持ちなぁ(犬語経由だけど)・・・」
「っと、その前に、量産できるかどうか聞かなくちゃねー♪」
医者の前に、おもちゃ会社、と、奈緒美が電話に手を伸ばし、あ、野長瀬お茶ね♪、と機嫌よく声をかけた。
「はいっ!」
そんな素晴らしいおもちゃを、今自分が装着しているなんて!と、張り切って答えた野長瀬は、バチン!という音とともに、チョーカー部分が破裂したため、ショックで気絶した。
精神は、貴婦人の野長瀬だった。
動かし続けたため、内部で熱を持ち、自ら発火、破壊されてしまった、このヒトリンガル。
残ったのは、破裂した後の残骸と、野長瀬の喉にできたヤケドだけだった。
何かの偶然で出来あがり、その後、技術者が会社を辞めてしまったという、そのおもちゃは、今現在、再度作ることはできないのだと、奈緒美は聞かされてがっくりだ。
今に、その技術者が、他から商品化させるかもしれない。
網を張らなければと真剣に思っているらしい。
「・・・・・ただいまぁ、智子ちゃぁん・・・」
喉痛い痛いとシクシクしながらアパートに戻った野長瀬は、ハニーというより、野長瀬家の主人といった風格のミニウサギ(大)、野長瀬智子に挨拶をする。
「今日は散々だったよ、智子ちゃぁん」
おざぶの上で、長々と伸びていた智子は、だっこされようとしたところで、体をよじって抵抗する。
「と、智子ちゃん・・・!大丈夫だよ、のどが痛くったって、智子ちゃんをだっこぐらいできるから!」
ウルウルしながら、たった一つの心のよりどころ、智子を追いかける野長瀬は、どこの誰からみても情けない存在だった。
もちろん。
智子の気持ちはバウリンガルや、ヒトリンガルなんかがなくても、誰にだって解る。
智子の目はいつだって、『バカだバカだと思ってたけど、ほんっとにほんっとに!性根の底からバカだなこいつ!!』とゆっているのだ。
がんばれ野長瀬!
バウリンガルって、でも、とりあえず猫とかにもつけてみたいですよね。どういう反応をするのかって(笑)
次回更新は、来週水曜日!の予定は未定にして決定にあらずっ!