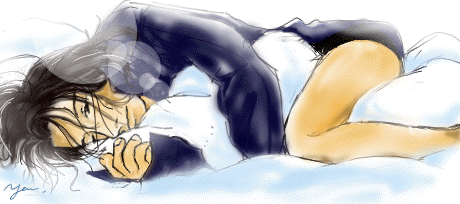
天からの贈り物じゃないけど、黙って受け取って?
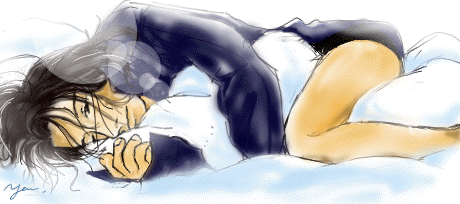
第21話前編『息子を届ける』
今までの簡単なあらすじ。
「野長瀬のせいで食中毒の被害にあった野長瀬人材派遣センターご一行様。しかし、その後野長瀬によってごちそうされた、春の膳は大変美味しいものだった。そしてすっかり元気になった正広は」

「えーっと」
ある日の午後、お使いに出かけていた正広は、銀行を出たところで立ち止まった。
「これで全部、だよね。銀行振り込み、クリーニング、郵便局、みんなのおやつは買ったし、・・・あれ?」
親指から一つずつ折って行って、まだ小指が余っている。
お使いの用事は5つあったはずで・・・。
「銀行!クリーニング!郵便局!おやつ!・・・んー・・・!」
もう一度指を折りながら数えて、うーんと考えて、考えて、でもなかなか思い出せない。もちろん、ポケットには、ちゃんとメモを入れてある。仕事を言い付けられた時には、ちゃんとメモを取るように奈緒美に言われてもいた。けれど、正広はここのところ記憶力アップの努力中。図抜けた記憶力の兄にはとてもかなわないだろうけど・・・。
でも、なんでたった5つが覚えられないんだよぉー!
うーうー、唸りながら、小指を立てたまま、思い出そう、思い出そうとしていたら、
「女の子がどうかしましたか?」
と声をかけられた。
へっ?と顔を上げると、見知らぬ中年の男が正広に話し掛けてきていた。
「女の子・・・?あ!」
小指と言えば、女の子。自分がものすごく怪しい人間になっていたことを思い出して、正広は慌てて手を後ろに隠す。
「い、いえ。なんでも・・・」
エへへ・・・、と照れた顔をした正広は、あっ!と声を上げる。
「本屋!」
「本屋?」
「あ、すみません、俺、本屋に行かなきゃいけなかったんですっ」
あぁ、と、その見知らぬおじさんは、ニコニコと微笑んだ。
「本屋に」
「はい。本屋で、アンアン買って来いって言われててっ」
とある有名アイドルのちょっとエッチな写真が載ってるらしい。
「あぁ。アンアン」
そして二人はなぜか向かい合ったまま、ニコニコと笑いあった。
「あ。えっと・・・。じゃあ・・・」
はっと先に我に返った正広は、ペコン、と頭を下げてその場を立ち去った。なんだか、人懐っこいおじさんだなって思いながら。
アンアンは急がないとなくなるかもしれないから、と言われていたのを思い出し、とっとと本屋に行き、奈緒美と典子の分をGET。これで、全部の用事が済んだっ、と元気よく歩き出し、公園を突っ切ろうとした正広は、ベンチでぐったりしている人を見つけた。
あれ。
記憶力がそんなによくない正広でも、それがさっきのおじさんだというのは解る。
「あ、あのぉ、だ、大丈夫ですか・・・?」
ベンチに横になるようにしていたおじさんが顔を上げて、あぁ・・・、と小さくうなずく。
「さっきの、アンアンの・・・」
「あ、はい。どしたんですか?」
「ちょっと・・・、具合が・・・」
「えっ、おうち、どちらですっ?俺、送りましょうか?」
「いや・・・あぁ・・・」
ベンチに座り直したおじさんは、大丈夫と言うように小さく首を振ったが、やはり苦しかったのか、正広にタクシーを拾ってくれるように頼んで来た。
「いいですよ。ちょっと待っててくださいねっ」
アンアン2冊を抱え、お菓子の入ったビニール袋を腕にかけたまま、正広はタクシーを止めに公園から走り出た。
すぐにタクシーは捕まって、正広は荷物を放り込み、おじさんを迎えに行く。
年は、多分、正広の父親ぐらい。眼鏡をかけた、笑顔がいい感じの人だった。我ながら細い肩を貸してタクシーまで連れて行く間、なんだか、正広はえらく嬉しくなってきてしまった。
正広が入院してる間に両親は事故死してしまって、こういう風に、父親を助けて何かする、なんて事はついぞしたことなかったから。
荷物が奥にあるし、タクシーから降りてから大変だろうし。
心の中で言い分けしながらタクシーに乗ったのは、そういう息子気分を味わって見たかったからかもしれない。
「ここ、ですかぁー・・・?」
正広でも知ってる、そして入った事のない有名ホテルにタクシーは止まった。
「そう・・・、あぁ、悪かったね、ここまで突き合わせて」
「いえ。いいんです、けど・・・」
ちらっと自分の姿を見る。Tシャツに、ジーンズ・スニーカー。アンアン2冊に、おやつの袋。このカッコじゃあ・・・。
でも、おじさんはなんとなく具合の悪そうな様子でタクシー代を払っている。
このまま放って帰るのは、と思って、小さくなってりゃわかんないだろ、と肩を貸して、こそっとホテルに入った。
そして。
「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・」
言われた通りの階について、正広は言葉を失った。
「高橋様!」
フカっ、と靴が沈むような絨毯のひかれたエレベータホールには、分厚そうな木の扉があって、その前に上品で綺麗なホテルの女性がいて、正広が連れてきたおじさんに驚いたような声を上げる。
「どうなさいました?」
「あぁ、ちょっと・・・。いや、大した事は・・・」
その女性は、正広と反対側に回って、労るように体に手をかける。
「お医者様をお呼び致しましょうか」
「いや、ちょっと横になれば大丈夫。それより、ケーキでも頼んで貰えるだろうか。この子に助けてもらったので」
びっくりしたままの正広はそう言われ、え、いやいや、と小さく首を振る。おっそろしく場違いなところにいるようで、おたおたしてしまう。
けれど、そのホテルの女の人は、にっこりと柔らかく正広に笑いかけた。
「まぁ、ありがとう。うちのケーキ、とても美味しいから、ぜひ食べて行って?」
「あ、え、はい」
堅苦しくなく話し掛けられて、こくん、と首を縦に振る。
「どんなケーキが好き?」
「え、いえ、なんでも・・・」
「じゃあ、一番の自信作にしますね。お飲み物はどうしましょう。コーヒー、紅茶、ジュースも色々ありますけど」
「こ、紅茶・・・」
「はい、解りました。それじゃあ、高橋様・・・」
女の人はおじさんに軽く頭を下げて、ドアを開けた。
おじさんに肩を貸して、足元をフカフカさせながら廊下を歩きながら、正広は小さな声で聞いた。
「あ、あの・・・」
「ん?」
「あの、しゃ、社長さん、です、か・・・?」
「えっ?」
「いや、だって・・・」
これで意外と正広の世界は単純で、お金持ち=社長という図式が成り立ってしまっている。でも、今日はそれだけじゃあない。きっとこのおじさんは、このホテルの社長さんだ!
だって、さっきホテルのお姉さんが、俺に、連れてきてくれてありがとうみたいに言ったから!
と主張したら、おじさんの体がガクンと重くなった。
「うわっ、だ、大丈夫、ですかっ!?」
やっぱりお医者さんを!と慌てたら、ふかふか絨毯に膝をついたおじさんは、クククク・・・と笑っていた。
「あぁー・・・」
正広は不服そうな声を上げる。
「俺んこと、バカにしてるでしょぉー・・・」
「いや、してない、してない。君の勘違いだよ・・・」
それでも、笑いをこらえながらおじさんは手を振る。
「宝くじだよ」
「宝くじ?」
「おじさん、宝くじ当ててね、それで贅沢しようと思って。ホテルの女の人が『ありがとう』って言ったのは、自分とこのお客さんを連れてきてくれてだし」
「・・・なぁんだぁーっ!」
バンバン!と正広はおじさんの肩を叩いた。
「びっくりさせないでよねぇー!」
なんだよ。宝くじかよぉー。まさか1億3千万じゃあないだろうと、正広はいきなりリラックスした。そもそも、そんな大人しい質じゃない。
だから、どでかいスィートルームに入っても、すっげーっ!と部屋中を駆けずりまわって、これ何?これは?とおじさんに質問攻勢をかけた。
「すっげー!これがスィートルームってヤツだぁー!」
ふっかふかのソファに沈みこみながら、キョロキョロと辺りを見る。で、ようやく視線を向けたおじさんが、ニコニコしてるのを見て、はて?と首を傾げた。
「あ、あの・・・。具合、もういいんですか?」
「あぁ、座ってれば。ありがとうね」
そっか。
それじゃあ、と、また盛大にきょろきょろしてるうちに、ケーキと紅茶が届けられる。
「うめぇーっ!これ、すっげ、うんめぇー!!」
「そりゃあよかった。お代わりするかい?」
「えっ?」
正広の食べ方は一気食いが基本のため、ケーキは、わずか4口で姿を消していた。
空になったお皿を見下ろして、お腹の具合と相談して、おじさんは宝くじを当てたんだから、と言い訳して、こっくん!と正広はうなずいた。
「君は、えっと・・・」
結局ケーキ3っつを一気食いして、んー、満足っ、気分の正広は、おじさんが自分を指差してる事と、ちょっと首を傾げてる事から、名前を聞かれてんだと、溝口正広という名前を名乗った。
「正広くんか。正広くんはー、中学生?」
「・・・。高校生の年ですぅー。行ってれば、ですけど」
「あ、ごめんね。え、じゃあ、学校は行ってないの」
「うん、行ってないです。俺、仕事してっから」
順番としては、学校に行ってないから、仕事してる、なんだけどね。
「そうかぁ。えらいねぇ・・・」
「あ、いえいえ」
お使いとか、留守番とか、そのくらいだし。
正広は顔の側で両手を振る。そんな風にえらいとか言われるような事じゃあない。
けれど、おじさんはニコニコと正広を眺めている。
「あ、の・・・?」
「あぁ、ごめんね。おじさんにも、正広くんくらいの子供がいて」
「あ、そうなんですか」
「でも、外国なんだよ」
「じゃあ、別々なんです、か・・・?」
「うん」
おじさんには、息子が二人いて、でも、二人とも外国にいるらしく、おじさんは一人で住んでいるという。
「正広くんは、兄弟は?」
「俺は、兄ちゃ・・・、あの、兄が、います。一人。でも、両親はもういないから、二人だけで・・・」
「あぁ、そう・・・」
しばらく二人は黙った。
親がいなくっても、由紀夫がいてくれるから、そんなに寂しいとは思わなかったけど、もし親がいて、それなのに会えなかったら、もっと寂しいかなぁ。
そんな風に正広は思った。
「じゃあ、会いたい、ですねぇ」
ぽつん、と言った言葉に、おじさんは小さく頷いた。
「そうだねぇ。なかなか会えなくてね」
おじさんは、優しく微笑んで正広に言った。
「おじさんは東京の人間じゃないんだけど、まだしばらくこっちにいるから、よかったら、また会って貰えるかな」
「あ。いいですよ、俺でよかったら。それに、あの、よかったら俺の兄ちゃんも」
「そうかい?」
「うんっ。兄ちゃん、じゃないや、兄は、25歳なんですけど、おじさんのとこの子供と一緒くらいでしょ?」
「そうだね。じゃあ、よかったら連絡先、教えてもらえるかな」
「うん。えっと。会社ー・・・」
「会社?」
「あ、会社はいっつもいるって訳じゃないから・・・」
バッグから、おたおたと取り出したのは、小さなPHS。
「俺ね、ピッチしか持ってないから、ひょっとしたらつかまんないかもしんないけど」
「今は、若い子でもみんな持ってるねぇ」
「そう。これは、兄ちゃんが持たせてくれたヤツで、なんで携帯じゃないんだよって言ったんだけど、子供はこれで十分だって言われてぇ。しかも、ほら、なんかあるじゃん。1万円超えたらかけられなくなるヤツ?あれ。だから、俺、自分で携帯買おうと思ってんです」
「そう。じゃあ、それはもう要らなくなるねぇ」
「え?」
自分の番号を覚えていない正広は、PHSのボタンを押して、自分の番号を表示させていたが、驚いた顔でおじさんを見た。
「これ?」
「だって・・・、携帯電話買ったら、PHSはいらないだろう?」
「え、だって、これはぁー・・・」
おじさんは小さく笑う。
「せっかくお兄さんが買ってくれたヤツだもんね」
正広は小さく舌を出して、笑った。
「バレたら怖いし」
「お兄さん、怖いかい?」
「んー、時々」
PHSの番号をメモに書いて渡し、正広はスィートルームを出た。
普段の正広は、小心者のため、用心深く、そんなに簡単に自分の電話番号を教えるような事はしない。
部屋を出た瞬間に、もしかしてまずかった!?と思ったほどだ。
でも、どうもおじさんと相対してると、そういう警戒心がなくなってしまうのだった。いつも穏やかな微笑みを浮かべてるからかなぁ、と思う。
うーん・・・、と考えながら、お姉さんに見送られエレベータに乗った正広は、何気なく見た時計に、げっ!と内心叫びを上げる。
ケーキを3つ平らげてる間に、時間はすでに3時を回っている。
今日のおやつは、正広が手に提げてるビニール袋の中!
やばぁーい!怒られちゃーうっ!!
優秀なホテルマンたちが、ひっそり眉間に皺を寄せそうになってしまうスピードでロビーを突っ切り、正広は事務所に急いだ。
<つづく>
休みの日は、いつまでも寝ている。夜も早く、朝は遅い。そんな人間のクズ子でございます。ここんところ、やたらと正広くんの登場シーンが多いですが、今回はなんと正広くんだけでございます!由紀夫ファン、ゴメンネっ!!
次回、来週の水曜日!の予定は未定にして決定にあらずっ!