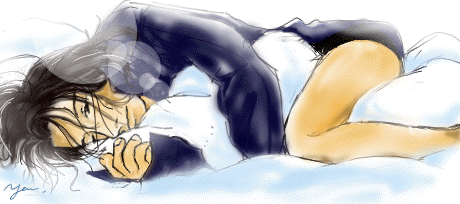
天からの贈り物じゃないけど、黙って受け取って?
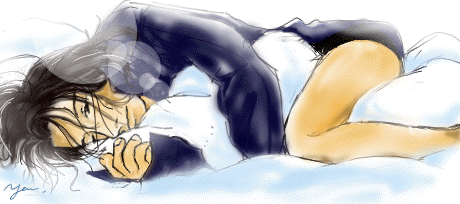
第21話後編『息子を届ける』
今までの簡単なあらすじ。
「おつかい中の正広が拾ったおじさんが、家族の真似事がしたいと、由紀夫たちのうちにやってきた。そのまだ見ぬ挙動の不審な男と、弟を近づける事を嫌がる由紀夫は万全の態勢で、男を迎えるのだが、よりにもよって、世界で一番怪しい、自分の父親であったことに愕然とする」

「兄ちゃんの、お父さん・・・?」
「だから、君のお父さんでもあるんだよ正広くん」
「え。だって。えっと」
憮然とした由紀夫が正面に、ニコニコとご機嫌な笑顔の岸和田が隣にいる正広は、きょときょとんと二人を見比べる。
「あんまり見るな、バカがうつる」
「でも、面白いだろ」
「自分で言うなっての!大体なんだよ!何、嘘ついてんだ!?俺らがいつ外国にいたよ!あ。てめぇ、他の子供だな?」
「違う、違う。心配しなくても、俺が認知してるのは、おまえだけだから。嫉妬しなくても」
「誰がしてるよっ!」
「お兄ちゃんはいつもこんななの?正広くん、毎日うるさい思いしてるんだねぇ」
「あ。いえ、ううん」
人形みたいにぶんぶんと首を振り、ぎこちなく椅子を勧める。
「んなもん、座らせなくていい!」
「でもぉー・・・。せっかく作った、しぃー・・・」
「おぉ、すごいね。ありがとう」
由紀夫の不機嫌な顔なんてまったく気にせず、ご機嫌な笑顔のまま岸和田は席についた。
「これは、正広くんが?」
「あ、はい」
向かいの席に腰掛けて、つんつんと兄の袖をひく。納得できねぇという顔をしながら仕方なく由紀夫も席についた。
一体どうすりゃあ!と思いながら、正広はホスト魂を発揮して、どうぞ!と手巻き寿司をすすめる。
遠慮なんか、するはずのない岸和田は、はいはいと海苔を手にした。
「はい、兄ちゃんも」
隣の兄に、海苔を差し出す。チラっと自分を見るだけで、手を出さないものだから、がしっ!と手をつかんで、ぐいぐいと手のひらを開いて、そこに海苔を乗せた。
「乾いちゃう。ね?食べよ?」
偉そうに言うと、岸和田がふと口元を押さえる。
「えっ?大丈夫ですかっ?気持ち悪い・・・っ?」
何せ、岸和田が具合を悪くしたところを助けた正広だから、立ち上がってオロオロしてしまう。
岸和田は、イヤイヤと手を振り、それでも口元を押さえたまま俯いた。
「あ、のぉー・・・」
「正広、笑ってる」
「え?」
具合が悪くて震えてるのかと思った岸和田は、肩を震わせながら笑いをこらえている。
「へっ?」
岸和田は、震える声で言った。
「たった二人の兄弟なのに・・・、肩寄せあって、仲良しで・・・!」
年からは連想できないすばやさで立ち上がった岸和田は、がしっ!と息子たちを抱きしめた。
「いい子に育って!!」
「やかましぃ!」
自分と正広から岸和田を引き剥がし、無理矢理座らせた由紀夫は、自分も座ってじっと生物学上の父親を見た。
このスチャラカ大バカ親父との別れには、ほんの少しジーン、とするものもあって、変な親父だけど、これが自分の親父なんだなと思ったりもした。
思ったりもしたが、普通じゃないことは身にしみているので、なんで、自分たちの前に姿を現したかが解らない。
「さ、食べましょう。乾く、乾く」
せっかくの刺し身が!と正広が、はいはい、と二人を座らせる。
「康晴って言うんだぁ」
「ううん。由紀夫だぜ」
もう、康晴って言っても返事しねぇ、と、ツンとする由紀夫に、子供みたいと正広は小さく笑う。
一緒に暮らすようになって、いつもしっかりしゃっきりのお兄ちゃんだったのに。
「あのね、兄ちゃんね、あんまりうちにはいなかったけど、あん時は一緒に来たよね!」
「あん時?」
「デパート行く時!」
「へぇー」
驚いたように岸和田が声を上げる。
「えー・・・?そうだっけぇ?」
「そうだったじゃん!」
時々日曜日にデパートに行く。
そんな習慣が溝口のうちにはあって、正広はそれがとても好きだった。おもちゃを買ってもらえる、屋上で遊べる、レストランでプリン・アラモードが食べられる、そして、家族4人が揃っている。
「兄ちゃん、プラモの前から離れなかったもんね」
「あそこ、品揃えすごかったよなぁ」
「一家揃ってデパートか・・・。いいね、そういうの」
岸和田が言った。
「家族なんていなかったからなぁ・・・」
しんみりとした口調に、正広が少し気の毒そうな顔をした。
「どうだろう、これを食べたら、買い物に行かないか?」
「買い物?」
「誕生日プレゼントも1度もしてないことだし、ちょっとプレゼントさせてもらえないかな」
「え、でもー・・・」
「やばい金じゃねぇんだろうな」
何せ、50億もの金を横領し、しかもそれだけの大金を、おそろしくバカバカしい事に使ってしまう男だ。まともな金なんか、持っているはずがないと由紀夫は思う。
「何言ってるんだ」
にっこりと、本当に機嫌のいい満面の笑顔を岸和田は浮かべる。
「息子にプレゼントするのに、やばい金でって事はないだろう?」
信じちゃいけねぇって解ってるのに!なんで信じちゃったんだ俺!!
5人前はあった手巻き寿司が綺麗になくなった後、3人は出かけた。歩いて駅まで行き、電車に乗る。ずっと外国にいた岸和田は懐かしい様子で、車内を眺めていた。
ガイドブックには載らないほどの、超一流ホテルに泊まり、リムジン乗り回し、米軍基地からパスポートなしで海外に行ってしまうような男だったけど、あぁ、今は普通なんだな、と思った俺がバカだった!
由紀夫は激しく後悔した。足元がふかふかで安定が悪い。
「岸和田様、お久しぶりでございます」
極々丁寧に、上品に頭を下げられ、岸和田は鷹揚にうなずいた。
「息子たちなんだがね、タキシードをと思って」
「左様でございますか」
「えぇぇーっ!?」
銀座の、一般人立ち入りお断り、みたいなテーラーには似つかわしくない叫び声を上げた正広は、慌てて口元を押さえ、由紀夫の後ろに隠れるように小さくなった。
ジーンズにスニーカーという二人は、ヨーロッパ!重厚!落ち着き!という店内では浮き上がり、浮き上がり、浮き上がった挙げ句、吹き抜けのまだ上の天井にぶつかりそうで、正広を不安にさせる。
「・・・いらねぇよ、タキシードなんて」
精一杯押さえた声で由紀夫も言った。
「なぜ?タキシードはオーダーするもんだろう」
「オーダーだぁーっ!?そんな事は知らねぇし、そもそも、あっても着る場所がねぇ!タンスの場所ふさぎだっ!」
店員には聞こえないよう、耳元で、小声で、かつ、怒鳴る、という器用な真似を由紀夫はした。
「まぁまぁ」
しかし、笑顔で肩を叩いた岸和田は、店員たちの前に、二人を押し出した。
あっちを向けの、こっちを向けの、腕を上げろだの、下げろだの。何をしてくれる!というほどあちこち採寸され、ようやく終わったと思ったら、とりあえず似たようなサイズのものを試着してくれと言われる。
由紀夫はともかく、スーツですら、ほとんど着たことのない正広は、あまりの違和感に困り果てながら試着して、鏡を前に思わず笑った。
「七五三!」
自ら笑いながら試着室を出ると、先に出ていた由紀夫が、どこか魂の抜けたような様子で、大人しくカフスボタンをはめられているところだった。
「なぁんかさぁ、見て!もー笑っちゃわない?」
臨界点を超えると、正広はシャイから一転、ナチュラルハイになる。
「すごーい、七五三だ、七五三。千歳飴はどこっ?」
「いいえ、でも・・・」
笑って、笑ってと、きゃいきゃいはしゃぐ正広に、彼の祖父の年代であろう店員は静かに言った。
「よくお似合いですよ。袖が長く思えるのは、肩幅があってないだけですし・・・」
肩をつままれ、腕の付け根と袖を合わせると、確かに長すぎる袖は、適当な場所に収まる。
「正広スタイルいいし」
「おまえはスタイルがいい訳じゃないけど、雰囲気で見せるなぁ」
「うるっせぇよ。どーせ日本人体型ですぅ」
と、文句が出たのも最初だけ。
それよりこっちのシャツが、だったら、この上着で、と、とっかえひっかえ着せ替え人形状態に陥った二人は、自分たちがどうされてるのかの、正確な判断が働かなくなってきていた。
「いかがですか?」
日頃、年配の客ばかりを相手にしている店員たちだから、そりゃ、若くて、綺麗な客がたまに来れば燃える。燃え燃えのボーボーで燃えて、店中ひっくり返してでも!と、現在の手持ちをすべて出さんばかりの勢いで整えられた二人は、あら、不思議。まるでどこかの御曹司。
「あぁー、いいねぇ」
退屈する様子もなく、あーだこーだと指示をしていた岸和田が満足そうに笑う。髪のセットまでされてしまった正広は、鏡を見てパチクリと大きく瞬きをした。
「まぁ、信じられない!これがあたし?って、あんたなぁー・・・」
その正広よりは、相当冷静な由紀夫が、こちらは一つに髪をまとめられて、キリっとした空気を身に纏い、キっ!と父親を睨む。
「よく似合う。まぁ、これで冠婚葬祭どこでも通用するぞ」
「冠婚祭までは通用しても、葬はまずいだろ、葬は・・・」
「正広もいいね」
「そぉですかぁー・・・。なんか、俺じゃないみたいー・・・」
「ん?」
ブツブツ言っていた由紀夫が、岸和田を指差す。
「なんで、あんたまでタキシード?」
「親子3人で、記念写真でも撮ろうかと思ってね」
笑顔のまま近寄ってきた岸和田は、二人の肩を抱き、テーラーとは思えない、暖炉のある一角をバックにシャッターを押させる。二人だけの写真も何枚かとり、フィルムがなくなったのか、カメラをしまった。
「また、すぐ行かなくちゃいけないから・・・。まぁ、息子たちとの思い出って事で」
何枚か撮り終えて、ポツンと岸和田は言った。
「え?もう、どっか行っちゃうんですか?」
ごくごく大人しめに、前髪をほとんど下ろしたままになっている正広が驚いた顔になる。
「もうって言うか、今日の夕方なんだけどね」
「えぇーっ!?」
「それで、羽田って・・・」
「中華航空だぁー・・・」
新羽田ができて、初めての旧羽田空港の喫茶店でプリン・アラモードを食べながら、正広は珍しそうに眺める。
タキシードのオーダーは一朝一夕でできるものではないため、出来上がり次第連絡が来る。岸和田の飛行機の時間の関係で、断りきることはできなかった。
「あんた今、どこにいんの」
「さぁ、どこかなぁ。いつも移動してるから・・・。でも、安心しろ。康晴の、・・・由紀夫の事も、正広の事も、どんな遠くからでも見守っているから」
「いっそ忘れてくれよ・・・」
うんざり、といいながら、結局見送りにここまで来てしまっている自分に歯噛みする。
「正広、こないだのホテルな、岸和田裕二郎の知り合いですって言えば、ただで泊まらせてくれるから。彼女ができたら使いなさい」
「えっ!?」
「バカな事言ってんじゃねぇよぉー!」
「由紀夫は今からでも使っていいから」
「なんで、俺には彼女がいないって決め付けんだよぉ!!」
「「でも、いないだろ?」」
ダブルで言われが正広は、ちっ!と小さく舌打ちし、多少なりとも攻撃できそうな方に、小さく刃を向けた。
「さすがは親子だねぇー、兄ちゃん」
「それを言うなぁーっ!!」
会ってくれてありがとう。
二人に会えて、本当に楽しかった。
岸和田は、ストレートにそういって、二人と握手をする。
「また、帰ってくるんでしょう・・・?」
「そうだな。また、な」
「そしたら、うち来てくださいね」
「誘わなくていい」
「兄ちゃぁーん・・・」
「どーせ、黙ってたって、勝手に来るんだろ?なんだかんだ言っても、寄る年波には勝てなくて寂しっぽくなってんだろうし」
「それは、ちょっと図星かも知れんな」
小さく笑って、岸和田は搭乗ゲートに消えた。
由紀夫と正広は、しばらくそこに立っていた。
すごく遠くに、地球の裏っかわかもしれない場所に、家族がいるって言うことを考える。
「南米ってぇー・・・。ちょうど日本の裏っかわって行った?」
「確かそうだって」
「じゃあ、踏んでる事に、なんのかな」
子供みたいにスニーカーの裏を見ながら、正広は笑う。
「そりゃ、向こうも思ってんじゃねぇの?」
言いながら、南米に戻るのに、中華航空・・・?
由紀夫は小さく首を傾げた。
その後、台湾に怪しい日本人が顕れ、香港一の財閥の御曹司から依頼されていると怪しげな仕事に乗り出す事になる。その男は、親しげに御曹司の肩を抱いている写真を持っており、その御曹司には、目つきの鋭い、いかにも優秀なボディガードがついていることも判明しているが、それはまた、別の話である。
後日、由紀夫と正広がタキシードを作ってもらった事を知った奈緒美は、腰越人材派遣センター10周年記念祝賀パーティでも開いて、一気に顧客数を増やすか、と計画を始めたが、これは別の話ではないかもしれない。
そして、あの日、その存在を忘れさられた野長瀬が、いつまでも、いつまでも、いつまでも、いつまでも、由紀夫の家の近所で待機させられていたのは、明らかに蛇足である。
<つづく>
先日のブラザーズで、かつてこのギフト番外編で使ったのと同じ台詞があり、あらあら、ブラザーズの脚本家まで、ギフト番外編を見ていただなんて、クスクスっ(笑)と思っておりました。誰でも思うような台詞だったって事やね(笑)
気づいてくださった、野長瀬智子おねいさま!同じく名字は違うがH智子様!ありがとうございますー!
また、新たなネタを下さったMaki様ありがとうございますぅー!使わせていただきますぅー!
次回、来週の水曜日!の予定は未定にして決定にあらずっ!