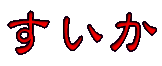
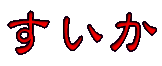
すいかはおそろしい。
夏の味覚すいか、それがあんなに恐ろしいことを起こすだなんて思ってもみませんでした。
「たねなしすいか、などというものがあるが、あれはやっぱり邪道だな。」
浦久保さんは種をぷっと吐き出して、そう言った。
「やはりすいかの種はこうやって吐き出すのがいいんだよ。」
「そういうものですか。」
「最近はたねなしすいかってのも見ないだろ?」
「そうですね、あまり。」
「あれはな、まずたねなしすいかの種を作るところからはじめるんだ。すいかの花を薬剤につけて、そしてできた種をもっぺん薬剤につけてからまく。それがたねなしすいかなんだな。」
「はあ、そうなんですか。子供のころは種無しスイカの種ってどこからくるのかって思ってましたけど。」
「薬剤につけることで一種の遺伝子異常を起こさせるんだ。それで種が無いすいかができるのだ。手間だけかかって誰もそんなに食わなきゃ、減るのもあたりまえだよな。」
「そうですね。あっ、もうぜんぶ食っちゃったんですか?」
「うーん。もう一個あったろ。それ切ろうや。」
「はあ。」
「あのな、しまの所は切るなよ。緑色の部分に包丁を入れるんだ。黒いところには種が集まってるんだ。」
「はあ。」
まな板の上にごろりと転がるすいか。包丁をひんやりとしたすいかに押し当てると、なぜか背筋がぞくっとしました。
ざろん。
すいかの切れ目から、どろりと赤黒い液体が流れ落ちた。むっとするような異臭が鼻をついた。
腐っていたのか?激しい後悔の念がおそう中、すいかはゆっくりと二つに倒れた。
ぴちぴちとすいかの中でうごめくそれは、イセエビだった。
「浦久保さん!すいかにイセエビが…!」
はっとしてみると浦久保さんの口にはサワガニが数十匹もうごめいていました。甲殻類が、甲殻類が、すいかの中に侵略を開始したとでも言うのでしょうか。
はっと目をやると、むこうから赤いからのついた足を不器用に動かしながらすいかがたくさん歩いてきます。
「遺伝子だ…遺伝子をいじるからこんなことに…。」
浦久保さんがサワガニまみれの口を動かしてかすかにそう言ったような気がしました。
さらに犬やぶどうやとうもろこしなどが甲殻類の足やはさみがはみ出した姿でごろごろ転がってきます。
「うわあああっ!」