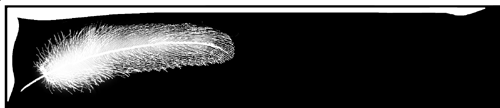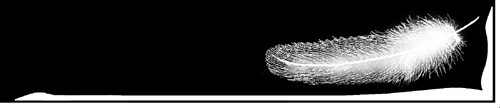行方郡(茨城県)に現れた谷や湿地を守護する角のある蛇。奈良時代に編纂された「常陸風土記」によれば、継体天皇(西暦507年即位)の御代、箭括氏麻多智(やはずのうじのまたち)が葦原を切り開き水田を開墾する際に夜刀神が多く現れ、この作業の妨害を行いはじめた。夜刀神の姿を見たものは後継ぎができず、家門は滅びるとされていたため、麻多智は鎧兜に身を固め矛を持ってこれと対峙した。夜刀神を山まで追い上げた麻多智はその麓に杖(矛とも解釈される)を突き立て、「これより上は神の地となすこと許さむ。ここより下は人の田となすべし。今より後、我は神の祝となりて、永代に敬ひ祀らむ。願はくは祟ることなく、恨むことなかれ」と告げ社を建てて祀り、麻多智の子孫もこれを受け継ぎ祭祀を行った。これによって、以後しばらくは姿を見せることはなかったが、孝徳天皇(西暦645年即位)の御代に、壬生連麻呂(みぶのむらじまろ)が水害を防ぎ新田を開くためこの池に堤を築いた際にも現れ、辺の椎の木に集まりだした。そのため連麻呂は「この池を修めしむるは、要ず民を活かすにあり。何の神(天津神)、誰の祇(国津神)ぞも風化(おもむけ・ここでは民のことを思う天皇の大御心)に従はざる」と伝え、配下の者にこれでもなお妨害するようであれば斬るように命じると、水田工事が民のためであり、またそれが天津神である天照大御神の直系である天皇の大御心である事を理解した夜刀神はすべて引き上げていき、以後作業の妨害をすることはなくなった。なお、夜刀神はこの水源及び水田を守護する神として現在でも椎井の池に祀られており、近くの愛宕神社では夜刀神の石碑を見ることができる。
|