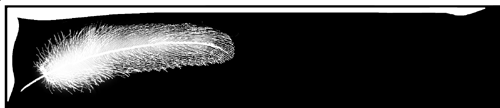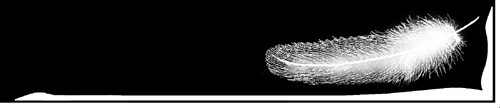「北欧神話」の神であるオーディンに仕え、戦死者の魂を天上の神殿ヴァルハラへと導く乙女。その天翔る姿は選ばれた者にしか見えず、それは死者の館を意味するヴァルハラへと導かれる事つまり戦死を意味するため、古い時期や一部の地域では死神に近いイメージで捉えられる事もあったが、散文や詩文では戦場で傷ついた戦士たちの前に舞い降りる幻想的な恋人として謳われるようになり、現在最も広く認識されているイメージ、英霊を導く乙女として広まっていく。 「北欧神話」によれば、主神オーディンは来るべき世界の終末であるラグナロク、つまり悪神との決戦に備えワルキューレに人間の勇敢な戦士を集めさせる。ワルキューレはこれを受けて光り輝く鎧兜に身を固め槍あるいは剣を手に駿馬にまたがり、戦死者の魂を導くために虹の橋を渡り戦場に赴くのである。このとき天翔る馬の蹄の音は雷鳴となり、谷には露の雫、森には霞が降り、夜間であればその輝きはオーロラとなって現れる。そして、戦の勝敗を決し、戦死する運命を持つ者の魂を救い上げ、フレイヤにも仕えている彼女たちは戦士の魂を選別し一方をフレイヤの元へ、残りの一方をヴァルハラへと導く。ヴァルハラへと導かれた戦士はエインヘルヤルと呼ばれ、昼間は来るべきラグナロクに備えて死者が出るほどの激しい戦闘訓練を行うことになるが、夜には宴が催され、昼間の訓練での死者もここで蘇る。ワルキューレは戦士をヴァルハラへ導くだけでなく、ここでは戦士達の歓待も行う。また、平時においては彼女たちは機を織るのだが、ここで織り上げるものは戦士の運命であり、この運命についてはオーディンが決定する。そのため、オーディンの意思に背いた運命を織り上げるとワルキューレとしての資格は剥奪され、人間界へと追放されることとなる。この際にはただ追放されるだけではなく、例えば、ワルキューレの一人ブリュンヒルドは英雄によって目覚めさせられるまで眠り続けるという罰を与えられた。ちなみに、この運命の人物が現れるまで眠り続けるというモチーフは文学作品にも採り入れられており、ペローの童話集「鵞鳥おばさんの話」の「眠れる森の美女」(後にグリム童話にも収録)や、グリム兄弟の「子どもと家庭のための童話」いわゆる「グリム童話」に収められている「白雪姫」などでも同様の描写が見られる。 ワルキューレは戦士の魂を集める時以外でも時折人間界に姿をあらわすことがあり、ときには人気のない森の奥の湖や池の近くに舞い降りる姿もみられる。その際は白鳥の翼を持つ乙女の姿であり、休むときにはその翼を脱ぐ。兜や背中に白い翼を持つイメージが見られるのはこのためだとも考えられる。この時に翼を奪われてしまうとその相手に従わざるを得ず、その者の妻にされることが多い。しかしそういった場合でも大抵その関係は長く続く事はなく、いずれはその翼を取り戻しワルキューレとしての任務に戻っている。なお、自らの意思で人間の妻となることもある。その一人としてスヴァーヴァというワルキューレがおり、彼女は見初めた人間・ノルウェーの王子ヘルギと恋仲になり、ヘルギに助力して手柄を立てさせ結ばれている。また、ワルキューレは転生してもやはりワルキューレとなるようで、先のスヴァーヴァはヘグニ王の娘シグルーンとして転生し再びワルキューレとなって、やはり転生していたヘルギと結ばれており、さらにその次にハールヴダンの娘カーラとして転生した際もワルキューレとなったとされている。 一般にいわれる「北欧神話」はもともと、神話や伝説を主体とした「エッダ」、散文や文学的内容を持つ「サガ」や「サットル」からなり、解釈などによってはそれぞれで神や人物の描写などに微妙な差異が見られるものもある。ワルキューレも英霊を導く姿以外にもそれぞれでいろいろな姿が描かれており、人間との恋に陥る姿や、女神としての役割を持つ姿も描かれている。ワーグナーの「ニーベルンゲンの指輪」では、ワルキューレはオーディン(歌劇中ではヴォーダン)の娘とされているが、もともとは、他の神族(あるいはそれに近い立場)や人間の王女等の出身となっている伝承が多い。地域によって綴りや発音が異なりヴァルキュリア、ヴァルキリーなどとも呼ばれる。
|