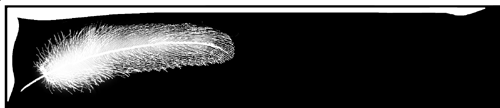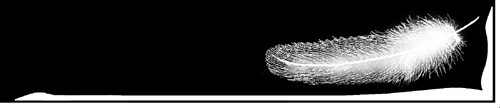人魚は地域性のある幻想生物の中では珍しく洋の東西を問わずに海洋国家、あるいは長い海岸線を持つ地域で広く目撃され、最も古い目撃例は神話時代にまでさかのぼる。しかし、その姿は地域や時代によって違いもあり、一般にイメージされる上半身が美しい乙女で下半身が魚の鰭を持つ姿をはじめ、人間のうら若き乙女と変わらぬ姿からほば魚と変わらぬ姿まで様々である。中には古いケルトの伝承にあるように身の丈数十メートルもの姿や、中国の「山海経」に記述されている陵魚のように四つ足で嬰児の顔をもつ姿もある。また、セルキーなど他の海棲性の幻想生物とは違い淡水域でも活動できるようで、日本では川での目撃例があり、スコットランドでは湖で若い領主が人魚に襲われ湖に引きずり込まれそうになる話もある。 おもに西洋方面では鏡と櫛を持ち岸辺などに腰掛け、髪を梳かしながら美しい声で歌を歌う。姿をあらわすのは嵐の前触れであり、さらには男を魅了し死へと誘う。これに従えば「ギリシア神話」に見られるセイレーンとも共通する性格を持ち、たんに災厄の前触れというだけでなく、実際に災厄を引き起こす力かそれほどまでの魅力を持っていることになる。実際に人間の男は人魚に出会うとまるで魔法にでもかけられたようにその魅力の虜となり、よほど強い精神力を持つか賢明な第三者が引き留めなければそのまま帰らぬ人となっている。しかし、人間の男を魅了する場合には抗しきれないほどの魅力を発揮する人魚も、人間の側からこれを捕らえようとした場合はあまりなすすべが無いようで、不幸にして捕らえられると解放してもらうために人間の願いをかなえるなどしてい場合が多い。これは人魚の決まり事のようで、悪意無くたまたま網にかけてしまった人魚を漁師が逃がしてやる場合でも人魚はこの約束を守って願いをかなえている。また、西洋域の人魚には男も居り、マーメイドに対してマーマンと呼ばれている。マーマンはマーメイドのように人間に恋することは無く、人間とあまりかかわりを持つことは無いものの醜い姿で気が荒いとされており、一説にはマーメイドに危害を加えると嵐を起こすとも言われている。なお、同じ西洋域でもデンマークやノルウェーなど北欧の人魚は比較的穏やかで、アンデルセンの「人魚姫」に見られるようにマーメイドは人間に恋をしたり、人間の友人の病気などを治すために必要な薬草の知識を授けたりもしている。同様にマーマンも人間に危害を加えることは無く、時折岸辺や崖などでも姿を見かけることもあるようだ。 東洋域の人魚は鏡と櫛を持つイメージは無く、姿は一般的なイメージから中国などの人面魚とも言えそうな姿のものもあり、「人魚のミイラ」に見られるように比較的小型なイメージもある。日本の人魚も一部ではこれらのイメージでとらえられるものがあるが、ほとんどはやはり人それも乙女の姿をしているものが多く、「日本書紀」にはすでに川での人魚の目撃例が近江の国からの報告として記述されている。鎌倉時代には上半身がうら若き乙女でふくよかな胸がありきれいな黒髪の人魚の話があり、嵐を知らせているのやも知れぬとして神社にて祈願が行われている。日本の人魚は西洋域の人魚のようにすすんで災厄を起こすようなことはほとんど無く、海が荒れることを漁師に知らせたり、恩を感じた人間や恋した人間のために健気な努力をしたり想いの証として自分の鱗や真珠を残すなど、人間との関係を大切にする傾向が見られる。 人魚の身あるいは血は不老不死の妙薬として古来より求められ、いくつかの話しがあるが有名なものとしては、「八百比丘尼」の伝承に見られる平安時代に若狭の国の少女がそれとは知らずに食べてしまい、自ら命を絶つまで年をとることがなかったというものがある。
|