するとこんな画面になります。
4.打ち込む・・・MPTのやつに4つ打ちのリズムを教え込むのです
本来打ち込みなんて人によってそれぞれなのですが・・・ここに書いてあることなど無視して自分を表現しましょう。
しかしもともとおせっかいすぎるこのページなのでついでに打ち込みまでやってしまいます。Sampleの設定、Instrumentの設定で準備した4つの音を使って、4つ打ちのリズムを打ち込みます。
手順
1.MPTのやつに音を鳴らすタイミングを覚えさせてみる
要は打ち込むことです。まずは![]() をクリックして心の準備をします。
をクリックして心の準備をします。
するとこんな画面になります。
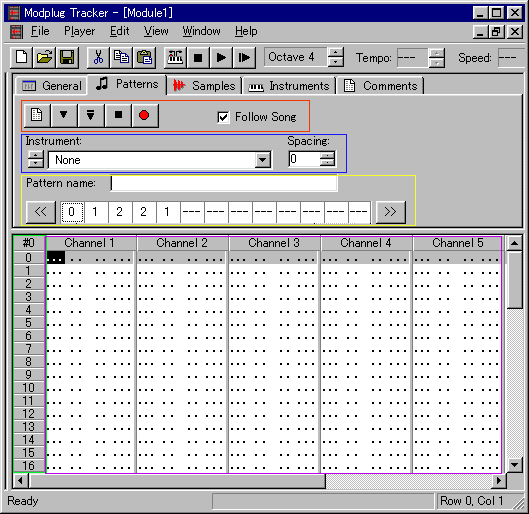
これがMPTのパターンウィンドウです。このウインドウでは初期設定では楽譜で言う4小節を表しています。は〜?なんだあ〜?あわててはいけません。冷静になって色で囲んだところだけみてください。
緑色で囲んだ部分に0〜64までの数字が書かれています。(写真は途中で切れてますが)つまり、4小節を64分割するのでこの番号の1つが1/16音符分の長さということになります。1小節はこの数字が16個分になります。
#0となっているのは現在の表示がPattern0であることを示します。
次に青色で囲んだ部分を見てください。Instrument:Noneとなっています。ここで入力したいInstrumentを選んで紫で囲んだ部分にカーソルを持っていき、おもむろに入力するのです。
他のところは無視して、とりあえずやってみましょう。4つ打ちのキックドラムを入力します。
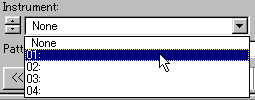 Instrument01のC-5の音がキックドラムになるので、フォームからInstrumentの設定で作成しておいたInstrument01を選びます。
Instrument01のC-5の音がキックドラムになるので、フォームからInstrumentの設定で作成しておいたInstrument01を選びます。
左上の矢印、またはキーボードのCtrl+方向キーでもいいです。
Instrument: 01 が選択されたら紫で囲んだ部分の
Channel 1 の一番上(0)にカーソルを持っていき、キーボードのQを叩いて、0〜4〜8〜12〜・・・・60と入力します。
ここで![]() のところを4にしておけば入力するたびにカーソルが4つづつ下に移動してペンティアムⅡ850MHzなみの快速な打ち込みができます。
のところを4にしておけば入力するたびにカーソルが4つづつ下に移動してペンティアムⅡ850MHzなみの快速な打ち込みができます。
0 C-5 01
4 C-5 01
8 C-5 01
12C-5 01
・
・
・
と入力されましたか? C-5のCは英語のドレミファソラシのドのことでドレミファソラシはCDEFGABとなります。また、
C-5 01の01はInstrument01を指します。
それでは聞いてみましょう。
2.MPTのやつに演奏させてみる
赤色で囲んだ部分を見てください。これがプレーヤーメニューです。
![]() パターンを新規作成します。
パターンを新規作成します。
![]() カーソルの位置から再生します。
カーソルの位置から再生します。
![]() パターンの最初から再生します。パターンをループします。
パターンの最初から再生します。パターンをループします。
![]() 停止します。
停止します。
![]() このボタンをおすと記録可能になります。
このボタンをおすと記録可能になります。
![]() これにチェックを入れておかないと再生してもカーソルがついていかず、どこを再生しているかわかりません。要チェックです。
これにチェックを入れておかないと再生してもカーソルがついていかず、どこを再生しているかわかりません。要チェックです。
とにかく聞いてみます。![]() ボタンを押します。ドン、ドン、ドン、ドン鳴りましたか?
ボタンを押します。ドン、ドン、ドン、ドン鳴りましたか?
鳴れば成功です。MPTのやつは4つ打ちリズムのキックを鳴らすタイミングを体で覚えました。ひとまずほめてやり、もう一度同じように他の音を鳴らすタイミングを教えてやります。
3.もう一回教えてやる
それでは勢いに乗って他の音も入力します。Instrumentの設定でドラムキットを作りましたが、混乱しそうなので
Sample01=Instrument01・・・・・キックドラムの音
Sample02=Instrument02・・・・・Close hi hatの音
Sample03=Instrument03・・・・・Open hi hatの音
Sample04=Instrument04・・・・・スネアの音
として話を進めます。Instrument設定画面で![]() をあと3回連打してInstrumentを4つ作ってください。
をあと3回連打してInstrumentを4つ作ってください。
どうしてもドラムキットとして使いたいときはC-5 02=C#-5 01、C-5 03=D-01、C-5 04=D#-5 01と置き換えてください。
いざ、入力します。
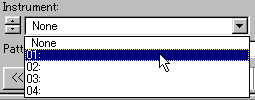 ここでInstrument02(Close hi hat)を選択します。
ここでInstrument02(Close hi hat)を選択します。
左上の矢印、Ctrl+↓でもいいです。
選択されたのを確認して、
![]() のところを4にし、高橋名人の1秒間16連射なみの早さでキーボードのQを連打します。同じように紫で囲んだところのChannel 2
にカーソルを持っていき、1〜5〜9〜13〜と教え込みます。こうすることによって、1秒*4小節となり、1パターンを4秒という驚異的な早さで入力することができます。
のところを4にし、高橋名人の1秒間16連射なみの早さでキーボードのQを連打します。同じように紫で囲んだところのChannel 2
にカーソルを持っていき、1〜5〜9〜13〜と教え込みます。こうすることによって、1秒*4小節となり、1パターンを4秒という驚異的な早さで入力することができます。
さらに同じようにInstrument03(Open hi hatの音)を選択し、2〜6〜10〜14〜と叩き込みます。
Instrument04(スネアの音)は鳴らしすぎるとうるさいので、![]() のところを8にして、2〜10〜18〜26〜とぶちこみます。
のところを8にして、2〜10〜18〜26〜とぶちこみます。
全部教え込んだらこんな風になります。
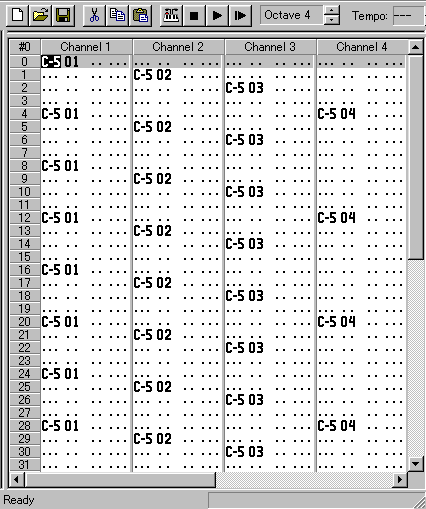
![]() ボタンを押して聞いてみてください。ドンチキチー、ドンチキチーと鳴りましたか?
ボタンを押して聞いてみてください。ドンチキチー、ドンチキチーと鳴りましたか?
きちんと鳴れば4つ打ちリズムパターンは完成です。おつかれさまでした。
こんなのが出来ましたか?
これだけの簡単なリズムパターンでも音圧を上げることによってだんだんトランス状態になり、踊り狂うことが出来ます。(僕はね。猿だから。)できない?出来ない人はもう少しがんばって4に進んでください。あるいは・・・まあいいや。
4.折り合いをつける
う〜んいまいちだな、なんて繊細な人は![]() をクリックして、いろいろ設定し、MPTのやつと相談して折り合いをつけます。
をクリックして、いろいろ設定し、MPTのやつと相談して折り合いをつけます。
ここで設定するのはテンポとかChannelごとのボリュ−ム、パンなどです。
とりあえず下の画像を見てください。
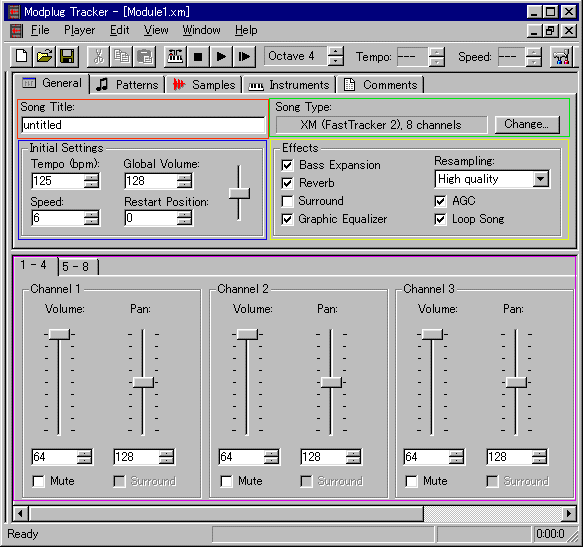
赤色ので囲んだところ、見ての通り曲の名前を入力するとこです。タイトルでも入れてイマジネーションをかりたてます。![]() と入力してください。うそです。日本語は無理です。英語のかっこいいのでもつけてください。
と入力してください。うそです。日本語は無理です。英語のかっこいいのでもつけてください。
次、緑で囲んだところです。MODのフォーマットですね。XMを選んだから、初期設定で8チャンネルになっています。チャンネルが足りなくなったらChange..をクリックして変えてください。
大切なのは青で囲んだところです。
Tempo(bpm):
Beat Per Minute1分間に4分音符が何回鳴るかです。曲の速さですね。
Speed:
MPTのやつが演奏するときのスピードです。BPMとは別で、6が初期設定であり、設定したBPM本来の速さで演奏します。3にすると倍の速さになります。同じ1BPMを表現するとして、これを倍の速さの3にすれば、1つのROW(パターンウィンドウの0〜64の数値のひとつひとつ)を32/1音符としてより繊細なパターンを作ることができます。
Global Volume:
何も設定しないときの全体のボリュームですね。
Restart Position:
最後のパターンまで演奏した後、ここで設定したパターンまで戻って繰り返します。パターンの番号ではなくて何番目のぱたーんかを設定します。黄色で囲んだとこのLoop
Songにチェックしておくのが前提です。普段は使いません。ミキサー通してMTRとかにレコーディングするときに使うと、やりようによっては便利でしょう。
紫で囲んだところはごらんのとおりです。Channelごとのボリュームとパンをつまみで設定できます。はっきり言って使えません。このつまみで設定しても保存されません。ミックスダウンに使うか(タイムラグがあるからリアルタイムは無理)パターン組むときのテストとかですか。
最後に黄色で囲んだところです。再生するときに曲全体にかけるエフェクトです。絶妙なエフェクトをかけて自己満足に浸ってください。他のプレーヤーには影響しません。自分のための設定です。(ここの設定はモジュールに含まれません)
![]() ボタンをを押すと、下の画面が出て各パラメーターが設定できます。
ボタンをを押すと、下の画面が出て各パラメーターが設定できます。
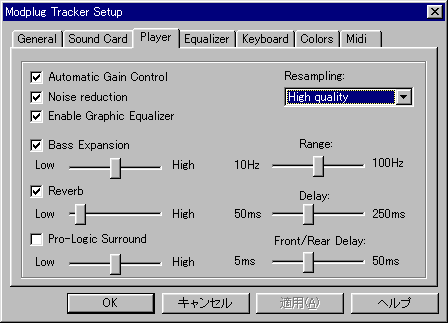
Bass Expansion:
低音を強調します。最近はやりですね。MC−505とかにもついてますねダンスミュージックは低音が決め手です。![]() ボタンでききぐあいが調整できます。
ボタンでききぐあいが調整できます。
Reverb:
リバーブをかけます。![]() できき具合が調整できます。
できき具合が調整できます。
Surround:
三次元音響空間を再現しようというものですね。同じく![]() で設定できます。
で設定できます。
Graphic Equalizer:
5バンドイコライザーですね。Flat
Jazz Pop Rock Clear Hallの6つのプリセットパターンがあり自分でもいじれます。調整するには![]() →Equalizerタブです。
→Equalizerタブです。
Resampling:
No Resampling, Linear, High
qualityの3つの設定があります。High quality がいいに決まってらい。いやたぶんそうだ。知らねーんだ。ごめん。
AGC:
Automatic Gain Controlですな。偉そうに!なんのことか知ってんのかあ?ごめんなさい。
Loop Song
これは分かるよ、もちろん歌をループさせるんだろっ。ループってなんだっ?回んのか?え、おい、回んのか?いつもよりぎょ〜さん回してまっ。
以上でおしまいです。折り合いがつきましたか?意のままを追求してもいいんですけど、なかなか思った通りに表現するのは難しいですね。でも基本的にはこれらの作業の繰り返しです。何度も試行錯誤して、あとは自分なりのテクニックなんか身につけて自分を表現しましょう。たのしいですね〜。
最後におまけ。今回使った4つの音を使ったデモトラックです。こんなのが出来たはずです。