
No.008 東日本旅客鉄道 167系快速「川崎〜奥多摩ハイキング号」 (9351M〜9354M)
川崎 ⇔ 奥多摩間 試乗日 2000年5月28日(日) 全4ページ Page 1

多摩川橋梁を渡る「川崎〜奥多摩ハイキング号」
首都東京の西端に位置する奥多摩地方。 この地方は、緑豊かな山林と多摩川の清流に恵まれ、時として東京
都内にいる事を忘れさせてくれる。 この奥多摩と、多摩地方の交通の要所である立川を結んでいるのが、青梅線
である。 また青梅線は、かつて奥多摩地区で産出される石灰石輸送で、活況を呈していた時期があった。
最盛期には、同じく石灰石輸送ルートとして整備された南武線を通じて、京浜工業地帯への貨物輸送が、盛んに行
われていた時期あった。 この石灰石輸送は、1998年の貨物輸送全廃まで、休む事なく続けられてきた。 こんな
歴史を背負った「石の道」を、2000年5月27・28日の両日、臨時列車が走り抜ける事となった。
今回はその臨時快速「川崎〜奥多摩ハイキング号」に乗車して、往年の「石の道」を味わうと共に、新緑の奥多摩
を楽しんで来ようと思う。 また使用車輌が田町電車区の167系電車(アコモ車)という事なので、近年活躍拠点が
狭まる「急行形電車」の走りも含め、楽しんで行きたいと思う。
  |
(左)綺麗な専用ヘッドマークが 用意されていた。 (右)南武線停車駅には専用の |
5月28日、午前6時。 早朝の川崎駅は、前日の夕方から降り続く雨で濡れていた。 また時折、強く雨が叩き付
ける場面もあり、全くもって最悪の空模様であった。 しかし「ハイキング号」の出発する川崎駅5番線ホームには、
この時点でも約20〜30人位の乗客が入線を待っていた。 この天候にしては予想以上の乗客なので、沿線各駅
での告知広告が功を奏した処ではないだろうか? また鉄道ファンと思われる乗客も、かなりいる様であった。
またホーム上には、「ハイキング号」専用の乗車位置案内も設置されるなど、この列車にかけるJRの「やる気」が
十分伝わってきた。
6:14分。 いよいよ5番線には、特製ヘッドマークも誇らしげに「ハイキング号」が入線してきた。 編成は田町電
車区の167系アコモ改善車で、他にも「ホリデー快速ときわ鎌倉号」に使用されるなど、行楽列車には定評の有る
車輌である。 今日はH16編成4連が充当されていた。
いよいよドアが開くと、早速乗り込み私は席を確保した。 まだ発車まで時間が有るので、編成先端では多くのファ
ンが撮影に興じていた。 やはり期待通り、ヘッドマーク付きの運転となったので、それなりの人出であった。
やがて発車時刻が近づいてきたので、私は観察を終えると、席に戻っていた。
  |
(左)乗車を待つ乗客の姿。 (右)尻手駅付近では101系電車 |
そして発車時刻の6:20となった。 ゆっくりと「ハイキング号」は川崎駅5番線ホームを離れて行った・・・。
発車するとすぐに第2京浜国道をオーバークロスして、尻手駅付近へ到達していた。 ここでは、今まさに尻手駅を
発車した101系電車(南武線浜川崎支線用)とすれ違った。 さてこの尻手駅を通過する頃には、一通りの案内放
送が終わっていたが、快速運転でしかも青梅線直通列車という事で、停車駅の案内に多少の違和感を感じずには
いられなかった。 この先も多くの駅を通過して行くのだが、いつもは各駅停車しか運転されない南武線内では、か
なり新鮮な車窓が展開していた。
ここで、川崎発車時の乗車率を調べて見よう。 4両編成で定員248名のところ約120名の乗車があり、50%近
い乗車率であった。 また通過駅を含め、各駅には通常より多めの駅員配置が見られ、ホーム上の案内に明け暮
れていた様である。 そんな車内外の風景を眺める内に、列車は横須賀線・新幹線の高架をくぐり、最初の停車駅
である武蔵小杉に到着していた。
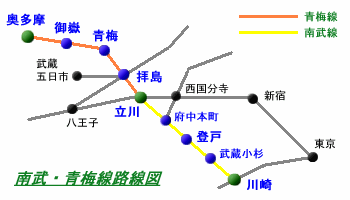 |
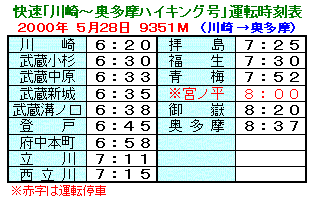 |
この武蔵小杉を発車すると、武蔵中原・武蔵新城・武蔵溝ノ口と続けて停車し、各駅で乗客を乗せて行く事にな
る。 なお途中の武蔵中原では、先行する「稲城長沼」行きの103系電車が待避し、こちらとの接続を図っていた。
そして溝ノ口を出るとまた快速運転となり、次の停車駅は登戸である。 この時点では、制服を着た学生の乗車を
含め、一般客がかなり乗り込んでおり、かなり車内の様子に変化が見えてきた。 それでもなお、雨の南武線を
167系電車は快調に飛ばして行くのであった・・・。 こんな最悪な天候状態の中、カメラを構えた熱心なファンの
姿も、沿線には多く見られた。(本当にご苦労様です。)
そして6:44分、小田急線と接続する登戸駅に到着していた。 ここではかなりの乗客が降りたのだが、逆にそれ
以上の乗客が乗車して来た様で、これでほぼ定員の乗車率となっていた。 また客層には、競馬新聞を片手にした
乗客も見られた。 これから東京競馬場で、第1レースから楽しむという事なのだろうか? 登戸発車時点で再度、
停車駅の案内放送が行われたのだが、ここでは奥多摩地方の現在の天候情報が放送された。 内容は「奥多摩地
方では現在雨が降っていません」との事であったが、全く「今」の状況では想像すら出来なかった。
  |
(左)武蔵中原では、先行する 103系電車を追い抜いた。 (右)雨の中、通過駅を過ぎて |
ところでこの列車には、異常なほど?の車掌が配置されていた。 大体各デッキに1名の配置であった様である。
丁度、デッキに詰めていた車掌さんから話を伺う事が出来たが、停車駅での乗客案内を兼ねての応援乗務との事
であった。 また乗車率についても、雨天でありながらも、かなり多数の乗客が乗られているとの回答だった。
そして列車は、連続立体交差化事業が進む稲城長沼付近を通過し、東京都内に足を進めていた。 やがて南多摩
駅を通過すると、いよいよ多摩川橋梁を渡る事になるのである。 この多摩川橋梁に差しかかった時点で、雲間か
ら太陽の光が見えてきた。 どうやら天候が回復しそうな兆しが見えてきた様である。 そんな多摩川河川敷にも、
カメラを構えたファンの姿が確認出来た。 この多摩川を渡り切ると、東京競馬場最寄の府中本町駅である。
武蔵野線と接続する府中本町では、隣のホームにオレンジ色の103系が停車し、また側線を轟音を立てながら、
コンテナ列車が通過して行った。
  |
(左)雨に煙る多摩川を渡る・・・。 (右)7:09分、立川駅に到着。 |
この府中本町でかなりの乗客が降車し、また登戸以前の乗客数に戻っていた。 この先立川までは、先行列車が
ある為か、ゆっくりとした速度で進んで行った。 天候の方は列車が進むにつれて、徐々に回復の方向に向かいつ
つあった。 さてここで車掌の方から、記念のスタンプ台紙が乗客全員に配られた。 こちらは、ヘッドマークがデザ
インされ、運行時刻も書かれていた。 やがて中央本線が右手側から近づいてくると、もう立川駅の構内であった。
とにかく、南武線を管轄する横浜支社の「やる気」には、終止ビックリさせられた旅路であった。