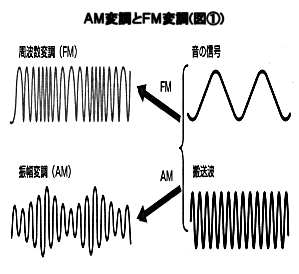データ通信講座
第1回 アナログとデジタルとは
第2回 データ伝送
第3回 変調
第4回 多重化 未
第5回 デジタルオーディオ1(アナログ→デジタル変換) 途中
第6回 デジタルオーディオ2(MD、MP3等) 未
第6回 CD-R/RWについて 未
第7回 ISDN
第8回 インターネットの仕組み 未
番外 ブロードバンド
第1回 アナログとデジタルとは
1.アナログとデジタルの違い
アナログとデジタルは、物理現象を数量表現する場合の方法をいいます。
アナログとデジタルといわれてすぐに思いつくのは時計だと思います。
では、時計の場合、アナログとデジタルでは一番何が違うのでしょうか。
アナログは、長短2本の針が文字盤を回り、デジタルは、時刻を数字で
表します。この事を具体的な違いに分けるとアナログは、連続した量を
表すのに対してデジタルは、離散した量を表します。ここに大きな違い
があります。
アナログ→連続した量
デジタル→離散した量
という違いがあります。
たとえていうとズボンベルトには、穴の位置でウエストサイズを調整す
るものと、穴なしで無段階にサイズ調整可能なバックルタイプがありま
す。穴の位置で調整するものがデジタルでバックルタイプはアナログと
いえます。 |
目次へ戻る
2.デジタル量の表現について
デジタル量の表現方法として一般的には、10進数を用いますがコンピ
ュータで処理する場合等には、2進数を用います。これは、何故かとい
いますと入ってきたデータを見るのに電圧のあるなし(又は、低い高い)
を見て判断するほうが処理を行いやすいからです。そして電圧のある無
し又は低い高いを表すのに通常は、0と1またはH(ハイ)とL(ロー)を
使います。これは値ではなく表現として0と1を使っています。多くの
ICでは0を0V、1を5Vまたはその逆に1を0V、0を5Vで表します。
では、0Vと5Vの間の電圧ではどちらになるのでしょうか。
実はデジタル回路ではこの事を判断することが重要になります。
0と1の間には境界線があります。この境界線をスレショールドレベル
といいます。その境界線は、半導体によって異なります。ただこの一線
を画して0と1に振り分けられることはあり得ないことで、実際にはスレ
ショールドレベルをはさんで不安定領域がありこの部分は使用できな
くなっています。 |
目次へ戻る
3.デジタルの利点
アナログとデジタルの違いについては上記の説明でなんとなくわかった
と思います。では最近、何故デジタルが用いられるようになったのでし
ょうか。それは、パソコンを代表とする半導体回路が色々なところで使
用されるようになったこととデジタルはノイズに強いからです。
パソコン等は、処理をデジタルで行います。そのことはご理解いただけ
ると思いますが、デジタルは何故ノイズに強いのでしょうか。またノイ
ズとは何なのでしょうか。
ここでいうノイズとはよけいな電気のことをいいます。テレビやラジオ
を見たり聞いたりしているときに画面に線が走ったり音に雑音が入るこ
とがありますがこの線や雑音がノイズなのです。そして音声を例に取り
ますとアナログではノイズがのってくると違う音に聞こえます。しかし
デジタルでは、「2.デジタル量の表現について」で説明したように0
と1で表しますので、ある一定まではノイズがのっても0と1の区別が
出来ますので本来のデータ通りに再生することが可能なのです。
このようにノイズに強いということは、データをやり取りするという点
に置いては非常に利点になります。また半導体回路で処理を行うと、機
器の部品数を減らし安くできる場合が多くノイズに強いデジタルで処理
が行えるためです。
目次へ戻る
4.補足(単位等について)
パソコンでは、様々な単位や規格用語あります。ここでは、初歩的な
用語について説明します。
ビット(bit)
2のデジタル量の表現で説明しましたようにデジタルでは0か1で表しま
すが、これを別の表現をすると2進数です。そして2進数では、最小の桁
(0か1しか値を持ちません)をビットといいます。1ビットを10進数に直す
と2です。2ビットは、4です。Xビットを10進数に直すと2のX乗になります。
コンピュータに置ける最小単位です。
バイト(byit)
コンピュータでよく出てくるというより必須の単位です。
1バイトは、8ビットです。また、通信の世界では、バイトの代わりにオク
テットを使う場合があります。バイトに関しては、ちょっとややこしい話が
あります。1キロバイト(1KB)は、1024バイトになります。
キロは後でも説明しますが10の3乗(1000)倍なので1キロバイトは
1000バイトとなると普通は思います。では、なぜ1024バイトなのでし
ょうか。これは、コンピュータが2進数で処理することに関係があります。
1024は、2の何乗でしょうか。
2の10乗ですね。コンピュータにとっては、2の倍数で処理することが都
合が良いために1キロバイト(1KB)は、1024バイトになります。
ですが、実際はそんなに気にしなくても問題がないので(プログラムを
組む人には関係がありますが)1キロバイト=1000バイトと考えてよい
でしょう。パソコンのカタログを見ると最近のものでは1GB=1億Bという表
記がほとんどされています。この表記も実際は違うんだけども実用上は、
問題が起こらないためにそうなっています。
目次へ戻る
乗数単位
| 10の3乗 |
キロ(K) |
1000 |
| 10の6乗 |
メガ(M) |
1000000 |
| 10の9乗 |
ギガ(G) |
1000000000 |
| 10の12乗 |
テラ(T) |
1000000000000 |
| 10の−3乗 |
ミリ(m) |
0.0001 |
| 10の−6乗 |
マイクロ(μ) |
0.000001 |
| 10の−9乗 |
ナノ(n) |
0.000000001 |
| 10の−12乗 |
ピコ(p) |
0.000000000001 |
※これは、パソコンでよく使われるものだけ取り上げました。
目次へ戻る
第2回 データ伝送
・ベースバンド伝送と帯域伝送
データ伝送で取り扱う信号は、コンピュータなどのいわゆるデータ端末
装置が入出力する符号です(前回書いた0と1)
データを送ることをデータ伝送というわけですが、その送り方には、ベー
スバンド伝送と帯域伝送の2つがあります。ベースバンドは、デジタル信
号をそのまま送りますが、帯域伝送は、デジタル信号をアナログ信号に
変えて送る方法です。前回、デジタルの方がアナログより良いと書いた
のに何故と思われる方もおられると思います。これは、普通の電話回線
では、デジタル信号を取り扱えないので変調し送るためです。
みなさん方がインターネットをするときにISDNやケーブルテレビ以外で
する場合は、必ずモデムが要りますよね。モデムは、日本語にすると変
復調装置といいます。モデムは、パソコンからのデジタル信号をアナロ
グ信号に変えて電話回線に流し、電話回線から流れてきたアナログ信
号をデジタル信号に変えてパソコンに渡す働きをしています。
目次へ戻る
第3回 変調
1.変調
変調とは、アナログ信号の周波数を変えて送る又はデジタル信号をアナ
ログ信号変える又はその逆の方法の事で、アナログ信号で送るの方式
が振幅変調と周波数変調が主なものです。デジタルで送る方式ではPC
M変調が主に使われています。
変調の際には、搬送波というものが使われます。これは読んで字のごと
く運ぶための波です。ラジオを思い出してもらうとわかるのですが周波
数何KHzでお送りしていますと時々アナウンスが入りますがこの周波
数がそのラジオ局の搬送波の周波数なのです。人間の音声は、高い人
で4KHzなのでそのまま電波で送るとまず届きません。そのために搬送
波を使い変調して送っているわけです。
2.振幅変調方式(Amplitude Modulation AM変調)
振幅変調方式は、元の信号を搬送波にのせるときに元の信号の高さだ
けを生かして送ります。(図1参照)この変調方式は、AM放送で使われ
ています。他の変調方式に比べて変調が簡単ですが、ノイズには弱い
です。
目次へ戻る
3.周波数変調方式(Frequency Modulation FM変調)
周波数変調方式は、元の信号を搬送波にのせるときに元の信号の振幅
に応じて搬送波の周波数を変化させる変調方式です。(図1参照)この方
式は、2の振幅変調に比べて広い周波数帯域を必要としますがノイズに
よる妨害に強いです。この方式は、FM放送やテレビの音声伝送に使わ
れています。
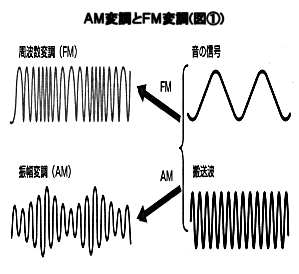
4.PCM(Pulse Code Modulation)
2と3が、アナログ信号で送る方式だったのに対してデジタル信号で送
る方式がPCMでデジタル伝送の基本技術でありパルス符号変調とも呼
ばれています。第5、6回のデジタルオーディオは、これが基本となっ
ています。ここでは、詳しい説明は省きます。第5回で詳しくやります。
目次へ戻る
第4回 多重化
まだ出来てません(^^ゞ
第5回 デジタルオーディオ1(アナログ→デジタル変換)
1.PCM(Pulse Code Modulation)
アナログ信号(音声信号)をデジタル信号に変調する方式がPCMでデ
ジタル伝送の基本技術でありパルス符号変調ともよばれています。
変調の方法ですがまず連続的なアナログ信号を等間隔に分割し、その
とびとびの振幅値を取り出していきます。アナログ信号を一定の間隔に
分割して、各グループの代表値を取り出すことを標本化(サンプリング)
とよんでいます。次に標本化した振幅を実際の数値で表現することを、
量子化とよんでいます。この量子化値を0と1の符号で表すわけですが、
この場合、何桁の2進数で表現するかによって、サンプリングで取り出
した振幅をどれだけきめ細かく表現できるかが決まります。
1−2.標本化
アナログ信号を一定の間隔に分割してその分割点のアナログ信号の
振幅を取り出すのが標本化です。
標本化する場合、1秒間にどれくらいの回数で標本化するかは、音声
や画質を決める重要な要素になるわけですが、これを標本化周波数と
よんでいます。標本化周波数は高いほど良いのですが、最小限どのく
らいが必要かといいますと、音声や映像に含まれる最高周波数の2倍
といわれています。これを標本化定理、染野・シャノンの定理といい
ます。電話の場合は、電話の音声信号は、一般に3.6kHzどまりですか
ら標本化周波数は、8kHzになっていて、CDでは、音声信号の周波数
数帯域は20Hzから20kHzまたは22kHzですから標本化周波数は44.1kH
Zと48kHzになっています。
目次へ戻る
1−3.量子化
標本化した振幅を実際の数値で表現することを量子化とよんでいます。
ビット数で決まる量子化で近似することになります。したがって、標本化
した信号振幅を正確に表すことは不可能ですが、ビット数を増やすに従
って限りなく正確な値に近づいていくわけです。
そのビット数は、電話の場合、8ビットで、CDの場合、16ビットになってい
ます。ちなみに8ビットで256通り、16ビットで65,536通りの表現ができま
す。
標本化と量子化を簡単にいうとアナログ信号の波の数字を取り出すの
に周波数(標本化)を使って縦線を引き、量子化で横線を引くことです。
そして目盛をどうつけるのかということで、サンプリング周波数と量子化
のビットが決まります。
ちょっと一服Oo。.(^。^)y-〜
実は、PCMの理論は古く1937年、フランスのA.H.Reevesによって発明
されています。その時は、見向きもされなかったのですが1948年にシャ
ノンが通信理論を発表することにより、一躍脚光を浴びることになったの
です。
アナログ音声からデジタル信号への変換というとCDやパソコンで扱う
デジタルオーディオと思われがちですが、実は身近なところでこの技術
が使われています。実は、電話の交換機は、ほぼ100%デジタル交換
機になっています。ですからみなさんが、聞いている電話の声というのは
いったんデジタル信号に変換されてからアナログ音声にもどされた声を
聞いているのです。
目次へ戻る
2.CDへの記録方法
アナログ音声をPCM変調によってデジタル信号にしたものを記録して
いる代表的なものにCD(コンパクトディスク)がありますが、このCDは、
どのように0と1の符号を記録しているのでしょうか。CDを見ると円周上
に線があるのはわかりますが、それ以外はわかりませんねCDは、レー
ザー光線を当てて反射してくる光で0と1の符号を読みとっています。
その反射を変えるためにピットといわれる突起があります。
反射光は、ピットのない部分で強く、ピットの部分で弱くなります。
このピットの突起の高さは、わずか0.1マイクロμmで幅0.5μmwです。
ピットとピットの間は1.6μmです。
そしてCDはレコードとは逆に内側から外側に向かって時計方向に渦巻
き状に音声データを記録していきます。
実は、CDはPCM変調したデータをさらにEFM変調して記録してい
ますが、この変調方式については説明しません(ややこしすぎるから)
詳しい理論を知りたい方は、電波新聞社のハイテクブックシリーズの
「CD技術のすべて」という本を読まれると良いでしょう。いっぺんに頭
が爆発します(^^ゞ
目次へ戻る
第6回 デジタルオーディオ2(MD、MP3等) 未
第6回 CD-R/RWについて 未
第7回 ISDN (5月8日訂正)
ISDN(Intergrated Services Digital Network)とは、日本語でサービス総
合デジタル網のことでITU-Tで勧告化されている。通常の家庭用のISD
Nは、64kbpsのスピードを持つBチャネル2本と16kbpsのスピードのDチャ
ネル1本の3本からなっている。ただし、日本の場合はアナログ回線と同
じメタリック線を使用するため、ピンポン式にB、Dチャネルを切り替えて
使用している。(基本インターフェイスのチャネル構造と呼ばれています)
※NTTの商品名では、INSネット64とINSネット64・ライトがあります。
一般家庭用以外に1次群インターフェイスと呼ばれている23個のBチャ
ネル+1個のDチャネル又は24個のBチャネル+1個のDチャネルの形態
もあります。
※NTTの商品名では、INSネット1500です。
電話やインターネット接続に使用されているのは、Bチャネルである。そ
のため、インターネットに接続しても電話が使用できますし、TAに電話を
2台つないでいれば2台同時に電話が使用できます。
当初、ISDNは、テレックスやファックス等の異なるサービス網を一つに
まとめるために策定されたが現在のインターネット接続においては、時代
遅れのものとなりつつあるのは否めないでしょう。
また、電話回線の基幹部分ではほぼ100%デジタル化されています。
目次へ戻る
第8回 インターネットの仕組み
インターネットの始まり
そもそもインターネットは、軍事利用を目的として1960年に研究開発された
ものです。当時は、冷戦のさなかにあり、特定の軍事通信サイトが破壊さ
れても他の通信サイトで代用できるようにするために開発されました。
この時にパケット交換方式の通信が提唱されました。ドコモのiモードで、
一躍有名になったパケット交換方式ですが、このころから既に実用化され
ていました。パケットとは、小包という意味です。データをパケットと呼ばれ
る単位に分けて送信するのですが、パケットにする際に宛先とパケット番号
を付けて送ります。こうすることによって違うルートをパケットが通っていって
も相手に届けることが可能になります。これは、ある特定の通信サイトが、
故障しても他の通信サイトが代替えされてデータを届けることが可能になる
ことと回線の使用効率が上げられると言う利点があります。一対一の通信で
一回線を使用していた場合、データを送信していなくても通信を切断しない限
りその回線を占有していて非常に効率が悪いものととなります。
また、パケット交換方式を用いることにより相手との通信速度が違っても問題
になりません。