 |
           |
 |
蘇民祭に行ってきましたー。蘇民祭って言うのは岩手県・水沢市にある黒石寺で行われる裸祭です。オレもかなり前から蘇民祭の存在は知っていたんですね。いろんなとこのHPにこの祭りの写真載っているから…。興味はあったけどこの寒い時期にわざわざ岩手の山奥まで足を運んで見るものでもないなーって、ましてや出るなんて…って感じでした。ところが去年の夏ですね。ここ数年急激に六尺褌に魅力を感じるようになっちゃって、その一環で蘇民祭のビデオを購入したんです。褌男目的ですね。はは(^_^;;;
ビデオを見た時はもーすっごい衝撃でした。初めは全裸の男にハマってたのですがぁ(>_<)…何度も何度も見ているうちに、参加してる男達が、すっごいカッコ良く思えてきたんですね。そしたらもー出たくて出たくてたまらなくなっちゃいました。性欲?ナルシズム?自虐的欲求?この衝動がどこからくるものなのか、なんか良くわからないんですけどね…。 |
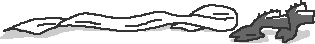 |
最初の行事が10時からなので、余裕を持って7時半くらいに着く新幹線に乗りました。乗り換えの大宮で、夕飯と向こうで食べる食料なんかを買いこみます。大宮には雪苺娘の売店があるんですよねー。ゲットー。。。したのはいいんだけど、新幹線に乗ったらすっごい緊張してきちゃってぜんぜん腹減らない。でも、荷物になるからと無理矢理食べました。
水沢江刺って言う駅で降りるんだけど、ちょっと手前からすっごい雪が降ってきましたー!ひぇー駅を出てまたびっくり、一面の雪景色。しかも電気ついてる建物とか全然なくて真っ暗。早速タクシーで黒石寺へ。タクシーの運ちゃん、群馬からの参加ですーって話したらすごくビックリしてました。めちゃくちゃしゃべるおっちゃんで、蘇民祭の事いろいろ教わりました。
20分くらいで黒石寺に到着。結構大きいお寺です。山に面して建っているみたいで、高い杉の木(松かな?)が沢山あり、雪もたっぷり積もっているから、まさに東北のお寺ぁーって感じ。めちゃくちゃ雰囲気あります。入り口には食堂とトイレ、結構新しい建物で、その前には観光案内所のテントが出てました。そこで参加方法を聞いて、お土産を買って、境内に入りました。
お堂までの道の両側に、ワラとビニールシートでできた小屋が続きます。小屋には食堂と休憩所があって、休憩所には地元の青年団とか企業とか、専用のモノもいくつかあります。本堂にお参りして、すぐ下の参加者用の無料休憩所に入りました。中は20帖くらいあるかなーワラが円形に敷いてあり中心に炭火が炊かれていてワラを椅子にして座れるようになっています。1つの炭に8人くらいは座れるのかなー。そんなのが小屋の中に10箇所くらい作られていました。オレが入った時にはそれぞれに数人ずつが座っていて、どうやらグループ毎に炭を陣取っているようでした。 |
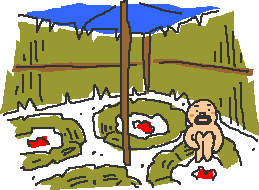 |
コネ無し単身で来ちゃった事に、ちょっと後悔したのだけど、しょうがないから入り口近くのおっさんばっかりの炭にあたらせてもらいました。そこは地元の人たちの席らしく、人が来るまでの間って事で一時的に座らせてくれました。でもまた、群馬から初参加ですーって話になったら、すごく歓迎してくれて、結局ずーっとその席に居て良い事になりました。ふー良かった。話も凄く盛り上がって、祭りの流れとかいろいろ教えてくれたり、お酒もらったり、さっきまでの不安は一気にぶっ飛んで、なんか幸せ〜な気分に浸ってしまったのでした。
炭火で暖を取るって、普通経験ないと思うんだけど、これが実に暖かいんですよー。遠赤外線ですねー。体の芯からポカポカでした。それから、小屋の床はなんと雪なんですー!5cmくらいの雪が踏み固まっているの。炭の周りだけ丸く雪が溶けている。おシリはワラの座布団があるから全然冷たくないんだけど、足は休憩の間ずっと足袋履いてたからめちゃ冷たかった〜。
9時過ぎになると雪も止んで、小屋の中も人で一杯になってきました。と、周りの席を見回すと見た顔ばかり!そう、去年の蘇民祭ビデオで見た事ある人が沢山今年も来ていたのでしたー。なんか、何度も何度も見ていたビデオだから、まるで自分がテレビの世界にやって来た様な不思議な気分です。
10時少し前、そろそろ最初の行事「裸参り」が始まります。六尺と足袋に着替えて小屋の外に出ると、もう行列ができて進み始めてました。最初は寒いぃぃぃ〜って思ったけど、風が無いからなんとか平気。ホントは寺務所に行って角灯を借りて来て、それ持って歩くらしいんだけど、なんか遅かったみたいで、手ブラで出発です。 |
 |
 |
←角灯。
中にロウソク立てて下の方持って歩きます。これは無地だけど黒石寺とか書かれたのを持ってた人もいました。持って帰ってもいいって事なんで、記念にもらってきましたー。 |
|
「ジャッソー」「ジョヤサ」と言う掛け声を掛けながら行列は進みます。最初は恥ずかしかったけど、大声出しながらみんなで歩くのってすっごい気持ちイイです。本堂の石段をずーっと下って行くと川が流れてます。いよいよその川に入って水をかぶるのですねー。いやーもードキドキです。だってその場所だけ異様なくらい明るいし(ビデオカメラのライトですね)、冷たくて歩けなくなったらどうしようぅぅぅ、とか、いろんな考えが頭の中をグルグル〜、まさにジェットコースターのカンカンカンカンって言う所の気分。。。
順番に川に入って桶で3回水をかぶります。瞬間は思っていた程冷たくはなかったなー。サウナの水風呂とか、家で練習した時(爆)の方がよっぽど冷たかった。がっ!川から上がると寒いっ!特に水に浸かっていた下半身はもー感覚無いよ〜って感じ。ぷるぷるぅ〜
で、それから本堂まで戻ってお参りし、本堂の裏山をぐるっと回って出発地点に戻ります。この裏山、石段を昇り降りするんだけど滑ってかなり恐いの。反対側が崖みたいになってるし。。。全長500mくらいあるのかなー結構長いコースで、長いおかげで歩いてると多少はポカポカしてきます。声も出してるしね。で、これを全部で3周するわけです。 |
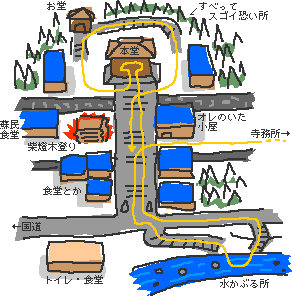 |
2周目の時、隣に全裸の人が3人くらいいたのですね。やっぱり蘇民祭の醍醐味と言えばフルチンだよなーって事で、暫し悩んでオレも褌外しちゃいましたー(>_<)。ははは。でもって近くに角灯を2つもってるおじさんがいたので、頼んで1個もらっちゃいました。うーん。コレで完璧だーね。「完璧」になったおかげで写真に取られ率もグーンとアップ。1周目とは明るさが違いましたもんね。もー寒さでかなりのちびっ子サイズだったんだけど…、ま、いっか。
水をかぶる時は「蘇民将来!」って叫ぶのですね、オレったら緊張していて言うのすっかり忘れてました。3周目に来てようやっと思い出して、叫んでみたんだけど、寒さで「蘇民しょうらぁ〜い」ってなんか声が裏返っちゃいましたよぅ。カッコ悪ぅ〜。もー3周目ともなると、つま先凍ってるんじゃないのー?って感じでした。
裸参りが終わって小屋に戻ると、見物の人達が沢山いて席が一杯だったんですよー。でもね、さっきのおっちゃんが席を開けてくれたんです。おまけに濡れた足袋まで乾かしてくれて、う〜、感激。戻って来て炭火にあたってからの方が寒かったー。暫くは震えが止まらなくて、足も感覚が無くて動かないのだ。ひえ〜。暫くして、暖まってきたので着替えようとすると、なんか入り口の方が明るいぞっ!そう、見物人が数人ビデオ構えてますよー。着替え風景を撮影中なのねん。。。
次の行事「柴燈木登り」が始まるまで1時間程。周りの人達と雑談。若い人達も近くに座るようになって、オレと同じ初参加の東京の人、秋田から来た人達とか、いろいろおしゃべりしました。そろそろ「柴燈木登り」の時間。裸になって六尺を締めてると、位置が下過ぎるよーって後ろにいたおじさんが言うのですね。オレあんまし締め慣れて無いからそうなのかなーって思ってると、おじさんが褌外して締め直してくれました。ところがね、へその上で締めるんだよー、左右のバランスも悪いし…結局自分で締め直し。このおじさん、どうやら「締めてあげる」のが目的だったらしい。。。ふがー(`o´) |
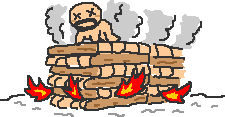 |
「柴燈木登り」ってのは木をキャンプファイアーみたく井桁に積み上げて、下から火を着けてその上に登って、掛け声あげたり「山内節」と言う民謡?を歌う行事です。これ、話に聞いた時には「まさかー?」って思ったのだけど、ホントに火がついてる上に登るんですよー。横からもがんがんに炎が出てるんですよー。上も炎は出て無いまでも、かなりの熱さ。だって火って上が熱いでしょ。この日は風が殆どなかったから煙りも真直ぐ上に昇っていて、オレも上がったのだけど、煙りで何にも見えないし、息はできないし、足は熱いし、木の間に足はハマっちゃうしで、もう死んでしまうかと思いました。あー酸素ってありがたい。。。で、数分で降りてしまいました。あぅ〜根性なし。
積み上げた木の高さは2メートル以上はあるんです。横から炎も出てるし。登り降りって結構危険。煙くて落ちちゃう人もいるくらい。だから、登ろうとしたり、降りようとすると、周りにいる参加者達が助けてくれるんですね。オレも他の人が登るの手伝ったり、こんな風に見ず知らずの人が助け合うなんて事、今どき無いでしょ。うーむ。なんかイイんだな〜。
小屋に戻ると、またまた人で一杯で、いままで座ってた炭には座れなくなり、隣のグループの炭に入れてもらいました。同年代のお仲間さん達のグループで、オレが利用している祭り系の掲示板に書込んでいる方も何人かいて、ずっとお話していました。途中、一般参加は(たぶん)出来ない行事「別当登」「鬼子登」を見たり、食堂の小屋でうどん食べたり、4、5時間はあったと思うんだけど、なんかあっと言う間に過ぎてしまった。
いよいよ最後の行事「蘇民袋争奪戦」です。六尺になって小屋を出るとまた雪が降ってきてました。ホントはすっごい寒いはずなのに、この頃になると裸で外にいるのが、すごく気持良くなってました。服着てるとブルブルってくるでしょ。あーゆー寒気が全然ないんだよね。肌がピリピリするの。これが実にイイんだなー。不思議。
本堂に入ると、まだ参加者は6人しか来てないのですー。でも、カメラ持った見物人はすごい数。最初は本堂の格子戸によじ登ってスタンバイするんですね。で、オレも登ろうと思って手伝ってもらったのだけど、寒くて膝に力が入らなくて、ずるずるずるぅぅぅ〜登れませんでしたー。あうー(>o<)情けないっ。オレ寒くなると膝が痛くなっちゃうんですよねー。最後の方は立ち上がるのも辛かったの…。くぅ〜、来年は膝鍛えて絶対登っちゃるぅぅぅ!と堅く心に誓うのであった。
参加者も増えて来て、なんかいろいろ出し物があって、いよいよ争奪戦スタート。最初は小間木が沢山入った麻袋が投入され、暫くするとその袋が切り裂かれて、中の小間木を奪い合います。もー激しいです。足が痛いです。足袋だから足踏まれるとひじょーに痛いのです。服着た人とかカメラ持った人とか入り交じって押しくらまんじゅう。オレも頑張って3個の小間木をゲットしました。 |
 |
 |
←これがゲットした小間木。
拾うときしりもち着いちゃって、潰されなくて良かったー。 |
|
小間木が無くなると、今度は麻袋の結び目の麻縄?の奪い合いになります。この結び目を最後まで掴んでた人が優勝者になるそうです。参加者は一固まりの押しくらまんじゅう状態になって、境内を出て、一般道をがんがん進んで終着点の田んぼ?まで向かうのです。ずーっと押しくらまんじゅうだから、どっちに進むかわからないでしょー、石段で転ぶは、ガードレールで転ぶは、そりゃーもー大変でした。
最初、体力がまだあるうちは、頑張って中心に入り込み、結び目を掴むことができたりして、もー無我夢中で熱くなって、すごく楽しかったです。でも、後半はヘトヘトになっちゃって、周りに張り付いてついて行くだけで精一杯。やっと終点の田んぼに到着。参加賞なのかな?木の札をもらってお寺に戻りました。
もう夜が開けて明るくなってきています。オレは六尺していたけど、全裸になっちゃった人もかなり多かったです。中心部でもまれていると外れちゃうんですね。お寺に戻るのに、雪が沢山積もってる国道を2キロ近く歩きました。やり遂げたって言う充実感で一杯。だからぜんぜん寒くなーい。
小屋に戻って着替えて、木の札を景品と取り換えてもらって、仲よくなった人達と一緒にお風呂に行きました。蘇民祭の後は「マイアミ健康センター」って言うサウナがホモの定番らしいけど、時間的な事情から石田温泉って言うスーパー銭湯へ。。。
ぷは〜気持ちいぃぃぃぃ〜。体が冷えきっているから、いくら入ってても湯中りしない。もーすごいよー。湯に浸かってると芯から冷えてるってのが良く分かるの、体の中から冷たいのがやって来るって感じ。上がった後も暖まってはいるんだけど、芯からポカポカって感じが全然ないの。こんなの初めてだー。で、そのまま大広間で仮眠して、飯食って、新幹線で帰ってきましたー。ふーっ。お疲れさま。 |
 |
 |
←現地で売ってる六尺(晒し)
「黒石寺蘇民祭」って朱印が捺してあるのだ。黒足袋とセットで\1,000也。友達に頼まれてたので六尺×2本で\1,000にしてもらっちゃった。 |
|
いやー長かったですねー。書くのも疲れましたー。読むのも疲れたと思いますぅ。なんか少しでも雰囲気が伝わればいいなーって思って、詳しく書いてみました。どうです、蘇民祭出たくなっちゃいましたー?普通は出たくならないよなー。オレも何に魅かれて今回岩手まで行ったのか、来年もまたぜーったい行くぅーとか思ってるのか、突き詰めると良く分かんないんだよね。
地元の人たちの温かい人柄とか、祭りの一体感とかすごく感動するし、もちろん裸が見られるとか、フルチンで外歩けるとかってのも大きな魅力。常識じゃあ考えられないような行事の連続で、ブチ切れられるって快感もあるし…。古風な小屋で待ち時間をまーったり過ごすのも楽しい。だけど、それだけじゃ岩手まで行く原動力にはならないような…、そう「髭が好き」とか「短髪が好き」とかの感覚に近いような気がするな。。。うむむ
あ、それから、1つわかったコト。「何で裸祭りはみんな、わざわざ寒い冬にあるんだろー?」ってずーっと疑問に思っていたのだけど、そんな疑問自体バカげてました。裸祭りは『冬』以外には考えられません! |

