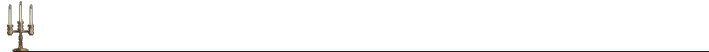一千年の刹那
春の宵は長い。
幾種類もの蕾がその花弁をおとなしやかに一枚一枚外側へ捲る如く、ゆるやかな暖気はそうっと京都を包み込む。そして、フライパンの底のような盆地は、桜を筆頭に、自然の施した色とりどりの絵の具で飾られる。
夏は鴨川の納涼床や五山の送り火に、多くの名刹を彩る紅葉が美しい秋、しんしんと音も無く降り積もる雪化粧を施された冬の名園など、季節毎に豊かな表情を見せるこの町が、僕は好きだ。そして、一千二百年以上栄えた都が見せる顔の中でも、春のそれは別格で、何とはなしに気持ちが浮き足立ってしまう。
4月の声を聞くとすぐ、多くの人が京都中の花の名所へ足を向ける。そうでなくても歴史的建造物だの寺社だのと、年がら年中観光客で華やいでいる町が、一段と賑やかさを増し、週末の河原町界隈は、多くの酔っ払いどもでごった返す。
我が英都大学推理小説研究会―――通称EMCにも、部創設以来初の女性部員が誕生することになり、その紅一点のマリアを囲んで酒を酌み交わそうと言い出したのは、望月だったか織田だったか。共に経済学部三回生のデコボココンビが「女の子がいるんだし、たまには外で飲みたいですね、部長」と、この春も学び舎へ留まった江神さんにお伺いをたてて、冬の間、宅飲み中心だった我が部の酒宴へ久しぶりに外気を当てることとなった。
一応、マリアの歓迎会という名目だったが、実は彼女の入部が決まったその日に、喫茶店でそう名のつくものをやっている。結局、理由は何でもいいのである。集まって、飲んで、ミステリの話が出来ればそれで楽しい。
授業を終えた僕とマリア、学課のない四限は思い思いに時間を潰したらしい望月・織田の一対が学館ラウンジに顔を揃えた。午後からバイトに精を出していた江神さんとは、四条大橋の袂で落ち合った。はぐれないよう気を配りつつ、五人共雑踏の中へ呑み込まれていく。
新入生に新社会人が誕生するこの季節は、どこの居酒屋も異様なまでの混みようだ。金の無い貧乏学生御用達の店は既に満席である。せっかく「飲もう!」という気合の元に集合しているのだから何が何でも飲む、と織田が言い張り、木屋町の隅の隅まで歩き回ってやっと、とある居酒屋に五人分の席を確保した。
まず、ビールで乾杯。さっきから「腹が空いた」と騒いでいた望月と、飲み気より食い気のマリアがテキパキとつまみを決め、次々に注文した。明日は授業の無い土曜日ということで、自然と酒量が多くなる。たわいない話から始まった宴会は、白熱したミステリ談義へ突入した。
好みの問題に還元されるそれらが一段落すると、マリアが突然「花見をしたい」と言い出した。聞けば上洛したばかりの昨年、ガイドブック片手に桜の名所と言われるところは、一通り行ってみたという。しかし何処へ行っても人垣ばかりで、結局揉みくちゃにされて独り、釈然としない気分で下宿へ戻ったそうだ。
花の咲く時期は限られている。その麗しい姿を一目拝もうとして、多くの人間がそれぞれ『名所』と言われる処へ押し寄せるのだから、無理もない。
東京だって花見シーズンは何処もあんなものだけど―――と、言いつつ、
「もうちょっと静かに、お花見したいと思うわ。古都の風情が、台無しよ」
マリアは可愛らしい口許を軽く尖らせる。手許の箸袋を弄びながら、彼女は更に言葉を続けた。
「だから今年は、去年みたいな目に遭いたくないな―――と思ったんですけど・・・何処かお勧めの場所、ないですか? 皆さん、私より長く京都にいるんだから、詳しいでしょう?」
純粋な好奇心を瞳に湛えて、新入部員が一同の顔を見回した。
「う・・・ん、桜、かあ―――去年は、どやったかな」
織田が、望月に話しかけた。
「どこ行っても、人がおるしなあ。今日、金曜やろ。祇園さんも清水寺も、大変なことになってるんやないのか」
頼りない先輩二人のやり取りに焦れて、マリアが僕の方を向いた。
「アリスは? 関西人だもの、どこか穴場知ってるんじゃない?」
無茶言うな。こっちは大阪からの通学生やで。
「せやかて、地元って訳でもないしなあ。観光ガイドに書かれとるような名所しか、よう知らん」
僕の言葉にマリアは「役立たず」と言いたげな一瞥を寄越し、江神さんへ縋った。
「江神さんなら、知ってますよね。どこか、静かに桜が見られる場所」
「桜、か―――夜桜で、ええんやろ?」
穏やかな顔で、後輩たちのやり取りを聞いていた部長は小さく笑った。
「心当たりが無い訳でもないがな。そないに、期待されても困るぞ―――でも、ま、行くだけ行ってみるか?」
皆がそれぞれに頷いた。この店へ腰を落ち着けてから、軽く4時間が経過していた。いい加減、店の方も嫌がる。そろそろ潮時だろう。
「それじゃ、行きますか」
織田がさっさと伝票を手にして席を立つ。男だけで会計を割り勘にすると、僕たち五人は、酒臭い息を吐きながら河原町でうねる喧騒の中へ再び繰り出した。途中から路地を入り、何度も曲がった。先頭を歩く江神さんの後姿だけが、薄闇の中に浮かんでいる。酔いが回った身体の火照りに、夜気がひんやり気持ちいい。親鳥にピタリとついて後を追う雛の如く、皆、無言で歩き続ける。
どれくらい歩いただろうか。酒に浸りきった脳味噌は、よく知っている筈の京の町を異国のように知覚させ、眩惑する。右に左に折れる度、初めて見る路が目の前へ開ける。
「江神さん、何処まで行くんですか〜」
若干情けなさの混じる望月の声と江神さんの動きが止まったのは、ほぼ同時だった。
「此方や」
江神さんは細い私道の奥を指差し、確かな足取りで、敷地内へ入っていく。示されたのは、寺の境内の裏手にある、やや小ぶりだが立派な枝垂桜だった。
「うわ・・・ええやん」
「ほんまや―――江神さん、ここ、何処ですかね?」
口々に感嘆の声を上げた経済学部コンビへ、江神さんは短く「国上寺」と答えた。
「その脇に墓地があるやろ。昼間はこの裏手からも入れるんや」
夜だから、さすがに門は閉められている。少し前、低い木戸を順繰りに乗り越えて、僕たちはここまで入り込んでいた。厳密に言えば"不法侵入"というやつだ。
江神さんが、簡単に現在地を説明する。
「まぁ、観光コースからは外れとる処やからな。昼間は近所の人が花見くらいするかもしれへんが、夜は誰も来ないやろ。ライトアップされてる訳やないし」
だが、その枝垂桜は花の姿を墨が滲んだような夜空へ柔らかく光らせている。光源の在り処を捜すと、それはすぐに見つかった。
水銀灯の発する光が四方の高層建築の壁に受け止められ、ビルの谷間に囲まれた小さな古刹を淡い光の粒子でくるんでいるのだ。薄い色の花びらは受けた煌きを控えめに反射させ、不可思議な空間を決して広くないこの場所へ作り出している。そして、上空には朧月。
「凄い・・・綺麗―――」
さっきからずっと黙ったままだったマリアが呟く。
「ああ、綺麗やな・・・」
僕は仄かな輝きを内包する姿に心打たれていた。法学部二回生コンビもまた、ただ桜に見惚れる。
周囲から切り取られたように唐突な風景も、夜という懐に抱かれているせいか、然程違和感を覚えさせられない。しかし、マジシャンが掌からポンと出した如くに思われる、この静謐な場所は、なぜか僕の心を和ませてくれた。江神さんはポケットからキャビンを取りだし、一本咥えた。のんびりと紫煙を燻らせ、宵闇に浮かぶ羽衣のような桜の大木を見上げている。
辺りはしんとしていた。時折、遠くでアスファルトを軋ませる車音が、微かな唸りを空気中へ伝わらせてくる。
一本だけの枝垂桜は優雅に頭を擡げ、光のシャワーを浴びているように幸せそうである。気持ちが洗われるような光景だと感じた。
もはや、言葉を発する者は誰もいない。そうして五人とも、暫く静かに花見をした。国上寺の裏門を再び突破して、今夜の酒宴はお開きになった。下宿の方向が同じだからということで、望月と織田がマリアを送っていくという。僕は江神さんにくっついて、地下鉄の駅がある方へと足を向けた。
ギリギリ終電に間に合うかどうかという時刻だ。西陣の下宿まで歩いて帰る部長のゆっくりした歩幅に合わせている場合ではない。だが、「間に合わないんで、先、行かせてもらいます」という一言を口に出来ないまま、僕は江神さんの背中へ視線を投げかけていた。無駄な贅肉のついていない、すっきりした体躯が、何かを確かめるような足取りで僕の少し先を歩いている。
―――帰りたくない・・・
意味もなく、そう思う。さっき見た、清冽な桜の姿がまるで僕の足を引っ張っているみたいだ。
そんなこちらの心を知ってか知らずか、僕の数歩前を行く江神さんは左腕を軽く上げた。時刻を確認したのだろう、僅かに顔を捩り、
「アリス、電車の時間、ええんか?」
と、聞かれた。
今なら、まだ間に合う。ここで江神さんに一礼して全力疾走すれば、2〜3分の余裕をもって地下鉄の最終に飛び込める筈だった。それなのに僕の足取りは重く、速度が更に落ちて遂に動かなくなった。
次の瞬間、江神さんはその場で立ち止まり、僕の方へきちんと向き直った。
「なんや、そないな顔して」
優しく響いた江神さんの声に絡め取られそうな気がして、僕は思わず俯いてしまった。
「どないしたんや―――具合でも、悪いんか?」
至近距離まで引き返してきた部長は、そっと僕の顔を覗き込んだ。
江神さんの暖かい眼差しに全身を愛撫される。心臓がそれに反応して心拍間隔を縮める。僕は自分の中に起った異変を自覚した。
一体、僕は今、どんな表情をしているのだろう。
深夜、人通りの無い裏道で、僕と江神さんは無言で向かい合っている。このまま時が止まってしまいそうだと思ったけれど、一千年も続くかと思われた刹那は、江神さんの右手であっさり振り払われた。スッと伸ばされた指が僕の髪へ絡まり、柔らかく頭を撫でられる。
「もう、あかんのやろ」
チラと、左手の腕時計を見遣る。そう、間に合わない。最終電車は行ってしまった。まだ、言葉を紡ぐことが出来ないでいる僕に、江神さんは微笑した。
「うちに、泊まるか?」
ややあって、僕はやっと口を開く。咽喉がカラカラに渇いていて、掠れた声は、町を覆う静寂に吸い込まれていった。
「・・・ええんですか?」
「帰りとうないんやろ? 泊まってったら、ええ。ただし―――寝る場所は、自分で作ってもらうで」
「はい」
最後の一言に、つい吹き出しそうになる。江神さんの下宿へは何度もお邪魔しているが、いつも書籍やCDで溢れかえっている。溜まった本は適当に積み上げ、座る場所を自分で作るのが来訪者の心得なのだ。
「じゃあ、いこか」
いざなうような江神さんの声を聞いて漸く、僕は夜の町を再び進み出した。今度は、どちらからともなく歩幅を合わせる。
「江神さん」
並んで歩いている部長は、「ん?」というように少し頭をこちらへ傾けた。しかし、目線は前方へ向けたままである。顔を見られていないのを幸いとばかり、一息に喋った。
「なんで、気がつきはったんですか。その、帰りたくないって・・・」
言ってしまった後で、僕は視線を落とした。やはり、今日はどうかしている。こんなこと、部長に聞いてどうするんだ。
いつもより過ごした酒量と朧月に照らされた桜が、僕を狂わせた。見慣れた筈の町並みに蠱惑的なフィルターをかけ、秘めやかな幻想が紡がれる。
「さっき―――」
逡巡するような間があったが、結局言葉は続けられた。
「なんや、人恋しそうな顔しとったから・・・」
普段だったら、穴に入り込みたいほどの失態だ。だが今晩は、そんな気持ちが露ほどにも湧かない。江神さんも特別気にしてないふうだった。
淡い月の光が僕たちの頭上で瞬く。僕の隣を歩くひとの顔は聖人のように端正だ。
彼を月人派だと言ったのは、誰だった? 理代か、それとも月の子ルナか―――
僕は、上目使いに江神さんの横顔を見つめた。そして、今更ながら、自分の本心に思い至る。
―――人恋し 灯ともしごろを さくらちる
誰でも良かった訳じゃない。少なくとも別れた三人と共に帰路へついていたら、今頃僕の身体は間違いなくJR最終電車に揺られていただろう。
でも、今日は、あんな綺麗な桜を見た後で、この人と一緒にいたくなった。だからあの時、江神さんのあとを追いかけたのだ。確かに、地下鉄の駅は方角を同じくしていて、それが僕に一応の言い訳を与えた。
出会ったばかりの頃、幼い時に死別した兄の面影を江神さんへ重ねていたからか、今でも彼を実の兄以上に慕う気持ちはある。だけど、もう、それだけでは満足しない自分がいることも知っている。
そしてまた、はたと気づく―――もしかして、僕はとてつもなく愚かな行動を起こしたのではないだろうか?
切ない気持ちを抱えたまま、自分にそういう感情を抱かせる張本人と同じ屋根の下で眠るなんて、どう考えても自虐的だ。しかし、もう引き返せない。江神さんと一緒にいられる時間は、僕にとって何物にも代えがたいのだから。
そんな想いを持て余してか、さっきまで居た国上寺のことが口をついて出る。
「それにしても、あの桜の木、もの凄く綺麗でした。よう、あんな場所、見つけはりましたね」
「そうやなあ。前は表門の方からも、あの木が見えたんや。月の綺麗な晩にフラフラと迷い込んで―――桜に誘われた、という感じやった」
よく響く声が、僕の耳と心をくすぐる。
「暫くして、正面の通りにビルが建ちよった。なんや悲しくなったなあ・・・けど、夜、通ってみて、驚いた。ビルの壁が街灯の光を跳ね返して、あの姿や」
そう言って、江神さんは、いいものを見つけたというようにくすりと笑った。
「それ以来、時々、行くようになってな―――もちろん、夜だけやけど」
「あそこ、僕もよう気に入りました。あの桜、来年も一緒に―――」
見られるといいですね、と言うつもりだった科白を慌てて呑み込んだ。いい加減、卒業したいのじゃないだろうかという考えが、頭を過ったからである。だが、不自然に途切れた科白の行方を気にする間もなく、勘の良い部長は僕の耳元へ「心配せんでええ」と囁いた。心地よく湿った吐息が、僕の鼓膜を暖める。
「幾つになっても、俺はアリスの先輩や。お前が『イヤや』言うたら、考えるけどな」
そう言われただけで、嬉しくなってしまう自分のゲンキンさにいささか呆れるが、こればかりはどうしようもない。
この人に出会えて良かった―――寄せる想いは微妙に変化し始めているけれど、矢吹山下山の途中で告白した通り、あなたに会えただけで、あの大学へ入った甲斐があったというものだ。
僕は、きちんと江神さんの顔を見て応えた。
「イヤな訳、ないやないですか」
本当のところ、それ以上のことを望んでいるとは、さすがに言えない。だけど、今はこれでいい。僕を弟のように可愛がってくれる優しい兄と一緒にいられれば、それだけで幸せだ。
自分に言い聞かせるつもりで、口に出す。
「江神さんが『イヤや』言うても、僕は江神さんの後輩です―――ずっと、後輩です」
それを聞いた江神さんは花が開くように笑った。僕の好きな笑顔だ。
大勢でいる時の優しい笑みとはやや趣を異にして、妖艶な色っぽさが其処にある。男を掴まえて『妖艶』だの『色っぽい』だのという表現はいただけないと呆れるむきもあるだろう。だが、男にしか出せない『色香』というものをこの人は確かに持っている。
普段は露わにされない彼の魅力が、僕を強く惹きつける。そして、二人でいる時にそういう姿を見せてくれることが、部長にとっての僕はやや特別な存在であるという証拠だと信じることにした。物事を全て自分の都合のいい方へと解釈したがる癖はどうかと思うが、今日くらい大目に見てもらおう。
こうして僕は幸せなひとときを抱きしめ、泣けてくるくらい綺麗な晩を満喫しながら、江神さんと一緒に夜道を辿った。(2000/5/10)
へ戻る
うわー、この話、何なんでしょうねぇ???
地理的要素は滅茶苦茶です。大体、モチ・信長・マリア各人の下宿の位置関係がどうなっているのか、よく判っていません。もちろん『国上寺』なんて寺は、おそらく、京都市内にありません。そして、関西弁もテキトーです。一応、大阪弁変換辞書を使ったんですが(大爆笑)
もう、見事に自己満足な話です。内容は、無いよー<ばき
要は桜と江神さんとアリスを書きたかっただけなんですね。しかも書き終わってから気がつきましたが、アリスに自覚があるとすると、この年の夏の『望楼荘in嘉敷島』はどーなるんだ〜〜〜(大笑) 尤も二晩目には殺人が起きてしまったので、それどころじゃなかったでしょうけれど。
しかし、ショートのつもりで書いても、この字数……(死)更に―――この話を書いた時点では、すっかり忘れてたんですねえ、マリアの入部時期。先日、幸運にもアンソロジー集『五十円玉二十枚の謎』を手に入れることが出来、短編『老紳士は何故・・・・・・?』の再読が叶ったのですが、それによると、マリアが入部したのはナント四月の末……(爆死) いくらなんでも、桜で花見は出来なかったんじゃないでしょうか。
ということで、のっけから大ウソ書いてしまったようです。どうも、すみませんでした〜!!!