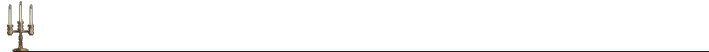Summertime Blues
開け放した車窓の桟が朝日を受けて煌き、爽やかな空気を流れ込ませてきた。
加速する列車は景色をぐんぐん遠ざけ、視界から至極あっさりと理代を奪い取ってゆく。彼女の姿が完全に見えなくなったのを確認した後、僕は身体を屈めて床に落ちた『ソレイユ』のマッチを拾った。揺れる車体の中は、奇妙に落ち着ける場所のような気がした。
先輩たちの待つ座席へ戻る。
四人掛けのボックスシートから、ひなびた在来線の匂いがしている。いつものように一年上の先輩二人が並んで座り、部長の隣を指定席の如くに空けておいてくれた。
僕が腰掛ける時、望月と織田は一瞬だけ探りを入れるような視線を寄越したが、何も聞いては来なかった。江神さんも窓外の虜となっていて、ほとんどこちらを見ない。先輩たちの気遣いがこそばゆく、また、ありがたかった。
車輪とレールの摩擦音が小気味良いリズムを刻む。会話も無いままに何駅かをやり過ごし、そうして、旅することだけに全身を委ねる。
長野駅で特急に乗り換えてからは話の花もポツポツ咲いた。車内販売のメニューやら停車駅の広告看板やら、その時その時で目についたものを主なタネとして四方山話が続けられた。誰も彼もが、少し前の出来事を振り返るまいとして必死に会話を紡いだ。あの、悪夢の如き惨劇を思い出させかねない単語は間違っても口にしないよう、各人が細心の注意を払った。
名古屋駅へ到着した。織田が降りる。
「あんな目におうてしまうと、平平凡凡が一番やと痛感するなぁ」
額に絆創膏を貼った先輩はそう言った後、名残り惜しそうにホームへ留まり、僕たちを見送ってくれた。
東海道線と合流した特急は更に西へとひた走る。夏の陽射しが窓ガラスの向うで光り、軽やかに跳ねる。
次に下車するのは江神さんだ。
車内アナウンスが「次は〜京都〜」と告げ始めるやいなや、部長は網棚から荷物を下ろし、身支度を整えた。
「また、大学でな」
軽く手を上げた彼が、降車口を目指して歩き出す。
全てを解決へ導いた賢者の後ろ姿。徐々に遠ざかるそれを見ていた僕は、その時、唐突な胸騒ぎへ見舞われた。
なぜかは解らない。急に湧き上がってきた、やるせない不安とでも言おうか。慌てて立ち上がり、夢中でその背中を追いかける。後方から望月の声が聞こえたような気もしたけれど、そんなことには構ってられなかった。
京都駅へ滑り込んだ列車が車輪を軋ませて止まった。
デッキは下車する人々が溢れかえっていて、すこぶるつきの大混雑だ。その中にて漸く、彼の羽織っているシャツの裾を捕えた。
「江神さん」
車外へ出られる前になんとか追いついたものの、ただ、名を呼ばわるのが精一杯だった。
振り向いた人は微かに首を傾げ、その目を眇める。
「自棄(やけ)酒なら、いつでも付きおうたる――― 一人で飲むんやないぞ」
穏やかな口調がじわりと僕の中へ沁み入ってきた。まるで、剥き出しの神経を柔らかく包み込まれたかのようだ。
プチンと音がして、張り詰めていた『何か』が砕けた。身体の奥からせり上ってきて眦へ溢れ出そうとしている感情を必死に抑えるべく、何度も瞬いた。鼻の奥へ微かな痛みが走った。
返す言葉もないまま、ホームに佇む涼やかな目を見つめた。
耳障りな機械音を立てて扉が閉まる。
急いで座席へ戻った。窓に貼りつくようにしながら望月と二人、江神さんの姿に手を振った。
プラットホームも遥か後方へ置き去りにされた頃、銀縁眼鏡をかけた先輩から恨めしそうな視線を投げられる。
「なんや、いきなり飛び出していきおって―――驚くやないか」
そう言われても、力無く微笑み返すしかなかった。
その後、新大阪で南紀白浜方面への特急に乗り換える彼を送り出し、とうとう一人になった。
大阪、終着駅。
降り立った僕の目に、午後の街が白っぽい残骸となって映る。頭上で傾く太陽は黄色いままだった。もはや二度と戻れないのでは・・・と危惧していたにも拘わらず、普通の生活が再び始まった。
家族と暮らす毎日はひたすら平和である。寝坊して、母親の小言を聞き流しつつ食事を済ませる朝。昼間は本屋を覗いたり、地元の友人たちと旧交を暖めることもある。夜には父親の晩酌に付き合い、阪神タイガースの不甲斐ない順位へ肩を落とす―――多少のバリエーションはあれど、こうして一日は終わり、残る夏期休暇日数を着実に減らしていく。一週間、十日と過ぎゆくうち、あの悲痛な記憶だけが異質なしこりとなりつつも、少しづつ僕の中へ埋もれようとしていた。
それでも、ひとたび目を瞑れば、皆の顔が即座に脳裡へ甦ってくる。
廊下のように奥行きの深い喫茶店『ソレイユ』を出たところで雄林大学と我が英都大学、二組のパーティが顔を合わせたところから始まった、山での夏休み。バス発車間際に走ってきた神南学院短期大学の三人も加わった。五合目の旧キャンプ場跡にて、また一組のグループと出会い、仲間は男女合わせて十七名にまで膨れ上がった。
知り合ったばかりにも拘わらず、グループ間の垣根はことごとく取り払らわれ、旧知のような人間関係が出来上がった。大自然に後押しされて、開放的な気分が瞬く間に全員へ伝播される。山は緑に光る風を渡し、人間をその懐に絡めていった。都会より脱してきた三十四の瞳は刻一刻と輝きを増してゆき、下山の折には銘々が得た最高の思い出を手にして散会する筈だった。
小百合の失踪も突然の噴火も殺人も、露ほどの予期すら出来なかったことである。この事件を外から見ていた人は、それら全てを不幸な事故と片付けることだろう。しかし当事者たちは、仲間の『誰か』が抱く殺意と地球の脅威にことごとく翻弄され、身も心も極限まで苛まれた。生還者十二名という結果は、寧ろ奇蹟だった。
たった八日間とはいえ、寝食を共にし生死の狭間を潜り抜けてきた面々が最終的に受け入れなければならなかった現実は、あまりにも惨かった。そのショックを考えてか、身近な人々は誰しも、僕に詳細を訊ねようとしない。それは非常に感謝すべきことではあるものの、腫物を触るような扱いには違いなく―――だからだろうか、尚更、事件のことばかり思い出してしまう。そしていつの間にか、意識は目に焼きついた一つの光景へと収束する。
早朝の小諸駅に白いワンピース姿を見せ、淋しげな笑顔で僕の想いを拒絶した理代。
フラれた理由は、はっきりしている。あの子にはちゃんと彼氏がいるのだ。つまり、自分は理代にとってその彼氏を袖にするほどの存在とはならずに終わった、というだけのことだ。
理屈でなら、いくらでも自分を納得させられる。それに―――
二度と目を開けることもない、息をすることもない者たちに比べれば、生きている僕がした失恋くらい何だというのだ?
問題を擦り替えていると言われそうだが、そう考えたのも事実である。居直ったのかもしれない。とまれ、前向きに捉えなければやってられないではないか。
何しろ、殺人事件や二百年ぶりの大噴火がセットになった思い出なのだ。忘れようとしても忘れられそうにないのなら、しかと向き合っていくしかないだろう。
そうこうしているうちに8月は最終週へ突入し―――僕は手帳を開いて、京都に住む先輩の電話番号の確認を済ませた。四条河原町にて江神さんと落ち合う。少し歩き、近くの居酒屋へ移動した。いつも大勢の人々で賑わっているチェーン店だが、夏休み中で学生客がほとんどいない分、やや混み具合が緩和されているようだ。
二人ということもあってか、カウンター席へと案内される。
当り障りの無い雑談が皮切りになった。開幕まで半月となったソウル五輪で日本はどれだけメダルを取れるか?という世間の興味をなぞったようなものから、読了したミステリの当り外れ、バイト中の珍体験など―――何も、夏休み中、わざわざ京都へ遠征してきてまで話すような内容でないことは、自分でも重々承知している。
けれど、己の口から矢吹山で共に過ごした日々について触れる踏ん切りがつかない。そうして、僕はただ喋り続けた。物静かな先輩もこちらが作る会話の流れに敢えて逆らわず、時々、新しく接ぎ穂の出来そうな話題を蒔いてゆく。
もう、何度、追加注文しただろう。つまみの類いは既にオーダーストップされてしまった。酒量だけが増える。
かなり飲んでいる筈だが、酔う気配は未だない。隣りの江神さんも、勿論けろりとしている。
「ラストオーダーになりますが、どないしますか?」
振り向くと、僕と同じような年恰好の男子店員が注文を取りにきていた。
互いのグラスへ目をやる。どっちも、まだ半分くらい残っているんやけど・・・
「あと一杯づつ、頼むわ」
江神さんがそれぞれの中身を指差して、言った。
伝票を持って遠ざかる姿を確認してから、隣の人はその身体を心持ち僕の方へ傾けた。
「残り一時間で閉店やな。店、替えるか?」
囁くような声が耳元にかかった。唇を強く引き結び、微かに首を横へ振る。
このままではタイム イズ アップだ――― 一体、何しに来たんだ自分は。
そもそも今日の約束を言い出したのは僕自身なのだ。
京都駅で別れた時、部長は「自棄酒なら、いつでも付きおうたる」と確かに言ってくれた。けれど、慰めてもらおうとして出向いてきた訳ではない。実らない恋の理由は様々で、悪かったタイミングや相性をいくら愚痴ろうと、虚しいだけだ。
だが―――どうしても江神さんへ訊いてみたいことがあった。
連日、矢吹山で起きた事件と最後の最後にどんでん返しをしてくれた彼女のことを考えているうち、僕はある疑問を抱え始めた。それをなんとかしてほしくて、わざわざ時間を取ってもらったのだ。
大学が始まれば二日と置かずに顔を合わせることになるだろうから、とも思ったが、一度気になりだすとどうにも落ちつかない。これぞ、ミステリマニアの悲しい性というやつか。
ラストサービスのつもりだろうか、なみなみと満たされたグラスが二つ、目の前に置かれた。
「江神さん」
正面を向いたまま、部長の名前を呼ぶ。
「何や」
「なんで、"あかん"て判ったんですか」
そう、僕がずっと抱えていた謎である。なぜ、この人に限って、僕と理代がああなると判っていたのだろうか。
少しの間、逡巡していた彼は、チラリとこちらを見てから口を開いた。
「まあ、お前と理代との間にあったことを全て知っとる訳やないからな。カンみたいなもんや」
「けど、理代に誰かいてるってこと・・・気づいてはりましたよね? だから、『仲よくするのも、ほどほどにな』って言わはったんやないですか?」
「気づいてた、という訳やないんやけどな」
鼻の頭を掻きながら、部長はぼそりと呟いた。
「あの時は、女の子たちの組み合わせを考えてたんや」
「組み合わせ・・・ですか?」
「そう―――美加、夕子、竜子。以上がウォークの三人やな。それからサリー、理代、ルナで、数だけやったら合計六人になる」
そう告げられても、彼が如何な思考を抱えていたのか、さっぱり見当がつかない。僕は頭の中で首を捻った。
咥えたキャビンに火を点けて、江神さんは話を続ける。
「全てのトリオに当て嵌まる訳やないけど、一般的に三人というのは二対一になり易いやろ」
いきなり話題が飛んだ。しかしまあ、三人のうちの二人が結託して残る一人と仲違いするというケースは確かによく聞く話である。僕は無言で首を縦に振った。
「東京組の方やと、竜子にはピースが始終ちょっかい出しとったこともあって、何気に美加と夕子で行動してたようやったな」
そう言われれば、そんな気もする。ゲームや雑談の際には男女混合となって様々にバラけたものの、それ以外のシーンだと大人しい竜子は美加や夕子から一歩離れたところにいる、という感じだった。尤も、彼氏の隆彦が始終傍にいたのだから、それも然りだろう。
「次、神戸組の方やけど」
山崎小百合、姫原理代、深沢ルミの女の子三人組。ワンダーフォーゲル経験者の小百合が言い出し、矢吹山でのキャンプを決めたと理代が言っていた。
「こっちも上手くいってた。多分、ルナが独りでいることを気にせんタイプやったから・・・やと思う」
「理代とサリー、ルナ―――というふうに割れる、という意味ですか?」
「割れる、いうほど深刻なもんやないやろ。なんとなく、そういう線引きがされてるんやないか、と感じたんや」
ここからは完全な憶測やけど、と断って、江神さんは話を進めた。
「理代はサリーを頼りにしておった筈や。キャンプに来ようと言うたのがサリーだったということを差し引いても、サリーとペアを組むのは自分やという気持ちがあったやろうな」
そこへ、武が割り込んだのである。
「初日、武とサリーが互いに強く引きおうたのは間違いなかった。キャンプファイヤーの時には、傍目にもはっきりと判るくらいやったからなぁ・・・ピースと竜子の間もそうやけど、ベンや文雄がやっかむ要因は既に最初の晩からあったんや」
なるほど、そうだったのか。尤も、僕は理代ばかり見ていて、その辺りのことには気づきもしなかった。けれども、翌朝、歯を磨いていた時の喋喋喃喃とした二人のやり取りからすれば前夜も推して知るべしだろう。
「そらまあ、一目惚れというやつは現実にあるんやろうし・・・アリスもそうやったんやろ? バスに乗った時からずっと視線が理代を追っかけとったようやから」
うわ、と叫び出しそうになってしまう。江神さんの観察眼を決して見くびっていた訳ではないのだが、しっかりバレていたとは。今更ながらに頬の火照りを体感してしまい、恰好がつかない。
「ルナは元々、独りが好きなタイプなんやろう。足を怪我して歩行に難儀するようになっても、自力でよく散歩しておったくらいやし」
淡々と回想を巡らす先輩の言葉に、またも黙したまま頷いた。わざわざ杖を突いてまでうろつき回ることないやないの、とぼやいた理代の科白は今でもはっきりと思い出せる。
「せやから・・・理代は不安になったんやと思う。サリーは武と一緒に行動するようになってしまい、ルナは独りで歩き回る。それで、誰かの隣りを確保しとうなった―――」
そうして熱い視線を向けた男、有栖川有栖の存在意義が出てくる訳か。
聡明な人は続く言葉を殊更ゆっくりと紡いだ。
「同じ関西人ということもあるし、アリスが理代の好みに一番近かったという点は事実やろうけど」
「それはそうかもしれないです、けど・・・」
武と小百合の間にあった親密さと僕と理代の間にあったそれの違いを、なぜ、この人は嗅ぎ分けられたのだろう。
百歩譲って、当事者である僕の心は盲目状態だったとしよう。しかし傍から見て判るほどに、二組の差が顕著に現れていたとはとても思えない。自惚れ心からでなく、今、思い返してもそれが判らないのだ。
僕がフラれると予見していたのは、おそらくこの人だけだったに違いない。だから知りたかった。どうして、江神さんは『それ』に気づいたのやろう?
言葉で問い掛けずとも、僕の目が発した疑心を部長は正確に掬い上げたようだ。蕭条たる笛の音のような声が説明した。
「根拠らしい根拠なんか、大してあらへんのやけどなぁ・・・まあ、強いて言うなら、理代がやけに『京都』という土地へ拘っておったことや、お前が一言一句、事細かに再現してみせた理代との会話内容を彼女は殆ど覚えてなかったこと―――それらが、俺の中で引っ掛かったんやろう」
つくづく見聞きしたことをきちんと覚えている人だと感心する。
江神さんが僕の前でその素晴らしい推理力を披露したのはあの時が初めてという訳ではないけれど、それはこういう緻密な観察力に裏付けられているのだと改めて思い知った。この人の頭脳は、どんなに些細な事柄でも決して疎かにしない。名探偵ともなれば、かくあるべきなのだ。
「参りました」
僕がそう呟くと、江神さんは困ったような顔をした。
「たまたま当ってしもうただけや―――『カンや』て言うたやろ?」
さっきから弄んでいた飲みさしのグラスを空けた後、部長が小さく溜息した。
確かにこの件に関しては、こじつければ幾らでも反証が挙げられるだろう。しかし、今更そんなことをして何になると言うのだ。記憶をほじくり返し、理代との間にあったやり取りを全て部長に話したところで、結果が変わる訳ではない。とまれ、失恋は失恋のままだ。
残っていた酒を勢いよく呷った。途端に酔いが回ってくる。ずっと気になっていたことへ一応の理論付けがなされ、もう、頭を悩ませる必要はないと判って気が抜けたらしい。
所詮は一夏の恋だった。やがて甘酸っぱい思い出として重ねられていく種類のものとして認めるべきだと、己の理性が諭す。けれども、心はまだ、それを受け容れてくれそうにない。
なんだか涙が出てきそうだ。そんな顔を見られなくて、僕はそっと俯いた。
空になったグラスや皿を押しやり、テーブル上で両腕を組む。自分の頭をゆっくりとそこへ乗せる。
江神さんが手を伸ばし、僕の髪を無造作に掻き回した。大きな手は物言わぬ優しさを伝え、体内で波打つリズムと呼応する。そうして、昂ぶった意識は徐々に落ち着きを取り戻してゆく。いつの日かこの傷も癒されるだろうと強く確信した。
1988年の夏は、やがて僕の中で幕を閉じる。
蒸暑い夜の底が闇に千切れ、跡形もなく消えていった。(2001/5/5)
へ戻る
え、えーと、これって何の話なんだろ……
元々は「アリスの自棄酒に付き合うとしたら、江神さんでしょー♪」ということで考えたんですね。アリスもまだ、この時点では特に自覚(って何の・笑)ないだろうと思います。え? 江神さんの方ですか?? うーん、どうなんでしょう←オイコラ
しかし―――おかしいなぁ、"傷心のあまり江神さんに甘えまくるアリス"という当初の構図は、一体何処へ(滝汗) なんか大してヘコんでませんよねぇ(爆) ウチのアリスって、やっぱ図太いのかしらん???
尚、チャットにて貴重な意見を沢山くださった美沙子様、井上★律子様へ深く感謝いたします!! でも、それを全然活かせてないのが情けない〜〜〜(しくしくしく)
ところで、現在も長野−大阪間を走る特急に『しなの』がありますが、時刻表を確認したところほぼ全部が名古屋止まり。大阪まで行くのは日に僅か一本(!)なんです。しかし名古屋乗り換えとしてしまうと、モチにも下車の可能性が出でくるんですよね。だって、名古屋から先は新幹線使うしかないんだもの。江神さんとアリスはそうする他ないんですけど、紀伊半島の下方へ帰省するモチの場合、同じ位時間かかって料金はバカ高くなる新幹線利用より、名古屋から那智勝浦経由で帰る!って言い出すに違いない(断言) そうなると、余計な描写が増えて、字数も増える…ってな訳で、9時〜10時台に長野発大阪まで直通の『しなの』が存在する、ということにしてしまいました←実は結構、鉄ちゃん(笑)
まあ、原作は1988年の出来事。この部分はどうか見逃してやってください〜