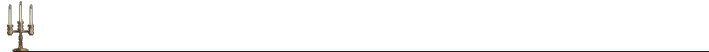心地よく秘密めいた場所
明け方、静かに覚醒した。
雨が降っているらしい。音はしていないものの、ただ気配だけが其処にある。
暗い部屋の中で目を開けた。何度も見たことのある天井が視界いっぱいに拡がる。
今は、何時だろう。
枕元に置いてある筈の時計を求め、そうっと視線を動かした。秒針の動く音だけが、しんとした室内へ降りてくる。
だが、どんなに一所懸命、目を凝らしてみても、求めるものは見当たらない。僕はすぐ傍らで眠るひとを起こさないよう、注意深く頭を傾けた。
時計の姿は依然として行方不明のままだった。
諦めて、瞼を閉じた。暖かい毛布にすっぽりと包まれた身体は軽い疲労からくる心地よさを伴い、僕を再び睡魔の棲み家へ連れ帰ろうとしている。
窓の向こうはまだ暗いようだ。もう一度、眠ることにする。
幸福感に満たされた意識が宵闇を彷徨い始め、僕は、あっという間に眠りの底へ落ち込む筈だったのだが・・・朝、起きた時、どんな顔をすればいいのだろう。
自分がしたことを考えると、顔から火が出そうなくらい、恥ずかしい。
昨夜はどうかしていた―――そう、僕も部長も。一言でいうなら「飲み過ぎた」ということに尽きるだろう。やけに調子よく、次々とグラスを空けたような気がする。休みの前日だから、と言い訳するのも莫迦莫迦しいくらい、皆して飲み、食べ、騒いだ。
望月がクイーン礼賛をとうとうと演説しながら水割りを流し込む脇で、織田がチューハイのお代わりを頼む。マリアは時々鋭いツッコミを入れつつ、手にしたグラスの中身を空にする。別に普段と変わらない飲み会の光景なのだが、ペースがいけない。何かに取り憑かれたような勢いだと感じたのは一瞬で、結局、僕も自分の分を追加オーダーしてもらう。それは、江神さんも例外ではなく―――誰も彼もが、極限まで飲んだくれた。
今考えると、よくあの状態でちゃんと会計できたものだと思う。
それでも、ここ、西陣の江神さんの下宿へ辿りつくまでは、僕にもまだ、理性が一欠片残っていた。靴を脱いだ僕が、よたよたと廊下に上がりこんだのを確認してから、江神さんはきちんと玄関の戸締りをした。覚束ない足取りで廊下を歩く間中、僕の身体はしっかりした腕に助けられた。部屋の鍵を開ける時も、部長は僕を抱きかかえるように支えてくれていた。
「着いたぞ―――水、飲むか?」
部屋へ入った途端、一番近くの壁に凭れ蹲ってしまった僕の耳元へ、江神さんがいつもより低めの声で囁いた。大騒ぎした酒宴の後だけに、咽喉は大旱魃へ遭遇したかのような渇き具合である。僕はコクコクと首を縦に振った。
江神さんは冷蔵庫を開けて何かやっていたようだったが、やがてコップを持って戻って来ると、僕の手へそれをしっかり握らせ、更に上から自分の掌を重ねた。その状態でグラスを口許へ運ばれ、僕はよく冷えたミネラルウォーターを嚥下した。正体不明になる一歩手前の状態を見かねてのことだったのだろう。確かに、江神さんの手で導いてもらわなかったら、コップの中の液体を自力で飲めたかどうか怪しいものである。
冷たい感触が体内を下へ下へと降りていくのをはっきり感じた。それと同時に、僕の中で何かが吹っ飛んだ。
両腕をスッと伸ばし、僕は部長に抱きついた。そのまま、彼の右肩へ顔を埋める。軽くウェーブした長髪から、微かにキャビンの香りがする。
「・・・ア、リス?」
困惑したような声が放たれ、僕の意識の中をぐるぐると回る。にも拘わらず、僕の脳は次に言われるであろう言葉を奇妙な冷静さで検証し始めていた。
―――大丈夫か?
とか、
―――気持ち、悪いんか?
とか。
―――吐くんやったら、盥(たらい)持ってくるから・・・もう少し我慢せえ。ええな?
どれもこれも、過去、したたかに酔っ払って江神さんの下宿へ転がり込んだ折、何度か言われたことのある科白だった。所詮酔っ払いのやることに脈絡なんかないのだから、まず、具合の良し悪しや吐き気の有無を確認するのが普通だ。僕は江神さんにしがみついたまま、そういった種類の問い掛けが己へなされるのを待った。
だが、江神さんは何も言わなかった。僕の上半身へゆるりと手を回し、黙って背中を撫でてくれた。
甘えるような僕の行動が指し示す感情の正体を彼は判っていたのかもしれない。柔らかく弧を描くような仕草が、僕の体内へじんわり沁みこんでくる。
どれぐらい、そうしていたのだろうか。
江神さんの身体から伝わってくる体温と、僕の中で燻っている熱と。過ごした酒量の引き連れてくる高揚感があまりに気持ちよくて、このまま夢の中へと引き摺り込まれそうだったが、それではこうしている意味がない。僕は重い頭をなんとか持ち上げた。
すぐ近くにある江神さんの瞳が揺れる。
「大分、酔うたようやな」
そう言う、彼の吐く息も酒臭い。
「少しは落ち着いたか」
首筋へ回した両腕を緩めて、自分の背を少しのけぞらせた僕は、正面から江神さんの顔を見つめた。
「江神さん」
ゆっくりと部長の名前を呼んだ。呼ばれた人は、僕の腕を双肩へ乗せたまま、首を少し傾げる。その仕草と表情が、僕の胸をドキドキと高鳴らせる。
「何や」
ふわりと笑う顔があまりにも艶っぽくて、僕の心臓は止まりそうになる。それは摂取過多なアルコール分が引き起こす幻想のせいだけではないだろう。二枚目の部長は、普通にしてても充分男前なのだけど、こんなのはズルい。酔いが回っているせいか、目元がほんの少しとろんとして、それがたまらなく色っぽい。
ああ、なんでこの人は、こんなにカッコええんやろう―――つい、その顔へ見惚れてしまっていた僕を江神さんの柔らかい声音が引き戻した。
「何や、言いたいことあるなら、言うてみ。ちゃんと、聞いたるから」
そこまで言われて、僕の理性は完全に蒸発した。
「―――ずっと前から、部長、が・・・好き、です」
声がみっともなく掠れる。一世一代の告白もまともに出来ない自分が、情けないやら恥ずかしいやら。江神さんは悪戯っぽく微笑むと、
「俺も、アリスのことは好きやで。まぁ、比較する訳やないけど、部員の中ではダントツや」
と言ってくれた。
同じサークルの、仲の良い先輩と後輩。多少の義理は果たさなければならないにしても、いけ好かない相手なら付き合わないでやっていける大学生活だからこそ、友人や部活の先輩後輩という『仲間』は自分が好意を持てる相手ばかりだ。だけど、僕が彼に抱いている感情はそういものじゃない。
僕は、じっと部長の目を見つめた。
「江神さん―――僕は、真面目に告白しとるんです」
「せやから、俺も真面目に答えとる」
しれっと言ってのける部長に、軽い苛立ちを覚える。この、剛胆ともいえる落ち着きと明晰な頭脳を持ち合わせた彼の本心を知るのが怖くて、僕は可愛い後輩の位置からはみ出さないよう、ずっと気をつけてきた。江神さんが僕に優しくしてくれる度、自意識過剰になりたがる己を懸命に諌めてきた。
だが、もう限界だ。答えが欲しい。
思いきって顔を近づけると、僕は江神さんの唇へ口付けた。そうっと自分の唇を押し当ててすぐに離れた僕の視界に、瞠目した部長の表情が飛び込んできた。江神さんの目が微かに眇められる。「参ったな」という小さな呟きがその口から漏れたのを聞きつけた瞬間、僕の心は凍りついた。
やりすぎたのかもしれない。江神さんが僕に示す優しさは、本当にただの後輩もとい弟分へ向けられる種類のものなのでは・・・と思ったら青くなった。血の気がサーッと引いていくのを体感した。
普通に考えれば、それが当り前だ。男同士、誰がそんなことを想像するもんか。でも、好きになってしまったのだからしょうがない。江神さんのことが本当に好きなんだから、どうしようもない。
いざとなったら、酔った挙句のご乱心ということで誤魔化すしかないだろう―――慌てて目を逸らし、そう考えたのだけど。
「アリス」
僕を呼ぶ、いつもの優しい声が耳元で響いた。
「・・・ええのか?」
言葉の意味を計りかねて視線を戻した僕は、江神さんの中にある感情をしっかりと捉えた。それは、僕の想いと同一のものだと―――その時は、確信したのだが。
はい、と返事をした途端、僕の唇は江神さんに塞がれた。軽く閉じていた上唇と下唇を長い舌でそっと割られる。深く濃厚な口付けが僕の身体の奥を更に熱くした。
部屋の片隅へ腰を下ろしたまま、抱き合い、何度も口内を貪った。もう、これ以上待ちきれないといわんばかりの性急さで何かに突き動かされる如く、互いを絡め合うかのような接吻が繰り返され、僕たちの隠し持っていた情欲へ火を点けた。江神さんの指が、唇が、だんだん下へと降りてくる。自分の着ているシャツのボタンが、一つ一つ丁寧に外されてゆくのを僕は溶けてしまいそうな脳味噌の片隅で見ていた。身体から剥ぎ取られた二人分の衣服をまとめて脇へどけると、江神さんは僕を一組しか用意していない寝具の上へゆっくりと組み敷いた。
これからすることへ対し、全く恐怖心がないと言えば嘘になる。というより、冷静に考えたなら、やはり怖い。一応、話に聞いて知っているつもりだけど、一体全体、どんなことになるのか、皆目見当はつかないでいる。
僕の不安を感じ取ったらしい江神さんが、上から柔らかく微笑んだ。
「怖いか」
「・・・はい、少し」
そっと口付けられた。優しく、確かめるように、江神さんの舌が僕の唇の上を這い回る。幾度となく繰り返されるキスに、僕の緊張が少しづつ解されてゆく。
彼は僕に対して、いつでもひどく優しい。その優しさが今、具体的な『愛撫』という行為を伴って、直裁に伝わってくる。それが僕の全てを溶かしてしまいそうになる。時折、耳元で「大丈夫か」と囁かれるその声にすら反応し、気持ちが奇妙に昂ぶってゆく自分を持て余すことしか叶わなくなる。初めて触れ合い、重ねる肌の熱さが、僕の意識を戸惑いと至福の中へ置き去りにしていった。
どこかで、小鳥の囀る声がする。厚みのあるカーテンの向こうでは、既に陽の光が濡れた路面を暖めているようだ。夜の間中、暗がりと同居していた湿り気が室内から綺麗に拭われているのを感じ取った僕は、漸く目を開けた。即座に江神さんの方へ向き直ることができないで、そのまま天井と対面する。
思い出すだに、恥ずかしい。いくら酒の力があったとはいえ、僕は自分から部長へ襲いかかったのだ。
一応、想いを遂げることは出来たけれど、あれは勢いに流されただけだとも考えられる。僕はまだ、江神さんから答えを貰っていない。だけど、それをもう一度訊くのは―――酔いが醒めた今、怖くてとても出来やしない。
「アリス」
突然呼ばれて、僕は反射的に江神さんの寝ていた方へ顔を振り向けた。部長は、軽く片肘をついて上体を起こしている。心の準備が全く出来ていない僕は、やや高い位置から視線を注がれていることに気づいて、すっかりうろたえてしまった。
慌てて、おはようございますと言った僕をいつもの笑顔が迎えてくれた。
「おはよう―――身体、大丈夫か」
そっと腰を浮かせてみるが、然程痛みは感じられない。
「・・・はい・・・大丈夫・・・やと、思います・・・」
おずおずと答える僕を少し心配そうに見ていた江神さんが、ホッと息を吐いた。しかし、すぐに考え込むような難しい表情を纏った彼の様子を目にするなり、僕の心臓は壊れそうな勢いで心拍を刻み始めた。
「なあ、アリス。昨夜のことやけど・・・」
息の根が止まりそうだった。
「・・・えらい酔ってたし、勢いみたいなもんで・・・その、アリスに・・・してもうて・・・」
すまん、というように頭を下げられてしまった。
それでは、やはり数時間前のことは一夜の幻だったのか。シラフで迫ったりしていたら、完全に拒絶されていたということか。
とんでもないことをしでかしてしまったという激しい後悔に襲われる。
「そんな、謝らんでください。酔っ払ってしたことですから」と、普通に―――自分は平気だという顔を装って言えるだろうか。いいや、よく考えたら、あんな行為をしておいて『気にしてない』というのは不自然かもしれない。この場合、ストレートの男としては、どういう心理状態が一般的なのか。混乱した脳は何一つ解答を捻り出せないでいる。
頭の中で盛大なパニックを起こしている僕に構わず、江神さんは言葉を続けた。
「本当は、俺の方から言おうと思うてた・・・」
僕は自分の耳を疑った。今、このひとは、なんて言った―――?
「・・・え?」
やっとのことで、疑問符つきの短い一音を咽喉から絞り出した。江神さんは神妙な顔をしている。軽く瞬きすると、彼はゆっくり話しだした。
「ずっと、アリスのことは想っとった・・・けど、自信、無かったんや。その・・・好かれとるのは判っておったけど―――それは・・・一般的に考えたら、先輩としてのことやろ。それ以上のものを求めるのは、俺の我儘やろか、思うて・・・な」
ああ、こんなことがあっていいのだろうか。
全く同じ事を幾度も考えた自分に笑い出しそうになるのを堪えようとして、僕は思いっきり首を左右に振った。突然、口が利けなくなった子供の如く、殊更に大仰なジェスチャーで意志表示する僕を前にした部長は、やっと表情を緩め、いつものように微笑んだ。
「けど、そう思うてもええみたいやな」
今度は力いっぱい上下運動し始めた僕の顔を江神さんが覗き込んだ。意を決したような瞳に射抜かれる。
「アリスの方から、言わせてしもうて―――かんにんな」
「そ、そんなことっ・・・」
思わず目を伏せてしまう。あまりに幸せ過ぎるこの展開が、もう、とめどなく頬を緩ませている。激情の赴くままに起こした行動だったが、禍転じて福と為すとは正にこのことだろう。だらしなくニヤけた顔を見られたくないばかりに俯くと、ついさっきまで胸中を去来していた懸念が口をついて出た。
「酔うた結果の間違いや、もう二度とせえへん―――言われるのかと・・・」
もごもごと口篭もった僕の後頭部へ江神さんが長い指を伸ばし、引き寄せた。そのまま彼の暖かい腕の中へ自分が抱き込まれてゆくのをなんともいえない心地よさのうちに体験する。
「なんで、そないな勿体無いこと、言わなあかんのや」
至近距離でそう囁かれて、僕の心臓は再び激しく走り始める。この、早鐘のような鼓動が伝わってしまいそうで、非常に恥ずかしいのだが、それでも僕は己の上体をぴたりと江神さんに擦り付けた。
柔らかいキスを貰う。軽く唇に触れた後で、江神さんははっきりこう言ってくれた。
「アリスが、好きや」
僕は泣きそうになりながら、何度も何度も頷く。
「これからも、ずっと、傍におってな」
「はい」
短い返事に込めた僕の想いは、もはや溢れ出す寸前だった。たまらなくなって、自分から唇を合わせる。
するりと入り込んできた舌が僕の口内を弄るように動く。より深い口付けに背筋がぞくりと震え、肌が粟立つ。収まった筈の官能が目を覚まし、どこか体内の奥の方で熱い何かが分泌されているような気がした。眩暈がする。
漸く唇を離すと、互いの身体を固く固く抱きしめた。このひとの持つ温もりさえもが愛しくて、より強くしがみつく。そんな僕の耳元や首筋に、江神さんが触れるか触れないかの淡いキスを時折落してくれる。
あと少し、こうしていようと、二人して毛布の中へ潜り込む。
やっと手に入れた、心地よく秘密めいた場所。
長いこと想い続けていたひとの中へ触れることが許された朝。
とろけてしまいそうな幸福は、現実のものなのだ。
暫くの間、互いの感触を愉しんだなら、今度こそ起き上がろう。そして、いつかそうしたように、土曜日の河原町へ二人して出掛けてゆくのもいいだろう。
暖かい懐に抱かれたまま、僕はうっとりと目を瞑った。(2000/6/12)
へ戻る
ごめんなさいーーー!!! この二人の初夜っていうと、"はずみ"というシチュエーションしか思い浮かばない私(大爆笑)
ベロベロに酔っ払ってのアリス襲い受ですね〜 本当は江神さんの下宿に辿りつくまでの攻防(?)もあったのですが、長くなるので削りました←結局、短い話が書けない(T_T)
時期としては、やっぱり『双頭の悪魔』後だと思うんですよね。もしくは『月光ゲーム』の後、暫くしてからか…でも、そうするとマリア入部前にデキてしまったことになるので、私としては前者でいきたいと思っています←オイコラ
なんていうのか、江神さんとアリスって、書いてて本当に楽しいんですよ。するすると筆が滑っていくので、嬉しい限りです。でも、この状態がいつまで続いてくれるか、謎なのですが。
ところで、今回もちょっとだけ信長&モチ&マリアを入れましたが、ちゃんと彼らが出てくる話を早く書きたいと思う今日この頃です。しかし、どうやっても、ギャグノリ→ド阿保話(笑)になりそーな予感がして、密かに怖い……
そして―――タイトルはモチにあやかって、クイーン作品より拝借いたしました←なんでやねん(By 望月周平)