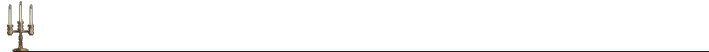あの夏、いちばん静かな海。
照りつける南国の太陽が上空より光線を放つ。抜けるような空の青さは暑さをより増すだけで、気持ちを少しも軽くしてくれぬままだ。煌く上天気とは裏腹に、僕の心は果てしなく鬱屈とし、疲弊していた。
空港の待合室に入ってもなぜか身体の中は熱く、よく効いている筈の冷房がろくに感じられない。
搭乗手続きを済ませた後、江神さんは僕へ荷物番を頼むと、電話をかけに行ってしまった。
出発まであと30分以上もある。何もすることのない僕は、読み止しのパット・マガーを開く気にもなれず(栞を外してしまったので最初からざっと辿らなければどこまで読んだか思い出せないだろう)ぼんやり外を眺めていた。
何か楽しいことを頭の中へ思い描こうとしてみたが、やはり無理だった。どうしても思考がある一つの方角へ向かってしまう。僕はずっと、昨日まで隣にいた同級生のことを考え、その心に負った傷の深さを憂えた。
嘉敷島へ外界からの船がやって来たのは、予定されていた通りの日―――8月7日のことだった。
無線機が壊されず即時に警察へ通報出来ていれば、少なくとも4日の午後には科学捜査の介入が叶ったことだろう。そうすれば平川至と有馬和人の死は避けられたのかもしれない。
だが、犯人は容赦しなかった。
三年前に婚約者を奪われた薄幸の女性は、自分を止められず、復讐の引き金を引き続けた。そして全てを達成し、遂に自らの命を絶ってしまった。血のつながりは無いとはいえ、信じていた従姉妹が一連の犯行を決したのだと知ったマリアの心中は如何なものかと思うとやるせない。愛する人を失い、狂気の淵に立たされた礼子を知るマリアは、従姉妹が幸せでいられることを切実に願っていたことだろう。けれども、礼子自身はそれを望んでいなかった。
結果的に実の息子達と気に入りの養女を失った有馬竜一の気持ちともなれば、更に複雑なことだろうと思う。
優秀な兄への劣等感に苛まれ続ける愚息が剥いた突然の牙。
其処から派生してしまった、憎悪の連鎖と悲劇の再生産。
それが、まさかこんな、痛ましい結果になろうとは。
誰も彼もが疲れ果て、島を離れたがっていた。しかし、五日ぶりに嘉敷島を目指してきた連絡船からの驚くべき通報を受けて警察船が同日午後遅くにやって来てから後、僕たちは引き続き島内へ留め置かれたのである。既に犯人も判明し、その生命反応が失われているのだから、捜査は簡単に済むだろうと思っていた僕の読みは完全に外れてしまった。
日が明けた8日の早朝には巡視船らしき影が船着場に現れ、鑑識や捜査員達が小さな島へ一小隊となって乗り込んできた。死者達の身体は運び去られたが、生き残った一同は望楼荘のホールで多くの時間を費やした。別に、法的権力で拘束されていた訳ではない。だが、時として一人づつ事情聴取を受ける為に席を外す他は何事をするのも憚られると皆が感じているようだった。
島中のありとあらゆる処から指紋が採取され、証拠品が徹底的に洗われた。そうして事件の全貌を裏付けるのに、丸二日を要した。
9日の夕方、やっと僕たちは全員、警察の船で奄美大島へ移された。名瀬市内のビジネスホテルは警察側で手配してくれたらしく、各々シングルルームをあてがわれた。
枕が変わって漸く、僕の身体はぐっすり眠ることが出来た。ただしそれは肉体的に於いてだけであり、心はとても安らぐどころでは無かったが。
翌日―――つまり今日のことだ―――嘉敷島で過ごした面々の中では部外者ともいえる江神さんと僕は、朝一番で警察に呼ばれ、供述書にサインした後、全面釈放された。その直後、僕たちは航空会社の予約カウンターへ連絡し、三日前に乗る筈だった便からの予約変更を手続きした。といっても、一切は江神さんがやってくれて、僕はただ隣にいただけだった。
名瀬署からホテルに戻り、荷物をピックアップする。午前便の席が取れたので、一足先に帰らせていただく旨を他の人々に伝えた。
竜一とその異母弟の犬飼敏之がロビーまで降りてきて、一同を代表し見送ってくれた。園部医師へは僕たちと入れ違いに警察からの出頭命令が下ったらしい。牧原純二、里美、そしてマリアの三人は部屋へ篭ったままだという。
一目マリアの顔を見たいと思ったが、彼女が下りてくる気配は無かった。無理もない。僕たちはギリギリ時間いっぱいまで粘ったけれど、結局マリアには会えぬまま、ホテルの玄関からタクシーへ乗り込んだ。
空港へ向かう車中では、二人とも始終無言だった。口を開いたら最後、事件についてしか話せないような気がして、僕は唇を噛み続けた。江神さんも黙したまま、ずっと窓外の風景に目をやっているようだった。
名瀬市内を抜け、山の緑に包まれながら、車は58号線をひた走る。龍郷湾に突き当たると右へ曲がった。その分岐点を逆に左折して15分ほど走れば、この町に流されていた西郷隆盛の住居跡がある筈だ。
昔、隕石によって出来たといわれる奄美クレーターが左手に望める赤尾木まで来ると、車は再び右折した。島内で一番幅の狭いこの場所は両側を太平洋と東シナ海に面している唯一の町である。そこから先は左手に山や畑を、右手には太平洋を眺めた。
やがて、遠目に銀色の滑走路が見えてきた。ぐんぐん近づいてくる空港ビルディングの縁が光線のように輝いて、目に眩しく映ったのはつい先刻のことだった。
僕は軽く伸びをすると、周囲をざっと見渡した。午前中ということもあってか、空港内はそれほど混んでいないようである。普通に考えたら観光でこの島へやって来る人間が殆どだろうから、午後便で帰る人数の方が多いに違いない。
腕時計で時刻を確認する。長針はⅣの位置をまわろうとしており、既に搭乗案内が始まっていた。
奄美空港から伊丹までは約1時間50分の空の旅だ。そろそろボーディングブリッジに向かった方がいいのでは・・・と思った矢先、江神さんが戻ってきた。
いつもと変わらぬ様子で、部長が荷物をひょいと持ち上げた。
「すまん、待たせてしもうたな―――行こか」
僕は無言で頷き、長身の背中に従う。機内へ入ってみると、結構空席が目立った。
午前11時35分。
僕たちを乗せたJAS 560便は、定刻通りに浪速の空へ向けて飛び立った。伊丹空港の到着ロビーは多くの人々でごった返していた。
夏休みも真っ最中なので当然の現象なのだが、ここ数日間、人垣に揉まれることのない生活をしていたせいか、勝手が狂ってしまう。少し気をつければ避けられた筈の肩にぶつかり、よろめいた僕の体勢を江神さんの強い腕力が瞬時に立て直してくれた。部長はそのまま僕の身体を引っ張っていき、壁際で一息ついた。
「アリス、しっかりせぇや」
「は、はい、すいません・・・」
恥ずかしさのあまり、僕は俯いた。
ああ、情けない。疲れているのは、彼も同じだろうに。
いたたまれないながらも、そろそろと視線を上げた。そこには江神さんの困ったような顔があった。
「一人で帰れるか?」
どうやら、僕の様子はかなり危ないらしい。気持ち的には心許なかったのだが、さすがに江神さんへ余計な労をかけてはいけないと思い、「大丈夫です」と言った。
「少し、フラついただけですから・・・もう、平気です、ちゃんと帰れます」
部長は訝しげにこちらを見ながらも、ポツポツと言葉を重ねる。
「なんや、えらく疲れているようやから、ほんまは送っていきたいんやけど・・・京都で待っとる連中のこと考えると、あまり遅なっても悪いしなあ」
その科白を聞いて、僕は夏休み前に取り決めした、とある約束のことを思い出した。
「待ってるって・・・まさか―――信長さんとモチさん、ですか?」
部長は少々大袈裟な仕草でそれを首肯してくれた。
―――ああ、やっぱり。
本来、江神さんと僕は、7日の午後便で伊丹へ戻って来る筈だった。宝捜しが成功したかどうかを夏休みが終わるまで知らずにいるのは耐えられないと望月・織田両人が主張した為、7日の夕刻に大阪市内で落ち合い、結果報告がてら夕食(というより飲み会になるだろう)を共にするという段取りになっていたのである。
尤も、嘉敷島に一般架設電話はない。だから、連絡船へ備え付けられている船舶電話を通じて初めて、僕たちは親族や知人に一報を入れることが叶った。銘々が、予定の日に帰れなくなった事情を相手へ説明していた。
その時、江神さんは織田の実家へ電話した。教習所通いの望月に比べたら織田の方が捕まりやすいだろうと踏んだ部長の思惑通り、後輩はすぐ電話口へ出てきたらしい。江神さんは言葉少なに島を出るのが何日か遅れる旨を告げ、望月にもそれを伝えてくれるよう、頼んだ。
「昨日、ホテルに着いてから下宿に電話したんや。そしたら、大家さんのところに信長から電話があったって聞いてな・・・」
江神さんが京都に戻ったら、即座に各人の下宿へ連絡してほしいとの伝言を託(ことづか)っていたそうである。
「あいつら、9日には揃って下宿に戻っておったらしい。俺がいつ京都に帰ってもすぐ連絡がつくようにと考えたんやろ」
そうまでして、パズル解読の結果を知りたかったのだろうか。呆れたような表情になっているであろう僕の顔を見て、江神さんは一瞬苦笑したが、すぐ真顔になった。
「ホテルのロビーで見た時には、どこの新聞にも事件のことが載っとった。全国紙は一通り扱ったみたいやな。小さな記事ばかりやったが、『嘉敷島』と『有馬』という単語から、信長やモチが気がつくのは時間の問題や」
確かに、充分考えられることではあった。掲載されていた場所が地方面ではなく23面だったことを僕も記憶している。あの島の事件は、日本全国に配られるどの新聞にも印刷されたのだ。
「記事自体は被害者と加害者の名前が記されていただけで、詳しいことは何一つ述べられておらん。事件そのものが未解決という訳ではないから、警察側は事実だけの会見を行ったんやと思う」
礼子が自殺というかたちで罪を償ったということも考慮に入れ、やや複雑な有馬家の内情を暴かずに済ませたのだろう。それに、その辺りを詳しく発表したら、事は三年前の事件へ飛び火する。そうなれば有馬英人の死を事故として片付けた警察側の落ち度も、取り沙汰されかねなかった。然るにそれを避けようという計算もあったに違いない。
「事件のことやパズルの結果についても多少は聞きたいんやろうが、モチも信長も、マリアのことを心配してる。日を置いて、俺の方が話し辛くなる前に話してやった方がええと思うてな、奄美空港から二人の下宿に電話してきたんや」
それで、部長は長いこと電話をかけていたのだと、僕は漸く得心がいった。
「まぁ、またもや、いろいろご苦労さんな夏になってしもうたなあ。アリスも、早う帰って・・・」
「いえ、僕も京都へ行きます!」
強引に江神さんの科白を遮った僕を見て、部長は驚いたようだった。
「・・・けど、疲れてるんやないのか? 結果報告くらい、俺一人で充分やろ」
「疲れてるのはお互い様やないですか。僕かて、あの場所にいたんですから、説明する責任はありますよ」
「責任―――て、オーバーやなあ。別に、あったことを話すだけやないか」
江神さんが不思議そうに目を眇める。僕は、言葉に詰まってしまった。
一体、どう説明したらいいのだろう―――
僕はどうしても、事件の語り部という責を部長一人に負わせたくなかった。
このひとは、今回もその明晰な頭脳を悲劇的な事件の解明に使った。検証用に借り出された僕の頭は、結局、その推理を裏付けるばかりで、彼の走らせた馬を止められずに終わった。尤も、江神さんの組みたてたストーリーは真実に即していたのだから、僕がいくら屁理屈を並べたところでそれを撥ね返せた筈もないのだが。
自身で解き明かした事柄を礼子へ淡々と告げた時の、江神さんの悲しみに満ちた声が僕の耳へこびりつき、離れない。彼女がしたことの是非はともかく、流した涙の量や受けた地獄の如き責苦をつぶさに知る前から、こういう結果にしかならなかったことをこのひとは判っていた。
あの事件は、僕たちが島へ行こうが行くまいが、起こっていたかもしれない性質のものだった。たまたま居合せてしまった者達が不運だったというだけだ。
尾張と紀伊の空の下でそれぞれ気を揉んでいた二人が南の楽園で起きた惨劇の内容を知りたがる気持ちもまた、よく判る。大学が始まればマリアと顔を合わせるのだから、事前に真実を知っておいた方がいい。好奇心にかられてというより彼女を不用意に傷つけない為の配慮から、彼等がそう思ったに違いないことは、僕にも察せられた。
だからといって、それを江神さん一人にやってもらうのは、気が引けた。何も知らない望月と織田を前にして、あの悪夢のような日々を再構築するという『辛い役目』を彼だけに負わせるのは―――絶対、嫌だ。
「とにかく、僕も行きます」
懸命に言い募った。先程までの生気の無さが嘘のようだ。
とはいえ、僕が出向いたところで、然程役立つこともあるまい。おそらく、説明は部長がするだろう。パズルを解いたのも諸々の証拠から犯人を割り出したのも、全て彼が成し遂げたことなのだから、その方が自然だ。
それでも、僕は部長の傍にいたかった。今ここで、自分が一人になりたくないという思いも確かにあったけれど、彼だけを証言台に立たせるようなことは、何が何でもしたくない。
江神さんはなおもこちらの体調や気分を気遣ってくれているようだが、しつこく「行きます」と繰り返す。遂に、淡い微笑が僕へ向けられた。
「ほんまに大丈夫やな? なら、京都まで戻るか」
僕は強く頷いた。
人波を掻き分け、やっとの思いで、空港ビルの外に出た。そのまま、すたすたとバス停に向かって歩き出した僕の背に、江神さんが今一度声をかけた。
「ところでアリス、荷物はどうするんや? それ全部持って来たら、邪魔やろう」
「―――京都駅についたらロッカーにでも放り込みますよ。はよ、行きましょう。新大阪行きのバス、出てしまいます」
いつになく行動的になっている僕の肩を、部長はポンと叩いてくれた。新大阪でリムジンバスを降りた江神さんと僕は、手分けして望月と織田へ電話した。集合場所は江神さんの下宿である。こちらが到着する時間よりやや遅れて彼等がやって来られるよう、待ち合わせ時間を定めた。JRの快速に乗り継いだ僕たちが京都駅へ降り立ったのは午後3時少し前だった。
駅を烏丸方面へ出るとすぐ、僕はロッカーに大荷物を放り込み、身軽になった。地下鉄へ乗り換え、今出川駅で降りる。地上へ這い出た僕たちは、いったん英都大学を背にして立ったが、即座に西の方角へ進路を採った。
灼熱の如き照射と向かい合いながら、二人して肩を並べ、のろのろ歩いた。アスファルトから目に見えぬ湯気が発散し、この身を苛つかせるほどにまとわりついてくる。
だが、これくらいで音をあげてもいられない。この後、クーラーの無い六畳間へ大の男四人が詰めるのである。何分、外で話せる内容ではないのだから仕方ないとはいえ、考えただけで眩暈がしそうだった。
頭上で輝く太陽は、きっと嘉敷島と奄美大島へも厳しい暑さを投げかけていることだろう。あの、過ぎた日々を回想するのに、程よく冷えた心地よい空間は似合わない。空調の効いていた車中やビルの中へ多大な未練を感じながらも、僕はそれらを男らしくすっぱり諦めることにした。閉め切っていた窓を開け、部屋の空気を江神さんが入れ替える。失礼して、先に手と顔を洗わせて貰った。扇風機のスイッチを入れてからやってきた江神さんに洗面台を譲ると、僕は途中のコンビニで買ってきた飲物類を勝手に冷蔵庫へ収め始めた。
「全部、入れてくれたんか・・・すまんな」
頭上から、江神さんの声が降ってきた。顔を上げると、さっぱりした笑顔があった。長い髪の一部が濡れて露を含み、やがてポタリと僕の上に落ちてきた。
程なく望月が―――続いて織田も到着し、マリアを除くEMCフルメンバーが顔を揃えた。
「暑うて、かなわん」「ほんまや」と口々にこぼした居残り組の二人は僕たちの顔を交互に見遣った後、いつになく真面目な面持ちで、「江神さんもアリスも―――お疲れさまでした」と労ってくれた。
たった今、冷蔵庫に入れたばかりのウーロン茶や缶コーヒーを取り出し、銘々に配ると、江神さんはさっさと事件の話を始めた。織田も望月も神妙な顔をし、無言で聞き入っている。僕は江神さんのやや後手に座り、発言者の言葉を一言も洩らさまいと懸命に記録を取る書記のような心境になっていた。
斜め前方の顔は、如何なる感情をも遮断しているかのようだった。静かで綺麗な口の動きが、悲惨な出来事の一つ一つを詳らかにしていった。時々、僅かに辛そうな影が表面に浮かび上がってくるようにも思ったが、それは彼の話す内容を前もって知っている僕の目にだけ、そう映るのかもしれない。
江神さんは事件が起こった順に沿って、話を進めていった。南の島へ集っていた皆の上に突如として降りかかってきた災難が、蒸し暑い西陣の一角に再現された。
水平線の彼方に浮かんでいた黒い影が台風となったその時、既に小さな孤島は大いなる不吉なものに取り囲まれていたのだ。時を同じくして、バカンスを楽しんでいた人々は暫し亜空間へと落ち込み、閉じ込められることとなった。幸い台風の方は進路をやや変え、島の南百キロを通過していったが、僕たちの前に残されたのは五人の亡骸とやりきれない結末であった。
江神さんが語り終わっても、二人の先輩達は押し黙ったままだった。扇風機はその羽を狂ったように回し、室内へ篭ったままの熱気を懸命に散らそうとしている。街の奏でる喧騒が網戸越しに時折忍び込んできても、誰一人、そんなことを気に止めはしない。ただならぬ静けさだけが放心したように辺り一帯を占めていた。
暫くしてやっと、織田が口を開いた。
「マリア・・・可哀想に―――大丈夫やろか・・・」
呟いた言葉は祈りのようにも聞こえた。遠い空の下にいる彼女にそれが届くことを僕は心から願った。
江神さんの方を盗み見ると、目を閉じていた。役目を終えた彼の全身から、今まであまり感じられなかった疲労の色が滲み出ているように思えた。
望月は悲しげに頭を振り、
「とんでもない事件やな・・・南の島のホリデーが台無しやないか・・・江神さんやアリスも、二年続けて殺人事件に遭遇する夏休みになるとは、思うてへんかったやろう」
と、やや忌々しげな声で感想を述べる。
全く、その通りだ。去年の夏合宿でも散々な目に遭ったが、今年も負けず劣らずの凄まじい展開となった。
「それで・・・パズルも事件も全部、江神さんが、解いたんですか?」
エラリー・クイーンマニアの彼から発せられた質問に、部長は答えようとしない。望月の視線がこちらを向いたので、僕は口許を引き結んだまま肯定した。
「そう。やっぱりなぁ―――けど、事件が解決して、マリアにとっては良かったんやないのか」
少し強い口調でそう言い切った望月の顔を、僕は、まじまじと見つめた。
「だって、そうやろう? 事件が解決せんで、すっきりしないまま誰も彼をも疑って島を離れるよりは、江神さんに謎を解いてもらった方が、よっぽどええやないか」
確かにそれはそうだ。しかし、今のマリアがそういう風に捉えられるかどうか、甚だ疑問である。
僕の疑心を代弁するが如く、織田がキッパリ言い返した。
「モチよ、理屈ではそうかもしれんけどな・・・マリアの気持ち考えたら、そないに言わん方がええんやないか? こういう言い方はしとうないけど、その―――江神さんの推理によって、従姉妹へ引導渡されたと感じているかもしれへんやろ」
その一言に反応した江神さんが、薄く目を開ける。
「もう、やめよう―――この話は、終わってしまったことなんや」
悲痛な声だった。
仮に連絡船が来る以前に江神さんが真実へ到達出来なかったとしても、日本の優秀な警察は島中を調べ上げ、犯人を割り出したに違いない。だが、もしそうなっていたら、生きた礼子に手錠が掛けられるという結果を残った者は受け入れねばならぬ。どちらがより残酷な幕切れなのか、僕には判らない。
皆して口を閉ざす。まるで、熱砂の上へ寝転がっている貝のように、僕たちは身動き一つしなかった。午後も5時近くまでそうしていたのだが、その後は四人揃って、近場の喫茶店へ移動した。冷房がガンガン効いている店内で、申し訳程度に飲み物を注文する。アイスコーヒーやグレープフルーツジュースを時々ストローで吸い上げながら、望月の『教習所奮戦記』に皆して耳を傾け、ツッコみ、笑い転げた。こういう話題なら、どこで喋っていても問題はない。
一時間以上、気違いの如く騒いで、それから木屋町付近の居酒屋へなだれこんだ。お次は織田先生の『名古屋に於ける結婚式講座』を拝聴することとなった。
何しろ"嫁取り"がドラマになるような地域である。結婚についての様々なしきたりや決め事を織田は殊更に面白可笑しく話した。多少の酒が回って、僕たちは火がついたようにはしゃぎ続けた。
皆がミステリについての話題を避けたこともあり(そんなものを持ち出したら、何かの拍子に話題が嘉敷島での事件へ流れていきそうで怖かったのだ)8時過ぎにはお開きになった。この時間ならまだ間に合うので、望月も織田も一旦下宿へ戻り、支度を整えてから帰省するという。
飲み屋を出ると、僕たちは最初の交差点で立ち止まった。残る休みがせめて充実した日々になるとええな、などと口々に言い合いながら、まず、経済学部コンビが横断歩道を渡っていった。
信号が赤に変わり、車影が僕たちの目前を横切る寸前、向こう岸で手を振っている二人の姿が目に入った。部長も軽く右手を上げて、応えている。僕は両手で挨拶を返した。
「アリス、お疲れさんやったな」
隣で、低い声が密やかに囁く。
「今日は、もう、帰りや―――お休み」
そう言うなり、江神さんは僕の返事を待たずにくるりと背を向けた。僕は何故か慌てた。
「江神さん!」
部長は肩越しにちらりと僕を見た。
「今はそう思えなくても、いつか―――マリアが、その・・・部長に感謝する時がやってくると思います」
僕は、掠れそうになる声を必死に振り絞った。彼のしたことは正しいのだ。
「いつか、きっと・・・江神さんに会えて良かったと―――マリアもそう思える日が、来る筈です」
江神さんは白い歯を見せて笑った。その唇が音を立てずに、「ありがとう」と動いたような気がした。
無意識のうちに握り込んでいた掌へ汗が滴る。今、自分の中にある気持ちをどう伝えたらいいのか判らぬものの、口が勝手に動く。
「今夜・・・泊めてもらえませんか」
何の脈絡もなく飛び出した僕の科白に、今度は江神さんが慌てたようだ。きょとんとした顔が、僕の視界を占領した。
「そら、まぁ・・・構わんけど―――あの部屋、クーラー無いぞ」
判ってます、そんなこと。
「京都の熱帯夜を舐めてるんやないやろうな」
この暑い最中、扇風機だけを頼りに眠る部屋へ泊るなんて物好きな奴だとでも言いたいのだろう。「そんなつもりはありません」という意を込めて、僕は首を強く横に振った。
そう―――このまま地下鉄の駅へ向かい、預けた荷物を京都駅で取り出し大阪まで戻ったなら、遅くとも9時過ぎには家へ帰りつける筈だった。だけど僕の心中では、今宵、このひとを一人にしたくないという想いが強く渦巻いていた。
自宅へ帰れば、冷房の効いた部屋で快適に眠ることが出来る。家族もいるし、気も紛れる。しかし江神さんは、部屋へ帰っても、たった一人なのだ。
今日だけは、このひとの傍にいたかった。僕のこんな感情は迷惑かもしれないけれど、江神さんのことが心配で心配でたまらない。とにもかくにも一緒にいたい―――その一心から、口にした言葉だった。
暫し考え込むような表情をしていた部長は、長い指で鼻の頭を掻いた後に、
「それやったら、もう少し、何処かで飲んでくか?」
と言った。
「・・・そうですね」
僕もゆっくり賛意を表明した。今から西陣の下宿へ戻ったところで、暑い部屋の中、ごろごろするくらいしか、やることはない。かといって、まだ熱気の篭る街中をそぞろ歩いても、余計な汗をかくだけだ。
ならば、客の話す声も喧しい騒音が頭上を飛び交う大衆的な居酒屋で、今一度、咽喉を潤そう。
そして、とりとめの無い話を少し、しよう。
どこまでも碧く眩しかった海と、一番静かだった朝の光景は、瞼の裏側にくっきり焼き付いたままだろうけど―――
今年こそは思う存分満喫できる筈だった夏が、僕の中を通り過ぎてゆく。
だけど、僕にとっては、江神さんと共に過ごせたというだけで幸福であり、充実した時間だった。そんなことを口にしたら「何、言ってるんや」と笑われそうだけど、それは事実だ。
そう―――いつの日か、マリアも気がつくことだろう。
あの夏、いちばん静かな海を前にして、傍らにいてくれた先輩の存在が、どんなにありがたかったかということに。
7つ年上の江神二郎なる人物と英都大学で巡り逢い、彼を先輩に持てたということの幸運に。夜の京都は、相変わらず、うだるように暑い。
僕たちは訳知り顔に無言で頷き合い、人混みの中、次に入る店を探して泳ぎ出した。(2000/8/6)
へ戻る
『孤島パズル』の最後は、大学が始まりマリアが姿を見せなくなったというところで終わっていますが、その前は島に連絡船がやって来る直前のシーンなんですね。で、これは、その二つのシーン間の話っていうか、島を出た直後の出来事です。
本当は、もう一つエピソードを入れたかったのですが、もう、字数が…(涙) ということで、まず、ここで切りました←オイコラ あああ、もっと短い話にしたかったのに~~~(号泣)
実は私、奄美大島へは行っているんです。しかし、何分、四年程前のことなので、ウソ書いていたら許してくださいね(汗)
あと、江神さんの下宿にクーラーがあるかどうかなんですが―――だって、無いような気がしたんですもんっ(大爆笑) 部長、団扇と扇風機で生活してそう………
それから今回のタイトルは、言わずと知れた北野武監督の作品からです♪