ACT.1
高価そうな扉を開くと、静かなピアノにあわせて中年の女性が悲恋を歌っていた。薄紫色のドレスからこぼれるような豊かな胸を焦がす、切ない恋の終焉。
「――ねぇ、ここって凄い。よくこんなとこ知ってたよね」
いかにも落ち着いたクラブの、小さなざわめきと煙草のゆらぎをくぐり抜けながら、目だけを動かして柏木雪乃はそっと友人に耳打ちした。普段よく行く――湾岸署に配属されてからと言ったほうが良いが――居酒屋とはまるで違う雰囲気に、少々腰が落ち着かない。
久し振りに会った高校時代の友人は、何でも外資系の商社でOLをしているらしく、たまにはちょっといい感じの場所で飲もうよと連れてこられたのが、この場所だったのだ。
はっきり言って威勢の良い女将がいる居酒屋の方が好きだと、雪乃は心の中で溜息をつく。
「雪乃はこういう所って行き慣れてるかもって思ったんだけど」
「……どうして?」
「だってお嬢だったじゃない。うちのクラスでも結構イケてたのに、誰も声をかけられなかったもんね。純粋培養だったし」
ころころと笑いながら適当な椅子に座った友人が、「なに飲む?」と言うのに一緒でいいと答えながら、雪乃は小首を傾げた。『お嬢様だった』と署のみんなが聞いたら即座に言われそうだ。「昔はね」とかって。
(あの頃は確かに可愛いお嬢さんだったかも知れねぇが、今じゃ平気で死体を検分出来る強行犯の刑事だとさ)
――言いそう、和久さんあたりなら。
「でもさ、雪乃が警官なんて信じらんない」
友人、一之瀬彩子の言葉にはっと現実に戻って雪乃が苦笑した。
「そうかな」
「みんなだって聞いたらびっくりするよ?警察官で、しかも刑事なんて。どっかのサスペンスとか、ドラマみたい」
――ドラマほどカッコ良いもんじゃないけど。
取り敢えず夢は壊さないでおこう。雪乃は目をきらきらさせる彩子に、にっこり笑うだけに留める。刑事になってから高いヒールも、昔はよく着た可愛らしい服もやめた。髪だって手間のかからないものになったし……。隣できれいに微笑む彩子を見ながら、ちょっとだけ女として気後れしてしまいそうな自分に、指輪の似合わなくなった指を組んで雪乃は肩を竦めた。時間のかかりそうな髪型と手入れの行き届いた爪が、彩子の女としてのこだわりをかいま見せられ、いったい自分は女としてどう映っているのだろうかと、彼女はふいにひとりの顔を思い浮かべた。
思いのほか柔らかい髪と、少し困ったような眉と。笑うと子供のように無邪気なくせに、言い出したらちっとも聞かない頑固さ。正義感で曲がった事が大ッ嫌いで、いつも一生懸命な『刑事さん』――。
「ねぇ雪乃。いい男いる?」
「いる」
丁度その彼を思い浮かべていただけに、彩子の質問に即答してしまった雪乃は、はっと口を押さえる。
「ふぅん……」
意味深な眼差しに慌てて弁解しようとした雪乃だが、「そっか」と小声で呟いた彩子にふと、
「彩子……辛い恋、してる?」
と尋ねてしまった。
「刑事さんの勘?」
「って言うか――同類かな」
言ってからふふっと雪乃が笑う。
「判ってるんだ。私のこと全然見てないことくらい。知ってるから。でも自分の生きてきた中で、道を示してくれた人のこと簡単に思い切れるわけないじゃない?自分の人生決めちゃった人だもん」
「雪乃……?」
「それでも幸せかな?側にはいれるし」
「そっか――いいなぁ、雪乃は」
テーブルの上へ腕を伸ばして、綾子は小さく笑った。そして綺麗な指がグラスに浮いた
水滴を、コースターに落とす。
「私は駄目だなぁ。パパがあれだもん」
「高級官僚だっけ」
「そう。だから結婚なんて、自分で決めらんない」
「綾子……?」
――私はもう貴方なしでは生きられない。
なのに貴方はさよならと私に言うの?――
艶やかで少しハスキーな声が、恋をなくした女の未練をピアノにあわせて歌う。好きだったの、本当に。貴方なしでこの私にどう生きろと?私に映る全てのものが色を無くし、美しい月の光さえ寒々と私の影を消してゆく。
「私ねぇ、見合いするのよね、父に勧められた相手と」
淡いブルーのカクテルを一口のみ、綾子は首を竦めて雪乃を見た。その瞳は全てを諦めた老人のようで、雪乃は思わず綾子の腕をきゅっと握る。高校の時の綾子は、自分の考えで行動し、雪乃を羨ましがらせていた。こんな風に毅然と自分に自信をもてたら、きっと素敵なのに――と、口には出さないけれどいつもそう思っていた。なのに今の彼女は、まるで人生に疲れきっているかのような溜息を吐く。
「綾子はそれで良いの?」
「良いも何も、決めた事だから文句を言うな、ですって。相手はお前を幸せに出来る優秀な男だ。父親が太鼓判を押すんだから安心しろ――と、こうよ?」
丁寧に口紅を塗られた唇が、苦笑に彩られる。それぞれのテーブルは圧迫感の感じない程度に仕切られ、隣の席の会話は厚い高級感の漂う木材に遮られて殆ど聞こえてこない。それがこの才女で有名だった友人の口を、滑らかにしているのだろうかと、雪乃はそう思う。
テーブルの真中に程よく置かれたキャンドルの灯りが、切なく綾子の顔に影をおとす。尚もピアノは淡々と恋の終わりを奏で、急に雪乃はあの優しくて力強い声を聞きたくなった。
――大丈夫、雪乃さん。俺がいるから。
「その相手って?」
「どっかのキャリアらしいけど。うふふ……これって玉の輿?」
「……すみれさんが聞いたら、替わってって言いそう」
思わず出た言葉に、綾子が目で『誰?』と聞いてくる。
「先輩刑事なんだけど、とっても素敵な人。キャリア紹介してって言うのが口癖で、そのくせいざ見合いとなると、いつも駄目になっちゃう」
「なら、好きな人がいるんだ」
何気ない言葉に、雪乃の胸がぎゅっと掴まれた。そう、もしかしてと思っているのだ。すみれの結婚しない理由のひとつに、彼の存在があるのではないかと。
自分より長い時間を共に過ごしている。そしてあの阿吽の呼吸で、お互いが言いたい事を瞬時で判ってしまうところは、最近小さな嫉妬すら感じてしまうようになった。しかし、雪乃はすみれが好きだ。彼女は手放しで尊敬できるし、刑事として優秀なのは勿論、同僚としても申し分ない。だから彼が手放しで懐いているのも充分理解出来る。
でも、感情がついていかない。
いつになったら自分もあんな笑顔で、接してもらう事が出来るのだろうか。子犬のように、少し甘えを含んだあの瞳で見てもらう日が、いつになったら来るのだろうか。
いきなり張り付いたような笑顔になってしまった雪乃の肩を叩き、綾子は預言者のようにこう呟いた。
「雪乃。好きなら、その手を離しちゃ駄目よ。何があってもついていかなきゃ。そうしないと、本当に後悔するんだから。後悔ほど嫌なものはないわ」
「綾子……?」
「ああっと!私もう行かなきゃ。門限があるのよ、この年で」
「綾子?」
急に時計を見て声を上げた綾子は、ちろっと舌をだして首を竦める。見れば時間はすでに9時をまわっていて、ここに来てから2時間以上たってしまっていた。
「今日は私の奢りね。誘ったし愚痴も聞いてもらったし」
「あ、割り勘にしようよ」
「良いって。これは口止め料よ」
ね?と笑う綾子に「ご馳走さま」と頭を下げた雪乃は、何気なくもう来る事もないからと見渡した店の中に、見知った影を見つけてふと眉を上げる。
それは一枚の絵のような情景だった。
奥まったテーブルに置かれたキャンドルの向こう側、紫煙をくゆらせながら琥珀色のグラスに口をつけ、何かを言った後に微笑う男と、少し難しい表情を作りながらも、優しさを滲ませた瞳でそれを見やる男。そのふたりの私服を見たのは今日が初めてで、また仕事を終えた後にプライベートで酒を飲む間柄だというのも、雪乃は知らなかった。
いや、それより。
(あんな風に笑うんだ……)
――これ以上私を置いて行かないで。
どこか知らない処へひとりで行ってしまわないで。
私はここにいるのよ。
貴方を想いながらたった独りで同じ場所に佇んでいるの。
だから。
「雪乃?」
いつまでたっても来ない雪乃に痺れをきらし、綾子が声をかける。
「どうしたの?」
「あ……ああ、ごめんね。こんな所に来るのももう無いかなって思って」
「なに言ってるの、彼氏と来ればいいじゃない、ほら、雪乃の好きな人と」
肘で雪乃をつつき、綾子は昔のような笑顔でそう言った。それに笑顔で答え、雪乃は来たようにまた重いドアをゆっくりと開ける。
その背中に女性の唄が追いすがって、一瞬のうちに掻き消えた。
――私はここよ。
早く気がついてね。
愛しい貴方……。
−2001/10/14 UP−
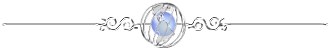
へ戻る

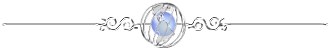
へ戻る
