ACT.2
携帯電話を見ながら電源を切る。
もうこれで今週に入ってから5度目になるだろうか。いい加減にしろよ――青島俊作は不機嫌なまま携帯をデスクの中へ放り投げた。そのままくるりと椅子ごと恩田すみれの耳元へ顔を持っていき、
「すみれさん、俺携帯壊しちゃった。経費でおちる?」
「何言ってんのよ、さっき鳴ってたじゃない」
「だからさっき壊れたの」
ふん。鼻で笑ってすみれは「おちない」ときっぱり言った。
「おちるも何も青島君の所有物じゃない。誰からの電話か知らないけど、いい加減諦めて出たら?こっちがうっとうしい」
「冷たい……」
大げさに傷付いた顔をしてがっくり首を落としてみせる青島に、とどめのように上から声が落ちてくる。見れば真下正義が引き締めた表情で彼を見詰めていた。
「先輩、冷たくないですから早く報告書書いてください。いったい何枚溜めてるんですか」
「……5枚」
大げさに真下が溜息をつく。ここ一週間青島の様子がおかしいのに首を傾げているのは、なにも強行犯係だけではない。盗犯係の面々、果ては袴田課長を含め神田署長までもが薄ら寒い思いで彼を伺っている。動く犯罪吸引体質の青島が最近妙に大人しく、派手な事件もここ数日起こっていない。
「青島君がおとなしいとホント、事件が無くて平和でいいよね」
「ホントです。これで書類さえきちんと書いてくれれば、もう言う事ないです」
すみれと真下が聞こえるように内緒話をするのに肩を竦め、煙草を吸うためにまた椅子を足で引っ張りながら――彼は移動するのにいつも椅子と一緒だ――自分の席へと戻る。ごそごそと机の引出しを掻き回しながら煙草のストックを探していると、嫌でも携帯が目の端にうつる。
これのせいで嫌な事ばかり思い出すんだ。たとえば着信履歴がひとりの名前で一杯になっている事とか。着信音が聞こえるのが嫌だったからバイブにしたら、胸が振動と共に痛くなったとか。とてもじゃないが机の上ほど綺麗に片付いていない引出しの中をごちゃごちゃしながら心の中で文句をたれる。
やっと一箱だけ探し出すことができてやれやれとマッチで火をつけると、今度は硫黄の匂いと共に僅かな整髪料の香りを思い出し、青島は小さく舌打ちした。こんなに胸が痛いとは流石に思いつきもしなかった。そう――こんなにも、想っていたなんて。
「青島さん、コーヒーどうですか?」
コトン――と音がして、コーヒーの良い匂いが鼻をくすぐる。目を上げると柏木雪乃が心配げにこちらを見付めていた。
「ありがとう、雪乃さん」
女性を心配させるなどと青島の名が泣く。いつもの笑顔でそう言って一口飲むと、雪乃の優しい心使いが一緒に胃へ流れ込んだ。途端胸が締め付けられるように痛くなる。これは正当な判断なんだ。何も間違っちゃいない――たとえそれでどんなに傷付こうとも、決めた事なんだから前進するしかない。
一番大事なのは二人の約束、なのだから。
「大丈夫ですか?青島さん。最近調子が悪そうですけど」
「ああ。大丈夫。心配してくれるんだ?」
「勿論です。だって青島さんは……」
雪乃が言葉を全部発する前に、すみれが「ほっとけばいいのよ、雪乃さん」とちゃちゃを入れる。
「甘やかすとすぐ図に乗るから」
「すみれさ〜ん」
情けない声と共に青島の眉が下がった。それでも判っているのだ、すみれが雪乃の言葉を遮ったのは。雪乃の儚い恋心を青島だって知っている。それを上手くかわし続けるのは一重に愛しい相手がすでにいるからだ。名前も言えない、世間に知られてはいけない――けれど心から大切だと言い切れる、相手。
それももうお終いか。
鳴り続ける携帯、プラグを抜いた電話、遮光性に変えたカーテン……チェーンロックされた部屋。
全ては相手の為。そう、全てが始まった時から決めていた事。
――こんなに早いとは思ってもいなかったけど。
それは丁度一週間前の事だった。
ばたばたと慌てて走りこむ音が聞こえたと思ったら、いきなりがしりと肩を掴まれて思いっきり上下に振られた。
声をあげる事も忘れて気持ち悪いと思った彼を救ったのは、やはりすみれである。
「真下君、殺すなら署外でして」
あんまりな言い方に文句を言おうとした青島だったが、取り敢えず真下の攻撃が収まったので不問にしてやろうと考えた。
「なんなのよ、いきなり」
「先輩、室井さんと友達じゃないですか!」
「……友達……」
「知ってたらどうして教えてくれないんです?僕はいつも提供してるでしょう?」
「何を」
「今更とぼけないで下さい」
「不毛な会話ね」
いつまでたっても本題が見えない事に業を煮やして、すみれが腕を組む。
「何があったの」
「はっきり言いなさいよ」
同時に青島とすみれに声を荒げられた真下が、うろたえながらもじっと青島を見詰めた。多分室井が関わっている話だろうと予測出来るものの、青島にはとんと思い当たる節がない。この間会った時も別段変わったことも無かったし。いつもの言葉少なめな、だけど寛いだ表情のした室井を思い出し、尚更首を捻って見せる。
「なに知ってんの?真下君」
「――そうやって高を括るならいいです。どうせ室井さんに黙っててくれって言われたんでしょうから。でも全然知らなかった……室井さんが見合いするなんて」
「見合い!?」
二人の声がまたもや重なった。
「見合いってなに?」
「あの室井さんが見合い?似合わないっ」
「本当に知らなかったんですか、先輩」
あからさまな驚きにむっと青島の眉が顰められる。見合いってなんだ。何で俺が真下から聞かされなくちゃならない。
――黙ってたな、室井さん。
大体想像がつくから腹が立つ。耳に入れず処理して何事も無かったかのような顔をして自分の前にいようとしたのだろう。きっと自分のために有利な見合いを断って、尚且つ理想の実現を目指してがむしゃらに駆け上がろうとする。出世は結局後ろ盾の大きさで決まるのだ。それを知らない室井ではないのだろうに。
――あんたはキャリアだ。きっと後ろ盾がいる。見合いを持ってこられるだけマシなんだから。それはきっと室井さんの実力が買われている証拠。
「決めた」
あっけらかんとした青島の口調に、真下とすみれが怪訝な表情で見た。それに笑顔で答
えた彼は、
「室井さんの見合いが上手くいくように、頑張ろっと」
「青島君?」
「だっていろいろ室井さんには世話になってるしね。上手くいくといいなぁ」
そうね、室井さんには偉くなってもらわなくっちゃ。すみれも首を竦めてそれに同意する。現場が動きやすくしてもらう為に、上へ行ってもらわないと話が進まない。
「ホント」
ポケットから煙草を取り出して青島はマッチで火をつける。紫煙と共に吐き出したのが哀しくなる程の愛しさだと知っていても、全てに目を閉じて黙殺しようと思う。何をおいても叶えなくちゃならないのは『夢』なのだから。
不器用な指や目じりで浮かべる微笑や――耳元で囁くかすれ声を忘れられないとしても。
一生死ぬまで想い続ける哀しい恋。見合いが上手くいけば結婚して子供が出来て。
「酒、もう誘ってもらえないなぁ」
思わず呟いた言葉に、すみれが「飲みに行く付き合いだったんだ」と驚いた顔をした。
「あんたたちって本当に仲良しだったのね。ま、見合いが上手くいけば彼女優先になるのは仕方ないんじゃない?でも室井さんってそんなで結婚するかな」
「あ、それは言えますね。愛の無い結婚って嫌いそう」
「何言ってんのよ、あんたも他人事じゃないでしょ?」
「僕は父がいますから。結婚相手は自分で選べます」
胸を張る真下に呆れ顔ですみれがため息を吐く。そんなだから雪乃さんに本気で向き合ってもらえないんじゃない。
「青島君――彼女つくったら?ほら、室井さんより先につくれば寂しくないじゃない」
「寂しくなんかないよ、すみれさん。だって約束してたし。それが前進するのは俺、すげぇ嬉しいから。それにね、人の心配するならすみれさんはいるの?彼氏」
「一言多い」
勢いよく睨んだすみれへ青島は大げさに
「こりゃ失敬」
と笑った。
不審なものを見るかのようなすみれの瞳がすっと色を変える。所詮他人が割り込める関係でないのなら、傍観したほうが随分ましだ。
――でもね、青島君。
無理してるの、バレバレ。一体何が彼をそうさせるのか知らないけれど、上司と部下だけではない絆がふたりには確かにある。副総監誘拐事件の時に思い知ってしまったすみれではあるのだ。
――普通、抱いてあげてる人間無視して運転手に話し掛けるかな。必死に息を搾り出して。それさえ言えば、後はおまけよね、青島君。
何がデートよ。してあげるもんですか。
煙草を燻らせながら何かを思い詰めた瞳をした青島をそっと伺い、平穏だったこの一週間がさらに長続きしますように――心の中ですみれは誰とも知らない神につい祈ってしまった。
それから一週間、青島は携帯がかかってきても無視するか電源を切るという不毛な態度を取り続けている。業を煮やしたのか発信音をバイブに変えたのは今朝の事。
「しばらく忙しくって連絡取れないんじゃないですかね。張り込み続いてるし。会えなくなりますけど元気でいてくださいね」
それが最後の言葉。
きっと気付いてる。見合い話がばれたのに気付いて連絡を取ろうとしている、室井の眉間に寄った皺が想像出来て青島は唇の端だけでそっと笑う。
リスクなんて始めから判ってるじゃないか、室井さん。理想の現実化が一等大切なんだって――あんたが上に行くのに俺が邪魔になればさっさと『さよなら』するって。俺の為に上へ行く階段を踏み外しちゃいけないんだ。
「俺は自分が正しいと思ったら、曲げないよ」
苦めのコーヒーを飲み干して、青島は机にほり込んだ携帯に向かってそう呟いた。
−2001/11/16 UP−
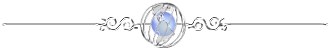
へ戻る


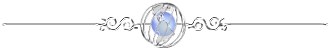
へ戻る

