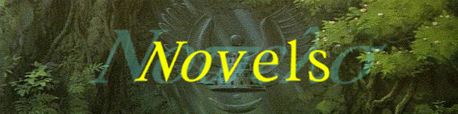|
天の橋立 (2)
第二話
それから数日が経ち、歌合せが間近に迫って来ると、都では様々な話しが飛び交っていた。歌合せの歌人はほぼ決まり、のこすは指折り片手で数えるほどもないとかとも言われていた。その中で定頼
は自分に歌合せの話しが回ってくるのを首を長くして待っていた。 中納言という身分も手伝って彼の歌もそれなりの定評があった。そ れは彼の自負心を支える一本の柱であった。
しかし、風の便りに聞くものはどれも小式部の内侍のものであっ た。第一にそれそのものが定頼をいらだたせる原因でもあった。
「なぜだ?なぜあの小娘なのだ?」
彼は時折そうぼやいていた。齢十三歳の天才少女歌人。そして、歌 の名手と呼ばれる和泉式部の娘である小式部の内侍は都でも一目おかれる存在であったのだった。
「しかし、あのような小娘にあのような歌が詠めるとはとうてい考えつかぬ」
定頼はひとりごちるとため息をついた。
似ているのだ。彼はかつて和泉式部に密かな想いを寄せていた。 その和泉式部によく似ているのだ。容姿も、歌も…。
初めに定頼が小式部の内侍の歌を知ったときドキリとしたのには そういう理由もあった。しかし、当の和泉式部は保昌と再婚して丹後の国へ移り住んでいたのである。以来、定頼は京に住む天才少女
歌人を避けるようになっていた。
そして、それを差し引いても彼女の歌は出来すぎているほどだっ た。
「あの歌は小式部ではなく和泉式部の歌に違いないのだ…」
定頼は彼女の歌を反芻しながら一人そう呟いていた。
第三話
歌合せの当日になって最後の一人が小式部の内侍だと知った定頼 の受けた衝撃はいかなるものであったろうか。彼は小式部の内侍を
憎んだばかりではなく、恐れさえも抱いていたのであった。
さて、定頼は(注1)衣冠束帯を着込むと(注2)内裏へと赴いた。 今日は待ちに待った歌合せの当日であり、つまりは帝の誕生日であ る。内裏ないも華装されていた。彼は(注3)清涼殿に途中でふと足
を止めた。特別に組まれた部屋。その中で小式部の内侍が待ってい るのが彼にはすぐにわかった。母親の代作のおかげで名を馳せた少女がそこにいる。だのに、自分は…。そう思った時彼の心にはある
種の悪意に苛まれた悪戯心が宿っていた。
「丹後の母親の下に出された使いのものは戻ってきましたか?丹後 は遠く、代作を備えた使いが戻るのが遅く、さぞ不安でしょうなぁ」
皆はだませても自分はだませない。自分は事実を知っている。そんな自信が定頼を支えていた。しかし、立ち去ろうとする定頼の裾を 引っ張り、引きとめるものがあった。部屋から半身を出した小式部
の内侍である。そして、彼女は小さく呟いた。
「大江山 いく野の道の 遠ければ まだふみもみず 天の橋立」
(母のいる丹後は遠く、大江山やいく野の道を超えねばなりません。 ですからまだ、丹後の地も天の橋立もふんではおらず、母からの文 ももらってはおりません。ですから、私の歌を母の代作と思わない
で下さい)
注1衣冠束帯:当時の常用服の直衣に対して正式な場で着る貴族の 衣装。女性は十二単。 注2内裏:京の都の中央の北側にある天皇のいる御殿全体を指す。
注3清涼殿:内裏の中で特に天皇がいつもおられる部屋。
|