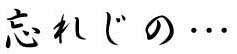
|
時は真夜中過ぎ、地面に突き刺さらんばかりの勢いで降りそそぐ 雨の中、その屋敷はそびえ立っていた。 西洋の館をまねて造られたその屋敷は、何者も決して寄せ付けよ うとしない厳しい拒絶を放っている。 照明ひとつ灯っていない屋敷は今や完全に闇と同化し、外の雨の 音の激しさにも関わらず不思議な静寂と共にあった。 そんな屋敷の廊下に、不似合いな小さな子供がいた。 「…に…ちゃ…。」 寒々とした廊下を、夜目がきかぬのか、それとも闇の醸し出す 本能的な恐怖の為か、おぼつかない足どりで幼い裸足が一歩 また一歩と進む。 「…にい…ちゃん…ひっく…。」 歳は六つか七つくらいであろう。 不安と脅えに彩られた二つの瞳には大粒の涙があふれ、 今にもこぼれ落ちそうだった。 華奢な造りの体の上に、生来の色の白さが闇の中ではいっそう 痛々しいばかりに目に映る。 「…兄ちゃぁん…にい…。」 兄の名を、呪文の様に繰返し繰返し呟きながら、たどたどしい 足どりで探るように歩く。 その後を、彼の小さな体には不似合いな程の白い巨大な塊が、 ずるずると、まるで連れ従う様に引きずられていく。 「兄ちゃぁん…えっえっ…。」 突然、真昼と見間違えそうな程の強い光が窓の外に広がり、 暗闇に慣れた少年の目をくらませる。 とたん、はたから見ても判る位、彼の体がすくみあがる。 そんな青白い閃光に続いてすぐ、今までの静寂を引き裂くような 激しい轟音が地面をも揺るがす。 何処か近くに落雷でもしたのであろうか。 「きゃああ!」 鋭い悲鳴をあげ両手を強く耳に押し付けると、子供はその 場にしゃがみこんでしまった。 固く閉じられた瞼から流れた涙が、幾筋も頬を伝う。 壁によりすがった体は、がたがたと小刻みに震えている。 「にい…ちゃん…こわいよぅ…!」 やがてゆっくりと音は遠ざかっていく。 それを感じてようやく少し落ち着いたのか、痺れるくらいに 押し付けた手をそっと離し、いっしょに引きずってきた巨大な 枕をきゅっと抱き締める。 まるでその枕が、自分を守ってくれるとでもいうかのように。 「もう…ちょっとだよね。 もうちょっとで、兄ちゃんにあえるんだよね…。」 自分に言い聞かせるように、震えながら何度もつぶやく。> 彼には大きすぎるパジャマの袖で、涙でぐしゃぐしゃになった 顔をごしごしと何度もこする。 そして、意を決したように枕を抱えたまま立ち上がると、 手探りで一歩、また一歩と進みはじめた。 窓の外で激しく降り続けている雨を、ベットの中からぼんやり とながめながら少年はぽつり呟いた。 「瞬の奴…ちゃんと寝たのかな…。」 歳は十くらいであろうか。 先程の少年とは対照的に、意志の強そうな瞳ときりりと結んだ 口許、年齢のわりに逞しさの感じられる体つきは、“強さ”と いうものをどこか感じさせられる。 それは、周囲の大人から見れば“可愛気のない”とか “生意気な”などと誤解される原因でもあったのだが。 「あいつ雷…怖がるからな…。」 地面を揺るがす轟音に、うるさいとばかりに軽く眉を寄せる。 落雷の音が遠ざかるにつれ、また雨の音が戻ってくる。 「泣いてなきゃいいけどな…。」 風邪をひいたのか、少し熱の出た彼の弟は、屋敷の離れに ある病室に移されていた。 元々あまり丈夫とはいえない上に、慣れない訓練の疲れが 出たのだろうか。思う様に病気は良くならなかった。 床について、今日で三日目になる。 「あいつだって男なんだ。大丈夫に決まってる。」 一輝は自分に言い聞かせるように、宙を睨みすえ言う。 そして頭からシーツをかぶると、このまま寝ちまえと言わん ばかりに目を強く閉じる。 しかし、一向に眠気は訪れなかった。 それどころか、かえって目が冴えるばかりである。 仕方なしに、もぞもぞと頭だけ出すとふうっと溜め息をつく。 「離ればなれになっちまうんだよな…」 三日後に、ここに集められた子供たちの運命が決定される。 皆ひとりずつ、どこかの国の修業地に送られるのだと聞いた。 そうなれば、当然自分たち兄弟も今までのように一緒には いられなくなってしまうのだ。 ──は・な・れ・ば・な・れ・に・な・る── 何度その言葉を心の中で繰り返してみても、全く実感は 涌いてこなかった。 遊ぶ時も、食事も寝る時も、二人はいつも一緒だった。 もともと兄弟仲はいい方であったが、両親に死なれて以来、 片時も離れていた事はなかった。 それが一輝にとって当たり前の事であったし、もちろん 瞬にとってもそうだった。 それがいきなり“別れる”と言われても、理解出来ないのは、 当然と言えば当然の事であった。 「………ちゃん。」 微かに弟の声が聞こえた様な気がした。 驚いてはね起きるが、耳をすませても何も聞こえない。 空耳かと思いもう一度寝ようとした時、今度ははっきりと 弟の自分を呼ぶ 声が聞こえた。 慌てて部屋のドアを開け、廊下に飛び出す。 するとそこにたよりなげに弟の瞬が立っているではないか。 「瞬…お前どうしてここに?」 「兄ちゃん!」 驚いた表情を浮かべたまま茫然と呟く一輝の胸に、 涙でぐしゃぐしゃの顔をした瞬が抱き付いた。 ピカッ…。 白いカーテンが青白く光るたび、ビクッと瞬の体が恐怖で すくみあがる。 そんな瞬を傍らで見ながら一輝が呟く。 「…解らないなぁ。」 一輝の腕にしっかりとしがみついていた瞬が、そんな兄の 言葉に不思議そうに顔を見上げる。 とたんに、耳をつんざくような轟音が響きわたる。 「きゃん!」 叫んだかと思うと、いっそう強く一輝の腕にしがみつく。 あいかわらずガタガタと体が震えている。 「やっぱり…解らない。そんなに雷が怖いのに、よく ここまで一人でこれたよなぁ。」 雷の音が遠くなり恐怖もやわらいだのか、しゃくりあげ ながら瞬が答える。 「だって…ぼく…カミナリこわいけど… 兄ちゃんいたら平気だもん。」 「…真っ暗だろ、廊下。こわくなかったのか?」 「ううん…こわかった。とっても。」 そこまで言うと、先程までの事を思い出したのか激しく 泣きじゃくり始めた。 「だってまっくらで…おばけ…出てきそうで… カミナリ ピカッって…すごくこわかった…けど、 兄ちゃんと いっしょだったらこわくないもん。平気だもん。 だから…だから…。」 ぽろぽろ、ぽろぽろと、後から後からまるで止まることを 知らないかの様に、次から次へとあふれでる。 一輝はそんな弟の言葉に、暖かいものがじわりと胸の中から 湧いてくるような感じを覚え、小さく笑ってしまう。 人一倍泣き虫でこわがりの弟がそんな怖い思いをしてまで、 自分に会いに、その為だけにここまで来てくれたのだ。 愛おしさに、思わず抱き締めたい衝動にかられる。 「そんなに泣くと、目玉、こぼれちまうぞ。」 からかうような一輝の言葉に、瞬は泣きじゃくるのを ピタリと止めると、驚きに大きく目を見張る。 「ほんと…?」 そのあまりに素直な、まっすぐな弟の視線に、ちょっとだけ いじわるをしてみたくなる。 「ああ、本当だ。」 一輝は、ひどくまじめな顔を作って言う。 「あまり泣くとな、目玉が涙と一緒に流れ出ちまうんだ。」 「流れ…ちゃうの?」 自分の言葉を信じて疑ってすらいないようだ。 そうやって、おそるおそる問い返す姿がひどく愛らしい。 「ああ。」 「流れちゃったら…何も見えなくなるの?」 「ああ。だから…何してんだ?」 急いでぎゅっと目を閉じ、さらにその上から両手で押さえる 瞬を見ながら、訝しげな声で一輝が尋ねる。 「目が流れないようにおさえとくの。」 「……。」 「だって目が流れちゃったら何も見えなくなるんでしょ? そしたら兄ちゃんや…氷河や…紫龍や星矢、みんなの顔も 見れなくなっちゃうんでしょ?ぼくそんなのいやだ。」 そう言う間にも、瞬の涙は押さえた腕を伝ってシーツに しみこんでいく。 今度こそきゅっと一輝は瞬を抱き締めた。 …瞬の髪は少し甘い匂いがしたような気がした。 「だから、あんまり泣かなきゃいいんだ。な。」 「ん…。」 腕の中でおとなしく頷く瞬に、一輝はふと思い出し言う。 「瞬…そう言えばお前、熱下がったのか?」 「ん…へいき。少しくらくらするけど。」 「バカ。早く寝ちまえ。またひどくなるぞ。」 そっと弟を寝かせて毛布をかけると、自分も隣に横になる。 すぐに瞬がすり寄るようにして、一輝にしがみついた。 「瞬…お前、やっぱ熱あるんじゃないか?体あついぞ。」 自分の体を気使い、そう尋ねてくれる兄の優しさが嬉しくて、 瞬はにっこりと微笑みながら答える。 「兄ちゃんも…あったかいよ。」 「そうか…。」 「うん…。とっても…。」 二人でくすっと笑う。 互いの温もりがひたひたと優しい眠りをさそう。 「瞬…。」 「なあに…?」 「お前…強くなれよ。離ればなれになっても泣くんじゃないぞ。 きっと…きっと日本に戻ってくるんだ。いいな、瞬。」 しかし、返事は返ってこない。 隣からは、規則正しい寝息が聞こえてくる。 「寝ちまったのか…。」 瞬のあどけない寝顔に少し微笑んで、ゆっくりと目を閉じる。 外は、まだ雨が降り続いていた。 |