- 科学的思考(1) -
ガリレオ・ガリレイの実験
1998.06.04 swing
2021.10.06 update
・2001.06.15 図を挿入
・2001.11.19 文言についてご指摘があり、一部改定
・2009.08.03 過去に頂いた ゲストブックのご意見 をアップ
・2015.01.07 解決方法は一つじゃない をフラクタルからこちらに移動
・2018.10.02 ノーベル賞:本庶佑さん 記者会見の要旨 をアップ
・2021.10.06 ノーベル賞:真鍋淑郎さん 記者会見の要旨 をアップ
【 はじめに 】
・科学的なことも取り上げて行きたいと思っています。
・ここでは、ガリレオ・ガリレイが行ったと言われている有名な「ピサの斜塔の実験」
について考えてみます。
【 1.ガリレオ・ガリレイの実験 】
・ガリレオ・ガリレイの有名な実験に、「ピサの斜塔から大小二つの金属の玉を落とす」
と言うものがあります。(第1図)
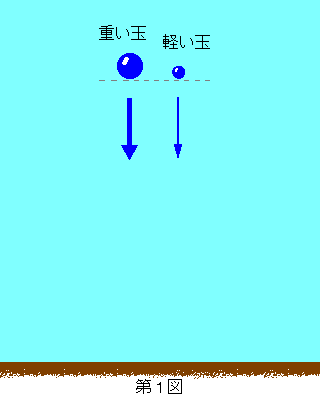 ・ガリレオ・ガリレイは、「物体の落下速度は その物体の重さよらず一定である」とい
うことを証明するために、『ピサの斜塔』から大小二つの鉛の玉を同時に落とし「大
小両方の玉が同時に地面に落下することを確認」することによって ...
「重力による物体の落下速度は、その物体の質量の大きさに依らない」
と言うことを証明(確認)した..と言われています。
・ここで「鉛の玉」を使用したのは「空気の抵抗をできるだけ無視する」ために必要だ
ったからです。
・ガリレオ・ガリレイは、「物体の落下速度は その物体の重さよらず一定である」とい
うことを証明するために、『ピサの斜塔』から大小二つの鉛の玉を同時に落とし「大
小両方の玉が同時に地面に落下することを確認」することによって ...
「重力による物体の落下速度は、その物体の質量の大きさに依らない」
と言うことを証明(確認)した..と言われています。
・ここで「鉛の玉」を使用したのは「空気の抵抗をできるだけ無視する」ために必要だ
ったからです。
【 2.思考実験による簡単な証明 】
・しかし、このような実験をしなくても思考実験によって以下のように簡単に証明する
ことができるので、その手順について説明したいと思います。
・思考実験とは、「実際に実験するのではなく、頭の中だけで理屈で実験する」と言う
か、実験したつもりになる(想像する)ことを言います。
▽思考実験:ステップ-1
1.まず、同じ重さの鉛の玉を二つ用意します。(用意したつもり)
2.次に、この二つの同じ重さの鉛の玉を『ピサの斜塔』から同時に落とすことを考
えます。
3.同じ重さの二つの玉は同時に地面に落ちる、としか考えられませんね。(違う訳
がない!)(第2図-左)
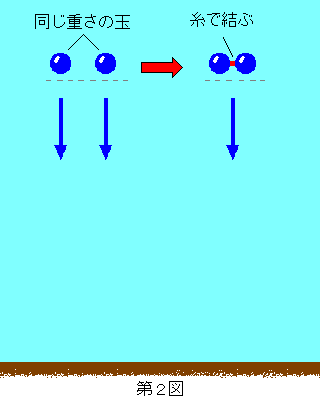 ▽思考実験:ステップ-2>
4.次に「第2図-右」のように、二つの玉を「細くて非常に軽い糸で結んでから落
とす」ことを考えます。
5.「細くて非常に軽い糸で結ぶ」ことにより、結ばないで落とした時に比べて落下
速度が変化することが考えられるでしょうか?
→細くて非常に軽い糸で結んでも、落下速度は変わらないと考えられますね。
6.では、その結んでいる糸をどんどん短くしていったらどうでしょう?
→糸の長さが落下速度に影響を与えるとは、考えられませんね?
7.では「第3図」のように、その糸の長さが「0」になったらどうでしょう?
→糸の長さが「0」になった途端に落下速度が変わる、とは考えられませんね?
..勿論、空気の抵抗とかは無視してます。
→長さ「0」の糸で結んだ二つの玉ということは、接着剤で二つをくっ付けて
しまったのと同じだし、そうなると形は丸くはないけれど、れっきとした一
個の玉といえますね!?..ただ重さは、別々の時の2倍になりました。
▽思考実験:ステップ-2>
4.次に「第2図-右」のように、二つの玉を「細くて非常に軽い糸で結んでから落
とす」ことを考えます。
5.「細くて非常に軽い糸で結ぶ」ことにより、結ばないで落とした時に比べて落下
速度が変化することが考えられるでしょうか?
→細くて非常に軽い糸で結んでも、落下速度は変わらないと考えられますね。
6.では、その結んでいる糸をどんどん短くしていったらどうでしょう?
→糸の長さが落下速度に影響を与えるとは、考えられませんね?
7.では「第3図」のように、その糸の長さが「0」になったらどうでしょう?
→糸の長さが「0」になった途端に落下速度が変わる、とは考えられませんね?
..勿論、空気の抵抗とかは無視してます。
→長さ「0」の糸で結んだ二つの玉ということは、接着剤で二つをくっ付けて
しまったのと同じだし、そうなると形は丸くはないけれど、れっきとした一
個の玉といえますね!?..ただ重さは、別々の時の2倍になりました。
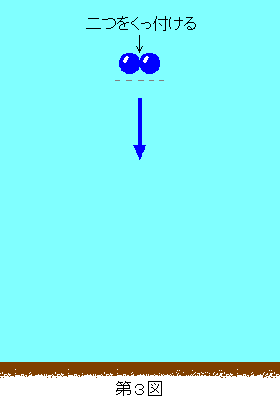 8.と言うことは ...
「玉の重さが2倍になっても落下速度は変わらない」
..と言うことになりますよね!?
▽思考実験:ステップ-3
9.同じように、3個、4個、5個…と玉の数を増やしても思考実験ができます。
あるいは、逆に1個の玉を2つ、3つ…に分割する実験もしてみることも考えら
れます。
→重さを何倍にしても、何分割しても落下速度が同じなら、落下速度に違いが
でるはずがない..と想像できますよね?
10.以上のことから「物体の落下速度は物体の重さにはよらない」という結論が得ら
れますよね!(^o^)
▽思考実験:応用問題
・全く同じ手法の思考実験により、
「人口衛星の軌道は速度のみに依り、その重さには依らない」
と言うことも簡単に証明できますので、皆さんやってみて下さい。
・この場合は、同じ重さで同じところを平行して飛んでいる二つの人口衛星を、「非常
に細くて軽い糸」で結び、その糸の長さを徐々に縮めて行けばいいんですよね。
・それで、最後に、その糸の長さを「0」にしちゃえば、OKです。
簡単に証明できますね。(^o^)
・二人が各々一本の矢を放っても、一本の時の倍にはならず、速さが変わることはあり
ません。100mを10秒で走る走者が二人同時に走っても、記録は半分の5秒にはなりま
せん。
・だけど、例えば、100mの間に落ちているゴミを10秒で拾うことができる人が二人いた
として、その作業を二人で同時にやったら、作業時間は半分の5秒でできますね。
..何がどう違うんでしょう?..あとは皆さんで考えてくださいね。(^^)
8.と言うことは ...
「玉の重さが2倍になっても落下速度は変わらない」
..と言うことになりますよね!?
▽思考実験:ステップ-3
9.同じように、3個、4個、5個…と玉の数を増やしても思考実験ができます。
あるいは、逆に1個の玉を2つ、3つ…に分割する実験もしてみることも考えら
れます。
→重さを何倍にしても、何分割しても落下速度が同じなら、落下速度に違いが
でるはずがない..と想像できますよね?
10.以上のことから「物体の落下速度は物体の重さにはよらない」という結論が得ら
れますよね!(^o^)
▽思考実験:応用問題
・全く同じ手法の思考実験により、
「人口衛星の軌道は速度のみに依り、その重さには依らない」
と言うことも簡単に証明できますので、皆さんやってみて下さい。
・この場合は、同じ重さで同じところを平行して飛んでいる二つの人口衛星を、「非常
に細くて軽い糸」で結び、その糸の長さを徐々に縮めて行けばいいんですよね。
・それで、最後に、その糸の長さを「0」にしちゃえば、OKです。
簡単に証明できますね。(^o^)
・二人が各々一本の矢を放っても、一本の時の倍にはならず、速さが変わることはあり
ません。100mを10秒で走る走者が二人同時に走っても、記録は半分の5秒にはなりま
せん。
・だけど、例えば、100mの間に落ちているゴミを10秒で拾うことができる人が二人いた
として、その作業を二人で同時にやったら、作業時間は半分の5秒でできますね。
..何がどう違うんでしょう?..あとは皆さんで考えてくださいね。(^^)
|
<解決方法は一つじゃない!>
・ガリレオ・ガリレイの実験や思考実験とは直接関係がありませんが、考える
と言う意味では同じだと思いますので、ここに余談として追加します。
・私たちは、学校教育の中で、問題の提示を受けるとともに、その解決方法も
教えてもらいます。それはそれでありがたいことですが...
・しかし、解決方法には幾つかの方法がある場合もあります。解決方法を自分
で考えることも重要と考えますがいかがでしょうか。
・NHK高校講座と言う番組で、秋山仁さん(数学者)は、一人ひとりが自分で
考え、自分なりの方法で解決できるように指導していました。^^
・例えば、次の図① は 数学者ガウスが少年の時に学校で出された問題:
「1+2+3+ ・・・ +10 は幾つになるか?」
の答えを出すためにガウス少年が考えたと言われている考え方を説明する図
です。
→青い丸が上から順番に 1個~10個が重なっています。
そこに、上下を反対にして図のように赤い丸を描いてみます。
赤い丸と青い丸を一緒に考えると、11個×10段なので、合計は 10×11
(=110)と言うことが分かりますね。
青い丸だけの合計ならその半分(=55)と言うことになるわけです。
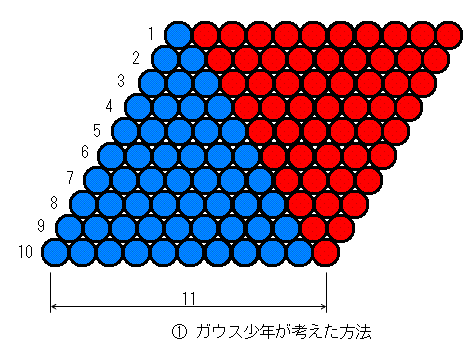 ・次の図では「無限等比級数」を考える時に私が考えた方法を表した図です。
・中学校時代の数学の授業で習った「無限等比級数」を求める問題:
「1/2+1/4+1/8+1/16+ ・・・ は幾つになるか?」
この答えの導き出し方は教科書に載っていますが、以下はそれとは別に答
えを出すために私が考え出した方法です。
→一辺の長さが「1/2」の正方形を描き、「1/4」の正方形、「1/8」の正
方形…と正方形を次々に並べて描いていきます。
そうすると、各正方形の陵(角)を結んでみると、図の赤線のように
「直角二等辺三角形」が出来上がることが分かり、結局問題の答えは
「限りなく1に近づく」であることが実感としてわかると思います。
・次の図では「無限等比級数」を考える時に私が考えた方法を表した図です。
・中学校時代の数学の授業で習った「無限等比級数」を求める問題:
「1/2+1/4+1/8+1/16+ ・・・ は幾つになるか?」
この答えの導き出し方は教科書に載っていますが、以下はそれとは別に答
えを出すために私が考え出した方法です。
→一辺の長さが「1/2」の正方形を描き、「1/4」の正方形、「1/8」の正
方形…と正方形を次々に並べて描いていきます。
そうすると、各正方形の陵(角)を結んでみると、図の赤線のように
「直角二等辺三角形」が出来上がることが分かり、結局問題の答えは
「限りなく1に近づく」であることが実感としてわかると思います。
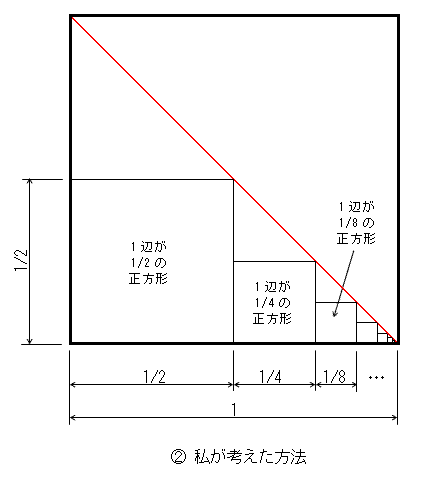 ・他に、「遠心力」と言う力学の概念から「曲線の曲率を導き出す」と言う
方法も作りましたが、これについては、また時間がある時に書いてみたい
と思います。
(2009.07.31)
・他に、「遠心力」と言う力学の概念から「曲線の曲率を導き出す」と言う
方法も作りましたが、これについては、また時間がある時に書いてみたい
と思います。
(2009.07.31)
|
|
|
・本ページ作成当初「ゲストブック」と言うページを設置していました。そのページに本
稿に関する次のようなご意見が寄せられました。
------------------------------------------------
<ゲストブック>
(無題) 投稿者:馬鹿者より 投稿日:2001年11月18日(日)22時35分13秒
its1.catv.ne.jp Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
ガリレオの実験がばかげているとは言いすぎではないのでしょうか?
今アナタが使っている考えも、ガリレオが発見したからこそ使える考えなのでしょう?
それを馬鹿だと言うのならそれは間違っていると思います。
貴方は賢いかもしれませんが、それは先人の上にたっているものだと気付いてください。
------------------------------------------------
・なるほどなあ と思い、私はさっそく現在の文のように改定しました。
・以下、当時の私のメモです。
------------------------------------------------
<改定の弁@大馬鹿者の管理人^^;>
以上のようなご指摘を頂いたので、早速本文を改定しました。
ご自分を「馬鹿者」と謙り、それでいて「間違い」を指摘し「気付く」よう諭して頂き
ました。
私は、「それは先人の上にたっているものだと気付いてください」と言う指摘には重要な
意味を感じていませんし、科学史的に考えたり、単に納得するだけと言う姿勢にもあまり
意味を見出し得ません。
「先人の上にたって…」..そんなことは当然のことです。実際、現時点に存在している
私たちは排除することも不可能ですし、歴史の中に身を置いている限り当然です。
ただ、だからと言って、その方法をただ結果が正しいからと鵜呑みにして素通りしてしま
い、先人として敬っているだけでは科学に発展はないと思いますし、考える力を養うこと
も出来ないと、私は思います。
この方(「馬鹿者より」さん)は私の本論については何もコメントがありませんので、
その部分についてはどのようにお考えになっているのか分かりません。
また、どの部分について「先人の上にたって…」とご指摘されているのかも分かりません。
「先人」がガリレオだけのことを指しているのか、全ての人を指しているのかも大馬鹿者
である私には分かりません。
しかし、私が期待するのはそう言うことではなく、一つの定理や原理であっても、別の
見方..各人が「自分なりに納得できる方法を自分で考え出すこと」の方により重要さを感
じます。
私は、ある意味センセーショナルに書きたかったわけですが、インターネットでは不特
定の方々がご覧になり、このように本論の部分とは別の部分についてご意見を頂いたりし
ますが、その結果言わんとするところが伝わらないようではまずいと思いますので、ご指
摘を尊重し、その部分をもう少し柔らかい表現に代えさせて頂いた次第です。m(__)m
------------------------------------------------
例えばですが、コンデンサに電池をつなぐと、その電極の片方にはプラスが、もう一方
にはマイナスの電気が帯電する、と習います ...
私は、ここで子供たちには納得して欲しくはないのです。
…電極内にプラスの電気が帯電しているんだったら、そのプラス同士はどうして反発し
合わないんだろう?...と言う疑問を持って欲しいのです。
各原子の原子核は元素毎に「数個の陽子と数個の中性子」から構成されている、と言う
ことは学校で習うので、たぶん小学生でも知っていることだと思います。同時に、電気は
「+と-」は引き合うが、「+」同士や「-」同士は反発する、と言うこともご承知と思
います。
それでは、原子核の中で、どうして同じ「+」同士である複数の陽子や電荷を持たない
中性子が一緒にいられるのでしょうか!?
不思議だとは思いませんか!?
これについて子供たちが疑問すら持たないことは、現在の教育現場の間違いだと私は考え
ています。
この疑問を真剣に考え「π中間子と核力の存在」の予測を理論的に立てたのが日本人初
のノーベル物理学賞受賞者の湯川秀樹さんでした。
π中間子の存在による「核力」を仮定し、原子核の安定に関する理論でした!
アインシュタインの特殊相対論は、マイケルソン・モーリーの実験結果「光速度不変」
とマックスウェルの電磁波方程式とからテンソルという数学的手法を用いて数学的に導き
出した理論ですが、彼は基本的に思考実験に基づいて頭の中で理論を組み立てました。
TV番組「ザ・プロファイラー~天才科学者の栄光と悲劇~アインシュタイン」によれば、
アインシュタインは「従来の科学の常識を疑い」、権威に対する次のような反発があった
とのことです。('19.01.05追記)
①「権威をむやみに尊敬することは真理にとって最大の敵だ」
②「真理や科学的思考が大切なのに、なぜ皆が権威をあがめるのか理解できなかった」
③「知識より大切なのは想像力だ」
(番組出演:ノーベル物理学賞受賞・益川敏英、脳科学者・中野信子ほか)
私自身は、いまだに次のような疑問を持っています...
物理学では、何故ルートの中が負になってはいけないんだろう?
円の半径は何故マイナスであってはいけないんだろう?
そもそも、虚数とは物理学的にはどう言う意味を持つんだろう?...
質量を持った物体同士は万有引力の法則により互いに引き合うが、ニュートンの式は実
験結果と一致していて正しいと考えられるが、では何故!?質量を持った物体同士は引き
合うのだろうか!?
..もっと根本的な古典力学的原理から導き出せるのではないだろうか?
私はこう言うことを日々考えている大馬鹿者です。どうぞ悪しからずご了承くださいませ。
m(__)m
|
【 ノーベル賞:真鍋淑郎さん 記者会見の要旨 】
・2021.10.05 真鍋淑郎(しゅくろう)さんがノーベル物理学賞を受賞しました。
真鍋さんは1931年生まれ、1958年に東京大学大学院の気象学博士課程を修了後、渡米
して米国国籍を取得し、現在はプリンストン大学の上席研究員をされています。
・人間活動が地球に及ぼす影響を早くから予見し、1960年代から気候変動について先駆
的な研究を続け、コンピューターを駆使して、地球の大気全体の流れをシミュレート
する気候数値モデルを開発しました。
・地球温暖化の予測モデルを切り開き、二酸化炭素濃度の上昇が地球の表面温度の上昇
にどうつながるのかを示しました。
・スウェーデン王立科学アカデミーは真鍋さんの功績について、「彼の研究は、現在の
気候モデルの開発の基礎を築きました」と称えています。
・以下、プリンストン大学で行われた会見の一部をご紹介します。
(2021.10.06swing)
<真鍋淑郎さんは、なぜ米国籍にしたのか?>
「おもしろい質問ですね」と答えた真鍋さんは、国籍を変更した理由について、「日本の
人々は、いつもお互いのことを気にしている。調和を重んじる関係性を築くから」と述べ、
以下のように語った。
「日本の人々は、非常に調和を重んじる関係性を築きます。お互いが良い関係を維持する
ためにこれが重要です。他人を気にして、他人を邪魔するようなことは一切やりません」
「だから、日本人に質問をした時、『はい』または『いいえ』という答えが返ってきます
よね。しかし、日本人が『はい』と言うとき、必ずしも『はい』を意味するわけではない
のです。実は『いいえ』を意味している場合がある。なぜなら、他の人を傷つけたくない
からです。とにかく、他人の気に障るようなことをしたくないのです」
その上で、真鍋さんは、「アメリカではやりたいことをできる」と語る。
「アメリカでは、他人の気持ちを気にする必要がありません。私も他人の気持ちを傷つけ
たくはありませんが、私は他の人のことを気にすることが得意ではない。アメリカでの暮
らしは素晴らしいと思っています。おそらく、私のような研究者にとっては。好きな研究
を何でもできるからです」
真鍋さんによると、研究のために使いたいコンピューターはすべて提供されたという。米
国での充実した研究環境や、資金の潤沢さを伺わせました。
最後に、「私はまわりと協調して生きることができない。それが日本に帰りたくない理由
の一つです」と語り、会場の笑いを誘いました。
【 ノーベル賞:本庶佑さん 記者会見の要旨 】
・昨日(2018.10.01)京大・特別教授・本庶佑さんがノーベル医学生理学賞の受賞の報道
がありました。
・本庶佑(ほんじょ たすく)さんの記者会見の要旨がNHK NEWS WEBに掲載されましたが、
参考になると思いますので、ここに全文を転記・掲載します。
・なお本庶先生の研究対象の「PD-1」は、細胞死(アポトーシス)の研究から発見された
たんぱく質だそうで、その命名の源は次の通りです。
Programmed cell Death 1
(2018.10.02swing)
<冒頭の挨拶>
このたびはノーベル医学生理学賞を頂くことになりまして大変名誉なことだと喜んでおり
ます。これはひとえに長いこと苦労してきた共同研究者、学生諸君、さまざまな形で応援
して下さった方々、また、長い間、支えてくれた家族。本当に言い尽くせない多くの人に
感謝しています。
1992年の「PDー1」の発見と、それに続く極めて基礎的な研究が新しいがん免疫療法と
して臨床に応用され、そして、たまにではありますが、この治療法によって重い病気から
回復して元気になった、あなたのおかげだと言われるときがあると、本当に私としては自
分の研究が本当に意味があったということを実感し、何よりもうれしく思っております。
その上に、このような賞を頂き、大変、私は幸運な人間だというふうに思っております。
今後、この免疫療法がこれまで以上に多くのがん患者を救うことになるように、一層、私
自身も、もうしばらく研究を続けたいと思いますし、世界中の多くの研究者がそういう目
標に向かって努力を重ねておりますので、この治療法がさらに発展するようになると期待
しています。
また、今回の、基礎的な研究から臨床につながるような発展ということで受賞できたこと
によって、基礎医学分野の発展が一層加速し、基礎研究に関わる多くの研究者を勇気づけ
るということになれば、私としてはまさに望外の喜びです。
<質疑応答>
▽受賞の連絡は何時ごろ、どんな形で届いたか?そのときの率直な思いは?
確か午後5時前後だったかと思いますが、電話でノーベル財団の私の知っている先生から
電話がありました。ちょっと突然でしたので、大変驚きました。ちょうど私の部屋で若い
人たちと論文の構成について議論しているときでしたので、まさに思いがけない電話であ
りました。もちろん大変うれしく思いましたけども。また、大変驚きました。
▽今後、このがん免疫療法をどのような治療の選択肢として発展させていきたいか?
この治療は、例え話としては、感染症におけるペニシリンというふうな段階でありますか
ら、ますます、これが、効果が広い人に及び、また、効かない人はなぜ効かないのかとい
う研究が必要です。世界中の人がやっていますから、やがてそういうことが、いずれは解
決されて、感染症がほぼ大きな脅威でなくなったのと同じような日が、遅くとも今世紀中
には訪れるという風に思っています。
▽自分が心がけていること、モットーは?
私自身は、研究に関して、何か知りたいという好奇心がある。もう1つは、簡単に信じな
い。それから、よくマスコミの人は、ネイチャー、サイエンスに出ているからどうだ、と
いう話をするが、僕はいつもネイチャー、サイエンスに出ているものの9割はうそで、10
年たったら、残って1割だと思っています。まず、論文とか、書いてあることを信じない。
自分の目で、確信ができるまでやる。それが僕のサイエンスに対する基本的なやり方。つ
まり、自分の頭で考えて、納得できるまでやると言うことです。
賞というのは人が決めることで、それは賞を出すところによっては考え方がいろいろ違う。
ひと言で言うと、私は非常に幸運な人間で、『PD-1』を見つけた時も、これが、がん
につながるとは思えなかったし、それを研究していく過程で、近くに、がん免疫の専門家
がいて、私のような免疫も素人、がんも素人という人間を、非常に正しい方向へ導いてい
ただいたということもあります。それ以外にもたくさんの幸運があって、こういう受賞に
つながったと思っています。
▽がん研究の転機となるような経験は?
『PDー1』の研究でいうならば、最初のこれが、がんに効くということを確信できる実
験というのは、『PDー1』遺伝子が欠失したネズミを使って、がんの増殖が、正常のね
ずみと差が出るかどうかということをやった。それが私はよかったと思います。というの
は抗体で実験していて効かなかったら、ひょっとしたら諦めていたかもしれない。抗体に
はいい抗体と悪い抗体とたくさんあり、それはやってみないとわからない。しかし、遺伝
子がない場合はそういうことは関係ないので、これは必ず効くということを確信できたの
で、それがやはり大きな転機になったと思います。
▽日本の研究の方向性についてどう思うか?また、日本の製薬企業についてどう感じてい
るか?
生命科学というのは、まだ私たちはどういう風なデザインになっているかを十分理解して
いない。AIとか、ロケットをあげるというのはそれなりのデザインがあり、ある目標に
向かって明確なプロジェクトを組むことができる。しかし、生命科学は、ほとんど何も分
かってないところで、デザインを組むこと自身が非常に難しい。その中で応用だけやると、
大きな問題が生じると私は思っています。つまり、何が正しいのか。何が重要なのかわか
らないところで、『この山に向かってみんなで攻めよう』ということはナンセンスで、多
くの人にできるだけ、たくさんの山を踏破して、そこに何があるかをまず理解したうえで、
どの山が本当に重要な山か、ということを調べる。まだそういう段階だと思います。あま
り応用をやるのでなくて、なるべくたくさん、僕はもうちょっとばらまくべきだと思いま
す。ただばらまき方も限度があってね、1億円を1億人にばらまくと全てむだになります
が、1億円を1人の人にあげるのではなくて、せめて10人にやって、10くらいの可能性を
追求した方が、1つに賭けるよりは、ライフサイエンスというのは非常に期待を持てると
思います。もっともっと、たくさんの人にチャンスを与えるべきだと思います。特に若い
人に。
製薬企業に関しては、日本の製薬企業は非常に大きな問題を抱えていると思います。まず、
数が多すぎます。世界中、メジャーという大企業は20とか30くらいですが、日本は1つの
国だけで、創薬をやっているという企業だけで30以上ある。これはどう考えても資本規模、
あらゆる国際的なマネジメント、研究で、非常に劣ることになる。なおかつ、日本のアカ
デミアには、結構いいシーズ=研究の種があるのに、日本のアカデミアよりは外国の研究
所にお金をたくさん出している。これは全く見る目がないと言わざるをえないと思います。
▽研究者を目指す子どもに思ってほしいことは?
研究者になるということにおいていちばん重要なのは、何か知りたいと思うこと、不思議
だなと思う心を大切にすること。教科書に書いてあることを信じない。常に疑いを持って、
本当はどうなってるんだ、という心を大切にする。つまり、自分の目でものを見る。そし
て納得する。そういう若い小中学生にぜひ、研究の道を志してほしい思います。
▽基礎研究を臨床につなげるためのコツは?
基礎研究をやってますが、私自身は医学を志しています。ですから、常に何かの可能性と
して、これが病気の治療とか、診断とかにつながらないかと言うことは常に考えています。
自分の好奇心と、さらに、その発展として、社会への貢献ということは、私の研究の過程
では常に考えてきました。ですから、そういう意味で、新しい発見を特許化したり、そう
いう応用への手順は非常に早い段階からいろんな局面でやってきました。突然、PDー1
は臨床につながりましたが、私の研究マインドとしては、基礎研究をしっかりやって、も
し可能性があれば、社会に還元したいという思いは常にありました。
▽ノーベル賞の受賞は待ちに待ったものか?
賞というはそれぞれの団体とか、それぞれが独自の価値基準で決められることなので、長
いとか待ちに待ったとか、そういうことは僕自身はあまり感じていません。僕はゴルフが
好きなので、ゴルフ場にしょっちゅう行きますが、ゴルフ場に来ている、顔は知っている
けど、あまり知らない人が、ある日、突然やって来て、『あんたの薬のおかげで、自分は
肺がんで、これが最後のラウンドだと思っていたのがよくなって、またゴルフできるんや』
って、そういう話をされると、これ以上の幸せはない。つまり、それはもう自分の人生と
して、生きてきてやってきて、自分の生きた存在として、これほどうれしいことはない。
僕は正直いって、なんの賞をもらうよりも、それで十分だと思っています。
▽ジェームズ・アリソン博士との共同受賞についての受け止めは?
極めて妥当だと思う。彼とは非常に古い交流がありますし、彼の研究と僕の研究とは、非
常に違う局面で、お互いに2つの抗体を組み合わせることで、より強い効果が出るという
ことが知られています。ノーベル財団の評価でもそのことをかなり詳しく説明していたの
で、僕自身としては、ベストな組み合わせではないかと思っています。
▽製薬企業があげた利益を大学などに還元することについて?
今回の研究に関して製薬企業は全く貢献していません。それはもう非常にはっきりしてい
ます。企業側は特許に関して、ライセンスを受けているわけですから、それに関して十分
なリターンを大学に入れてもらいたいと思っています。そのことによって、私の希望とし
ては、京都大学で次世代の研究者がそのリターンを元にした基金に支えられて育っていく。
その中から、また新しいシーズ=研究の種が生まれる。そして、それが日本の製薬企業に
再び帰ってくる。そういうよいウィン=ウィンの関係が望ましいと、製薬企業にも長くお
願いしています。
▽『PDー1』はがんだけではなくさまざまな疾患にも応用が期待されるが、今後の発展
についてどう考えるか?
『PD-1』は免疫のブレーキ役です。現在は免疫を活性化するためにブレーキを外すと
いう形で医薬品として使われているわけですが、逆にブレーキをかけるようにする。『P
Dー1』の本来の役割を強化するという方法で使うことも十分に考えられます。
▽がん研究を志した理由は?
がんで、在学中に同級生が、いわゆるスキルス性の胃がんで、非常に若くしてあっという
間に死んでしまった。非常に優秀な男だったけども、とても気の毒だった。僕だけでなく、
多くの同級生がそれを非常に残念に感じて、なかなか忘れられない思い出です。がんとい
うのは非常に大変な病気だと。それから、そういうことに少しでも貢献できればいいなと、
当時はかすかに思いました。結局、そういう、いろんな事が積み重なって、自分の心の中
にそういう大変な病気に役立つことにつながればいいなと、医学部で医学教育を受けた人
間なら、誰でもそういう心がある。僕はそれが重要だと思う。
▽さらに忙しくなると思いますが、いまいちばんしたいことは?
僕がいちばんやりたいのはゴルフの『エイジシュート』です。僕は76歳ですから、ゴルフ
でスコア76を出すことが最大の目標です。そのための努力は、筋力トレーニングと、毎週、
欠かさずゴルフをして、家でもパターの練習をしています。
▽本庶先生は特別厳しいと学生から聞くが、今後も厳しくやっていく?
他の人と自分を比べていないので、自分が厳しいのか分からないが、真実に対して厳しい
のは当たり前で、間違えではないか厳しく問う、何が真実か問う。研究では、常に世界の
人たちと戦ってきたつもりですから、戦うには厳しくないと戦えないです。
▽以前、高校生向けのシンポジウムで本庶さんが『基礎研究を徹底的にやっているから、
失敗は絶対しない』とおっしゃっていましたが、その考え方はいつごろから?
ことばを間違えて欲しくないのだが、実験の失敗は山ほどあります。しかし、大きな流れ
が進んでいて、『こうだ』と思っていたら断崖絶壁に落ちてしまった、というのはなかっ
たと申し上げた。それは、崖に行く前に気付かないといけないという意味です。サイエン
スというのは、だんだんと積み上がっていくんです。積み上がっていくときに、端と端を
つなぐというのは危ない。この間に、たくさん、互い違いつないでいくことで、その道が
正しいかどうかがわかる。そういうことを申し上げたわけです。(おわり)

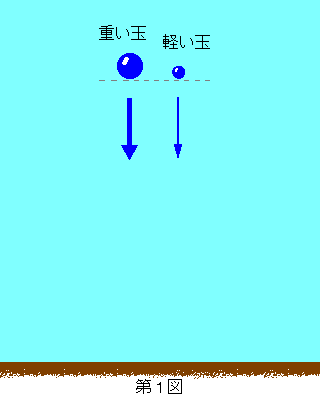 ・ガリレオ・ガリレイは、「物体の落下速度は その物体の重さよらず一定である」とい
うことを証明するために、『ピサの斜塔』から大小二つの鉛の玉を同時に落とし「大
小両方の玉が同時に地面に落下することを確認」することによって ...
「重力による物体の落下速度は、その物体の質量の大きさに依らない」
と言うことを証明(確認)した..と言われています。
・ここで「鉛の玉」を使用したのは「空気の抵抗をできるだけ無視する」ために必要だ
ったからです。
・ガリレオ・ガリレイは、「物体の落下速度は その物体の重さよらず一定である」とい
うことを証明するために、『ピサの斜塔』から大小二つの鉛の玉を同時に落とし「大
小両方の玉が同時に地面に落下することを確認」することによって ...
「重力による物体の落下速度は、その物体の質量の大きさに依らない」
と言うことを証明(確認)した..と言われています。
・ここで「鉛の玉」を使用したのは「空気の抵抗をできるだけ無視する」ために必要だ
ったからです。
・ガリレオ・ガリレイは、「物体の落下速度は その物体の重さよらず一定である」とい うことを証明するために、『ピサの斜塔』から大小二つの鉛の玉を同時に落とし「大 小両方の玉が同時に地面に落下することを確認」することによって ... 「重力による物体の落下速度は、その物体の質量の大きさに依らない」 と言うことを証明(確認)した..と言われています。 ・ここで「鉛の玉」を使用したのは「空気の抵抗をできるだけ無視する」ために必要だ ったからです。
▽思考実験:ステップ-2> 4.次に「第2図-右」のように、二つの玉を「細くて非常に軽い糸で結んでから落 とす」ことを考えます。 5.「細くて非常に軽い糸で結ぶ」ことにより、結ばないで落とした時に比べて落下 速度が変化することが考えられるでしょうか? →細くて非常に軽い糸で結んでも、落下速度は変わらないと考えられますね。 6.では、その結んでいる糸をどんどん短くしていったらどうでしょう? →糸の長さが落下速度に影響を与えるとは、考えられませんね? 7.では「第3図」のように、その糸の長さが「0」になったらどうでしょう? →糸の長さが「0」になった途端に落下速度が変わる、とは考えられませんね? ..勿論、空気の抵抗とかは無視してます。 →長さ「0」の糸で結んだ二つの玉ということは、接着剤で二つをくっ付けて しまったのと同じだし、そうなると形は丸くはないけれど、れっきとした一 個の玉といえますね!?..ただ重さは、別々の時の2倍になりました。
8.と言うことは ... 「玉の重さが2倍になっても落下速度は変わらない」 ..と言うことになりますよね!? ▽思考実験:ステップ-3 9.同じように、3個、4個、5個…と玉の数を増やしても思考実験ができます。 あるいは、逆に1個の玉を2つ、3つ…に分割する実験もしてみることも考えら れます。 →重さを何倍にしても、何分割しても落下速度が同じなら、落下速度に違いが でるはずがない..と想像できますよね? 10.以上のことから「物体の落下速度は物体の重さにはよらない」という結論が得ら れますよね!(^o^) ▽思考実験:応用問題 ・全く同じ手法の思考実験により、 「人口衛星の軌道は速度のみに依り、その重さには依らない」 と言うことも簡単に証明できますので、皆さんやってみて下さい。 ・この場合は、同じ重さで同じところを平行して飛んでいる二つの人口衛星を、「非常 に細くて軽い糸」で結び、その糸の長さを徐々に縮めて行けばいいんですよね。 ・それで、最後に、その糸の長さを「0」にしちゃえば、OKです。 簡単に証明できますね。(^o^) ・二人が各々一本の矢を放っても、一本の時の倍にはならず、速さが変わることはあり ません。100mを10秒で走る走者が二人同時に走っても、記録は半分の5秒にはなりま せん。 ・だけど、例えば、100mの間に落ちているゴミを10秒で拾うことができる人が二人いた として、その作業を二人で同時にやったら、作業時間は半分の5秒でできますね。 ..何がどう違うんでしょう?..あとは皆さんで考えてくださいね。(^^)