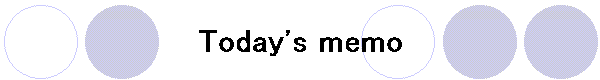2足の草鞋
このサイトを、2年の長きにわたって放置している間に、わたし自身の状況もいろいろかわってしまいました。
そもそも、更新できなくなってしまったのは、勤務と開業という2足の草鞋に、時間的に耐え切れなかったということなんですが、さらに行政書士と社労士という2足も、ここらあたりで解消しようかという気になりました。
このサイトを開設した当時、ちょうど韓国の国籍法改正がありました。わたし自身が在日であり、日本人の夫との間に子供がいることから、勉強会などにもでかけ、わずかばかりですが、その成果が役に立つことがあれば、とサイト上にまとめてみたりしました。それが「Topics」というコンテンツです。当時は、社労士のかたわら、渉外関係の行政書士として活動していこうというこころづもりでした。
しかしながら、家庭と仕事という2足だけでも、毎日の生活を切り抜けるのに必死な中で、とてもふたつの分野の勉強をすることはできず、このサイト同様、行政書士としての勉強も放置状態でした。「李」という名前で電話帳に行政書士として広告を出していたので、仕事の依頼も何件かいただきましたが、すべて、ほかの行政書士さんにお願いしてしまいました。というわけで、いまだに仕事の実績はゼロのままです。
ということで、長々とひっぱってしまいましたが、やっと社労士1本でやっていく決意をいたしました。たまたまBBSのほうに、渉外関係のご質問をいただいたことでもあり、サイト上でも表明しておいたほうがいいだろうと考えた次第です。
9月末をもって、行政書士は廃業いたします。いままでいろいろご教示、ご助力いただいたみなさまには、心からお礼を申し上げます。これからは、社労士としての勉強にいっそう身を入れたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。
2002/09/24

お知らせ
長らく停止していましたが、BBSを再開しました。みなさまの交流を目的として、お気軽に書き込んでいただければ幸いです。以前に増してのご愛顧をよろしくお願いいたします。
2002/09/23

雇用保険料率変更
この10月より、雇用保険料率が変更になります。(→厚生労働省よりのお知らせ)
仕事で職安に行くと、求職者でいつもあふれていて、駐車場に入るのも20分待ち、という状況ですから、雇用保険財政が逼迫している、ということは実感としてわかります。しかしながら、年度の途中での料率変更で、しかも変更のお知らせのチラシは職安や監督署の窓口においてあるだけ、事業所への変更通知は、12月になってから、いきなり納付額を送りつける、というやり方は、さすがにどうかと思ってしまいます。社労士の関与していない多くの事業所では、12月になって初めて料率の変更を知り、さかのぼって給与から差額を控除する、という手間をかけるところが多いのではないでしょうか。
しかも、12月に郵送による告知、1月に納付書送付ということですから、役所のほうでも二度手間であり、郵送料や事務にかかる費用などもばかにできないものになるでしょう。事業所によっては、値上げ分の差額が数百円ということもあるでしょうから、振込手数料のほうが高くなってしまいます。
足りなくなれば安易に値上げ、というやり方はいつものことですが、この稚拙で無駄の多い行政のやり方を見ていると、まったくため息をつきたくなります。
事業主の皆様、事務担当者の皆様には、10月からの定時決定にともなう社会保険料の変更とともに、雇用保険料率の変更も、お忘れないよう、お気をつけください。
お知らせ
長らく停止していましたが、BBSを再開しました。みなさまの交流を目的として、雑談、質問など、お気軽に書き込んでいただければ幸いです。以前に増してのご愛顧をよろしくお願いいたします。
2002/09/23

1周年のごあいさつ
8月26日をもって、このサイトも1周年を迎えました。
そして、1周年を2週間ほどすぎた9月10日に、このページのカウンタも1万ヒットを超えました。
このサイトを作った動機は、「いまどき、パソコンできます、というのにホームページもないなんてヘンだし、営業用に簡単に作っとこうか」というアリバイ的なもので、正直言って、これほどあちこちでリンクしていただき、たくさんの方に応援してもらえるページになるとは思っていませんでした。このサイトを育ててくれたのは、訪れてくれたみなさまひとりひとりです。心からお礼申し上げます。
とりあえず、現在リンクページの更新作業をしております。新しく加えたサイトで、まだコメントが入ってないところが多数ありますが、とりあえず見切り発車で公開してしまいます。読み応えのあるサイトばかりですので、ぜひ一度ご覧ください。
きょうは、シドニーオリンピックの開会式があります。ふたつに分かれているわたしの祖国は、統一旗の下に合同で入場行進を行います。それ自体は、単なる政治的ショーかもしれないし、わたし自身、オリンピックというものにさほどの思い入れはありませんが、どんなことでも、できることはすべて統一という最終的な目的に向かって、動いていかなければならない、との思いを強くしています。
まず夢を見なければ、それは決して現実にはなりません。
ひとりの職業人として、役に立つ専門家になりたいというわたし個人の夢、南北統一という大きな夢、そのどちらもが大きく動き出したこの1年を思いながら、さらに、新しい1年を、夢を暖めながら過ごしていこうと思います。
これからもどうぞよろしくお願い申し上げます。
2000/9/15
お知らせ
現在、お返事をする時間的余裕がとれないため、BBSを停止中です。荒らされたりしたわけではありませんので、ご心配なく。書き込みはできませんが、上のメニューから入っていただければ、ログは読めます。勝手ながら、ご了承のほどお願い申し上げます。
2001/1/11

質問の受けとめ方
こんな会話がありました。お相手は、顧問先の社長さんです。
社長 「社員が結婚したり子どもできたりしたら、休みはどのくらいやればいいのかね?」
わたし 「(就業規則の休暇規定の話かな?)法律的には、とくに決まっていないんですよ。会社の事情に合わせて、お決めになればいいということですよね」
社長 「出産のときもかい?」
わたし 「(産休の話かな?)出産なさるのは、社員さんですか? それとも奥さんですか? 社員さんご本人の出産でしたら、産休の期間は産前6週、産後8週と決まってますけど」
社長 「社員本人じゃないんだけど。子ども生まれると、3ヶ月とか6ヶ月とか休みをやらないといけないんじゃないの?」
わたし 「(6ヶ月?? あ、そうか)・・・ひょっとして、育児休業のお話でしょうか?」
社長 「そう、それ。それは有給で休みやるのかね? 期間は決まってるんでしょ?」
わたし 「育児休業は、ご本人が希望を出せば、お子さんが1歳になるまでとれるんですけど、有給でなければならない、という規定はないんですよ。ただ、雇用保険のほうから、お給料の2割が出て、仕事に復帰してから、さらに 5%出ることになってます。会社のほうから多少出すとしても、お給料の6割を超えちゃうと、この給付が減らされたり出なくなっちゃうんで、もし出すとしたら、6割までの範囲内のほうがいいでしょうね。もちろん、無給でもかまいませんし」
社長 「必ず休みにするってもんでもないわけだね」
わたし 「そうです。本人からの申し出があれば、ということですね。どなたか、男性で育児休業したいということを言ってる方がおられるんですか?」
社長 「いやいや、そういうわけじゃなくて。若いもんを入れたんで、どうなってるんかと思ってね」
わたし 「そうですかー。」
だらだらと書きましたが、お客様と話をしていると、相手がなにについて質問したいのか、それをつかむまで時間がかかってしまうということがよくあります。たとえば、出産・育児にかかわるものだけでも、いくつもの給付やそれにかかわる規定があり、質問するお客様のほうは、制度の正確な呼び方など、ご存じないのがふつうだからです。
なにについての質問なのかわかれば、こちらも専門家なのでそれについて説明するのはむずかしくないのですが、相手の知りたいことを的確につかむのは、単に知識だけですむ問題でもないようです。
このあたりにも、この仕事のむずかしさ、おもしろさがあると感じます。
2000/5/20

介護保険料
社会保険事務所、職安などの窓口の混雑も一段落ついた感じです。さすがに、監督署だけは新年度だからといって、格別混んでいるということはありませんでした。
いま、社労士事務所はどこでも、労働保険の年度更新で繁忙期です。今年はさらに介護保険への対応が加わっています。
具体的には、顧問先に健康保険料の変更の通知をする、給与計算をしている事業所については、全員の年齢を確認して、保険料変更の作業をする、ということです。さらに、お客様からの電話での問い合わせに答える、という仕事もあります。
介護保険なのに、なんで健康保険の保険料の変更? と思われるでしょうが、介護保険料は、40歳以上の健康保険加入者については、現在の保険料に1000分の6(事業主、被保険者折半でそれぞれ1000分の3ずつ)をプラスして徴収されます。
最近、社会保険事務所からそれぞれの事業所に送られた通知には、1000分の6の金額が書いてあって、実際いくらお給料から控除すればいいのか、という説明がどうも不十分で、読んだ社長さんや担当者が混乱しているようです。その通知の実物はまだ見ていなくて、電話での問い合わせの内容からの想像ですが。
さらに、40歳以上かどうか、というのは、月ごとに判断されます。つまり、毎月、従業員の中に今月40歳の誕生日を迎える人がいないかどうか確認し、該当者があれば、健康保険料を変更しなければなりません。
いままでも、65歳になれば厚生年金の被保険者資格がなくなり、保険料の控除は健康保険だけになる、ということはあって、年齢の判断は月ごとになされるので作業自体は同じなのですが、65歳と40歳では、該当者の数が大違いで、担当者の負担感は相当なものだと思います。もちろん、パソコンで、データベース、表計算などのソフトを使って管理していればたいした手間ではないのですが、専用のアプリケーションを使っていても、社員情報の管理は紙ベースという会社は珍しくないでしょう。
給与計算というのは、税や公的保険の知識を要求される、なかなか複雑な作業なのですが、さらに複雑さが増してしまいました。ここは専門家の出番でしょう、というのは、ちょっと手前味噌ですか。
2000/4/25

勤務と開業
花粉症のわたしにとって、一番苦しい時期も終わり、だんだん元気が出てきました。
突然思いついて、このサイトのグラフィックも模様替え。さわやかなイメージを狙ったのですが、いかがでしょうか。
ご報告が遅れましたが、1ヶ月ほど前から、社労士事務所に勤務しています。といっても、勤務社労士に変更したわけではなく、現在の顧問先の仕事はそのままさせていただいています。
社労士事務所に勤務して経験を積んだ後、独立開業、というのが理想的なのでしょうが、実際はそういう勤め口は少なく、不安を抱えながら開業する人が多い中、順序は前後しましたが、このような機会を得たのは、とてもラッキーなことだと思っています。いままでと比べて、時間的にはかなり厳しいですが、徐々にペースもつかめてきました。
なにごとも勉強、というと、いかにもきれいごとのようですが、今回のように「修行」という意味合いが大きい勤め口でなくても、いままでの仕事はすべて、現在の自分の基礎になっていると思います。パソコンの使い方ひとつにしても、お給料をいただきながら、会社の経費で参考書なども買ってもらい、しっかりと勉強しました。なにより、実際の仕事の中で出てくるひとつひとつの課題をこなす、ということ自体が、実践的な勉強でした。漫然と言われたことをやるのではなく、将来のために身につけられることはすべて身に付けよう、と貪欲になることが、その時点での仕事にも役立ってきました。
ただ、そういう考えで勤めていると、「この仕事を続けていて、これ以上学ぶものはない」と思った時点で、仕事自体が苦しくなってしまうという弊害はあります。その判断自体、自分の実力をきちんと評価できる力がないと、ただの思い上がりでしかないこともあります。また、ほかの問題があってやめたくなっているのを、「学ぶものがない」という、一見前向きな理由に転化してしまうという危険性もはらんでいます。このあたりに気づくかどうかというのも、やはり、実力のうちでしょうか。
わたしの場合は、上に書いたようなことをあまりきちんと分析するまもなく、個人的な転機がそのまま開業につながったという感じですが。
勤めだしたばかりで、「辞め時はむずかしい」なんて考えているのもヘンな話ですが、ずっと勤務する気がない以上、やはり考えておかねばならないことでしょう。勉強にこれでいい、ということはないけれど、どこかで区切りをつけなければなりません。
社労士をめざして勉強している方と、どこか通じる課題を抱えてしまったというわけですね。とりあえず今は、1年たったら、一度考えてみよう、と思っています。