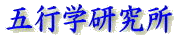
五行図による安田式四柱推命学(五行推命)に関する情報サイト
| 四柱推命学の歴史 |
| 四柱推命学の基本である、干支(天干・地支)は既に紀元前の夏代~殷代(BC2050~1050頃)に既に使用されていた事実が認められていますし、占術としても干支が使用されていまいしたが、生年月日の干支から、人の命運を占断する四柱推命学の基を始めて作ったのは、中国・唐代の大夫李虚中であると言われています。李虚中の死後、唐代の著名な大学者であった韓愈(昌黎韓公、786~824)が李虚中の業績を讃える墓誌(『殿中侍御史李君墓志銘』)を作って記念としました。後に呂大夫がこの法を受け継ぎます。 そして五代宋初の徐子平が、人の生まれ日を主として六事に分かち、議論精微を尽くし、李虚中の年月日に時刻を加えて四柱八字として、今日の四柱推命学の原型を完成させました。後の人々はこの中興の祖と言うべき徐子平の功績を讃えて、四柱推命学のことを「子平学」又は「子平の法」などと呼んでいます。徐子平によって宋代には四柱推命学は知識人を初め一般にも信奉者が増えて行くことになります。徐子平の功績は①生日を中心とする推命、②時刻の干支を加えて四柱とした事、と言えると思われます。その後に、同じく宋代の徐升が徐子平の法を研究し、その成果を踏まえて『淵海子平』の書を著しました。この書が今日の四柱推命学の原典とされています。 その後、中国では元・明・清の時代でそれぞれ推命学は発展と隆盛を続けて行きます。特に明代の推命学は量質ともに、最も優れた研究成果を残していると言えるでしょう。明代のものとして今日よく研究の対象となっている書籍は、明初の重臣であった劉伯温の編とされる『滴天髄』、沈孝瞻の『子平眞詮』、万育吾の『三命通会』、張楠の『神峰通考』等があります。 日本に初めて四柱推命学が翻訳紹介されたのは、江戸時代に入ってからのことで、仙台藩の儒学者・桜田虎門が文政元年(1818)に『推命書』を著したのが初めとされています。滝沢(曲亭)馬琴の随筆などで、以前から中国に「八字」「禄命家」などの、生年月日の干支で占う占術が、中国で流行していたことは、日本でも知られていたようです。 その後、明治・大正・昭和期に、阿部泰山、高木乗、松本義亮、伊藤耕月、板井祖山、朝田啓郷等の多くの研究者が現れ今日の四柱推命学の基礎が築かれます。特に西の阿部泰山、東の高木乗と言われた両氏の功績は大きいと思われます。 四柱推命学の代表的な中国の古典としては、『淵海子平』『子平真詮』『三命通会』『玉照神成真経』『滴天髄』『窮通宝鑑』『神峯通考』『星平会海』等があります。その中でも特に重要視されているものは『淵海子平』『三命通会』『滴天髄』で、これを三書と呼んで、四柱推命学の原典とされています。 現在主流的な立場に立っている泰山流では蔵干を中心に判断がなされていますが、高木乗は五行を中心に判断していましたし、又両氏は大運の出し方等に違いが見られます。(泰山派は十年運、高木乗派は各年運) また、高木乗は天徳貴人を重要視し、今まで吉凶星(神殺)の一つでしかなかった天徳貴人を天佑神助の星として掘起したことは高木乗の功績の一つであろうと思われます。このことを故・朝田啓郷氏などは「子平以後の大発見」と評価しています。 近年では、日本的な推命の他に、近代中国から直輸入された推命も紹介されるようになりました。従来、長く主流を占めていた泰山系の推命が、月律分野蔵干を主としていたのに対して、地支の蔵干全てを列挙し、天干に透干している干を重んじて、月令の得失から五行のバランスを数値化し、格局と用神を求める方法が中国流として紹介されています。 ただ、泰山系にしろ、中国流にしろ、天干よりも地支を重んじるという点においては同類です。初代高木乗も、昭和初期は従来の推命の方法論を踏襲していましたが、幾多の研究の結果、地支よりも天干を重んずべしとの創見を見出し、更には神殺などよりも五行のバランスによって判断すべしとの推命に転換をするようになりました。これが、昭和の天才・高木乗による推命の革新であったのです。残念ながら、初代が生前から嘆いていたように、二代目は何とか命脈を保ってはいたものの、初代程の才能には恵まれず、推命の世界でも評価は高くありませんでした。 初代・高木乗に親しく師事し、その法を受け継がれた五星術実践研究会の会長・安田靖先生は、高木乗流をより発展させ、秘伝的でもあった五行による推命学を近代的に整備され、「安田式・五行図」を用いることで分かりやすく、且つ的中率の高いものとして確立されました。又豊富な鑑定データをもとにコンピュータで統計を取り、その結果を元に従来の四柱推命学を整理されています。そして1972年(昭和47)に日本推命学研究会(NSK)を創始され、この五気五行を中心とした近代的な四柱推命学の研究と普及に努められて来られました。(この「近代的な」と言うのは、神殺や空亡などの枝葉的な部分を極力排除して、よりシンプルなものにされたという意味です。) また、昨年(2006年末)を以って、日本推命学研究会はその使命を終え、新しい時代の要請に答えるべく、安田会長の元、2007年より「五星術実践研究会」が発足しています。 |
2007/03/02更新