 |
051029: というわけで、パンク修理タイヤ交換ネター。 HANDY使ってて何が困るかというと、 へにょいタイヤのパンク…ですよね? HANDYのタイヤは、文字どおり HANDYのアキレス腱なわけで、 この弱点さえ何とか克服できれば 運用しやすくなると思う。 要するにあれだ、自分でタイヤ交換できたら、 パンクはそんなに怖くない。 とりあえず、HANDYBIKE関係検索すると、 パンクしたときのタイヤ交換が 大変とか耳にするので、 ちょっとその辺考えてみようかと。 少なくとも、純正タイヤなら 脱着はそんな大変じゃないです。多分。 結局はコツとかノウハウの問題だと思うので、 そのへんシェアして、全日本のHANDY稼働率を あげようという寸法。スケールでかいぜ! |
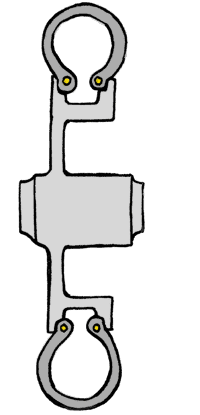 |
それではまず、タイヤの構造とか。 かなり適当な断面図ですが。 ホントはタイヤの内側にチューブがありますな。 この絵はアレだ、HANDY本で 使うつもりだった絵ですよ。 間に合わなかった!ふがいない! ここでミソなのは ホイール(リム)内部の形状です。 二段凹字型というか、 ビードが乗ってる部分より、中央部は 溝のように一段深くなっています。 さて、タイヤ交換ですが、 通常はタイヤレバーなる工具を 使用することと思います。 しかしこれが落とし穴と言うかなんというか。 タイヤのフチ(ビード)の中には ビードワイヤというものが入ってて、 (左図で黄色に塗ってある部分) そもそもコイツが鉄で出来てて伸びないので、 力づくで嵌めるのがそもそも無理っぽい。 さらに、タイヤ径が小さすぎるので タイヤレバーの入る余地が無い、 なので、レバーを使って無理やり入れるのは そもそも無理があるんじゃないかと。 |
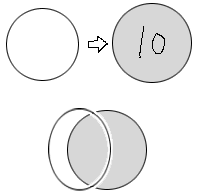 |
例えば1円玉サイズの輪と、10円玉があったとします。 1円玉サイズの輪の中に 10円玉をくぐらせるにはどうするか? 輪を楕円に変形させて、長径で10円玉をくぐらせる。 これを念頭においてみてください。 |
 |
そんなカンジで とりあえずはじめましょう。 まず、バルブのキャップを外し、 中央の突起を押して チューブ内の空気を抜きます。 パンクしてたら抜く必要ないですね。 でもって、写真のごとくバルブを押し込む。 |
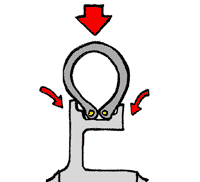 |
で、図のごとく、 タイヤをつぶして ビードをリムの溝に落とし(押し込み)ます。 多分ここがポイントだと思う。 |
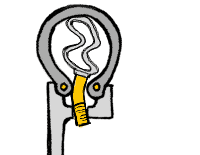 |
ちなみに、通常タイヤ外すときは バルブ側のビードをリム内に落とし、 バルブと反対側から外すのが定石と思います。 しかしHANDYBIKEの場合は、 図のようにバルブが邪魔をして ビードが落ちづらくなるので、 バルブ側のビードを落とすのは 避けても良いかもしれない。気がする。 |
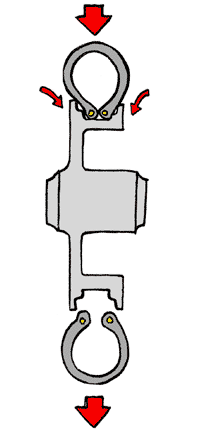 |
きっちりビードをリムの溝に落とすと、 反対側が浮き上がって、 ビードがリムの上まで上がってくる。 |
 |
ので、ここでタイヤレバー登場。 浮き上がったB側にレバーを突っ込みます。 ちなみに、こっち側の面から外したほうが、 外しやすいです。 向こう側に指突っ込んだ状態で タイヤをわしづかみにして、 A側でビードをリム内に 落とした(押し込んだ)状態で保持しやすい。 |
 |
B側をレバーでこじって ビードをリムの外へ外していきます。 なおかつA側のビードが ちゃんと落ちた(押し込まれた)状態になるよう、 A側を矢印方向へ押し込みます。 二本目のレバーを使用して、 ビードを外へ出していきます。 |
 |
ビードがこの位リムの外に出たら、 A側&B側から両手でタイヤを 中心方向へ押さえつつタイヤレバー外して、 ここから素手で作業。 A側をきっちり握って、 ビードをちゃんと落とした (押し込んだ)状態にしておかないと、 リムの外に出した部分がすぐに戻って 元の木阿弥に。 |
 |
写真のごとく、両側から中央に押して タイヤを楕円に変形させ、ビードを外していきます。 左手はビードをリム内に落とした状態で保持、 右手でタイヤを楕円につぶしつつ外していく。 |
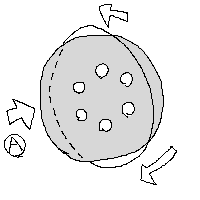 |
こんなカンジ。 1円玉サイズの輪を 10円玉に通す〜。 |
 |
ぐいぐい。どんどん外して行きます。 |
 |
ここまでくれば後は簡単。 片側のビードが外れました。 060918: もうちょっと簡単な取り方思いつきました。 『タイヤ交換のコツその2とパンク原因の考察』 参照してください。 |
 |
リムを奥に押し込んで、 もう片方のビードも外します。 素手で簡単に外せます。 というわけで外し工程完了。 |
 |
ちなみに今回は ここんとこにアナ開いてました。 空気入れるときとかに グリグリしたのが原因か。 |
 |
オマケ。もうなんつうか。 金属!ピカピカ!かっこいい! |
 |
ひとしきりニヤニヤしたところで、タイヤ装着。 今をときめくKAHENSHIKI KOMAのタイヤです。 MAXXISのロゴ入ってるけど、 CST(Cheng Shin Tire)のマークもモールドされており、 OEM製品と思われる。 純正より、肉厚で成型精度もよく、 かなり頑丈だとおもわれるが、 頑丈ゆえにやたら硬くて リムに嵌めるのに一苦労という代物。 まずタイヤの中にチューブを収める。 純正タイヤなどタイヤの回転方向に 指定がある場合は、バルブの向きに注意。 |
 |
バルブをリムの穴に通します。 ここもタイヤの回転方向に注意。 |
 |
まず、外したときと逆の要領で、 片側のビードをはめる。 |
 |
そんでもって、もう片方のビードもはめる。 ちなみに、写真下側に写ってるのは足の裏です。 あぐらかいて作業してます。 お目汚し失礼ー。 |
 |
もう力任せというか…。 すんません。必死ではめ込んでたので ちゃんと写真撮ってない…。 っつうか、両手ふさがってて写真撮りづらいのなんの。 |
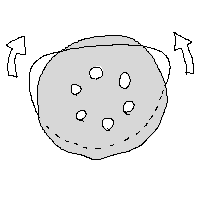 |
左右に押し広げつつタイヤを楕円に伸ばし、、 どこか一箇所、ビードをリム内側にはめ込んだら そこを基点に押し込んでいきます。 わかりづらいなー。 |
 |
ここまで入ったら一段落。 |
 |
入りました。 ただし、軽く空気を入れて(1気圧くらいかな) 回転させてみると、 少々偏芯して装着されているのがわかります。 |
 |
ビードのちょっと外側に ラインがモールドされているのですが、 タイヤを回転させたときにこの線がふらつかないよう、 均等にビードがリムに収まるように、 出っ張ってるところは押し込んだり、 入りすぎてるところは引っ張り出したり、 全周をゴムハンマー(100円均一で入手)で コンコン叩いたりして調整します。 まあ、均等にするのも限度があるので 適当なところであきらめます。 空気はゆっくりと入れ、 気圧低めで少し慣らし運転してから 規定圧まで上げると良いみたい。 |
 |
タイヤレバーは 外しの取っ掛かりを作るためだけに使用します。 金属製のはホイールに傷がつくので 避けた方がよいでしょう。 これはPanasonicのタイヤレバーです。 断面形状がなんだか良さそうなんでこれにしました。 角っこちょっと落としてあります。 使ってると時々へしおれそうになりますが 折れないです。意外と丈夫なのか? |
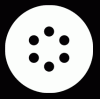 |
とりあえずそんなカンジでタイヤ交換の巻でした。 なんかアドバイスあったら メールいただけるとうれしいです。 パンク対処の手段として、 1.パンクしにくくする。 2.パンクしてもすぐ修理できるようにする。 3.パンクしたら家に帰って修理する。 1に対しては 1-A.より頑丈なタイヤへの交換 1-B.ノーパンク加工 2に対しては 2-A.タイヤ装着済みの交換用ホイールを持ち歩く 2-B.スペアタイヤとポンプを持ち歩く 3は、まあ、そのまんま。 というわけで、タイヤ交換さえできれば 1-B.以外は自分で対応できるので、 まあちょっとはパンク怖くなくなるんじゃないでしょうか? ちなみに自分は、遠出するときは ポンプ・チューブ・タイヤ・ 15mmレンチ・タイヤレバーの 一式持ち歩いてます。 そうそう、ポンプ持ってると パンクしないらしいですよ(笑)。 |