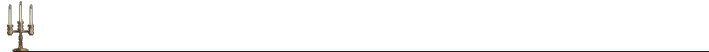はてしなく青い空 前編
やっと、今日の全講義が終わった。我先にと帰りを急ぐ学生たちの押し合いへし合いが一段落するのを待ってから、僕は教室を後にした。
屋外へ出、吐く息の白さに思わず顔を顰めた。盆地である京都の冷え込みは相当なものだ。大阪に比べ気温が3度違うという表現も決してオーバーな物言いではない。
さっさとキャンパスを横切り、烏丸通を越えた先にある学生会館へ向かった。総勢僅か四名という弱小サークル、英都大学推理小説研究会が部室代わりに利用している2階のラウンジへ行くためだ。
入口からヒョイと覗きこんだ途端、こちらを向いていた部長の江神さんと目が合った。煙草を挟んだ右手を上げ、合図してくる。彼と対面に座っている織田や望月も振り返って、僕の姿を確認したようだ。
小さくお辞儀を返してから、我が部の指定席ともいえる最奥のテーブルに近づいた。
江神さんがその長身を窓側へ移動させた。隣に腰を下ろすないなや、向か合うかたちになった織田が聞いてきた。
「どや、バレンタインはチョコ貰えそうか?」
いきなりそう切り出されて、面食らった。しかし、折りしも2月に入ったばかりの今日この頃、そろそろ気になりだすイベントには違いないと思い直す。付近のお菓子屋やコンビニの店頭はもちろん、生協の購買部になされていたそれらしきディスプレイの記憶も頭の中に蘇ってくる。
とはいえ、今の僕に彼女はいないし、誰かから想われているような心当たりも無い。見知らぬ相手から告白される可能性をゼロとは決め付けられないが、そんな劇的な展開などまず起こらぬものだ。男を19年もやっていれば、経験値から妥当な未来を予測するようにもなる。せいぜいが義理チョコ、よくノートの貸し借りをし合う女友達から貰えでもすれば万々歳というところか。
「まぁ、貰えても義理チョコくらいでしょうねぇ」
僕が答えると、
「なんや、不甲斐ない」
織田はつまらなそうな顔をした。続いて、望月がわざとらしく肩を落とす。
「頼みの綱はアリスだけやったのになぁ・・・アテが外れてしもうたか」
はて。一体、何を『アテ』にしていたのだろうか。先輩コンビを横目に見ながら長老こと江神さんの方へ顔を向けた。おそらく僕の表情そのものがクエスチョンマークと化していたのだろう。部長は直前まで交わしていた会話の内容を淡々と説明し始めた。
「去年、ここにおる三人が三人共義理チョコしか貰えんかったんやけど―――まぁ、その・・・義理やから手近なところで調達したってのがよう判るもんばかりやってなぁ」
そこいらで簡単に買える板チョコ一枚とかチョコレート菓子一箱とか。先輩たちの元へ集まったのはありがたみも珍しさもあまり感じられないようなものだったようだ。まぁ、義理チョコだからそうなる訳で、これが本命チョコなら間違ってもそんなことは有り得ない。ちょっとランクが上のチョコレートを用意したり、腕に自信のある女性なら手作りもするだろう。そんな話から、大学生活初のバレンタインシーズンを経験するEMC期待の新人有栖川有栖がどこぞからそれなりの本命チョコを貰って来るかもしれない―――と、こうなった。
まさに他愛ない雑談ではある。いや、放談というべきか。すっかり脱力したものの、少々引っ掛かりを感じたので、
「なるほど、話の流れはよう判りました。けど、仮に僕が本命チョコもろてきたとして、それが信長さんたちに何か関係するんですか?」
と、訊いてみる。
織田が臆面もなく言った。
「そりゃ、味見させてもらおうかと―――」
へ?
「つまりな、幸せは一人占めしたらあかんのや。『お裾分け』っちゅう言葉があるやろ?」
呆れた。後輩にそんな期待をかけること自体どうかと思うが、貰った本命チョコを分けてもらおうという発想の方もどうかしている。
本来、女性が恋する男性に告白の意をこめてチョコレートを贈るというのがバレンタイン・デイなのではないか。大量のチョコレートを貰うほどにモテる奴は別として、そもそも本命チョコとはたった一人からしか贈られないものだ。しかも本当に好きな子から貰ったものだとしたら人へ分けたりしたくない。いくら甘いものが苦手な男でも、それくらいは自分の胃へ納めるだろう。
唖然呆然。返す言葉に窮していると、江神さんがこちらを覗き込んできた。
「まぁ、意中の相手から貰うた本命チョコなら一人占めしたいのが普通の心理やろうとは思う。けど、貰った本人からみて、それほどでもない本命チョコやったら、分けてもろうてもええんやないか・・・ということや。たまにはポッキーやきのこの山といった義理以外のものも食うてみたいと思うやないか」
そう言われてみると、気持ちとしては判らないでもない。なんとなく納得もする。
「そうそう。俺らはバイト先やクラスメイトから貰う義理に縋るしかないから、アリスに望みをかけたっちゅう訳や」
ぼりぼりと耳の裏を掻きつつ、短髪の先輩が付け加えた。
しかし、そう言われたところで、どうにかなる訳ではない。期待するのは勝手だけれど、こっちの事情も察してほしいものだ。
「そんな、無理ですよ―――夏にフラれたばかりやし、そう、すぐに次が見つかる訳ないやないですか」
敢えて古傷を曝け出した。望月が考え込むような表情で言う。
「あぁ、そういえばそんなこともあったな。あれは残念やった。もし理代と上手くいっておったら、神戸のスィートなチョコレートが貰えたかもしれんのに」
「アホ、言ってええことと悪いことがあるやろ」
バシッと音を立てて織田が相方の頭を叩く。言った本人も慌てて口に手をあてた。「すまん」と頭を下げた望月へ、
「ええですって・・・ほんまに、もう気にしてませんから。大体、引き摺ってたら、自分で言うたりせえへんですよ」
と返した。
気まずい沈黙が訪れそうになったその瞬間、二つ向うのテーブルで華やかな嬌声が上がった。EPAこと英都大学プロレス協会の連中が取り巻きの女の子たちと雑談に興じているようだ。
とってつけたような動作で振り返り、その様子を見ていた織田が大きく溜息を吐いた。
「やれやれ、こういう時に男所帯のわびしさを感じるな・・・まぁ、推理小説研究会じゃ学生作家としてデビューでもせん限り、ファンはつかへんやろうけど」
再びこちらへ向き直った先輩は、真正面から僕を見た。目が据わっている。
「アリス。なんで、お前は男なんや」
はぁ?
絶句した。困惑気味に江神さんの方を見遣ると、苦笑している様が見て取れた。
「せめて推理研にも可愛い女子部員がおったら良ったのになぁ。そしたら義理チョコにしたって少しはマシなもんが貰える可能性が高くなるやんか」
あぁ、そういうことですか。今年度の新入部員が野郎一人で悪かったですね。
しかし、仮に僕が女だったとしても、告白するつもりの本命もしくは交際相手以外へは然程注意を払わないと思う。義理でしかないものにあまり金をかけたくないではないか。個人差はあれど、女性はそういう点に於いて我々男性よりもシビアな金銭感覚を持ち合わせているような気がする。
こっそり溜息を吐いた後、僕は言葉を選びながら反論した。
「あのぅ、それ、随分と都合のいい想像やないかと思うんですけど・・・後輩から先輩に渡すいうても、義理チョコは義理チョコでしょう。それなりのもんしか貰えないんやないですか?」
「アリス・・・お前、相変らずキツいこと言うなぁ」と望月。
「義理は義理でも、日頃世話になってる先輩相手やったら、多少、奮発してくれるかもしれないやろう」
そう食い下がってきた銀縁眼鏡の先輩は、さっきからこのやり取りを静聴していたひとへ同意を求めるような視線を泳がせる。
「さぁて、どうやろな。うちに女子部員がおったとしても、貰えるかどうかは、日頃の行いや先輩としての指導がものを言うんやないか?」
江神さんは悪戯っぽい表情でそう言うと、キャビンに火を点けた。賢者の部長からごく一般的な見解を示されて漸く、向かいの二人も大人しくなった。
テーブルの上方へゆるく紫煙が立ち昇ってゆく。会話が途切れたこともあり、皆して漂う靄の行く末を無言で追いかける。
暫くして望月が口を開いた。
「江神さん、今年も断るんですか?」
―――?
質問の意味が判らない。隣の様子を窺うと、もの静かな部長は微かに頷いたようだった。
織田がやや大仰に伸びをしながら言った。
「全く―――江神さんは本命チョコやと受け取らんからなぁ」
「え・・・? どういうことですか?」
思わず聞き返してしまった。身体中の気が、なぜかざわざわと騒ぎ始める。それを宥めすかすつもりで、膝上に置いていた手を丸め、拳へ変えた。
「本命受け取るんやったら、そのつもりでおらなあかん―――言うて、そういうのは全部断るんや、部長は」
僕にそう説明した織田は少し身体をずらし、長閑に煙をくゆらすひとへ目を向けた。
「バレンタインは告白される日で、返事はひと月後でしょう。貰うだけもろたらええと思うんですけど」
「こっちにその気が無い以上、真剣な相手をひと月も待たせたら、あかんやろ。最初に断った方が良心的やないか」
江神さんが柔らかい声音で諭すように答えた。このひとらしい科白だ。なんだか少しホッとする。
短くなった煙草を丁寧に灰皿へ押し付けた後、部長はゆっくりと言った。
「義理チョコやろうが本命チョコやろうが、好きな相手から貰えんかったら意味ないわ」
どきん。
心臓が大きく脈を打った。
「なんやイミシンな発言やなぁ。江神さん、もしかして『ええなぁ』と思うとるような娘がいてはるんですか?」
望月が訊ねる。口調に茶化しているような色は感じられない。純粋な好奇心から聞いているらしかった。
沸騰寸前の意識を抑えようとして、更に強く掌を握り込んだ。
何を慌てているんだ、僕は。落ち着け。江神さんだって気になる女性の一人や二人、いて当然だろう。
不自然にならないよう気をつけて隣へ顔を向けた途端、目が合ってしまった。淡い笑顔が僕の視界に飛び込んでくる。このひとのこういう表情は本当に素敵で―――同じ男ながらつい見惚れてしまう。
「部長・・・笑っとらんと、いてるかどうかくらい教えてくれたってええやないですか」
「そうですよ〜、別に減るもんやなし」
焦れた望月と織田がたたみかける。
けれど江神さんはただ微笑むばかりで、質問に答えようとはしなかった。学生会館を出たところで、僕たちは二手に分かれた。共にこれからバイトへ行く望月と織田は烏丸通を北へ向かう。
「義理でも何でも、貰えるもんは大事にせんとな」
ということで、ここ暫くはアルバイト先での態度についても気が抜けないらしい。家庭教師先の生徒が全部男である望月の場合は父兄というかその母親に、織田は土方を束ねている事務の女性へ、更なる好印象を与えようと必死だ。
また明日、と手を振って経済学部コンビを見送った。その後、なんとなく並んで江神さんと僕も歩き始めた。冷たい風が辺りで吹き荒ぶ。
数分も経たぬうちに角の交差点へ着いてしまった。今出川通の向うには地下鉄の入口が見えている。信号が青に変わり人波が道路を横断し始めた。渡りきってから、徒歩で下宿へ帰る江神さんと別れた。
もやもやした心を持て余しつつ、地下への階段を下りる。
―――江神さん、もしかして『ええなぁ』と思うとるような娘がいてはるんですか?
決定的な一言を繰り出したのは望月だが、それを聞く少し前から僕の心は著しく平静を欠いていた。
―――義理チョコやろうが本命チョコやろうが、好きな相手から貰えんかったら意味ないわ。
確かにその通りだと思う。好きな相手以外の人間から貰うチョコレートなんて、本来どうでもいいのだ。
そうはいっても、バレンタインにかこつけてアタックする者が出てくるのはいたしかたないだろう。傍から見ても充分に男前である部長を女性たちが放っておく筈はない。だから、そういう気になれないチョコの贈り主へきちんと線を引いている彼の姿勢に好感が持てたし、安堵もした。
けれど、あのひとに好きな女性がいるかもしれないと―――更にその、憎からず想っている相手からのチョコレートを待っているかもしれないとは考えたことがなかった。
一体、江神さんはどんな人を好きになるんやろう・・・
そう思った途端、心臓がギュッと締め付けられた。痛いなんてもんじゃない。何か鋭いものが身体の中へ突き刺さったかのようだ。
いつから意識し始めたかなんて、定かじゃないけれど。
傍にいるだけで、ドキドキする。
笑顔を見るだけで、心が暖かくなる。
それがどういう気持ちからくるかを知りながら、気づかないフリをして生活する―――本当にそうできれば、どんなにかいいだろう。頭では理解出来ても感情が納得しない。とまれ、心というのはそんなに都合良く出来ていないのだ。
それでも部長に恋人がいない今は、隣で安穏としていられる。しかし、サークル仲間よりも大切な存在を江神さんが得たならば―――僕たちと過ごす時間はきっと減るに違いない。
未来を憂えても始まらないとは思う。だがそんな日は遠からずやってくると覚悟しておいた方がいいのだ。
益々軋む心臓を抱えた僕は深い溜息と共に、たった今ホームに滑り込んできた車両へのろのろと乗り込んだ。週が明ければバレンタイン・デイも巡ってくるところまで押し迫った金曜日、僕は大学の近くにあるドーナツ屋のウィンドー前で足を止めた。見覚えのある顔がガラスの向う側に映ったからだ。丁度、入店しようとしていた高校生らしきグループの後に続いて、自動ドアをくぐった。
陳列ケースの前で何を注文しようかと迷っている人たちの後方から、働く女性の姿を確認した。同じ法律学科のクラスメイト、有馬麻里亜に間違いない。学籍番号が続いていることもあり、日頃よく話す女友達である。
テイクアウト用の箱を持った婦人に「ありがとうございました」とお辞儀をした彼女が僕を認め、声をかけてきた。
「有栖川君じゃない、どうしたの」
普通ならドーナツを買いにきた客ということになるのだろうが、考えてみると入学以来このショップへは数えるほどしか足を運んでいない。彼女がここで長期のアルバイトをしていたとしたら、珍しく思えて当然だろう。
だが、知った顔を見かけたので寄ってみたと明かすのも気恥ずかしい。僕はさり気く話の矛先をずらそうとした。
「有馬、ここでバイトしとるんか?」
赤っぽいセミロングの髪を後ろで軽く束ねた彼女はこくんと頷いてから「友達のピンチヒッターなの。だから、今日と来週の月・火だけなんだけどね」と小さい声で付け加えた。
隣のレジで会計をしていた高校生たちが銘々ドーナツや飲み物を乗せたトレイを手に奥のティールームへと移動する。注文カウンター前には僕だけが取り残された。
「で、何にする?」
トレイとトングを手にして、彼女が訊いてきた。
「ちょっと、考えさせてくれ」
僕はショーケースに整然と並べられているドーナツの数々へ急いで視線を走らせた。
砂糖をまぶしたようなもの、チョコレートでコーティングされたもの、穴の無いもの等、等。正直、これほど多くの種類があるとは思わなかった。つい、目移りしてしまう。
さんざん悩だ挙句、普通のとスクリューのような形をしたドーナツ、それにホットコーヒーを頼んだ。合計430円。釣銭とレシートをしまおうとしていると、テレホンカード大のカードを差し出された。
きょとんとしている僕の方へやや身を屈めた彼女が囁いた。
「これ、本当は500円以上買ってくれた人にだけ配布ってことになってるんだけど、帳簿とかで管理してる訳じゃないし―――全品30%OFFになるから、良かったら使って」
「ええの? ほな、貰っとくわ。ありがとな」
「それからこっちは、今、店で出してるドーナツのラインナップ。有栖川君、さっき大分迷ってたでしょ。参考にしてね」
折畳まれた小さなカタログも一緒にくれた。
もう一度礼を言った後、カウンター前を離れる。丁度、窓際の席が一つ空いていたので、そこへ座った。
飲み物へ口をつけながら、貰ったカタログを広げてみた。大きく種類分けされたドーナツにそれぞれバリエーションを持たせているので、結構な数があった。
どのタイプにも共通しているのがプレーンなものに対してココア生地のものを用意していることだ。大体どこへ行ってもバニラ味とチョコレート味が存在するソフトクリーム等を考えると、これは当前のメニュー展開なのかもしれない。
それにしても、ぎょうさんあるんやなあ―――
コップ半分くらいまでコーヒーを啜ってから、僕はドーナツに齧りついた。(2001/2/28)
へ戻る
すいません、無駄に長いです。日が空いているから、と言い訳してみたり(涙)
申し訳ありませんが、続きを読んでください…