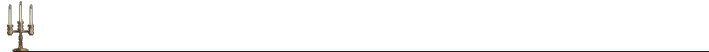運命の人
―I Meet My Fate―
Act.1 アリス
時間通り、二講目が終わった。
まるで岩場へ打ちつけられた波が一際高く飛沫を上げた後、ゆっくりと引いていくかのように大教室の出口から人気が無くなった。最後まで残っていた僕はやっと腰を上げる。元々、人混みに揉まれるのは好きじゃない。
一人で学生ラウンジへ向かう。本日、マリアが午前中の講義を休んでいるからだ。何でも外せない親戚筋の用事を仰せつかっているらしい。それゆえ、欠席分のノートを頼まれた。
所用が手際良く片付けばギリギリ昼休み時間内に大学へやって来られるかもしれないとのこと。「間に合ったらラウンジに寄るけど、駄目かもしれないから、江神さんたちによろしく言っといてね」と伝言を託(ことずか)ってもいた。
それにしても腹が減った。はよう行って、部長や織田、望月と昼を食べにいこう。多分、先輩の誰かがトレントの新刊を読み終わっている頃だ。ならば、その感想も聞いてみたい。
そんな風に自分の気持ちを引き立ててみるけれど、僕の足取りは床へ吸い付くほどに重かった。
―――どないしよう・・・
頭の中では、そんな言葉がさっきから回り続けている。
歩みを進める度に肩へ掛けた鞄が揺れ、その中身が僅かに踊る。講義テキスト、ノート、筆記用具、読みかけのミステリ本などに紛れた『それ』がカサカサと音を立てているような気がする。馬鹿馬鹿しい空耳だ。
どんなに時間をかけて歩いても、通りを挟んだ学生会館にはすぐに辿り着いてしまう。のろのろと階段を昇りながら、経済学部の両先輩がいてくればその瞬間がもう少し先延ばしになるだろう、などとぼんやり考えた。衆人環境の中でそれをやってのけるほど、僕もデリカシーの無い人間ではない。人のプライヴァシーを尊重する心得くらいは持っている。
ところが―――ラウンジにはなんと江神さんしかいないではないか。
困惑を隠せないまま、僕は英都大学推理小説研究会(通称EMC)の指定席へ歩み寄った。
「アリス、一人か? 遅かったな」
開いていた文庫本から目を上げた部長は、僕の好きな笑顔を見せた。
「あ、マリアは午前中いてへんのです。何や大津の親類に用事があるって・・・早く終われたら昼休みに顔出すようなこと言うてましたけど」
実をいうと、僕もマリアも次の時間は講義を取っていない。とはいえ、四講目には必修科目がある。だから彼女の場合、最悪それに間に合うようやって来れば良いということになるが、昼時に部員一同顔を合わせるのがほぼ習慣化しているので、一応の気遣いを見せたのだろうと思う。
「ところで、モチさんと信長さんは、どないしたんですか?」
僕は姿の見えない一年上のデコボココンビの動向を訊ねた。ひょっとして空腹に耐えかね、部長一人残して昼食をかきこみに行ってしまったのだろうか? まさかそんなことはないだろうと思いつつも、その可能性が絶対無いと言い切れないあたり、我がEMCのさもしさである。
江神さんは軽く前髪を掻き上げながら答えてくれた。
「ああ、あの二人もいてへんよ。二講目が突然休講になったから言うて、かねてから狙いをつけておった例の古本屋目指して突進しよったわ。ほんまに、羨ましい限りやな」
そういえば、先週あたりから今日の三溝目が休講になると両人が騒いでいたっけ。元から四講目の授業が無いので、昼飯を済ませた後は丸々空き時間ということになる。どうせだから何か有意義な時間の使い方をしたいと望月が言い、マリアが西京極に新しく出来た古本屋の偵察を提案して、織田が受託した。
「何か狙っている本があったら、言うといてくれ。取り置きくらいは頼んできてやってもええぞ」
織田がそう言ってくれたので、僕たちは己の懐具合と相談しながらそれぞれの探し本を検討しはじめた。金に糸目はつけず即買いしたいものと、購入金額に制限を設けるものと―――古本探しを人に代行してもらう際には、それなりの注意が要る。そんなこんなで出来上がったリストを、銘々が二人に手渡し終えたのは一昨日くらいだった。
講義が午前中だけで終わり正午過ぎには大手を振ってキャンパスを後にしても良いという僥倖なんて、我らが学生生活に於いてはそうそう無い。事前に判明していた休講分だけでも不真面目な学生たちの心を躍らせるには充分なのだけど、更に突発休講がプラスされれば、さもありなんだ。望月と織田の「してやったり」という表情が僕の脳裡にもありありと映し出される。
昼前から自由を満喫する幸運を与えられた二人は、今頃、思いっきり羽根を伸ばしていることだろう。遊べるだけ遊んで、そのまま下宿へ直帰となるのは間違いない。
となると、マリアが現れなければ、僕は昼休みを江神さんと二人っきりで過ごすことになってしまう。
普段なら手放しで喜べるような時間なのに・・・今日に限ってはあまりありがたくない展開だ。握り込んだ掌が汗をかきはじめている。
いっそ鞄の中身のことをすっかり失念してしまえたらどんなにかいいだろうと痛切に感じた。だが、『それ』を握り潰してしまえるほど、僕も人非人ではなかった。
「昼、まだやろ? 学食にするか」
「あ、はい」
動揺を必死に隠しながら頷いた。部長は緩慢な動作で立ち上がり、先に歩き出す。なんとなく肩を並べるのがいたたまれなくて、自然と後ろからついて行くようなかたちになった。
階下の学生食堂は飢えた学生たちの第一陣をやり過ごしたようだった。まだかなり混み合っているが、それでも其方此方に空席が見えた。二人並んで座れる場所をなんとか探し当て、僕たちは揃ってカレーを食べた。
マリアがやって来るかもしれないから―――ということで、再びラウンジの指定席へ戻る。いつも何の躊躇いも無く部長の隣に座るのだけど、僕は敢えて彼の正面へ陣取った。江神さんは少し驚いたようだったが、何も言わなかった。
出来ればマリアが此所へ顔を覗かせる前に事を片付けてしまいたい。僕は意を決し、脇に置いてあった鞄へ手を入れて、中から薄いブルーの封筒を取り出した。
無言で江神さんの正面へそれを置いた。濃い目の青いインクで宛名が書いてある。変なクセの無い、整った字体は、誰から見ても達筆と評価されるに違いない。
「・・・何や、これは?」
テーブルの上に載せられたものを一瞥した部長は、真っ直ぐ僕の目を見た。思わず、視線を逸らしそうになってしまう。今にも逃げ出さんばかりの意識を必死に抑えつけ、僕はなるべく冷静に聞こえるよう気をつけながら言葉を吐き出した。
「クラスの女の子から江神さんに渡してくれって、頼まれました」
「―――そうか」
江神さんは封筒を取り上げると、裏面を見、差出人の確認を済ませた。僕は少し下を向いて、自分の視界から彼の表情を外した。
パリッと音がした。封を切ったのだろう。そうっと窺い見ると、江神さんが便箋を手にしているのが判った。
どうしようもない沈黙が訪れる。周囲はそれなりに喧しい筈なのに、音が何一つ耳へ入って来ない。
苦しかった。江神さんが書簡に目を通している間中、僕は自分の内臓がキリキリと捩れるような錯覚に見舞われ続けた。更に、口の中には砂のようなものが溢れ出て、ざらざらした感触を舌の上へ積み上げていった。
気がつくと、弁解がましくどうでもいいことを口走っていた。
「・・・最初、マリアに頼んだらしいです。でもマリアのやつ、『自分で手渡さなきゃ意味ない』とか言うたらしくて―――で、今日、一講目が終わった後に呼び止められて・・・どうしてもお願いしたい、言われて―――あの・・・ええかげんな子やないんです。だから・・・」
「判っとる」
江神さんから発せられた声は優しかった。けれども、僕は部長の顔をちゃんと見ることが出来ないでいた。
「その子から必死に頼まれて、断れんかったんやろ? アリスは意外と優しいからなあ」
通常なら「『意外と』は余計です」くらい返すのだが、そんな勢いは微塵も湧いてこない。代わりに口を突いて出たのはなぜか「すいません」という意味不明な一言だった。
自分で自分が判らなかった。どうして、僕は詫びるんや? ただ、頼まれた手紙を届けただけやないか。
「・・・謝られる筋合いはないんやけどな」
部長からもそう言われてしまった。
確かにその通りなのだけど―――なぜだか、江神さんに負担をかけたような気がしてならない。
これが己の手を介さない出来事だったら、僕も普通にしていられただろう。多少、感じることはあったかもしれないが、それはまた別問題だ。
でも、こんなかたちで拘わったことによって、僕の心は冷静さを大きく失っていた。
「ほんまに、すいません・・・」
口が勝手に動き、またしても訳の判らない謝意を表明する。
「もう、ええて。アリスがそないに気ぃ遣うこと、あらへんやろ」
慰めるような部長の声が僕の中に響いて、不覚にも眦が熱くなった。
「けど、こういうのは―――早い方がええんやろな」
その科白を聞いた途端、心臓が鷲掴みにされたかと思うほどに軋んだ。身体の奥に震えが走る。彼が手紙に対する態度をこうも早く決めたということは何を意味するのだろうかと考え、ますます落ち着かなくなる。
「まだ、時間あるわな・・・ちょっと行ってくるわ」
僕が顔を上げるよりも早く、江神さんは腰を浮かした。荷物をまとめ、ラウンジの出口へ向かうつもりらしい。
こちらの脇を通り過ぎる時に、スッと手が伸びてきた。長い指が僕の髪をくしゃりと掻き回しゆく。
何だかあやされるようなその仕草を「心配せんでええから」という合図の如くに感じたなんて、自分本位な解釈も甚だしいとは思う。でも僕は、妄想といわれても仕方のないその曲解に縋りたくてたまらなかった。
振り返ると、長身の背中がどんどん距離を置いてゆくところだった。江神さんの後姿が戸口の向こうに消えたのを確認してから、僕は恨めしげに呟いた。
「ああ、なんで引き受けてしもうたんやろ・・・」
僕だって一応、「自分で渡した方がええんやないの」とやんわり断ったのだ。だけど彼女の思い詰めた表情を目にしたら、それ以上何も言うことができなくなってしまった。いつか自分も彼の前でこんな顔をするのではないだろうか―――そう思った途端、僕は目前のクラスメイトの気持ちを他人のものとして扱えなくなった。
想いを募らせている彼女が、どうしても自分と重なってしまう。
暫くして、「なんで直接、手渡さんの」と聞いた僕に、その女性はやや俯きながらこう言った。
「本当に、江神さんのことが好きやねん。せやから、怖くて・・・」
「江神さんは優しい人やで? 別に怖がることなんか、あらへんよ」
彼女は黙ったまま、弱々しく首を横に振った。僕はなんだか不安になってきた。
もしかしたら、よくある誤解を彼女もしているのではないかと思い、おずおずとそれを口にしてみた。
「あの・・・マリアのこと、勘違いしてへんか?」
この科白を聞いた彼女はやっと顔を上げてくれたけれど、その表情は泣き笑いしているかのように見えた。
「それは、マリア本人からちゃんと聞いたから」
なら、何が問題で彼女は江神さんを怖がるのだろう?
預けられた封筒を手にしたまま首を捻っている僕に、彼女は、
「ごめん、有栖川君に迷惑かけるつもりはないんやけど―――どうしても自分で渡せへんの。頼まれて、ね・・・?」
こう言って、今一度深く頭を下げた。
そこまでされてしまって、引き受けるしか道はなくなった。結局、僕はそれを断りきれずに請け負って、つい先程メッセンジャーの役を果たし終えたという訳である。
高岡律子という名前の彼女について、然程よく知っているわけではない。
同じ法律学科のクラスメイトで、数少ない女子の一人。理知的で涼やかな雰囲気を持つ彼女は、京都府最南端の木津町から通学している自宅生だ。マリアの話では父親が奈良検察庁知能犯係に勤める検事であるらしい。それで娘の名前が"律子"となったのだろう。
クラス内には、親である弁護士に「頭がよくて跡取りになれそうな男子をひっかけてこい」と言われて入学してきた女子もいるようだけど、彼女は違っていた。これもマリアから聞いたのだが、父親のような法と正義を守る職業に就くことを目的として、この学部を選んだそうだ。
目標がハッキリしている分、学業への取り組み方も真面目な律子嬢の成績は常にトップクラスだ。その上、凛とした美貌も持ち合わせているから、クラスの男どもが放っておく筈がない。頭が良くて美人の同級生と仲良くなれれば、鼻も高いし、ノートも貸してもらえる。まさに一挙両得というところだろう。そんな訳でマリア同様、彼女の人気もなかなかのものなのだ。
何人かがアタックして、その度にフラれたという話を聞いてきた。一体、どんな男なら彼女のお眼鏡に叶うのか、と思いきや―――それが、江神さんということか。
僕は、盛大な溜息を吐いた。
大体、なんで、あの男前な部長に恋人がいないのか、今だよく判らない。織田や望月も「引く手数多なのになぁ」「部長の方にその気がないんやろう」と、時々言ったりするが、その後で―――必ずといっていいほど―――なぜか僕の顔を見る。まあ、これは自分の気のせいなのかもしれないけれど。
ところが、マリアだけは「江神さんにはちゃんと好きな人がいるわよ」と断言した。その根拠を訊ねると、見ていれば判ることだと言う。しかし、マリアがそんなことを言う前から僕はずっと彼を見ているけれど、やはり判らない。
昨年の夏、彼との間に少なからぬ親しさを築いていた筈の女性について考えてみる。ルミとだって、かなりいい雰囲気だったのに。
山を降りる頃、武と小百合、僕と理代、そして江神さんとルミという組合せが出来上がると信じて疑っていなかったのは何も僕だけではあるまい。どのカップルも、それぐらい親密だったのだ。尤も、己がいかに脳天気だったかは後で思い知らされたけれど―――三組揃って見事にパアとなったのだから。
ルミが江神さんの助けを拒み、自力でロープをつたって崩れかけた道を一人歩ききった時のことが記憶の中へ甦ってきた。あの時、「江神さんにおんぶされて空中を行くよりよっぽど気が楽やわ」と言ったその気持ちがなんとなく理解できる。
あれはルミの出した一つの答えだったのだろう。江神さんという人から何度も助けてもらい、それなりに気持ちを寄せたものの、彼の中へは遂に踏み込むことの出来なかった彼女の『意地』だったに違いない。
男の僕の目には最初、江神さんの持つ『謎』がひどく魅力的なものに映った。だが、恋心を寄せる女性にすればそうもいかない。『謎』なんて、寧ろ不安を煽りたてる材料にしかならないのかもしれない。
尤も、江神さんの方にだって言い分はある筈で―――ルミには申し訳ないけれど、最終的な部分で江神さんはルミの手を取る気になれなかったということなんだろうと思う。
けれども、あのクラスメイトなら―――江神さんは違う答えを出すかもしれない。
しっかり者の同級生。齢二十歳にして、自分の採るべき進路をきちんと見極めている女性。
いい加減、部長に恋人が出来たっておかしくはない。そうなれば、僕たち部員と過ごすことは少なくなるかもしれないけれど、それは何も江神さんに限ったことではないのだ。望月や織田やマリア―――それぞれがサークル仲間よりも大切な存在を持ったなら、そちらを優先することが多くもなろう。
僕は、唇をきつく噛み締めた。
あの封筒が、織田や望月に対しての預かりものであれば、僕は二つ返事で伝書鳩役を務めただろうと思う。二人の先輩に対する好意や尊敬の念は遍く世間一般のそれと変わらない。
しかし、江神さん宛てなると話が違ってくる。それは、僕の中ではもう、どうしようもないことなのだ。
いつも彼と一緒にいたい、彼を独占したくてたまらないというこの気持ちをなんとか出来るものなら、とっくにそうしている。
最初はこんなこと、思いもしなかった。だけど最近は、彼に会う為だけに大学へ来ているといってもいいくらいだ。そう―――僕は毎日、江神さんの姿を追いかけて過ごしている。
正直、江神さんがこちらをどう思っているのか、はっきりとは判らない。一応、嫌われてはいないだろうけれど。後輩に対してやや多めの好意を抱いてくれているというのは確信できても、それ以上は如何なものか。
時々、彼の本心を確かめたくてたまらなくなる。ひょっとしたら、僕の想いなんてお見通しなのではないかと不安になることもある。
けれど、僕に向けられる江神さんの笑顔を目にするだけで心が幸福感に満たされ、そんな懸念も吹き飛ばされてしまう。だから、まだ我慢できると―――我慢しなくてはと、自分に言い聞かせる。
あの、青い封筒を預けられた時、僕は自分勝手な考え方から、それを託されることに躊躇いを感じた。
彼女が彼を射止めたなら、江神さんが僕相手に割いてくれる時間は確実に減る。それをイヤだと思う方がどうかしているということも理解している。そして、そういう気持ちを抑えられない自分がどんなに浅ましい人間かも。
判っているはずなのに。
覚悟しているはずなのに。
決して望んではならぬ恋。万が一、叶うことがあったとしても、叶えてはならない恋。
弟分として可愛がってくれている彼に、僕は満足しなければいけない。自分はただの後輩でしかないということを肝に銘じなければいけない。江神さんのすることへ首を突っ込む権利なんか、何処を探したって僕には与えられないのだから。
生まれてきた性を間違ったとは思わない。だけど、今の僕には、想いを打ち明けても不審がられることのない異性の存在が、ひどく羨ましい。
江神さんが女性なら良かったのに、と思ったこともない。そんな風に考えるまでもなく、彼が彼だからこそ、僕はあのひとを好きになった。江神さんをかたちづくる全ての要素へ、強く惹きつけられ、その魅力に囚われた。
しかし―――こんなことで、僕は大丈夫だろうか。
江神さんの周りで起こること全てを知りたいと思い、江神さんに関わる人の全てを把握したいと考える。その挙句、いつか江神さんを虜にするかもしれない相手に対して、激しい嫉みを向けてしまう自分がとてつもなく異常なような気がしてきた。気持ちが際限なく滅入ってくる。
一体ぜんたい、悔しいのか悲しいのか何なのか、もう、よく判らない。
テーブルにつっぷして、僕は呻いた。
「どうかしとるわ、俺・・・」
そのままの姿勢で窓の外を窺うと、どんよりとした雨雲が低い位置へ拡がりはじめている様が目に入ってきた。Illustrated by 奈緒 様
へ戻る
すみません、たった半日の出来事なのに、また(!)長くなってしまいました。
とりあえず続きます。どうか、次を読んでください…