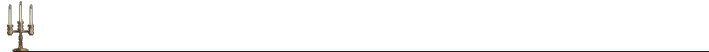運命の人
―I Meet My Fate―
Act.2 マリア
地下鉄今出川駅の改札を駆け抜けるようにして通過した私は、北方向へ進路を採って歩みを速めた。
京都駅へ着いた時にはもう、薄鼠色の雲がかなり低空へ降りてきていた。地上では既に降り始めているのかもしれない。傘は持っているけれど地下道でなるべく距離を稼ごうと思い、学生会館へ一番近い出口を目指した。
ぎりぎりセーフだったようだ。今すぐにでも泣きべそをかきそうな上空に眉を顰めながら、素早く会館一階の通り抜け通路を横切った。
あと15分で昼休みが終わる。午後、目出度く学業から解放される(といっても、本日だけなのだけど)望月・織田両先輩はもう古本屋探索へ繰り出してしまっているだろう。となると、ラウンジ奥の我がEMC指定席には相思相愛の一組がいるだけということだ。
入口から様子を伺い、特に問題が無いようなら即座に回れ右してこようと決めた。あの二人が仲睦まじく過ごしている処へ割り込むほど私も無粋ではない。ただ、アリスにノートをお願いしてあった手前、一応は覗いてみようという心積もりだった。
今、考えると、この時点で引き返そうと思わなかったあたりが運命の悪戯っぽくもある。階段の踊場にさしかかったところで、私は二階から降りてくる江神さんの姿を見つけた。
「・・・江神さん?」
やや俯き加減にしていた部長は、私の声を聞くと顔を上げ、微笑んだ。
「なんや、マリアやないか。用事、済んだんか?」
「ええ、なんとか。あ、もう授業、行かれるんですか?」
三講目が空きの法学部二回生コンビとは逆で、部長は次の時間に数少ない講義の一つを受けている。けれど彼がこんなに早くキャンパスへ戻るということは、もしかしたらアリスがラウンジにいないからかも・・・と思った私の疑心は顔に出たようだ。江神さんはその表情を苦笑いに変えた。
「俺はちょっと用があってな・・・アリスなら上におるで。少し、しおらしいなってるから、元気つけたってや」
「は?」
訝しげな声を上げた私を其処に残して、江神さんは手をひらひらと振りながら行ってしまった。部長の表情からすると、別に喧嘩した訳ではなさそうだ。それにしても、あのアリスがしおらしくなっているだなんて、どういうことかしら。
果たせるかな、ラウンジ最奥にはテーブルにへばりついた同級生の後姿があった。
それほど足音に気を遣ったつもりはないのだけど、床に響くヒール音も全く耳に入っていないようである。机に頭を投げ出して凹んでいるアリスの正面へ腰掛けると、私は声をかけた。
「どうしたのよ、アリス」
「なんや、マリアか・・・早かったな―――用事が終わって何よりや」
江神さんと同じような挨拶を返されたが、その口調にはかなりの差があった。
これはもう、しおらしいどころの話ではない。バックにはおどろおどろしい網目模様のスクリーントーン三枚重ねがとぐろを巻いている。何やら激しく意気消沈しているようだ。
私は顔も上げようとしないアリスの方へ上体を屈めた。小声で「どうしたの?」と訊いてみたが返事は無い。
暫くして、再度事情聴取を試みることにした。
「ねぇ、アリス、何があったのか言ってくれなきゃ、判らないじゃないの」
優しい声で諭すように訊ねてみても、向かいからは「あー」とか「うー」とか、よく判らない唸り声が聞こえてくるだけだ。私はだんだん心配になってきた。
「江神さん、何か用を片付けるために少し早く戻ったんでしょ? それと関係あるの?」
百発百中の問いかけ方をしてみる―――といっても、コツは会話の中へ"江神さん"という単語を挿入するだけなのだけど。効果てきめん、ずっと私を無視し続けていた同級生は見事に反応して、がばっと上体を起こした。
「マリア、江神さんにおうたんか?」
「? 会ったわよ? 階段の踊場で」
そう答えた途端、鬼気迫る顔で詰め寄られた。
「どんな様子やった?」
「ど、どんなって・・・普通だったと思うけど―――」
急に勢いづいたアリスの質問を受けて、私は懸命にさっき別れた部長の顔を思い出していた。うーん、確かに苦笑混じりではあったけど、普段の江神さんと何ら変わりは無かった筈よね。
だがアリスは、部長が私にしてみせたであろう表情になおも拘った。
「困ったわ、とか、しゃあないな、とか―――そんな顔、してへんかったか?」
そういわれてみると、"しゃあない"という感じだったのかもしれないな、と思い直した。けれど、その"しゃあない"はアリスの様子に対する感情のように感じられただけだ。
私がそう言うと、再び、アリスの表情と背景がセットで暗転してしまった。
「ああ、やっぱり―――俺のせいやねん」
「だから、何があったの?」
どよどよと落ち込む同級生から事の一部始終を聞き出すまで、なんと20分近くかかってしまった。そうこうしているうちに午後の授業が始まり、ラウンジ内の人波もかなり疎らになっていたのは、私たちにとって幸いだったのかもしれない。
どんっ!!!
アリスの話を聞き終わった私は、思わず目の前のテーブルを拳で強く叩いていた。
「馬鹿アリス!!」
私の大声に驚いた幾つかの視線が、付近から飛んできた。
「マ、マリア?」
怒鳴られた本人も、当然、目を白黒させている。周囲の好奇心がじわじわとこちらを注視しつつあったが、それに伴う羞恥心へ私の中の呆れたような怒りが打ち勝った。
「馬鹿だから馬鹿って言ってんのっ! もう、何、考えてんのよっ?!」
関西人に面と向かって投げつけてはいけないのは、『馬鹿』だったか『阿保』だったか。一瞬、気を取られたけれど、この際どっちだっていい。何にせよ、東京人の私からしたら『大馬鹿』としか言いようがない。
アリスは、心外だというような顔でこちらを見返してきた。
「・・・なんで、俺が馬鹿やねん」
当り前でしょう、恋敵に手を貸すなんて、どうかしてるわよ―――と言ってやりたい気持ちをグッと抑えた。まずは、事の発端について問い質す。
「そもそも、何だってそんなこと引き受けたのよ?」
「一限と二限の間に声かけられたんや。で―――しゃあないやろ。どうしても・・・って、言われてもうて」
あの律子から真剣に頼み事をされて、それを断れるクラスの男子はまずいないだろうと、私も思う。だけど、そういう問題ではない。私はわざと刺々しい言い方をした。
「ふーん、美人のお願いはホイホイ聞いちゃう訳ね」
「そんなんやないって!―――大体な、マリアのせいやで」
「ああら、どうして私のせいなのかしら?」
「せやから、マリアが断ったせいで、俺にお鉢が回ってきたんやないか」
痛いところを突かれた。一瞬、意識が引き攣ったけれど、その動揺を押しやって、私は冷たく言い放った。
「それは違うわよ。引き受けるアリスの方がどうかしてるの。だって、こういうのは自分で渡さなかったら意味ないでしょう? それに、そういう勇気が持てないんだったら、最初からその程度の気持ちってことじゃない」
本当は違う。彼女の恋心は決して軽いものではない。だけどそれを私が認めたら、事態はややこしくなる。
アリスの目がそっと伏せられた。
「・・・軽い子やないやろ、あの子は」
言い訳するように彼は話を続けた。
「俺かて、こんな役、引き受けとぉなかったわ・・・けど、高岡の顔見てたら、断れんようになってしもうて・・・」
要するに、ほだされたという訳か。私は天井を振り仰いだ。
「なあ、俺よりマリアの方が親しいんやから、よう知ってるやろ・・・彼女、ほんまに・・・好きやねん」
そんなこと―――嫌というほど、判ってるわよ。
ゆっくり瞬きして、私は己の気持ちを落ち着けようとした。
律子がどんなに真摯な想いで江神さんを見つめいていたか、多分、私が一番よく知っている。しかし、いくら才色兼備のあの子が頑張っても、この勝負、勝ち目は無いに等しい。
まったく、人の気も知らないで―――私は心中へ深い溜息を吐き出した。
彼女の頼みを私が断った理由は、二つの要因に根差している。
一つ目は、私にとって律子も江神さんも、同じように大切な友人だということ。それゆえ、あくまでも中立でありたかったから。
仮に、自分がこの役を請け負っていたとして、私が件の手紙を江神さんへ渡したなら。部長はちょっと困ったような顔をして―――でも、即座に答えを出すだろう。その時、私は彼女の魂が拒絶されるのをこの目で見ることになる。そんなのは耐えられない。狡いかもしれないけど、その瞬間に立ち会うなんて、絶対にゴメンだ。
そして、二つ目は。
EMC内で交わされている水面下の、とある感情を無視したくなかったから。
律子の想いに自身を重ね、立場も忘れて手を差し伸べてしまった同級生の気持ちと、その結果こうして情けなくへたり込んでいるこの大馬鹿者にしか向けられていない部長の気持ちと。知っているからこそ、其処に水を差すような真似はしたくなかったのだ。
傍で見ていれば明々白々なのだけど、江神さんもアリスもまだ、お互いの気持ちを計りかねているようである。惚れあっているのなら、さっさとくっついちゃえばいいのに―――というのは、外野の無神経な言い分だ。一見、何ら問題の無い男女の間でだって、時として意外な障害物に阻まれ成就しないこともある。ましてや、一般に禁忌とされる恋愛の行く末は、簡単な横槍で崩れ落ちたりもする。
少し前、私は望月・織田の両先輩と密かに約束を取り交わしていた。江神さんとアリスの想いを見守り、応援していこうと決めたのだ。
普通に考えたら、アブノーマルな感じ方なのもしれない。けれど、二人が相思相愛であることを知っても、私たち三人は驚きもしなければ、奇異なことのようにも思わなかった。EMCという小さな共同体の中で、それをごく自然なこととして享受した。
男同士の彼らが俗にいう恋人同士となるのが幸せかどうかまでは判らない。いくら自由恋愛といっても、家族や友人の目を考えると、どうしてもマイナス部分の方が大きそうだし。けれど、江神さんとアリスがより深い関係になったなら、私たちはそれを二人が選んだ結果として受け入れ、良しとするに違いない。
だからこそ、強く思っていた。こんな風に、彼ら二人の間へ余計な波風を立てたくないと。
それで私は、同性の親友、高岡律子の切羽詰った願いを突っぱねた。
だが、今となっては、「結果は期待できない」と諌め、告白前に諦めさせた方が親切だったのかもしれない、という気がする。そうしておけば、ある意味で被害は少なくて済んだのではないかと己を省みたくなる。
だって、まさか―――彼女がアリスを頼るとは、予想すらしなかったのだ。つくづく、律子の気持ちを甘く見ていたと痛感した。そしてまた、アリスがそれを引き受けるなんて、思いもしなかった。
そっと唇を噛む。
これは、私の判断ミスだ。なんとかしなくては。
とりあえず、この時間は図書館にいる筈の律子に話を聞いてこよう。
「アリス、まだ、ここにいるわね? 荷物、見ていて」
投げ捨てるように言って、席を立った。
相変わらず覇気の無い異性の親友は視線を落したままだが、軽く手を上げることによって了承を伝えてくる。
既にラウンジからは大半のギャラリーがいなくなっていた。西門を潜り、真っ直ぐ図書館へ向かった。
律子はこの時間、其処で蔵書区分けのアルバイトをしている。このバイトは授業の空き時間に合わせて働けるという魅力的なものであり、それゆえ競争率が高い。以前は抽選だったようだが、最近は学生課で成績優秀な生徒を人選すると聞いた。そんな訳で、大学図書館のバイトをしているというのは今や一種のステイタスにもなる。
カウンターで彼女を呼んでもらった。強引に休憩時間を繰り上げさせ、私は律子を非常階段へ引っ張り出した。
打ちっぱなしのコンクリート壁へ、並んで凭れかかった。ひんやりした感触が心地よい。
なるべく律子の方を見ないようにして、私は話を切り出した。
「江神さん、来たんでしょ?」
「・・・うん」
蚊の泣くような声が答えた。沈黙が頭上へ降りてくる。暫くして、彼女はポツポツと話し始めた。
「昼休みの後がすぐここでバイトやから、少し早くに入ってたんやけど―――江神さん、三限が始まる前に来てくれはったんよ。で、あっさりフラれたの」
部長は何と言って断ったのか、ふと気になった。しかし、いくらなんでも、今、それは聞けない。
「・・・マリア、判っとったんでしょう、だから引き受けてくれなかった―――違う?」
違わない。
だけどそれを口に出したりは出来ない。私は無言で律子の方へ身体を向き直らせた。
「・・・自分でも、多分、駄目だろうて思うてた。だから怖かったんよ・・・江神さんに直接手渡して、その場で断られるのが、どうしようもなく、怖かったの―――けど、間抜けやね。誰かに頼んだかて、断られる時は一緒やのに」
小さく震えている律子の細い肩へ手を伸ばした。私と然して変わらない体型の身体がゆっくりとこちらに預けられる。
「有栖川君にも、迷惑かけてしもうたわ」
涙声だった。私は律子の背中を撫ぜるように軽く叩いた。いいのよ、あの馬鹿のことは考えなくて。
「ねぇ、律子―――四限、自主休講しよう」
彼女を抱きしめたまま、出来るだけ優しい声で囁いた。
「え・・・」
「いいじゃない、今日くらい。まあ、必修には違いないけど、皆勤狙うような授業じゃないし」
「でも―――」
「ノートはアリスに頼むから、安心して」
「そんな・・・有栖川君に、また迷惑かけてしまうやないの」
私は自分の肩から律子の頭を外し、彼女の綺麗な目を見つめて「大丈夫よ」と言った。アリスには大分貸しがある。ノートの貸借数だけで比較しても、まだこちらが相当優位なのだ。だから、今日の午前中分を頼んだ時も全く気にならなかった。
「気分転換にバーゲン会場まわってもいいし、ケーキバイキングに付き合ってもいいわよ。あ、前から一回食べに行こうっていってた、『夕林』のお茶漬けは? この時間だったら、お三時に丁度いいでしょう」
「・・・そうやね、そういうのもいいかもね」
思いつくまま挙げた適当な提案に耳を傾けていた律子の顔が綻ぶ。いつものカラリとした笑顔にはほど遠かったけれど、その表情は私をかなりホッとさせてくれた。
「じゃ、決まりね。バイト終わるまで、私もここで時間潰すことにする―――と、ラウンジに荷物置きっぱなしなんだっけ・・・取ってこなきゃ」
滲んだ涙をそっと拭った彼女が落ち着きを取り戻すのを待つ。暫くして、私たちは重い金属製扉の向こう側にある図書館内部へ戻った。
やけに辺りが暗い感じがしたので窓の外へ目をやると、曇天が墨汁を零したような色へと変化していた。
ガラスの表面に細かい水滴が一粒、二粒と貼りつき、ゆっくりと流れ落ちだしている。とうとう降り出したらしい。
律子から傘を借りると、私は学生会館へとって返すことにした。再び烏丸通を渡る。徐々に多くなってきている降水量のせいか、鬱蒼とした気分に拍車がかかる。
恋の結末は、予想していた通りだった。今日、私が付き合って、どの程度律子が元気になれるか判らないけれど、親友として出来るだけのことはしようと心に決めた。
階段を昇り学生ラウンジへ戻ると、奥では、まだアリスがぐったりしていた。
一応、上体を起こしてはいるものの、辺りの空気を著しく澱ませたままである。こうも凹んでいる、後一人の親友をどうしたものか。ただ座っているだけというようなアリスの背中に視線を合わせつつ、何かいい方法はないかと考えを巡らした。
今、彼が落ち込んでいる原因は、おそらく自己嫌悪から来ているに違いない。江神さんへの手紙を預かってしまったことで、自分の複雑な立場を再認識させられてしまい、様々な感情に苛まれているのだろう。
このままでは良くない。アリスの性格からしたら、自分で自分の思考を閉じてしまい堂々巡りを繰り返して、更に激しく落ち込むのが関の山だ。
こうなると、今日に限って不在の先輩コンビが恨めしい。織田先輩や望月先輩と他愛無い雑談でも出来れば、大分違うのに。尤も、そうしたところで、何ら解決の足しにはならないけれど。
やっぱり、一番良く効く『薬』を服用させるしかないかしら。
私はもう一度、アリスの正面へ腰を落ち着けると、胡乱な目でこちらを見遣る同級生へ宣言した。
「四限、自主休講することに決めたから。アリス、二人分のノート、お願いね」
「ち、ちょっと待て、マリア―――学校へ何しに来とるねんっ」
さすがに慌てたらしく、まともな質問が返ってきた。
「しょうがないでしょう。こっちにもいろいろ事情があるんだから」
「大体、学生の本分っちゅうのはな・・・っと、二人分って、どういう意味や?」
人に散々ノートを借りてきたアリスから、お説教されたくはない。尤も、これについて隠しても意味がないので、淡々と告げた。
「律子と私の分よ―――どういうことか、判るでしょう?」
てきぱきと荷物をまとめて席を立つ準備を整えつつ、『律子』という名前に引き摺られて、思考が停止してしまったらしい同級生の目を見つめた。
「ねえ、アリス」
さり気なく、私は問いかけた。
「江神さん―――傘、持ってたっけ?」
「・・・さあ、覚えてへんわ」
やっぱりね。
手紙騒動で、注意力が何処かへ吹っ飛んでしまっていたのだろう。割と観察力に長けているアリスにしては情けないことこの上ない解答だけど、まあ、しょうがないか。
昼休みが終わる頃、すれ違った部長の手荷物に傘らしきものは見当たらなかった。天気予報が夕立の可能性を示唆していたとはいえ、朝はすっきりとした快晴だったから持参し損ねたのかもしれない。
私は低い位置に垂れ込めている黒雲の連なりを眺めた。
多分、あと少しで本格的に降り始めるだろう。この様子からすると、やがて土砂降りになる。私は、今、自分の手中にある二本の傘を確認した。
一本は律子から借りた淡いクリーム色の傘。そして、残りは、私が自分で持ってきたブルーの傘―――男性がさしてもそれほどおかしくない色の傘を用意していた偶然に感謝したい気分だった。
ぼんやりしているアリスの前へ、私はきっちり巻いてある青い傘を差し出した。
「これ、江神さんに貸してあげて」
「へ?」
「へ、じゃない。アリス、この後、四限受けにキャンパスへ戻るでしょ? 江神さん、この時間の授業、扶桑館で受けている筈よ。四限はその隣りの至誠館じゃない。通り道なんだから、ついでにこの傘、渡して」
「って、なんで俺が・・・」
判ってないわねぇ、というように溜息を吐いてみせた。
「この後、私は律子と一緒に行動するのよ? 江神さんとは顔合わせない方がいいに決まってるでしょう」
もちろん、ただの言い逃れである。でも、アリスはそれに気がついていない。
「せやけど、マリアかて傘は一本しか持ってないやろ? その・・・」
「私のことはご心配なく。律子と相合傘で帰るから」
クリーム色の傘を見せて答えると、一応、納得したらしい。だが、すぐに不服そうな顔が言い返してきた。
「マリア―――俺は、どないするねん」
え? 私はアリスの顔をまじまじと見つめた。
「俺かて、傘なんか持ってきてないわ。部長の心配はしても、俺のことはどうなってもええと思うとるやろ」
眩暈がしてきた。ちょっとしっかりしてよ、アリス。
「だって、アリスは地下鉄組でしょう。江神さんは徒歩なのよ? ここから西陣まで、部長に濡れて歩いて帰れっていうの?」
四講目が終わった後、地下鉄の駅までの短い距離を、誰かの傘へ入れてもらえばいいのだ。それくらいのことも思いつかないくらいに、アリスの中が混乱しているなんて。
こんなに安定を欠いたアリスを見るのは初めてだ。とにかく、江神さんという『特効薬』と対面させなくては。そして、部長がアリスの異状に気付き、なんとかしてくれるよう、祈るしかない。
「言っとくけど、この傘は江神さんに貸すのよ。アリスに貸したんじゃないからね」
私はしつこく念押しした。
何か口実を設けないと、江神さんとアリスは今日この後、顔も合わせず別れてしまうに違いない。明日はまた、いつもの二人に戻るということも無くはないかもしれないけれど、それではなんとなくわだかまりが残るような気がする。
折りしも本降りになろうかという中、傘を渡すために扶桑館へ立ち寄らせるというのは、苦肉の策だった。
「いーい、アリス。その傘、明日、江神さん以外の人が返しに来たら―――私、許さないからね」
これくらい言わなければ、今のアリスは動かないと思い、殊更に強い口調で告げた。
律子の想いは叶わなかった。でもそれは、あなたたち二人のせいじゃない。
「もう、判ったわ・・・言う通りにすればええんやろ・・・」
渋々ながらもアリスが微かに頷いたのを確認して漸く、私はラウンジを後にした。
へ戻る
すいません、まだ続きます。な、なんで、こんなに長いんでしょう(涙)
後一回で終わりますので、どうか続きを読んでください…