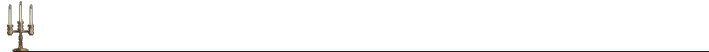運命の人
―I Meet My Fate―
Act.3 アリス
一人で怒っていたマリアは、僕に荷物番を命じて出て行ったかと思うと、戻ってくるなり自主休講するとのたまった。そして、人の都合はお構いなしでこちらへ青い傘を押しつけ、あっという間に僕の前から姿を消した。
結局、貴重な空き時間は、マリアに怒られているかボーッとしているかという、どうにも非生産的なものになってしまった。今日はとことんツイてない。
まだ3時前だというのに窓の外は宵闇と見紛うほどの暗さである。夕立が来るかもしれない、という予報が珍しく当たりそうだ。
時間的な余裕を考慮しつつ、学生ラウンジを出た。滅多には無いけれど、何かの拍子に講義が早く終わることもある。パラパラと落ちてくる雨の下、僕はマリアの青い傘を差して、烏丸通を渡った。
本当のところ、江神さんと顔を合わせるのは少々辛い。マリアが高岡律子と共に四講目への欠席を決めたことから、結果は自ずと知れた。だけど、問題なのはその理由だ。
織田や望月が言うように「その気がない」のか、マリアが考えているように「好きな人がいる」のか。彼があの手紙に対して出した結論の裏付けとなるものを質す権利は自分にないといくら戒めても、それが気になってしまう。そして、そんな僕の心中を聡い部長に見破られてしまいそうで、怖い。
尤も、江神さんが口にしなければ、この件について僕から聞くことは出来ない。まあ、傘を渡すだけの時間にそんな話題が出るとも思えないのだけど。
扶桑館へ辿り着くと、僕は下の通り抜け通路脇にある下足入れへ靴を放り込んで階段を昇った。そうして幾つかの教室を覗き見して回り、江神さんが受けている筈の授業がまだ講義中であることを確認した。
一階まで戻って階段側の壁へ背をあずけた。鞄の中から読み止しのポケミスを取り出し、ページを捲ってみるけれど、案の定、全く読み進むことが出来ない。諦めて、本を鞄の中へ戻した。
長い長い待ち時間だった。実際には11、2分のことだったのだろうが、僕はその間中、出口のない場所へ閉じ込められているような閉塞感につきまとわれていた。
ざわめきが頭上から降ってきた。三講目が終了したようだ。
あちこちで、教室の扉が開かれる音がする。私語が喧騒となってあたりを取り囲む。学生たちは下足入れから銘々の靴を取り出し、ある者は傘を広げ、ある者は鞄や上着で頭上を覆い、雨の中、この建物から去ってゆく。
最初は懸命に目を凝らし、江神さんの姿を探していたのだけど、あまりに多くの人間が目前を通過したせいか、途中から視覚が麻痺してしまったようだ。目前へフィルターをかけられたような気がして、ぼんやりとその場で佇む。
そして―――背後に優しい気配を感じた時には、既に僕の肩上へ部長の手が置かれていた。
「江神さん・・・?」
小さく顔を捩って見上げると、
「アリス、ここで何しとるんや」
驚きと呆れが綯い交ぜになったような声が降ってきた。
僕は慌てて、マリアの傘を差し出した。
「これ、マリアが・・・江神さんに貸したいからって―――傘、持ってなかったみたいやからて、言うとりました」
「そらまぁ、ありがたい申し出やけど・・・マリアの方はええんか? 自分の傘、人に貸してしもうたら、困るやろ」
部長の口の端に当然の疑問が上る。
「あ、それは大丈夫みたいです。マリアは高岡と相合傘で―――」
しまった。慌てて口を噤んだけど、遅かった。
江神さんの顔から表情が消えた。でもそれはたった一瞬のことで、すぐ穏やかな微笑にとって変わられたけれど。
「マリアにも余波がいってしもうたか」
部長はやや自嘲気味に呟いた。それから僕の手渡した傘をゆっくり開いて、こう訊ねた。
「アリス、次、必修やったろ? 教室、何処だ」
「至誠館の4階―――隣りです」
頭上を青い色が覆った。
「大丈夫ですって、すぐ近くですから」
「ええから、ちゃんと入りや。結構、降りが強うなってきてるぞ」
江神さんは僕の頭をぐいと引き寄せた。その、確かな力強さにつられて、身体が傘下へ導かれる。
ほんの数メートルの道程しか用意されていないのが却って恨めしい。一緒にこうしていられる時間がもっと長ければいいのに、と思う自分がいじらしかった。
ものの一分もしないうちに至誠館の昇降口へ着いてしまった。
わざわざ送ってくれた彼に向かって頭を下げてから、
「江神さん、その傘、明日までちゃんと持っていてくださいね。そうやないと、僕がマリアに怒られます」
と言った。
「何や、それは」
首を傾げた部長へ、マリアが去り際に残していった科白を正しく告げた。
「俺以外の人間、ねぇ・・・」
何か思うところがあるのか、江神さんは顎に親指を押し当てたまま黙り込んでいる。
「とにかく、そういうことですから」
もう一度頭を下げると、僕はその場から逃げるようにして階段を駆け上がった。出来るだけ、授業内容に集中しようとした。今、自分が考えるべきは日本国憲法のことなのだ―――そう、己に強く言い聞かせた。
だが、僅かでも気を抜くと、意識はたった一人の存在を求めてフラフラと彷徨い始める。少し前、僕の身体を傘の中へ強引に押し込めた手の暖かさを思い、心がのぼせ上がる。
壇上で喋っている講師の言葉が、右の耳から入って左の耳より出て行く。教室内にばら撒かれた文章は意識が追いつく前に単語単位へ分解されてしまうような状態だったけれど、ノートだけは懸命に取った。そうすることで、なんとか自分をこの場へ繋ぎとめようとした。
ぼんやりと窓外へ目を遣った。既に夜のような暗さだ。
閉め切った窓の向こうからも雨音がしっかり聞こえてくる。いつもなら明快な輪郭が取れる付属中学の建物は、沛然と降り続ける雨が撥ね返す水飛沫にかき消され、うっすらと霞むばかりになっていた。
この天候の中を、江神さんは一人下宿へ向かって歩いているのだろうか。マリアの青い傘は女性ものにしては大きな作りだったけれど、これほどまでに降りしきる雨が相手ではどんなに注意深く歩いても靴やジーンズの裾に染みを作ってしまうだろう。
授業が終わった時も、空はまだ激しく泣き続けていた。傘を持っていて尚且つ西門へ向かうという条件をクリアしそうなクラスメイトを掴まえるつもりでいた僕は、何気なく廊下の窓から下方を覗き、驚いて目を見張った。
見覚えのある青い傘が、梅雨空に映える紫陽花のような艶やかさで立っている。
慌てて階段を駆け下りた。飾り物程度にしか設えられていない一階昇降口の庇まで辿り着くと、傘を持った人物が此方へ近寄ってきた。
「授業、終わったか?」
「・・・江神さん、何で―――こんなところで、何してはるんですか」
部長はぽりぽりと鼻の頭を掻きながら答えた。
「何しとるって―――おまえを待っとったんやけど」
「ですから、何で・・・」
江神さんは、さっきと同じように僕の上へ傘をさしかけた。
「この降り方やろ。傘が無かったら、建物から一歩も出られへんやろうと思うてな」
確かに、僕が江神さんへ傘を手渡した時とは比べものにならないくらいの降りではある。しかしだからといって、自分の授業が終わってからずっと僕を待ち続けていたとは。全く、部長の常識は豊かなのか、乏しいのかよく判らない。
四講目が終わった後でまさか江神さんと会えるとは思わなかったから、この展開はもの凄く嬉しい。だがその結果、これから却って酷い雨降りの中を帰らなければならなくなったとは言えないだろうか。
「せやけど・・・あのぅ、早く帰ったほうが良かったんやないですか」
控えめにそう訊ねると、部長は僕の顔を覗き込んでにっこり笑った。
「どうやろな。確かに、三講目が終わった直後はどうということなかったけど、あれから10分くらいしたら、どーんと降り始めよってなあ・・・烏丸通を渡りかけたところやったから、とりあえずラウンジに避難したんや。これでも少しは雨足が弱うなったんやで。さっきは到底帰れる状態やなかったな」
そして、つい先程そうしたように僕の頭を抱くようにして、傘の中へと引き寄せてくれる。
僕の身体がきっちり彼の脇へ納まったのを確認してから、江神さんが訊いた。
「アリス、少し、時間あるか」
「はい。今日はもう、帰るだけですから」
彼は目を動かして扶桑館の方を見遣った。僕も頷く。
数メートルの距離を走るようにして、僕たちは扶桑館一階の通り抜け通路へ飛び込んだ。下足箱付近で帰り支度をしていた何人かの学生が、驚いてこちらを見返してくる。しかし、耳を塞ぎたくなるような雨音の凄まじさは、彼らの視線をすぐに外へ移動させた。
「ひゃあ、たったこれだけの距離やのに、ようまぁ濡れたもんやわ」
大袈裟に騒ぐ僕を江神さんは涼しい目で見ていたが、
「ずっとこのままやったら、たまらんな―――けど、丁度いい足止めかもしれん」
周囲を見回した後にこう言って僕の腕を取り、下足入れが設えられている方とは反対側の壁際へ移動させた。
階段の下に位置するこの場所は、やや奥まっていて風雨も吹き込んでこない。更に、人目にもつきにくい。江神さんが壁に凭れかかったので、僕もそれに倣った。二つの身体は肩が触れそうなくらいに近かった。
彼が何を話そうと思っているのかは想像がついた。あの手紙のことしかないだろう。
でも、僕はそれを聞くことに不安を覚えていた。話を聞いたら最後、部長が手紙の主の気持ちに応えられなかった理由を追求したいという己の本心を抑えることが出来なくなりそうだった。
それで、先手を打つことにした。
「勿体無いことしはりましたね。高岡、クラスでもえらく人気があるのに」
「そうかもな」
江神さんも認めた。
「アリスが言うた通り、ちゃんとした子やったわ」
手紙には図書館でのバイト時間のことが書かれていたそうだ。それで、彼は即座にキャンパスへ赴き、彼女の姿を探した。
「書いた本人からしたら、いつ返事が貰えるか、気が気でない状態やろ。せやから、早うに言った方が親切やと思った」
「そうですね・・・こういう場合、良い返事でも悪い返事でも、先延ばしにされたら生きた心地がせんでしょうし」
これで会話が終わればいいと思った。なのに部長の言葉は続いた。
「気持ちには応えられんから、かんにんしてや―――言うた」
なんでですか。
なんで、あの子の気持ちに応えらえれへんのですか。
付き合うてみたら、案外、判らんかもしれないやないですか。
そんな僕の心の声を見透かしたかのような科白を江神さんは口にした。
「特定の相手がいないんやったら付き合うてみるのも一つの方法やろうけど、俺には向かんな」
「どうしてですか?」
思わず、聞き返してしまった。やばい。俯きそうになる自分をなんとかこらえる。ここで視線を外したら、不自然なこと極まりないではないか。
「さあ、どうしてやろな・・・他に、好きな人がいてるからかもしれん」
そう言って僕の顔を見た江神さんの瞳は普段通りに優しかったけれど、笑ってはいない。
「アリス」
ぞくりとした。背筋を奇妙な戦慄が這い上がってきた。しかし―――
「・・・やマリアや信長、モチの方が好きやな。うちのサークル仲間といる時間が、俺は一番好きなんやろ」
とってつけたような言い方に、僕は脱力した。
確かに、EMCの中は居心地がいい。不必要に気を遣ったりしなくてもいいし、見栄を張ることもない。異性と一対一で付き合えば、自分を良く見せようとしていろいろ無駄な足掻きをしたりもするものだが、そういう背伸びとは無縁でいられる。等身大の自分を認めてくれる良き仲間は、僕にとっても一番大切で好きな人たちには違いないけれど―――
「江神さん、それって・・・何や、情けなくないですか」
「何でや」
「恋人の一人もいない学生生活なんて、お子様並やないですか」
「生意気言うとるな。大体、学生の本分は勉学と部活動やろ。気にすることあらへんわ」
どうも、うまく丸め込まれたような気がしてならない。でも、お陰で、僕の心はやっと落ち着きを取り戻した。
多分、このひとはたったこれだけのことを言う為に僕を待っていてくれたのだ。昼休みからずっと、みっともなく動揺していた僕の気持ちを鎮める為に、きっと。
こんな風に彼が僕のことを心配してくれる。それだけでも充分幸せな筈だ。今ここにある幸福に感謝出来ない人間は、いつまでたっても満たされることはない。
僕はいつの間にか笑い出したい気分になっていた。
江神さんがあの子を選ぶかもしれないと思ってハラハラし、自分が同じ土俵に立てないことへ腹を立てて。もやもやとした感情を一人で捏ねくり回し続け、声をかけてくれたマリアにも不快な思いをさせてしまった。そんな自分の方がよっぽど情けなくて、お子様ではないか。
隣りにある体温へ直接触れた訳ではないけれど、その暖かさが僕の中にあった冷たい何かを溶かしてくれる。彼の傍にいるだけで、僕は安らぐことが出来る。
視線を上げると、すぐ近くに部長の目があった。ずっと、僕を見ていてくれたのかと思い、胸が熱くなった。
暫くの間、二人とも黙って壁に体重を預けていた。横たわる沈黙はあたりを柔らかく包み込んでくれる。時折、吹き抜けの方を見遣りながらただこうしているだけの時間が、今の僕には愉しかった。
顔を捩って暗闇の中を見ていた江神さんが、やがてポツリと呟いた。
「参るなあ・・・全然、勢い衰えへんわ。この分だと大阪の方も、こないに降っとるんやないか?」
それは充分に考えられる。そういえば朝、夜半にかけて激しい夕立の可能性があることをTVの気象情報がしきりにまくし立てていたっけ。もしかすると、今ここで大雨を降らしている雲がこれから南下するのかもしれない。
江神さんは上空の様子と僕の顔を見比べながら訊いた。
「アリス、うちまで来れば傘貸してやれるけど、どないする」
「ええんですか? 助かります」
まだ部長と離れたくなかった僕は、喜んでその提案に乗った。
大阪についてから駅前のコンビニでビニール傘を買えは済むという心の声は、敢えて無視した。金欠なので、たかだか380円程度の出費もバカにできないと、一応、理屈もつけた。
「アリスに送ってもろうて、その後、この傘で帰ってもろたらええと思うたんやけど・・・マリアは『俺以外の人間が傘を返しにきたら許さない』て言うたんやろ? となると、これは俺が持ってなければあかんやろうし―――なら、うちまで来てもらって、俺のを貸す分には問題ないやろ」
マリアとしては、ああ言わないと僕が江神さんへ傘を渡しに行かないかもしれないと思って口にした程度のことだとは思う。しかしそれを適当に聞き流すほど、部長も彼女を甘く見てはいないようだ。マリアの記憶力の良さと約束を守らなかった時の怖さは男性部員一同、良く知っている。
とにかく、後少し彼といられることが僕の心を有頂天にする。
江神さんがマリアの青い傘を再び開いた。殆ど真っ暗な上空を軽く睨んで、部長は溜息を吐く。
「ゆっくり歩いていくしか、ないやろな・・・傘の中からはみ出んよう、気をつけるんやぞ」
子供にするような注意を僕に寄越した。
僕たちは青い傘の下で互いの身を寄せ合い、気が遠くなるようなスピードで歩いた。傘の柄を持つ江神さんの手が、なぜか大きく感じられた。
西門を出て烏丸通を渡り、今出川通から一本裏の道へ入った。表通りを行くよりいいだろうと思ったのだが、この雨ではなかなかそうもいかない。一挙に乗車率が高まったのか、普段は滅多に車両が通らない狭い路地までもがタクシーや自家用車の進入を受けている。僕たちはところどころで立ち往生し、飛沫を上げて走り去る文明の利器をやり過ごした。
いつもの倍近い時間を歩いても、まだ江神さんの下宿へは辿りつけない。殊更に気を配りながら歩いているせいか、妙に疲れてきた。いっそ、雨の中を走っていた方が精神衛生上いいのではないか。そんなことを思って部長の方を見ると、目が合った。
「歩くのが、たるくなってきたな」
「やっぱり、そう思わはりますか?」
以心伝心とはこのことか。
走るか?と訊かれて、僕は頷いた。一つ傘の下で大の男が二人、肩を突き合せ、そろそろ歩き続けるというのは、どだい無理がある。気力的にも体力的にも限界が近づきつつあった。扶桑館を出発した頃に比べたら、やや小降りになってきているような気もするし、ここからなら江神さんの部屋へもそう遠くない。
「あのコンビニまで我慢やな。あそこから用意を整えてダッシュする―――それでええか」
部長が数メートル先の店舗を顎で指し示した。僕は了解した。
申し訳程度の駐車スペースを備えたコンビニの軒下で、僕たちはいったん小休止した。僕の鞄に江神さんの荷物も入れてしまい、手に持つものを一つにした。傘の水をざっと払って、しっかりと巻く。やや重たくなった鞄を江神さんが引き受けてくれ、僕は閉じた青い傘を小銃のように小脇へ抱えた。
「行くぞ、アリス」
「はいっ」
僕たちは揃って飛び出した。
途端に滝のような雨が頭上を直撃する。前を走る江神さんのシャツに多量の水滴が襲いかかり、どんどん染みを広げてゆくのが目に入る。
気持ちのいいほど派手な水飛沫を上げて僕たちは走った。跳ねがばしゃばしゃと上がる音が耳へ小気味良く響く。子供の頃、大雨の日に公園を駆け回って泥んこ遊びに興じ、後でこっぴどく怒られたことを思い出した。
路地づたいに走ったので然程数は無かったが、行き会った信号をことごとく無視して、どうにか江神さんの下宿へ辿りついた。全身ずぶ濡れになっているのに、気持ち悪いとは感じない。寧ろ、奇妙な爽快感が僕の中で渦巻いている。
「さすがに、このままでは上がれんな・・・ちょっと、待っててくれ」
そう言って玄関をくぐった江神さんは程なく大きなバスタオルを手にして戻って来た。服そのものが水を吸ってしまっているのだから、あまり意味がないような気もするけれど、一応、滴り落ちる雫を拭った後、屋内へ上がり込んだ。
江神さんが貸してくれたスウェットに袖を通した後、僕は濡れた衣服をこの下宿共有の乾燥機へ放り込ませてもらった。服が乾くのを待っている間、自分も着替え終えた部長は僕たち二人が廊下に作った水溜りを雑巾で拭いて歩いていた。
手に暖かい衣類を持って、江神さんの部屋へ戻った。そのまま呆けていると、拭き掃除を済ませた部屋の主も戻ってきた。
ガス台の上で、お湯がしゅんしゅんと音を立て始めていた。
自前の服に着替え傘を借りて帰るだけとなった僕の前に、暖かい紅茶が置かれた。僕はお礼を言ってから、ゆっくりとそれを啜った。
他愛無い話を少しした。最近読み終えたミステリの感想や、大学内のちょっとした噂や、今しているバイトのことなど。寡黙な先輩は、僕の紡ぐ話の一つ一つに相槌を打ち、的確な意見をさし挟んでくれる。
そろそろ、腰を上げなければと思う。書籍やCDが溢れかえっているにも拘わらず、なぜか居心地の良さを感じさせるこの部屋からまだ出たくはなかったけれど、僕はどうにか自分を抑えつけた。
空になったカップを下げようとして立ち上がった。しかし部長が「そのままにしておいてええから」と首を横に振るので、お言葉に甘えさせてもらった。
部屋の隅で再び着替えてから、いよいよ彼に傘を借りる。
玄関まで一緒に行った。僕が「今日は、ありがとうございました」と言うと、江神さんは少し不思議そうな顔をした。
「別に、礼を言われるようなことはしとらんけど」
「せやかて―――雨の中、待っていてくれたやないですか」
僕のこの科白を聞いた部長の目がそっと眇められた。何かを躊躇っているらしい雰囲気が微かに見え隠れしている。そんな彼の様子に僅かな引っ掛かりを感じはしたけれど、気持ちだけは伝えたいと思い、先般からずっと自分の心中にあった感情を口にした。
「ほんまに、嬉しかったんです。あの青い傘を上から見つけたとき、吃驚しましたけど―――もの凄く、嬉しかったんです」
江神さんは黙ったまま僕の顔を見つめた。
穏やかで優しい彼の目が僕の中へ注がれる。何かを語りかけようとしているその瞳に捉えられて動けないでいると、彼はやがて静かな声でこう告げた
「アリスには、あの子にどう答えたかちゃんと説明せなあかんと思うたから・・・それで、待っとったんや」
江神さんの口から出た言葉の意味が耳からじんわり沁み込んでくる。僕は自分の頬が熱くなるのを感じた。
いくら、手紙を仲介したのが僕だったからといっても―――全く、なんてことを言うんですか。
僕は今、一所懸命、自分の立場を弁えようと努力しているのに。
そんな言い方されたら、望んでしまうやないですか。
正々堂々、あなたからそういうことを聞く権利が僕に賦される日が来るかもしれないと―――あなたにとって僕が特別な存在になる時がやってくるかもしれないと、期待してしまうやないですか。
そして、あなたが僕のことをただの後輩以上に思ってくれる可能性を願ってしまうやないですか。
心の中でそんな風に彼を責め立ててみても、その実、怒りはまったく湧いてこない。結局、部長が前にいる時の自分は、すっかり骨抜きにされているということか。
こんなにもこのひとを好きになるなんて想像だにしなかった。切ない恋心は、まだまだ僕を苦しめ続けるということらしい。それならば、毒を食らわば皿までとばかりに開き直ってやろうと思う。
いつの日か、この気持ちを彼に隠しておけなくなるのかもしれない。けれど江神さんが僕を疎ましく感じ拒絶しない限り、僕は自分の心を偽ってまでも、ずっと彼の傍に居続けるような気がする。
だって、僕たちは別れを予感するような出会い方をしなかったのだから。
彼の手から『虚無への供物』を落させた僕の動作そのものが、きっと運命だったのだ。ならば、その運命が江神さんと僕の為に用意しているもの全てと向き合い、それにとことん付き合ってみようではないか。
門の外まで出てきて、江神さんは僕を見送ってくれた。
「気をつけて、帰りや」
科白自体はごく普通だったにも拘わらず、言葉は何故か僕の中へ甘い響きをもたらした。それがまるで、近い将来僕たちの上へ訪れる運命がしろしめるように暗示的であったことを当時の自分は気づきもしなかったけれど。
一向に止まない雨の中、僕は如何ともしがたい不可思議な予兆を供にして家路を辿った。(2000/9/21)
Illustrated by 奈緒 様 実は今回、挿絵をお願いしていたのですけど、正直、こんなに素晴らしいイラストをいただけることになるとは思いませんでした―――と言いつつ、めっちゃ期待してましたが(オイコラ) あああ、嬉しいー♪♪♪
もうね、コンビニからダッシュする直前の二人を見た途端、顔がニヤけてましたよ、私。だって凄く幸せそうなんですもん。モチと信長はこういう二人を店の中から見てたのね、まさしく「お目の毒様」というトコロ(大笑) そして、江神さんに手紙を仲介した後で落ち込むアリスの表情が凄く切なくてたまんないです。目の前でこんな顔されたら、ウチの江神さんも抑えきれるかどうか危ないですね。思わず抱きしめているかもしれない(爆)
駄作を一足先に読んでいただいてどこかワンシーンの江神さんを…と甘えたことを申し上げたのですが、イメージ通り、いえ、それ以上の作品を二点も描いていただいて、とっても幸せです〜〜〜!!!
奈緒様、我儘を聞いてくださって、本当に本当にありがとうございました!!!!!
へ戻る
ラブレターの仲介、ヤキモチ、マリアに怒られるアリス、相合傘、雨の中の全力疾走等等、二人にやらせたかったことを全部書いたらこんな長さに……終わり方がなんだか曖昧なのですが、もう、力尽きてしまいました。
あああ、やっと終わったあぁ〜〜〜(嬉)
設定や動線にかなり無理があるのですけど、強引に処理しています。実は、それらについての言い訳分として書いたのが『傘』なのですね(爆死) モチと信長が推理している内容は、これらのシチュエーションをなんとか成立させる為に、作者が少ない脳味噌を悩ませた過程だったりするんです(苦笑) あと、この話に於いて全く出せなかったデコボココンビに対する罪滅ぼしのつもりもありました←つまり、この話の方が『傘』より先に出来上がっていた
ところで、"I meet My fate"という言い方には『最期をとげる』と『将来、伴侶とすべき相手に出会う』という二通りの意味があります。本当はフランス語のファム・ファタル(Femme Fatale)という言葉を使いたかったのですが、一般的に女性を指す言葉(『宿命の女』と訳されることもあり、狭義では『妖婦』と同じような意味合いで使われる)なので断念しました。
ま、"Homme Fatal"という表現をすることも無さそうですしねー(笑)