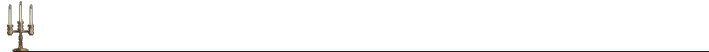決戦は金曜日 後編
「アリス。そろそろ行かんで、ええのか」
「え、もう、そないな時間・・・? うわっ、ほんまやー!!」
時計の針を気にしていたせいで、いつになく黙々と食してしまったのだけれど、取り立てて急がなかったのも事実だった。ざっと見渡した感では周囲に知った顔も見えぬし、いよいよとなったら、この場で部長のスケジュールを確認すれば良いだろうと開き直った所以だが―――時刻は無情な早さでその歩みを進め、僕の目論見はあっさり崩れた。
「ほれ、盆は片しておくから。早う行き」
まだもたもたしている後輩を気遣う科白によって、漸く我に返った。僕は慌てて立ち上がると、江神さんの顔を見た。
「あの、部長・・・今日の例会のことなんですけど」
判っている、と言いたげな表情が頷く。
「ちゃんと、ラウンジで待っとるから―――まず、行きや」
とにもかくにも荷物を引っ掴み、学食を後にした。もしかしたら僕にだけ見せてくれているのかもしれない、優しい笑みに送り出されたことで、少しく気持ちが上向かされはしたけれど、こうしてまた離れた途端、ありとあらゆるマイナス思考がぶり返してくる。
ああ、もう。こんなんじゃ、講義内容なんか頭に入らへん。
辛うじて、担当教授よりも数秒早く教室へ滑り込み、残っている空席の中で一番目立なそうな場所へ腰掛けた。お座なりにテキストを開いたのと時を同じくして、深い溜息が洩れた。三講目が終わった。「今日は、ここまで」という一声をこんなにも待ち焦がれたのはこれが初めてかもしれない。超特急で、学生ラウンジへ取って返す。
我がEMCの指定席と化して久しい部屋の奥では、先刻の言葉通り、江神さんが僕を待っていてくれた。
「結構、早かったやないか」
チラリと腕時計に視線を走らせた後、トレードマークの長髪が軽く掻き上げられた。全体としてスローペースな僕のこと、こうも早く、教室を抜け出してくるとは思っていなかったらしい。
「戸口に近い席やったんで、とっとと出てきたんです」
少しでも早くあなたに逢いかったから走ってきた、なんて言える訳ないではないか。
ほてり始めた顔を見られたくなくて、やや俯く。
部長が腰を浮かした。いつものように僕が隣へ座れるよう、窓際の席へ移動したのだ。
「そういえば授業に行く前、何か、言おうとしてたやろ」
僕は無言で頷いた。座ってから、望月・織田・マリアの三名が例会欠席となる旨を銘々の事情も含めて説明した。
望月たちからは「二人でも例会は敢行すべし」と言われたものの、部長の彼がそこに意義を見出すか、どうか―――そっと様子を伺う。
江神さんの眉が僅かに顰められる。
やはり、"総勢五名のうち僅か二名"での例会に、それほどの開催意欲が感じられなくて当然だろう。彼の表情を否定的見解の現れと取った僕は、心中やや消沈しながらも
「せやから、あの・・・今日の例会は中止しはっても・・・」
と、言葉を投げかけた。ところが。
「なんや、アリスも都合悪いんか?」
「あ―――都合悪うないです、全然!」
予想もしていなかった答えが返ってきた。思わず、咳き込みそうになる。
江神さんは小脇の荷物からクラブノートを取り出した。続いて、『推理小説研究会』と記された画用紙製ネームプレートがテーブルの隅に立てられた。
「まぁ、たまにはこういうのもええやろ。けど、例会をちゃんとやった、いう記録は残さんとあかんやろうから」
「いつもの様にテーマを決めて議論・・・しますか?」
「そうやな―――今から、やってしまうか」
え?!
「アリス、四限無かったやろ?」
「・・・はい」
「なら、時間は有効活用した方がええ。参加者は二人しかいないんやし、障りはないと思うぞ」
確かに、例会さえ片付けてしまえば、その後は自ずとプライヴェートな時間へ移行する。僕自身、一分でも一秒でも長く彼と居られる方が良い。
鞄から筆記用具を取り出し、クラブノートを受け取った。前回の討論テーマを引き継ぎ、軽く意見交換したとして―――目安は小一時間というところか。
望月や織田といった、異なる上に確固たる主義主張を持った参加者がいなこともあり、例会はすこぶる和やかに進行した。
時計を改めた江神さんが、僕の方へ視線を寄越す。
「ノートに書く分としては、この程度でええやろ・・・どうや、一ページくらいは埋まったか?」
「はい、何とか・・・せやったら、本日の例会はこれにて終了、ですね」
「そうやな」
部長が首肯するのに合わせて、ゆっくりノートを閉じる。とりあえず大義名分はクリアできた。そして―――遂に待ち焦がれた瞬間が訪れた。
何度も反芻していた科白をいよいよ口の端へ乗せようとしたのだが。
「あの・・・江神さん」
喉の奥が干からびて、擦れたような声にしかならない。
この後のことなんですけど、という一言が声にならない。
それなのに。
「なんや?」
憎らしいほど涼しげな瞳を向けられて、ますます僕の口許はこわばってゆく。これから、どないしますか―――ただそう問えばよかろうに、何故、こうも気後れするのだろう。質問文だけが頭の中を駆け巡り、平静さは失われる一方だ。
結局、口を開いたのは部長の方だった。
「アリス。この後のことやけど、何か予定あるか」
「い、いえっ何もっっ」
あたふたし始めた僕をやや眇めるように見ていたひとは、少し俯いて視線を外した。
「そうか―――なら、うちに来てくれんか? もちろんアリスの都合が悪うなかったらやけど」
「はい、ええです・・・けど」
語尾が震えそうになる。ほんの少し、目を合わせてもらえないだけで、こうも不安になる。江神さんの一挙一動によって、この意識は簡単に一喜一憂する。情けないけれど、これぞ我が身の実情なのだ。
それでも、誘われた事に気を良くして帰り支度を始めるあたり、僕も案外、現金なもので。
筆記用具一式を鞄へしまった。先に通路へ出て、奥の席から這い出してくるひとを待った。
そうこうして、学生ラウンジを後にしたのは四講目も終了間際になっていた頃だろうか。街並みは既に夕刻前の喧騒を従え、いつも通りのせわしなさを其方此方に漂わせつつあった。道中の会話は途切れがちだった。先刻より臆したままの心が少しずつ歩幅を遅れさせ、自然と、江神さんの後方へ留め置く。尤も部長は、そんな僕を時折チラリと見るだけで、特に訝しんでいる様子も無い。
西陣の下宿へ着いた。既に日はとっぷりと暮れていた。相変わらず山のような書籍やCDに占拠された部屋が、僕を迎えてくれる。
「何か、飲むか?」
いつものようにそう訊ねられて、心がそろそろと落ち着きを取り戻す。咽喉は然程渇いていなかったが、外気の冷たさを思い返し、コーヒーを所望した。
受け取ったカップから立ちのぼる湯気が、頬を湿らせる。一頻り掌を暖めてから、そっと啜る。
カップ一杯分の沈黙が、しんとした室内に降り注ぐ。
決して気まずい訳ではないのだが、飲み干した後もこのまま口を噤んでいる訳にはいくまい。さりとて、一週間ぶりの逢瀬に際し、どんな会話を交わすのが相応しいのか。考えれば考えるほど焦りが増殖していく。
殊更に時間をかけたものの、カップの中身は遂に空となった。
心の裡で小さく唇を噛む。
僕自身としては、どうしても訊ねなければならない事柄がある。けれども、それを今ここで持ち出してよいものかどうか、如何とも判断し難い。
あの夢のような一夜が明けて以来、燻り続けてきた疑念。今こそ対峙すべきであると理性が己を叱咤する。
江神さんが、本当にそういう相手として僕のことを見てくれているのかどうか、改めてこの口から問わねばならない。そして、何某かの回答を提示してもらい―――もしもそれが、自分にとって辛いものだったとしても―――受け容れなければならない。そうしないと、僕の心は永遠に平安を取り戻せない。
越えようとしているハードルは、とてつもなく高く感じられる。決して、登頂の叶わぬ山を目前にしているような気になってくる。
けれど―――ここで僕が切り出さなければ、おそらく始まらないのだ。
決意を固め、口端を上げる。
「江神さん・・・」
あまりにも弱々しい声音は、自身を更に追い込める。それでも、お守りにするような気持ちで、その名を繰り返す。
「江神さん・・・ほんまに、僕」
こちらに向けられた穏やかな瞳が、幾分見開かれる。
「・・・僕で、ほんまに・・・ええんですか?」
本当は「僕のこと『が』」と言いたかったけれど、さすがに憚られた。自意識過剰にも程がある。
「確かに、好きやて言うてもらいました。けど」
あなたは―――いつでも、誰にでも、優しいから。
「僕に・・・気ぃ遣うてるんやったら―――」
一瞬、部長の表情へ強張りが走った。やはり己の危惧は正しかったのかもしれない。もはや直視することができず、目線を落とす。
それでも、言葉は勝手に迸り出てしまう。
「江神さんは、あまり人と争わんでしょう? よう相手の身になって考える癖がついてる・・・いうか、思いやりがようある、いうか―――せやから僕のことも、傷つけたらあかんて思うとるんやないかって・・・けど、僕が自分の気持ち押し付けたからて、江神さんがそれに引き摺られることあらへん―――迷惑なら迷惑て、ちゃんと言うてもろた方が・・・」
「アリス、もうええ」
いつもと変わらぬ穏やかな口調が、僕の暴言を制したけれど。
駄目だ、顔が上げられない。膝上で握り込んだ拳の色味が刻一刻と白さを増してゆく。
「何か、勘違いしとらんか」
あやすような声。ほぼ同時に、僕の肩上へ大きな手がかけられた。一瞬、身体を引こうとする矜持へ理性を支配されたが、感情はついていこうとしない。結果として、江神さんのしようとする事へ抗うなどままならぬ現実をこの身へ再認識させられただけだった。
下から覗き込むようにして、視線を合わせられた。僕を見つめる瞳は殊の外真摯な光を湛えていて、思わず息を呑む。
「相手の身になれるやの、思いやりがあるやの、アリスがそんな風に言うてくれるのは光栄やけど―――それは買い被り過ぎや。俺はおまえが思うとるほど、人間出来てないぞ」
そう言ったひとは、やけにはっきりと溜息を吐く。
「言葉でどう言うたらええのか、正直、判らん」
至近距離で囁かれる声は、いつになく密やかで―――
「かといって態度で示す・・・いうのも何や、汚いオトナみたいで好かんのやけど」
長い腕が僕の身体へ廻された。あっという間もなく、引き寄せられる。
「不安にさせて、すまん」
これ以上ない程の簡潔さで詫びられた。そうして、強く、固く、彼に抱きしめられる。嗅ぎ慣れたキャビンの匂いが僕を包み込む。周囲は静々と凍りつき、紡がれる筈だった言葉をことごとく無用な屑と化した。
溢れそうな想いを間違いなく、感じた。おまえがええんや―――全身でそう言われた気が、した。
先刻まで砕け散る寸前だった意識は、極限まで捩れた神経の束をゆるゆると解し始めている。とくんとくんと、心臓の音が聞こえる。それが江神さんのものなのか僕自身の立てているものなのか判らなかったけれど、繰り返される鼓動の確かさに、いつの間にか安堵を覚え出す。
伸ばした腕を広い背中へ這わせた。少しばかり自嘲めいた科白が、僕の耳朶を染める。
「今回、つくづく自覚したわ。俺も意外に自制心無いんやなぁ・・・て」
「自制心・・・ですか?」
「アリスの姿を目にしてしまうと、その、抑えが効かんようになる。普通にしてられた一週間前が、ウソのようやわ」
「それは・・・僕かて同じです。けど・・・」
それ以上に僕は、あなたに逢いたい気持ちの方が強い。あなたと同じ場所にいて同じ空気を吸い、同じく瞬間(とき)を重ねたい。そして―――その瞳が少しでも多く僕を映し、愛しんでもらうことを願って止まない。
抱き合っていて互いの顔が見えないのをいいことに、思い切り本音をぶつけた。
「僕は、江神さんと出逢う為に生まれてきたんやと、そう思うてます。ここにこうして、いてることが、自分の運命なんやと、そう信じてます・・・」
「アリス」
僕の名を呼ぶ声は、ひどく優しくて。
江神さんの身じろぎを直裁に感じた。ほんの少し、頭を上げる。柔らかな瞳が僕を見ている。
ゆっくりと口唇を塞がれる。
閉じた瞼の奥が熱い。ゆるく舌を絡め取られ、なすすべもなく本能に身を任せる。江神さんの手が下降しはじめた。着衣のボタンを外す、その長い指に、途中から自分の手を重ねた。
何度目かの口付けを交わした後、部長が呟く。
「まったく―――どれだけ我慢したと思うとるんや・・・今晩、泊っていけるんやろうな?」
「・・・はい」
そうっと目を開けて答える僕を見た江神さんは、にやりと笑った。
「寝かせてやれんぞ、多分」
「!!!」
人の悪げなその笑みはたまらなく魅力的で、一瞬、呼吸が止まりそうになる。
「覚悟しとけや」
それこそ、望むところです―――と口にする訳にもいかず、自ら唇を重ねる。溶かされるようなキスは、濡れた音を立て、淫らに糸を引いて絡まり合う。直に施される愛撫さえ、もどかしく、互いの肢体が徐々に煽られてゆく。
それでも、すぐ傍にある穏やかなひとの存在が、僕の全てをえもいわれぬ幸慶に浸してくれる。
だからこそ、この胸が時折痛むことに、そしてそれは決して気のせいなんかじゃないということに思い至る。
こんなにも切なく、江神さんに焦がれているという事実を遥かなる高みより知ろしめされるのだ。どうして、これほどまでにあなたが恋しいのか。
どうして、これほどまでにあなたから目が離せないのか。
僕は再び目を閉じる。
そして―――
あなたも僕を恋しいと思っていてくれているのなら、他のことは、もう、どうでもいい・・・
眦の奥が緩み、熱を帯びてきた。やがて体内のどこかから徐々に広がりつつある、暖かな何かの気配を確かに感じた。(2007/8/15)
へ戻る
コンセプトは付き合い始めの不安をどう克服するか、なのですが…それにしてもウチのアリスって、どこまでも襲い受<ばき
例によって前半でシッカリ出張った経済学部コンビ+紅一点は、まだ、江神さんとアリスが一線を越えた事に気付いていないにも拘らず、常日頃敷いている応援体制(?)に則って、咄嗟に動いてます。つまり、信長とマリアが欠席を言い出した時点でモチも(これは俺も欠席した方がええな)と即判断、そのモチの掲げたやや弱い欠席理由へマリアが理屈をつけ、それでも躊躇って例会中止を示唆したアリスに対し、三人してひっくり返しにかかったという訳(爆)
で、アリスってば鈍感過ぎ!と時々言われることがあるのですが、だって、そんな余裕無いと思うんですもん(苦笑)
ウチのアリスは決してヌケサクではないんですけど、江神さんを好き(=好意や尊敬)なことは皆に知られているという認識はあっても、まさかその正体(=恋愛感情)を見抜かれているとは露ほども考えません。アリスとしては、とにかく一般的でない恋情を初体験している最中な訳で、当然、他人から(自分が)そんな風に見られる可能性には思い至らない。だから、江神さんとの関係が安定してきて初めて、持ち前の観察眼により三人の配慮を薄々感じ取れるようになるんです。まぁ、その点は、江神さんの方も御同様だと思いますね。
おそらくEMCメンバー以外の目には、二人の関係は『非常に仲の良い先輩と後輩』としか映らないでしょう。
なおタイトルは、Dreams Come Trueの曲より拝借いたしました♪